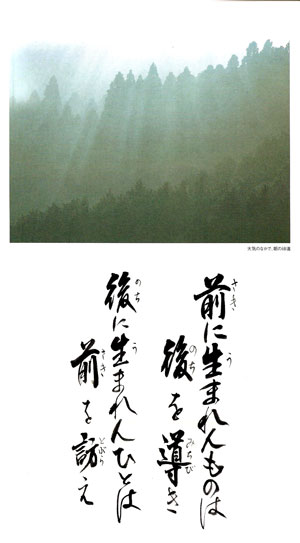 時代を去ること遥かに遠く
時代を去ること遥かに遠く
今月の言葉は、『教行信証』後序の終りに記されていて、この文は七高僧の第四祖、道綽禅師(どうしゃくぜんじ)の『安楽集』から引かれています。そこで、この言葉を浮き彫りにするために、それに先立つ前文を現代語に言い換えて紹介しておきます。それは、
今のときの衆生を考えるのに、ちょうど、お釈迦さまが世を去られてから後の第四の五百年に当たっている。これはまさしく懺悔し功徳を修めて仏の名号を称えるべきときである。一声、南無阿弥陀仏と称えるところに、八十億劫もの長い間の迷いの罪が除かれる。一声でそうである。ましてつねに念仏するものはつねに懺悔する人である。もしお釈迦さまの時代を去ることが近ければ、前のものが禅定や智慧を修めることが正しい学となり、後のものは兼ねることになる。もしお釈迦さまの時代を去ることが遠ければ、後のものの称名の方が正しい学となり、前のものの禅定や智慧は兼ねてすることになる。どういうわけでそうなるかと言えば、まことに今の時代の衆生は、お釈迦さまの時代を去ること遥かに遠く、宗教的素質が劣って、深いことを理解できず愚かであるからである。そのために韋提希夫人(『仏説観無量寿経』に説く「王舎城の悲劇」の主人公)は、自分や末世の五濁の衆生がとても長い間、生死を繰り返して、いたずらに苦しみを受けるのをあわれんで、仮に苦しい因縁にあって迷いの世界を超え出る道を尋ねたので、お釈迦さまは慈悲をもって、極楽に帰すべきことを勧められた。もしこの世界において修行して進もうとすれば、すぐれた覚りの結果はなかなか得ることができない、ただ阿弥陀如来の浄土の一門のみは、凡夫の情をもって願って往生することができる。もし多くの経典を開いてみるならば、これを勧められるところがたいへん多い。
(『註釈版聖典(七祖編)』一八四貢、参照)
と書かれ、これに続けて、今回の法語として取り上げる文章の、
真言を取り集めて、往益(おうやく)を助修(じょしゅ)せしむ。いかんとなれば、前に生まれんものは後を導き、後に生まれん人は前を訪へ(とぶらへ)、連続無窮(むぐう)にして、願はくは休止(くし)せざらしめんと欲す。無辺の生死海(しょうじかい)を尽さんがためのゆゑなり。
(『註釈版聖典』四七四貢)
があります。
五濁悪世
さきの『安楽集』の内容からも少しうかがえますが、道綽禅師について考えるときに重要なことは「三時思想」です。これは仏教の歴史観とも言えるもので、お釈迦さまが涅槃に入られてから時間が経過するにしたがって、世の中が濁って仏法が衰退していくというもので、それを正法(しょうぼう)・像法・末法の三時に分けることです。その三時の期間はどれぐらいとみるかについては各種の説がありますが、道綽禅師は正法五百年、像法一千年、末法一万年と考えておられたようです。ですから、禅師が生まれられた西暦五六二年は、お釈迦さま入滅後一千五百十一年目にあたりますので、すでに末法に入っていたと確信されていたようです。前述の文中でもありましたが、末法になると五濁が顕著になることをお釈迦さまは明らかにされていました。『仏説阿弥陀経』の終りに、「五濁悪世(ごじょくあくせ)、劫濁(こうじょく)・見濁(けんじょく)・煩悩濁(ぼんのうじょく)・衆生濁(しゅじょうじょく)・命濁(みょうじょく)」(『註釈版聖典』一二八貢)とあるのがそれです。道綽禅師がすでに末法の時代に入ったと自覚されていたことは、親鸞聖人も同じであられたし、現代の私たちも末法の真っただ中にあると明確に認識しておかねばなりません。そのような視点にたって周囲をみわたすと、無気力・無責任・無関心・無感動・無作法などの言葉を頻繁に耳にし、虚無主義的傾向が広がっているようにみえます。末法における五濁悪世の五濁について明らかにしておきましょう。
「劫濁」とは、時代の濁りで戦争や疫病や飢饉などが多くなることを言い、時代的な環境社会の濁りをさします。「見濁」とは、思想の乱れを言い、邪しまな見解や教えがつぎつぎにでることをさします。人間のご都合主義が大手をふるい、それぞれの信仰をつくりだしていきます。「煩悩濁」とは、煩悩がはびこることを言い、貪り・怒り・迷い(癡(ち)=愚かな心の暗さ)などの煩悩が燃え盛る、あさましいすがたをさします。「衆生濁」とは、人間の身・心がともに弱くなり、資質が低下することを言います。「命濁」は生命の濁りということで、寿命が少しずつ短くなることをさします。数十年来のわが国だけに限ると、お釈迦さまの説示を覆しているようにみえますが、世界に目を向け、末法一万年を考えると、五濁の他のものと合わせて納得せざるをえません。
「礼賛文(らいさんもん)」の、
人身(にんじん)受けがたし、今すでに受く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。
の言葉は、私たちが親しんでよく口にしています。道綽禅師も、この世に生を受けたことで仏法に出遭えた喜びをかみしめる一方で、教えがありながら覚りに到れない末法の世であることのくやしさ、悲しさは想像を絶するものであったことでしょう。しかし、そのことが他力浄土の世界に目を向けられる機縁となったのです。そこで、道綽禅師の教えの基本が約時被機(やくじひき)(時代と衆生の資質とに相応する教え)にあることをおさえておかねばなりません。時代と環境、そして自分の能力を十分にふまえたうえでの、道綽禅師の教えにむかう姿勢から、宗教はいつも現実の社会と自分自身のすがたを視野にすることが大切であることを知らされます。どんなに尊く深い教義であっても、それが私の手が届かないようなものであれば決して救われることはなく、したがって、その宗教は意味のないものとなってしまいます。
弥陀の本願
ここで再び最初に戻って、「真言を採り集めて」から「無辺の生死海を尽さんがためのゆえなり」までを現代語に言い換えると、
真実の言葉を集めて往生の助けにしよう。なぜなら、前に生まれるものは後のものを導き、後に生まれるものは前のもののあとを尋ね、果てしなくつらなって途切れることのないようにしたいからである。それは、数限りない迷いの人々が残らず救われるためである
(『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』六四六貢)
となります。
この文中の「前に生まれるものは後のものを導き、後に生まれるものは前のもののあとを尋ね」るについて、いろいろな受け止め方が生じてきます。その一例をあげますと、「わが家においては先に生まれた者が、後に続く子や孫をしっかり育てておかなければならない。また今、生きているお互いは先立たれた方々のご恩をいつまでも忘れないで暮らしたい」というような内容です。これは人間として大切な心がけですが、倫理・道徳のうえでとらえています。
ではこのところを、どのように考えればよいのでしょうか。『歎異抄』第二条で、親鸞聖人は次のように述べておられます。
弥陀の本願まことにおはしまさば、釈尊(しゃくそん)の説教虚言なるべからず。仏説まことにおはしまさば、善導の御釈虚言(おんしゃくきょごん)したまふべからず。善導の御釈まことならば、法然の仰せそらごとならんや。法然の仰せまことならば、親鸞が申すむね、またもつてむなしかるべからず候ふか。詮ずるところ、愚身の信心におきてはかくのごとし。このうへは、念仏をとりて信じたてまつらんとも、またすてんとも、面々の御はからひなり
(『註釈版聖典』八三三頁)
この言葉は、はるばる関東から命がけで京都に尋ねてきた門弟の不審に対する、聖人の返答なのです。なにか学問的、論理的な説明を期待してやってきた門弟に、かえって求める側の誤りを指摘するものでした。それは、
しかるに念仏よりほかに往生のみちをも存知し、また法文等をもしりたるらんと、こころにくく(はっきりと知りたく)おぼしめしておはしましてはんべらんは、おほきなるあやまりなり。
(『註釈版聖典』八三二頁、参照)
とたしなめられたものでした。
その後に、「弥陀の本願まこと」以下の話がでてきます。また、「まこと」について触れますと、同じ『歎異抄』後序に、
煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろづのこと、みなもつてそらごとたはごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておはします
(『註釈版聖典』八五三~八五四頁)
とあります。私たちが今生を過ごす娑婆世界には、ほんとうに頼りきれるものがありません。どれほどあてにしても人には別れがあります。まして財産であれ、地位・名声でも、やがては消えていくのです。さらに言えば、喪失するものばかりを追いかけているのです。それをむなしいと感じないところが、人間の愚かさです。そのような私たち(凡夫)をみすてることができずに、阿弥陀如来は〈必ずすくう〉との本願をたててくださったのです。そして、その願いが名号となってはたらいてくださっています。ですから、如来の本願を疑いをまじえずに受け入れることが信心であり、そこにおのずから〈南無阿弥陀仏〉が口をついてでるのです。そこを親鸞聖人は、ほんとうの信心には必ずお念仏がそなわっていると仰せになっています。
また「正信偈」は、
道俗時衆共同心(どうぞくじしゅぐどうしん)
道俗時衆ともに同心に、唯可信斯高僧説(ゆいかしんしこうそうせつ)
ただこの高僧の説を信ずべしと。
(『註釈版聖典』二〇七頁)
で結ばれています。ここで親鸞聖人は、出家も在家も今のときの人びとは、さらにはこれから後に生まれてくる人びとも、みんな同じ心をもって、この高僧方が口をそろえて説かれる〈弥陀の本願まこと〉の教えを信ぜよ、と勧められています。
私たちは各処で示されている、これらのおこころを疑いなく受け止めるための聴聞を欠かすことができません。それはまた、念仏相続に努めさせていただく生活として途切れることなく受け継がれていくことが望まれているのです。
(清岡隆文)
あとがき
親鸞聖人ご誕生八百年・立教開宗七百五十年のご法要を迎えた一九七三(昭和四十八)年に、真宗教団連合伝道活動の一つとして「法語カレンダー」は誕生しました。門信徒の方々が浄土真宗のご法義をよろこび、お念仏を申す日々を送っていただく縁となるようにという願いのもとに、ご住職方をはじめ各寺院のみなさまが頒布普及にご尽力をいただいたお陰で、現在では国内で発行されるカレンダーの代表的な位置を占めるようになりました。その結果、門信徒の方々の生活の糧となる「こころのカレンダー」として、ご愛用いただいております。
それと共に、法語カレンダーの法語のこころを詳しく知りたい、法語について深く味わう手引き書が欲しいという、ご要望をたくさんお寄せいただきました。本願寺出版社ではそのご要望にお応えして、一九八〇(昭和五十五)年版から、このカレンダーの法語法話集『月々のことば』を刊行し、年々ご好評をいただいております。今回で第三十二集をかぞえることになりました。
真宗教団連合各派において、二〇一一(平成二十三)年~二〇一二(平成二十四)年に親鸞聖人七百五十回大遠忌を迎えますことから、聖人のいただかれた聖典のお言葉を中心に法語が取りあげられることになり、二〇一一(平成二十三)年は、親鸞聖人の主著である『顕浄土真実教行証文類』(『教行信証』)のなかから法語が選定されました。この法語をテーマにして、四人の方に法話を分担執筆していただき、本書を編集いたしました。繰り返し読んで、み教えを味わっていただく法味愛楽の書としてお届けいたします。
本書を縁として、カレンダーの法語を味わい、ご家族や周りの方々にお念仏のよろこびを伝える機縁としていただくとともに、研修会などのテキストとしても幅広くご活用ください。
二〇一〇(平成二十二)年八月
本願寺出版社
















