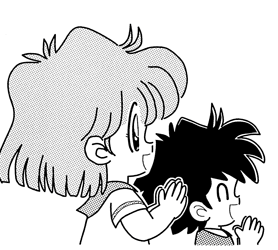寿命

もったいない
世界中に広がるMOTTAINAI
ノーベル科学賞(2002年)を受賞した田中耕一氏は、「私の発見は、失敗後も<捨てるのはもったいない>と実験を続けたことから生まれた」と話し、「もったいない」が一躍有名になりました。
ノーベル平和賞(2004年)を受賞したケニア副環境相(当時)のワンダリ・マータイさんは、「もったいない」に共鳴してキャンペーンの名誉会長に就任し、国連や全米記者クラブの講演などで世界に発信しました。
「もったいない」は仏教専門用語ではなく、室町時代に一般化した言葉を蓮如聖人(れんにょしょうにん)が取り入れて、浄土真宗の法味を的確に表現する言葉となったようで、多くの念仏者が口にしてきました。
蓮如上人が廊下に落ちている紙切れを拾い上げ、「一枚の紙もこれみな仏法領のもの(仏より恵まれたもの)、もったいない」と押し頂かれた話は有名です。
「もったいない」は、単に「無駄にしない」「節約する」だけでなく、「かたじけない」と感謝する心ではないでしょうか。

悪事千里を走る
戦争が勃発すると、戦場の悲惨な場面を逐一茶の間のテレビに映し出すようになったはじめは、1991年の湾岸戦争でした。この戦争の特徴は、ハイテクの使用とテレビ戦争でした。
以来、2001年のアメリカ同時多発テロ事件のときには、まるで実況中継でしたし、その後の世界各地での戦争状況もマスメディアを通じて世界中に伝えられています。
まさに「悪事千里を走る」です。
この諺は、悪い行いはすぐ世間に知れ渡る、という意味ですが、戦争という悪事は地球上を駆け巡りました。
『景徳伝燈録(けいとくでんとうろく)』に、「好事門を出でず、悪事千里を行く」とあるのが、この諺のもとです。
好いことはなかなか世に知られないが、悪いことはすぐに広まる。それが世相である。
だからこそ、達磨大使(だるまたいし)は好いことを伝えるために、インドから遠く中国までやってきたのである、というのです。
仏教は「不殺生戒(ふせっしょうかい)」の立場から、「いのちを大切に」をスローガンにしています。
一日も早く、ほんとうの平和という好事が、千里といわず、地球上を駆けめぐってほしいものです。
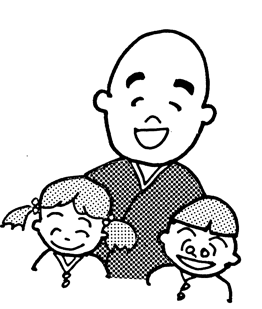
お蔭様
「お蔭様で」は、感謝の心を表す日常語です。お蔭とは、神仏の助けや加護のことで、そこから、人から受ける恩恵や力添えをいうようになりました。
王舎城(おうしゃじょう)に住んでいたシンガーラカは、亡父の遺言によって、毎朝、東西南北と上下の六方に礼拝をしていましたが、意味は十分理解していませんでした。
お釈迦さまは彼に対して、こう教えました。
「東方を拝むときは、私を生み育ててくださった父母に感謝し、南方を拝むときは、私を導いてくださった師に感謝し、西方は妻や子に、北方は友人に、上方は沙門に、下方は目下のもののご苦労に感謝せよ。それが六方を礼拝する合掌の意味である」
この説法は「シンガーラカへの教え(『六方礼拝経』と漢訳)」といい、在家向きの論理道徳を説いたものとして、原始経典中、重要なものとなりました。
仏教は、すべてのものは相互に関係しあい、多くのものの力、お蔭、恵みを受けて生きていると説きます。だから、当然、これらに感謝しましょう。