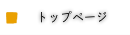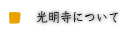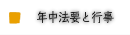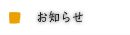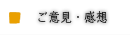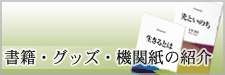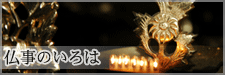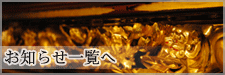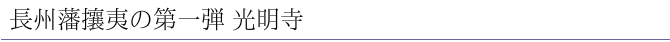
「明治維新」といわれる時代変革が、いつの時点をもって端緒とするかについては諸説のあるところであるが、下関の明治維新は攘夷戦をもって始まる。そして、文久三年(一八六三)五月十日に始まった下関海峡での攘夷戦をふり返るとき、―無謀ともいえる長州藩の突出―といった感懐が心をよぎる。
嘉永六年(一八五三)六月三日、アメリカ東インド艦隊司令官マシュー・カールブレース・ペリーの率いる四隻の艦隊が、わが国に開国を迫って浦賀沖に錨をおろす。これに驚いた幕府は、各藩に対して江戸湾警備のための出動命令を下す。この命令に、最も迅速にかつ見事に対処したのが他ならぬ長州藩であった。
長州藩では、米艦来航を知るや直ちに江戸藩邸の武庫を開き、三門の火砲と百丁の和銃で武装した五百人の藩兵を編成、六月七日の夜、幕府から出動命令が届いたときにはすでに態勢を整えており、その夜のうちに大森海岸へ向かったという。
それは、すでに太平の世になれ、武士階級は戦闘への準備から遠ざかり、藩邸に武庫を持だない藩も多い有様の中で、慶長五年(一六〇〇)の関ヶ原の闘いによる防長二州への減封以来、徳川幕府への対決の意識を潜在させながら、ひたすら富国強兵の道を歩んで来た一つの成果でもあった。
このため、再来を言い残してペリーの艦隊が日本を去ったのち、長州藩は幕府から「相模国防衛」、即ち江戸湾の警備を正式に任命され、くにもとから武器・弾薬を送り出すかたわら、江戸葛飾の長州藩別邸で三十六門の巨砲を鋳造させるなど、さらに武備をかためる。ペリーが再び浦賀に来航したのは安政元年(一八五四)一月十六日のこと、今度は七隻の船を従え、前回以上の武力的威嚇をもって開国を迫る。この強行態度の前に、幕府は遂に三月三日、十二条からなる日米和親条約に調印。これによって、長年にわたる鎖国政策が崩れ、以後オランダ、ロシア、イギリス、フランスと相次いで和親条約、通商条約を結ぶことになる。


いったん長井雅楽を中心に公武合体論の妥協的方向に傾いた藩論も、藩内尊攘派の大いに反発するところとなって再び尊攘論に立ち返り、朝廷に対して破約攘夷を幕府に申し付けるよう強く要請。文久二年(一八六二)十月、勅使三条実美卿が江戸に下って将軍に勅書を手渡す。

長州藩は、わが意を得たりとばかり、攘夷決行の場を下関の海峡と定め、藩兵を下関市に集結させる。その兵力は萩本藩から正規兵六百五十余人、下関細江の光明寺に駐屯していた久坂玄瑞率いる浪士隊(光明寺党)約五十人、長府・清末両藩から三百人が出動し、およそ千人となった。
一方、海峡に沿って彦島老の山、同弟子待、永福寺、専念寺、亀山社、八軒屋、壇之浦、杉谷、前田、長府城山などに砲台が整備され、記録によれば二十五門程度の大砲が配備される。もちろん台場の整備や大砲の配備は漸次行われていったものであり、元治元年(一八六四)八月の下関戦争の後、四国連合艦隊が戦利品として持ち帰った大砲の数は百門を越えるに至っているが、最初の攘夷戦を迎える段階ではまことに貧弱なものであった。また砲台の設置とともに海岸には長州藩の軍艦丙辰丸(へいしんまる)・庚申丸(こうしんまる)・壬戌丸(じゅんじゅつまる)・発亥丸(きがいまる)の四隻が待機し、外国船打ち払いに備えた。
そして五月十日、折しも雨にけぶる海峡に一隻の外国船が姿を現わし、九州側の田野浦沖に停泊した。長州藩ではただちに小舟を近づけて偵察、アメリカの商船ペンブローグ号であることを確認。日本人の通訳から、同船が神奈川奉行から長崎奉行にあてだ書状をあずかっていること、横浜を出て長崎に寄港、上海に行く途中であることなどを聞き出す。
外国船を目の前にして、砲台に待機する者たちは心はやらせるが、公儀の書状を持つことを知って総奉行毛利能登は攻撃をためらう。しかし、久坂玄瑞ら光明寺党浪士の面々はこの絶好の機会を無にしてはと、遂に総奉行の下知を待たずに行動に走る。
彼等は、下関の港に待機する庚申丸を訪れてペンブローク号攻撃の強談判に及び、庚申丸・発亥丸両艦による攻撃を決定。いよいよ五月十一日に入った午前二時、決死の浪士たちを乗せた両艦が、暗闇の中を出撃、亀山砲台から合図の一発が放たれ、続いて両艦からも撃ち出す。
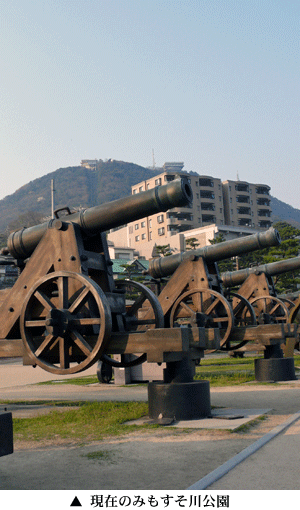
この光明寺党による一発こそ、長州藩における攘夷の、ひいては維新回天への第一弾となったのである。
攻撃は、亀山砲台から弾はとどかず、もっぱら庚申・発亥両艦によって行われた。といっても両艦から打ち出した弾丸は十二発、うち三発が命中してわずかに損傷を与えたに過ぎず、ペンブローク号も自衛のために数発打ち返しただけで、すでに出航準備をしていたところでもあり、船足早く周防灘方面に逃走してしまった。
まことにあっけない攘夷戦ではあったが、長州側は黒船を追い払ったと意気あがり、戦勝の報は早駕龍で萩城下にも報告され、長州藩全体を興奮させた。藩主もまたこれを朝廷に奏上、朝廷からは早速長州藩に対して褒勅が下されたというから、その興奮ぶりが如何なるものであったかが想像出来よう。
この第一次攘夷戦において、攘夷の第一弾を放ったという名誉をになうことになった浪士隊は、光明寺を屯所としたことから光明寺党といわれる。

その光明寺は、市内細江町の中通りの山手の小高い位置にあり、昭和二十年(一九四五)の大空襲で周囲が焼失し、その炎は石垣まで迫ったが無事焼け残り、久坂玄瑞ら浪士隊の人たちが居住した当時のままの姿を今日に伝え、貴重な維新史跡の一つとなっている。
常陸の国の人釈正善の開基で、大永年中(一五二一~一五二七)、豊浦郡西市村に一宇を建立。その後内日村、幡生村と移転、享保十七年(一七三二)に現在地に移ったといわれる浄土真宗のこの寺にも、まさにドラマがあった。
第一級の維新史料である『白石正一郎日記』の中に「六日(文久三年四月)、中山公子今日又狐狩ニ御出長府より御猟方来ル、得もの狐壱疋光明寺へ御持行被召上候」という記述があるが、中山公子とは急進派公卿中山忠光卿のこと。光明寺党激励の意味での訪問でもあったろう。中山忠光や久坂玄瑞らが狐を食べ、浪士たちが手をふれた柱や肩いからせて歩いた廊下などを、今私たちも手にふれ、歩むことが出来るのである。
なお、光明寺にかかかる語り伝えとして、“艦首像”の話がある。長州藩の軍隊発亥丸は、イギリス製のランリック号を購入したものであったが、光明寺党の隊士たちが、その艦首に飾りつけられていた艦首像を切り取って来て光明寺本堂の階段下に据え置き、出入りの度ごとにその像を蹴とばし、攘夷の思いを高揚させていたというのである。若者らしい稚気ではあったが、これもまたある意味で強い結束への踏絵であったろう。