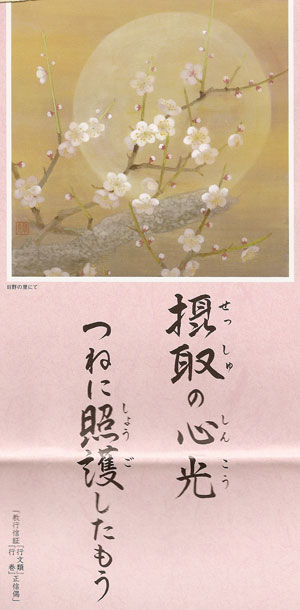
「正信偈」の文
今月の法語は、『教行信証』「行分類」の「正信偈」の文から選ばれました。
まず、「正信偈」について少し述べることから始めたいと思います。「正信偈」は正式には「正信念仏偈」と呼ばれます。われわれ浄土真宗の門徒が心の依りどころとする根本聖典、『教行信証』の最も重要な一部分の抜粋です。それは、六十行百二十句からなる讃歌です。
「帰命無量寿如来 南無不可思議光(きみょうむりょうじゅにょらい なもふかしぎこう)」(『日常勤行聖典』六貢)から始まるこの偈頌(げじゅ)は、多くの人に親しまれ、読誦されています。また、この二句のなかに、親鸞聖人の喜びと如来の光のなかに見も心も投託された信条が、余すところなく表されています。
一月の法語解説でも少し触れましたが、「正信偈」は二つの部分に分けられ、「法蔵菩薩因位時(ほうぞうぼさついんにじ)」(『同』)からは『無量寿経』に基づいて述べられる依経段、「印度西天之論家(いんどさいてんしろんげ)」(『同』十七貢)以下は三国七高僧の釈によって説かれる依釈段と呼ばれます。
そしてこの偈のなかに『教行信証』の全体が圧縮されているのです。したがって、「正信偈」を読むことによって真宗教義の全体が鳥瞰(ちょうかん)できるのです。そしてまた、「正信偈」を学べば真宗教義のすべてを学んだことになるといっても、過言ではありません。
さて、その「正信偈」のなかから、
摂取心光常照護(せっしゅしんこうじょうしょうご)
(『日常勤行聖典』十三貢)
(摂取の心光、つねに照護したまふ。『註釈版聖典』二〇四貢)
の文が取り上げられてあります。この一句は『観無量寿経』の、
光明は、あまねく十方世界を照らし、念仏の衆生を摂取して捨てたまはず。
(『註釈版聖典』一〇二貢)
や、善導大師の『観念法門(かんねんぽうもん)』に、
ただもつぱら阿弥陀仏を念ずる衆生のみありて、かの仏の心光つねにこの人を照らして、摂護(しょうご)して捨てたまはず
(『註釈版聖典(七祖篇)』六一八貢)
等とある文に依られていると考えられます。
「摂取」の心
ところで、摂取という語につきましては、国宝本(真筆本)の『浄土和讃』「弥陀経讃」(「阿弥陀経和讃」)の左訓に次のようにあります。
おさめとる
ひとたびとりてながくすてぬなり
せふはものヽにぐるをおわえとるなり せふはおさめとる、
しゆはむかえとる(『真宗聖典全書』第二巻、三七九貢・原文片仮名)
とあります。
「摂はものの逃ぐるを追はへとるなり。摂はをさめとる、取は迎へとる」(『註釈版聖典』五七二貢)という言葉から、桐渓順忍和上のおっしゃっておられたことが思い出されます。それは、「逃げても逃げても救われる。救われるのに逃げている」という言い方をされていたことです。私たちは阿弥陀さまに背を向けて逃げているのですが、どこまでも追っかけてきて抱き取って離さないというのが摂取の意味である、といわれています。
また、「摂」と「取」に分けてそれぞれの意味を示しておられるのも、親鸞聖人の説明の特徴です。たとえば、「慶喜」という語についても、
慶(きょう)はよろこぶといふ、信心をえてのちによろこぶなり。喜はこころのうちによろこぶこころたえずしてつねなるをいふ。
(『註釈版聖典』七一二貢)
とあります。このような例は他にもいくつかありますが、分釈することによって元の言葉の意味がより深く味わわれるように思われます。それは、言葉が動的に生きた姿をとってくるということでしょうか。
このように、「弥陀経讃」の摂取の語に意味を示しておられます。その和讃一首の全体をみますと、
十方微塵世界の
念仏の衆生をみそなはし
摂取してすてざれば
阿弥陀となづけたてまつる(『註釈版聖典』五七一貢)
十方のさまざまな世界にうごめき念仏を称えながら生きている衆生をご覧になって、光明のなかに摂め取りお捨てにならない方を、阿弥陀仏と申しあげます。
と詠っておられます。
この和讃では、阿弥陀仏という名告りは、十方世界に生きるあらゆる者を念仏の衆生に育てあげ、光明のなかに摂め取って捨てないからであり、それゆえに阿弥陀と名付けるのであるといわれます。といたしますと、摂取ということが「阿弥陀仏」という名告りの基盤をなしているということです。摂取不捨ということを離しては、阿弥陀仏という仏さまを語ることはできないということです。
ですから、阿弥陀仏の仏像を拝見しますと、右手を高く掲げ、左手を下にしておられます。それは、摂取と不捨ということを表しておられる姿といわれています。もっとも智慧と慈悲を示されているとの見方もあります。いずれにしましても、この和讃からは阿弥陀仏と名付ける理由として、念仏の衆生を摂取して捨てないからだといわれます。
このように、摂取といわれる阿弥陀さまのはたらきは、心光によって表されます。
私どもが目にする太陽とか月の光、あるいは蛍光灯の光などは色光といって、心光とは区別されます。色光は波動とか粒子でできていると、物理学では考えてきました。しかし、心光とはそのように分析できるものではありません。心光に遇えば、見えなかったものが見えてくる、気付かなかったものが気付かされる、知らなかったものが知られてくるとでも説明できるでしょうか。心光とは、信心を得た人を護り育ててくださる仏さまの智慧のはたらきをいうのです。それは救いの光ということであります。
親鸞聖人が真実の経といわれる『無量寿経』には、名号による救いの論理が説かれているとともに、光明による救済が説かれています。たとえば、第三十三願には、
たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界の衆生の類、わが光明を蒙(こうぶ)りてその身に触れんもの、身心柔軟にして人天に超過せん。もししからずは、正覚を取らじ。
(『註釈版聖典』二一貢)
とあります。摂取の光明に包まれた者は、煩悩が消えて身も心もやわらぐという、願いです。光明は本来智慧を表すのですが、ここでは慈悲の光明として、その意義を担っています。浄土教では、慈悲としての光明が強調されてくるように思われます。
親鸞聖人もまた、光明を智慧と慈悲の両方を表すものとみていかれます。『御消息』のなかで、
無礙光如来(むげこうにょらい)の慈悲光明に摂取せられまゐらせ候ふゆゑ、名号をとなへつつ不退の位に入り定まり候ひなんには、
(『親鸞聖人御消息』『同』七七七貢)
と述べられて、光明によって慈悲を表されています。また、『浄土和讃』には、
慈光はるかにかぶらしめ
ひかりのいたるところには
法喜をうとぞのべたまふ
大安慰(だいあんに)を帰命せよ(『註釈版聖典』五五八貢)
(曇鸞大師(どんらんだいし)は、)はるかに離れた浄土からの阿弥陀さまの慈しみの光明をいただいた者は、仏法を喜ぶ心をいただくとおっしゃっています。大きな安心と慰めをお与えくださる阿弥陀さまに、帰依いたしましょう。
と、やはり慈悲の光明を讃詠されています。
このように、心光について窺うことができますが、その心光によって常に照護される利益に恵まれていると述べられるのです。
讃嘆と自省
ところで、阿弥陀さまの光に照らされているのであれば、もはや貪りや瞋り(いかり)といった醜い心は起こらないのでしょうか。このことについて、親鸞聖人は巧みな比喩を用いて、次に続く「正信偈」の文のなかに述べられています。それは、
巳能雖破無明闇(いのうすいはむみょうあん)
貪愛瞋憎之雲霧(とんないしんぞうしうんむ)
常覆真実信心天(じょうふしんじつしんじんてん)(『日常勤行聖典』一三貢)
(すでによく無明の闇を破すといへども、貪愛・瞋憎の雲霧、つねに真実信心の天に覆へり。『註釈版聖典』二〇四貢)
というお言葉です。ここでは、雲や霧によって日光がさえぎられるように、私たちの貪愛や瞋憎の妄念は常に起こり、信心の大空を覆ってしまっていると喩えておられます。しかし、次に、
譬如日光覆雲霧(ひにょにっこうふうんむ)
雲霧之下明無闇(うんむしげみょうむあん)(『日常勤行聖典』一四貢)
(たとへば日光の雲霧に覆はるれども、雲霧の下あきらかにして闇なきがごとし。『註釈版聖典』二〇四貢)
と続いています。これは、いかに雲霧がその日光を遮ろうとも、地上のすべてはあきらかであるという喩えですが、これは、一度信心を獲れば、その後は往生についての疑いの心は起こらないということを表しています。そして、このような譬喩によって、摂取の心光によって護られてる姿を明らかにされているのです。
ここで一つ注意してみたいことは、「摂取心光常照護(せっしゅしんこうじょうしょうご)」に常とあり、「常覆真実信心天(じょうふしんじつしんじんてん)」に常の文字が見られるということです。この二つの常の文字のなかに、親鸞聖人の限りない讃嘆、そして喜びの思いが伝わってくるようですし、同時にまた深い自省の思いが込められているように窺われます。
親鸞聖人は、『教行信証』で、信心を「誠なるかな・慶ばしいかな・悲しきかな」(三哉)と、喜びと悲しみの思いをもっておっしゃいました。今の二つの常もそうです。二つの常が別々にあるのではないのです。煩悩具足の凡夫であるということと阿弥陀さまの慈光に浴するということとは、けっして切り離しては考えられないのです。
松影の暗きは月の明かりかな
という歌があります。月の光によって影が写るのです。光と影、これもひとつのものであります。
ところで、この「摂取心光常照護」の文を、親鸞聖人は『尊号真像銘文』のなかに、
「摂取心光常照護」といふは、信心をえたる人をば、無礙光仏(むげこうぶつ)の心光つねに照らし護りたまふゆゑに、無明の闇はれ、生死のながき夜すでに暁になりぬとしるべしとなり。
(『註釈版聖典』六七二貢)
と説明されています。阿弥陀さまの心光は常に照らし護ってくださるのです。源信和尚(げんしんかしょう)も、
大悲倦むことなくして、つねにわが身を照らしたまふ。
(『往生要集』『註釈版聖典(七祖篇)』九五六~九五七貢)
と述べられています。大悲の光明は、すっぽり私を包み照らしているのです。その光明のはたらきに気付いた時、すなわち信心をいただいた時、無明の闇が晴れるといわれるのです。その闇を長い夜に喩えられています。闇は、闇を破ることはできません。「明来闇去」という言葉がありますように、光によって破られるのです。自分の煩悩の深さを徹底的に内省していく時、阿弥陀さまの光に遇うことができるということです。同じ「正信偈」のなかにあります、「極重悪人唯称仏(ごくじゅうあくにんゆいしょうぶつ)」(『日常勤行聖典』三二貢)(極重の悪人はただ仏を称すべし『註釈版聖典』二〇七貢)という言葉の「極重悪人」をわがこととして思う時、弥陀の大悲のなかに摂め取られているということであります。
「摂取心光常照護」の言葉から、親鸞聖人が『教行信証』「信文類」で、現生において十種の益を得ると述べられているなかに、「心光常護の益」があることも思い出されます。この句によって、ほのぼのとした歓喜の心が生じてくる、そんな法語として味わうことであります。
(大田利生)
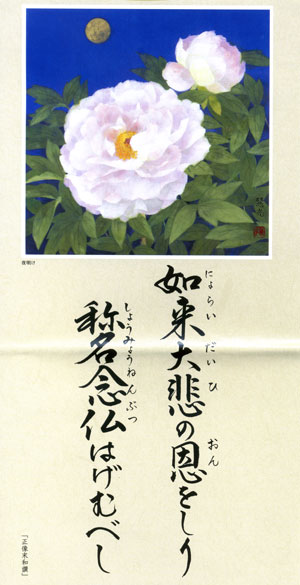 「三帖和讃」の成立
「三帖和讃」の成立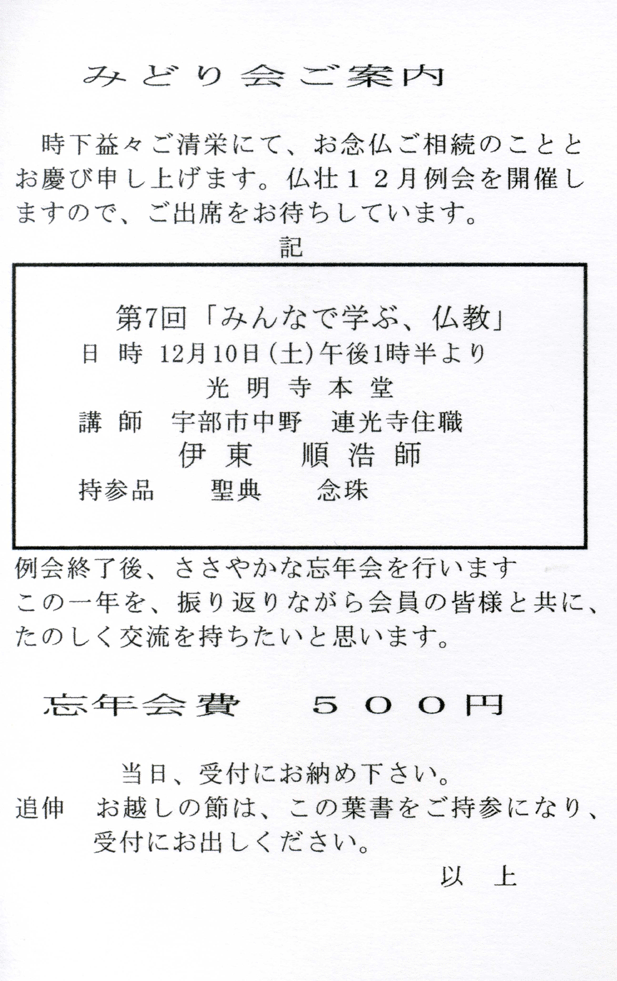
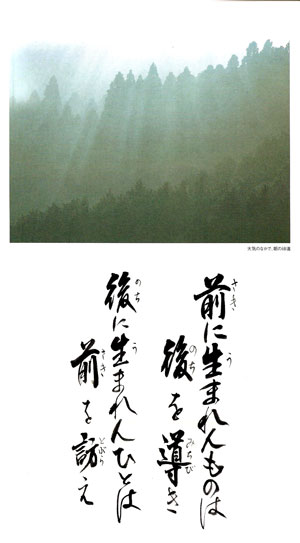 時代を去ること遥かに遠く
時代を去ること遥かに遠く
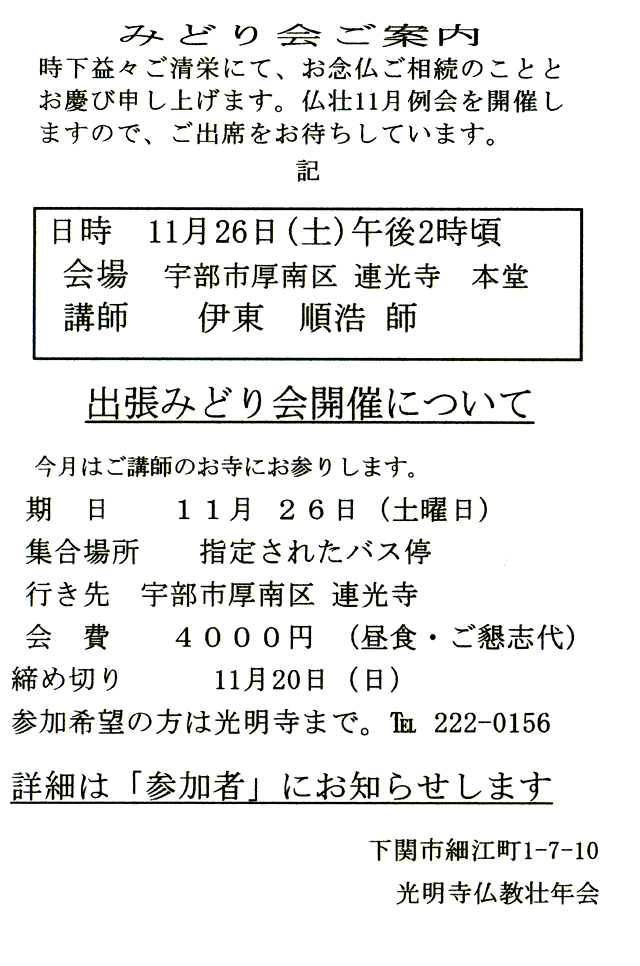
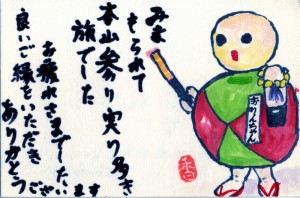
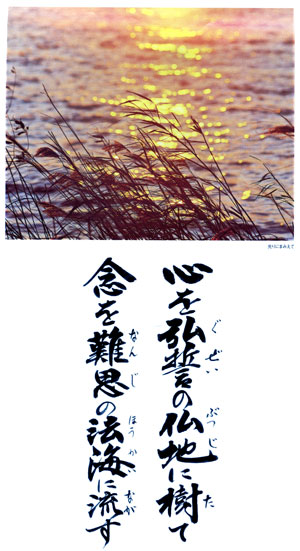 慶ばしいかな
慶ばしいかな
















