このギャラリーには2枚の写真が含まれています。
2011年10月11日から13日までの間、京都・西本願寺へ親鸞聖人750回大遠忌法要へ行って参りました。
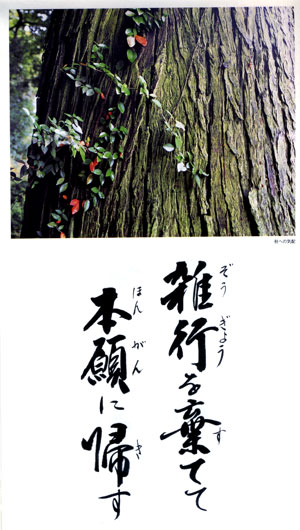 本願に帰す
本願に帰す
九歳での得度出家から二十年間、比叡山においての日々は、この世で覚 りをひらこうとするものですから、言語に絶する厳しいものであったと推 察できますが、親鸞聖人の山での生活の詳細はわかっていません。ただ、 みずからの能力を尽くして学問にうちこみ、もろもろの修行に励んでも、 かえって苦悩は深まるばかりでした。親鸞聖人において、最大の課題は、 妻の恵信尼さまの消息(手紙)に、「生死(しょうじ)出づべき道をば、 ただ一(ひと)すぢに仰せられ候(そうら)ひしを」(『恵信尼消息』『 註釈版聖典』八一一頁)とあるように、生死の迷いから越え出る道を究め ることにあったのです。ところが、比叡山においては、かえって「いづれ の行にても生死をはなるることあるべからざる」(『歎異抄』第三条 『 註釈版聖典』八三四頁)ということを、知らされることになりました。
解決の糸口すら見いだせない苦悶を胸に、訪ねた法然聖人の言葉が、ま さに乾ききった大地に恵みの雨がしみこむようであったことでしょう。こ のことに触れて『御伝鈔』第二段では、
真宗紹隆(しんしゅうしょうりゅう)の大祖聖人(たいそしょうにん)( 源空)、ことに宗の淵源(えんげん)を尽し、教の理致(りち)をきはめ て、これをのべたまふに、たちどころに他力摂生(たりきせっしょう)の 旨趣(しいしゅ)を受得(じゅとく)し、あくまで凡夫直入(ぼんぶじき にゅう)の真心を決定(けつじょう)しましましけり。
(『註釈版聖典』 一〇四四頁)
と、法然聖人に出会うことによって、ただちに他力本願の世界に入られた ようにうかがえます。ところが一方、『恵信尼消息』第一通によりますと 、
法然上人にあひまゐらせて、また六角堂に百日龍らせたまひて候ひけるや うに、また百か日、降るにも照るにも、いかなるたいふにも、まゐりてあ りしに、ただ後世(ごせ)のことは、よき人にもあしきにも、おなじやう に、生死出づべき道をば、ただ一すぢに仰せられ候ひしを、うけたまはり さだめで候ひしかば
(『註釈版聖典』八一一頁)
と書かれています。かつて深い苦悩をもって六角堂に百日間龍られたよう に、また同じ日数を区切って、一途に生死の迷いから越え出る道を求めて 通い続けられたというのですが、このご消息から親鸞聖人の心境がより強 く伝わってきます。
私たちは日々の暮らしのなかで、愛を求め、財を求め、地位を求め続け ています。そして、それらを得るために手段を選ばず、人の心を傷つける ことにもなっています。さらに欲望はとどまることなく拡がっていきます 。もしかなえられないときには、人を怨み、社会をのろい自暴自棄になっ てしまいます。
さて、法然聖人は当時、吉水において、阿弥陀仏のすくいを信じてただ 念仏するばかりであることを説いておられました。そこには、どのような 人をもすべて受け入れる、ちょうどあらゆる河川の水が流れ込む広大な海 にたとえられる、すくいの世界が示されていました。かつて三十年にもお よぶ長いときを比叡山で過ごされた法然聖人には、親鸞聖人の胸のうちが 容易に見通せたことでしょう。師と仰ぐ方からの心温まる説法によって、 親鸞聖人の苦悶はあざやかに解消していきました。そのことを『教行信証 』後序(ごじょ)で、
しかるに愚禿釈(ぐとくしゃく)の鸞(らん)、建仁辛酉(けんにんかの とのとり)の暦、雑行(ぞうぎょう)を棄てて本願に帰す。
(『註釈版聖典』四七二頁)
と記しておられます。これは、親鸞聖人自身にとってはもちろん、私たち にとっての凡夫往生の道が明らかにされたのです。
私たちは、直接に目にできない多くの人びと、さらには気付くことすら できない無数のいのちによって、護られ生かされていることを知らず、し たがって、自覚覚他(自身がめざめるとともに他をもめざめさせる)をこ ころがけるどころか、自害害他(白身が傷つき、他をも傷つけてやまない )の日暮らしを繰り返しています。親鸞聖人は、そのありかたをみずから のこととして「愚禿(ぐとく)」の表現をもって呼び、さらに「煩悩具足 のわれら」と述べておられます。
義なきを義とす
今月の法語の「雑行」について考えてみましょう。中国の唐の時代にで られた善導大師は浄土への往生を願った方で、真宗七高僧の第五番目の方 として仰いでいます。
大師の主著である『観経疏』の「散善義(さんぜんぎ)」に、「正行(し ょうぎょう)」と「雑行(ぞうぎょう)」が説明されています。
まず正行とは、阿弥陀仏の浄土に往生するための純正の行という意味で 、雑行は邪雑の行としています。もちろん善導大師や法然聖人がすすめら れるのは正行で、雑行は誡めておられます。雑行は本来、この世で覚りを ひらくうえでの行である諸善万行をもって、浄土に往生するための行とし て転用するものであるために、このように言うのです。私たちは、なにか 善いことを行って、それを認め讃えてもらって浄土に往生できると考えて いるのではないでしょうか。それは凡夫のはからいであり、かえって阿弥 陀如来の本願を疑うことになってしまいます。
親鸞聖人の言葉が集められている『歎異抄』が、現代の苦悩する人びと に活力を与え続けていますが、そこに、
しかれば、本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、念仏にまさるべき 善なきゆゑに。悪をもおそるべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪 なきゆゑに
(第一条 『註釈版聖典』八三二頁)
と述べられています。自力による諸善万行は、仏教一般において求められ ているところであり、親鸞聖人も比叡山時代を通して取り組まれた難行で ありましたが、それは究極的に覚りにいたることができないものでした。 今ここに、法然聖人との出会いによって「義なきを義とす」他力信心の世 界が開かれたのです。「義なきを義とす」とは、晩年に記された『御消息 』のなかで「自然法爾(じねんほうに)ということについて」においてし めされています。そこを現代語に訳して言えば、
「自然」ということについて、「自」は「おのずから」ということであり 、念仏の行者のはからいによるのではないということです。「然」は「そ のようにあらしめる」という言葉です。「そのようにあらしめる」という のは、行者のはからいによるのではなく、阿弥陀仏の本願によるのですか ら、それを「法爾」というのです。(中略)これは「法の徳」すなわち本 願のはたらきにより、そのようにあらしめるということなのです。人がこ とさらに思いはからうことはまったくないのです。ですから、「自力のは からいがまじらないことを根本の法義とする」と知らなければならないと いうのです。(『親鸞聖人御消息(現代語版)』五六~五七頁)
となります。ここでうかがえるように、「義なきを義とす」とは「自力の はからいがまじらないことを根本の法義とする」ということです。
ところで、前の文中の「法爾」について一言しますと、「法」とはもの みなすべてということです。「爾」とはしかりという字ですから、合わせ ると、ものみなすべてがそうなっているということです。法然聖人の〈つ ねに仰られける御詞(二七条)〉のなかに、
法爾の道理といふ事あり。ほのをはそらにのぼり、水はくだりさまにな がる。菓子のなかに、すき物ありあまき物あり。これらはみな法爾の道理 なり。
(『昭和新修法然上人全集』四九三頁)
があります。すなわち火(ほのを)は燃え上がるものであり、水は下へ下 へと流れていくものである。菓子(この時代は果実、すなわちくだものを 指している)には、酸いものもあれば、甘いものもある。どうしてそうな のかと言えば、結局はそうなっているということになります。それがまた 自然の道理というものなのです。したがって、「本願を信じ念仏を申さば 仏に成る」(『歎異抄』第十二条 『註釈版聖典』八三九頁)ことは法爾 の道理であると言われるのです。『歎異抄』では、前半の第一条から第十条に、門弟の唯円房が直接親鸞聖人から聞いて耳の底に強く残っている法 語を記していますが、とりわけ第一条は法義の要がのべられています。そ の冒頭が「弥陀(みだ)の誓願(せいがん)不思議にたすけられまゐらせ て」(『註釈版聖典』八三一頁)で、阿弥陀如来がなぜ私たちを救ってく ださるのかということは、どれほど頭をめぐらせ、論理をもって説明しよ うとしても不可能であることを力説されるところで、結局そうなっている としか言えないと、素直に受け取ることを勧めておられます。
帰命の心
親鸞聖人が「本願に帰す」と表明される、この「帰」についてさらに詳 細にうかがってみましょう。これについては、『教行信証』の「六字釈」 (南無阿弥陀仏の解釈)をとりあげなければなりません。そこでは、「し かれば、『南無(なも)』の言(ごん)は帰命(きみょう)なり」(行文 類 『註釈版聖典』 一七〇頁)からはじまって、まず「帰」の字と「命 」の字とを分けてしめされるところで、「帰」の字をいくつもの文字をも って解釈されます。
その最初に「至」とあります。この意味は「いたりつく」ということで 、私たちみずからがはからうことをやめて、阿弥陀如来の本願力にいたり つくということです。
次に「帰悦(キエツ)」と表現されます。この悦は喜びを表す文字で、こ こに聖人はカタカナで「ヨリタノム」と読んでおられます。これが浄土真 宗のまことの信心を明かされる大切な言葉で、如来の本願力にまかせきっ たところにめぐまれるやすらぎのすがたが「帰悦」であります。阿弥陀如 来は、力のない者に如来が力となり、本当にあてにできるよりどころを持 たない者に如来が依りどころとなろうと、今はたらいてくださっています 。さらに、聖人は「帰税(キサイ)」と表現されます。税の字は「さい」 と読むときは、やどるという意味で、ここでもカタカナで「ヨリカカル」 と言っておられます。
これらのことより、如来の本願をわが心の宿りとすることになって落ち 着くことになるのです。私たちは宿るところがあって、初めて心にやすら ぎが得られます。阿弥陀如来の本願は、罪悪深重にして煩悩の火がつねに 燃え続けているこの私を救うために、みずからのいのちをかけて誓ってく ださったのですから、如来の慈悲をわが心の宿りとして落ち着くすがたが 「帰税」であり、さきの「帰悦」とともに、私への阿弥陀如来の喚びかけ なのです。
(清岡隆文)
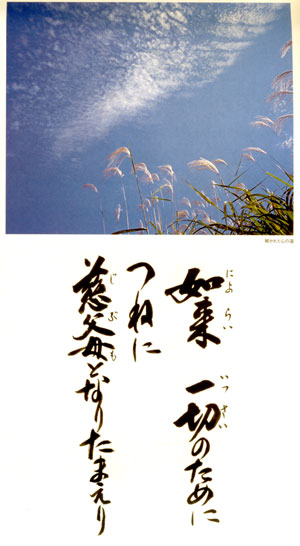 王舎城の悲劇
王舎城の悲劇
今月の法語は、『教行信証』信文類の『涅槃経』の長い長い引用のなかの一文です。
お釈迦さまの最晩年、インドで最も栄えたマガダ国に一大悲劇が起こりました。皇太子である阿闍世(あじゃせ)が、お釈迦さまの弟子の提婆達多(だいばだった)にそそのかされて、父の頻婆娑羅(びんばしゃら)王を殺し、王位を奪ったのです。しかしその後、阿闍世は猛烈な後悔に襲われ、激しく苦しむのです。やがて、お釈迦さまによって阿闍世は救われます。阿闍世は救われた喜びを詩にして、お釈迦さまを讃えます。その詩のなかの一節が、今月の法語です。
そんなわけで、この法語は阿闍世王がお釈迦さまを讃える言葉なのです。
しかし、親鸞聖人は阿闍世王が救われたこの事実を、すべての凡夫のため、すべての五逆罪を犯す者のためのことであり、迷えるすべての衆生の救いを表すものと考えられました。『涅槃経』も、またそのような意味で説かれています。ですから、私たちも今月の法語をそのように味わいたいと思います。
親鸞聖人は、悪縁に遇えば親殺しもしかねない私たちの姿を阿闍世王の上にご覧になり、このような悪人こそ第十八願の救いの目当てであると考えられたのです。この悲劇の展開と救いこそ、釈迦・弥陀の種々の巧みな手だてによる我々の救いに他ならないと、親鸞聖人は考えられました。
『高僧和讃』に、
釈迦(しゃか)・弥陀(みだ)は慈悲の父母(ぶも)
種々(しゅじゅ)に善巧方便(ぜんぎょうほうべん)し
われらが無上の信心を
発起せしめたまひけり(『註釈版聖典』五九一頁)
(お釈迦さまと阿弥陀如来は慈悲においての父母である。様々に真実巧みな手立てをなされ、私たちにこの上もない信心を、起こさせてくださったのである。
北塔光昇著 『聖典セミナー 高僧和讃』二二三頁)
とあり、『浄土和讃』に、
弥陀・釈迦方便して
阿難(あなん)・目連(もくれん)・富楼那(ふるな)・韋提(いだい)
達多(だった)・闍王(じゃおう)・頻婆娑羅(びんばしゃら)
耆婆(ぎば)・月光(がっこう)・行雨等(ぎょううとう)(『註釈版聖典』五七〇頁)
(『観経』『涅槃経』は、阿弥陀如来と釈迦如来が私たちを救う手だてとして説かれた経典である。如来の救いの手だて、方便として浄土から現れてくださった方々は、阿難尊者、目連尊者、富楼那尊者、韋提希夫人、提婆達多、阿闍世王、頻婆娑羅王、耆婆大臣、月光大臣、行雨大臣等である。
黒田覚忍著『聖典セミナー 浄土和讃』二九〇頁)
大聖(だいしょう)おのおのもろともに
凡愚底下(ぼんぐていげ)のつみびとを
逆悪(ぎゃくあく)もらさぬ誓願(せいがん)に
方便引人(ほうべんいんにゅう)せしめけり(『同』)
(韋提希夫人や阿闍世王のほか、阿難や月光、行雨等、王舎城の悲劇に関係した人びとは、本来、皆浄土の大聖者であった。その聖者方がおのおの善人となり悪人となり、王となり妃となり、一緒になって愚かな凡夫、生死の大海の底に沈んでいる悪人を、十悪、五逆の罪人ももらさずお助けくださる第十八願に導き入れてくださった。
『同』二九三頁)
と讃嘆されています。
この王舎城(おうしゃじょう)の悲劇をもとに、『観経』では韋提希夫人の救いが説かれています。経典は異なりますが、ともに凡夫、悪人の救いがテーマです。
慚愧の心
『涅槃経』に説かれる阿闍世の救いで、特に心に留まる言葉が二つあります。一つは、阿闍世は慚愧(ざんぎ)の心をいだいているとあることです。もう一つは、阿闍世が救われたことを無根の信を得たと表現されていることです。
慚愧という言葉は、当時、お釈迦さまの信者で名医と言われた耆婆大臣が、阿闍世の次のような告白に対して言った言葉です。
〈耆婆よ、わたしは今重い病にかかっている。正しく国を治めていた王を非道にも殺害してしまったのである。どのような名医も良薬も呪術も行き届いた看病も、この病を治すことはできない。なぜなら、わたしの父は王として正しく国を治めており、まったく罪はなかったのに、非道にも殺害してしまったからである。(中略)わたしは昔、智慧ある人が次のように教えを説かれるのを聞いた。
《身・口・意の三業が清浄でないなら、この人は必ず地獄に堕ちるのである》
と。わたしもまたそうなるのである。これがどうして安らかに眠ることができようか。どのようにすぐれた医者でも、今のわたしを治すことはできない。病を治す薬となる教えを説いてわたしの苦しみを除くことはできないのである〉と。
(『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』二七五~二七六頁)
という言葉に対して、耆婆大臣は王に、
善いことを仰せになりました。王さまは罪をつくりましたが、深く後悔して慚愧の心をいだいておられます。(中略)今王さまが十分に慚愧の心をいだいておられるのは、実に善いことです。
(『同』二七六~二七七頁)
と、王の深い後悔の心のすばらしいことをほめ、お釈迦さまは必ず王の心の病を治してくださるから、お釈迦さまのもとへ行くように強く勧めます。しかし、王はなかなかためらって決心がつきません。そして王は耆婆に対して、「如来は、わたしのような者にも会ってくださり、心をかけてくだざるのであろうか」と尋ねます。王は、自分の犯した悪業にとらわれて、自分のような者に如来は会ってくださらないだろう、自分のような悪人に心をかけてくださらないだろう、と考えていたのです。
その王に対して、者婆大臣は次のように答えます。
たとえばあるものに七人の子がいたとしましょう。その七人の子の中で一人が病気になれば、親の心は平等でないわけではありませんが、その病気の子にはとくに心をかけるようなものであります。王さま、如来もまたその通りです。あらゆる衆生を平等に見ておられますが、罪あるものにはとくに心をかけてくださるのです。放逸のものに如来は慈しみの心をかけてくださるのであり、(中略)王さま、仏がたはあらゆる衆生に対して、その生れや老若や貧富の違い、また、生まれた日の善し悪しなどを見られるのでもなく、(中略)たとえば王さまのおこされた慚愧の心のように、善の心ある衆生を、ただご覧になるのです。そして、もし善の心があるなら、慈しみの心をかけてくださるのであります。
(『同』二八三~八三四頁)
無根の信
耆婆大臣は、このように仏の慈悲の大きいことを繰り返し繰り返し説きますが、王は過去の罪にとらわれて、自分を責め卑下し、お釈迦さまに会いに行くことをためらいます。しかし、どうにか耆婆に連れられて、お釈迦さまに会いに行くことになりました、この光景は『教行信証』には引用されていませんが、たいへん重要です。概略は次のようです。
二人は、お釈迦さま入滅の地、沙羅双樹のお釈迦さまの所に来ました。そこにたくさんの人が集まっています。そのとき、お釈迦さまは”大王”と呼びかけられました。王は、自分のような罪深い悪人が、「大王」と呼ばれるはずがないと思い、あたりを見まわしました。すると今度は、「阿闍世王」と呼ばれたのです。この言葉を聞いて、王は自分のような者を「大王」と呼んでくださった仏の慈悲を、全身に感じたのです。
「真に如来が、諸(もろもろ)の衆生に於(おい)て、大悲憐愍(れんみん)して、差別無きを知る」(『大般涅槃経』『国訳一切経』涅槃部一・三八八~三八九頁)と言い、お釈迦さまに対するゆるぎない心が生じ、王の過去の罪に対するかたくなな心がとけ、説法を聞くことになります。
こうして、阿闍世に信心の心が開けてくるのです。王は、次のように述べています。
〈世尊、世間では、伊蘭(いらん)の種からは悪臭を放つ伊蘭の樹が生えます。伊蘭の種から芳香を放つ栴檀(せんだん)の樹が生えるのを見たことはありません。わたしは今はじめて伊蘭の種から栴檀の樹が生えるのを見ました。伊蘭の種とはわたしのことであり、栴檀の樹とはわたしの心におこった無根の信であります。無根とは、わたしは今まで如来をあつく敬うこともなく、法宝(ほうぼう)や僧宝(そうぼう)を信じたこともなかったので、それを無根というのであります。世尊、わたしは、もし世尊にお遇い しなかったなら、はかり知れない長い間地獄に堕ちて、限りない苦しみを受けなければならなかったでしょう。わたしは今、仏を見たてまつりました。そこで仏が得られた功徳を見たてまつって、衆生の煩悩を断ち悪い心を破りたいと思います〉と。
(中略)
〈世尊、もしわたしが、間違いなく衆生のさまざまな悪い心を破ることができるなら、わたしは、常に無間地獄にあって、はかり知れない長い間、あらゆる人びとのために苦悩を受けることになっても、それを苦しみとはいたしません〉と。(『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』二九五~二九六頁)
と救われた喜びを述べています。
如来さまからの喚びかけ
今月の法語は、始めにも述べましたが、救われた喜びからお釈迦さまを讃える詩のなかの一説です。長い詩ですが、その中心は「如来一切(にょらいいっさい)のために、つねに慈父母(じぶも)となりたまへり」(『註釈版聖典』二八八頁)です。
如来に救われた喜びから過去をふり返ったとき、仏法から逃げまわっていた自分の姿に気づかされたのです。自分が殺した父が仏のもとに行けと命じても、耆婆がどれほど誘っても、自分の犯した罪にとらわれて仏のもとに行くことができませんでした。仏のもとに赴いたことも、説法を聞く心が起こったことも、私の力ではありませんでした。この罪深い者、自分の犯した罪にとらわれている自分に向かって「大王よ」と呼びかけ、聞く心を起こしてくださったのです。
もっと過去から考えますと、この世に生まれる前から私たちの苦悩の現実をお見通しになって、如来は私を思い続けていてくださったのです。
(黒田覚忍)
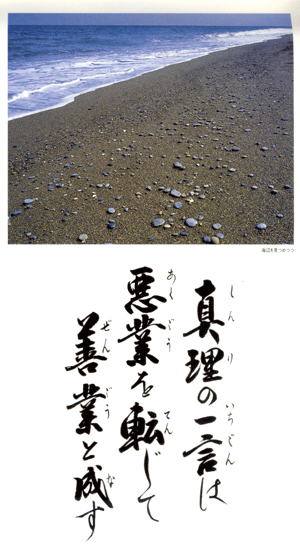 煩悩を断ぜずして涅槃を得
煩悩を断ぜずして涅槃を得
「真理の一言は、悪業を転じて善業と成す」とは、『教行信証』行文類「一乗海釈」の文です。
『楽邦文類』にいはく、「宗暁禅師(しゅうぎょうぜんじ)のいはく、〈還丹(かんたん)の一粒(いちりゅう)は鉄を変じて金と成す。真理の一言は、悪業を転じて善業と成す〉」と。
(『註釈版聖典』一九九頁)
(宗暁が『楽邦文類』にいっている。「還丹という薬はたった一粒で鉄を金に変える。
真実の道理である如来の名号は、悪い行いの罪を転じて善い行いの功徳とする」『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』 一三一頁)
とある文の一節です。
この八月の法語は、七月の法語「煩悩の氷解けて功徳の水となる」と表現は違いますが、同じ内容が述べられているのです。
如来の智慧の眼から見れば、煩悩と覚り、悪業と善業とは、氷と水のように本性は同じで違いはないと、仏教では言います。しかし、悪業と善業、煩悩と覚り、迷いと涅槃とが、本性は同じだといくら聞かされても、私たちはどうしてもそれを覚ることはできません。その智慧のない私たちに、如来の真理の一言である南無阿弥陀仏の名号を与えて、仏の覚りの智慧を与えてくだざるのです。
「正信偈」に、
能発一念喜愛心(のうほついちねんきあいしん) よく一念喜愛の心を発すれば、
不断煩悩得涅槃(ふだんぼんのうとくねはん) 煩悩を断ぜずして涅槃を得るなり。
(『註釈版聖典』二〇三頁)
(信をおこして、阿弥陀仏の救いを喜ぶ人は、自ら煩悩を断ち切らないまま、浄土でさとりを得ることができる。『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』 一四四~一四五頁)
などと、親鸞聖人は讃嘆されています。
聖人のお心を考えるとき、そのもとになっているのは曇鸞大師(どんらんだいし)の教えです。大師は『往生論註(おうじょうろんちゅう))に、
荘厳清浄功徳成就(しょうごんしょうじょうくどくじょうじゅ)とは、偈に「観彼世界相(かんひせかいそう) 勝過三界道(しょうかさんがいどう)」といへるがゆゑなり。
これいかんが不思議なる。几夫人ありて煩悩成就するもまたかの浄土に生ずることを得れば、三界の繋業(けごう)、畢竟(ひっきょう)じて牽(ひ)かず。すなはちこれ煩悩を断ぜずして涅槃分を得。いづくんぞ思議すべきや。
(『註釈版聖典(七祖篇)』 一一一頁)
と述べられています。
曇鸞大師の意は、次のような意味でしょう。天親菩薩は「阿弥陀如来のお浄土を思い見ると、迷いの世界である三界の因果を超え勝れている」と言われている。これがどうして不思議であるかというと、几夫のわれわれは、煩悩づくめの生き方をしているが、このわれわれが浄土に往生できれば、この世界で作った煩悩の行為の果を引くことなく覚りに到ることができるのである。このことをすなわち煩悩を断ぜずして涅槃を得というのである。不思議ではないかということです。
この曇鸞大師の教えを、親鸞聖人は受けつがれました。「真理の一言は、悪業を転じて善業と成す」の「真理の一言」とは、われわれのところに南無阿弥陀仏となってはたらいてくださる阿弥陀如来の名号のはたらきです。その名号のはたらきが、われわれの悪業を転じ変えて覚りと成す。すなわち、われわれに浄土の覚りをあたえてくださるというのです。
また、煩悩の氷解けて功徳の水とならなければ、われわれは苦悩から出ることはできません。我執煩悩のために角を立て他と対立し、苦海を出ることはできません。その煩悩の氷を解かすのはわれわれの力ではなく、阿弥陀如来のわれわれをお救いくださるおはたらきなのです。
われわれの悪業を転じてくださるのも、煩悩の氷を解かしてくださるのも、阿弥陀如来のおはたらきでした。ですから、私たちの側で煩悩を断ずる必要はないのです。いや、断ずる力がわれわれにないからこそ、仏力、他力によって断じてくだざるのです。
信心の利益
自力の仏教では、一般に煩悩を断じて涅槃の真理を悟るという意味で、「断惑証理(だんわくしょうり)」という言葉が用いられます。しかし、他力の教えでは仏力、他力によって覚りに到ると考えるのです。
なお、ここで注意しておきたいのは、「煩悩の氷解けて功徳の水となる」のも「悪業を転じて善業と成す」のも、あるいは「煩悩を断ぜずして涅槃を得る」ということも、すべて浄土で得る利益、すなわち覚りのことです。この世で覚りを得られたら、浄土往生は必要ありません。
「悪業を転じて善業と成す」のも、「(悪業)煩悩の氷とけて(善業)功徳の水となる」のも、ともに浄土に往生してから後に得る利益であるのなら、この世で得る利益はないのでしょうか。
真理の一言である南無阿弥陀仏の名号のはたらきを身に受けている信心の行者は、将来浄土に往生して必ず覚りを開く徳を身にいただいている、正定聚(しょうじょうじゅ)の人です。
正定聚の人がこの世で得る利益は、種々に表現されます。『教行信証』では、信心の行者がこの世で得る利益を十種の観点、側面から表されています。そのなかで、「心光常護(じんこうじょうご)の益(やく)」(『註釈版聖典』二五一頁)に注目したいと思います。心光常護とは、信心の人は常に阿弥陀如来の心光に護られているということです。このことをまた聖人はお手紙に、
真実信心の行人は、摂取不捨(せっしゅふしゃ)のゆえに正定聚の位に住す。
(『親鸞聖人御消息』『註釈版聖典』七三五頁)
とも述べられています。摂取不捨とは、阿弥陀如来の心光に摂取されてお捨てにならないということです。信心の人は、如来の光明のなかに生きる人だとも言われています。信心をいただいた人の人生は、それまでの人生が煩悩海、苦海であったものが、その人の人生すべてを通して、如来の光明のはたらきのなかに生かされていると感じられる人生に変わるのです。
如来の光明のなかに生かされる信心の人は、「転悪成善の益」を得るとも言います。
私の身近な人たちで、よく聴聞なさる方々は、「歳を取るといいことは何もないという人もあるけれども、歳をとったおかげでわからせていただいたことがたくさんある。病気を通しても、体が弱ったことを通しても、気づかせていただくことがたくさんあります。本当におかげさまで有り難いことです」と言われます。
「転悪成善の益」とは、浄土に往生して覚りを開くという意味もあります。しかし、信心の人がこの世で得る利益とも考えたいものです。歳を取ることも、病気になることも、体が弱ることも、いやなことです。一般的には避けたいことです。しかし、避けられないいやなこと、不幸なことが、それはそれとして人生の意味を持つ、あるいは意義が与えられることも、「転悪成善の益」と味わいたいものです。
感謝の生活
私のよく存じあげている、ある篤信の年配女性のことです。娘時代のことですが、その方の言葉によると次のように話されました。
私のお父さんは、お医者さんから治らぬ病と告げられていました。そのとき、私は十八歳で、妹や弟もいました。一番下は小学校三年生でした。私は、お母さんを助けて妹や弟を一人前に育てなければと思っていました。
戦争も激しさを加えていたある日、出征兵士を村はずれまで送って行きました。その日を最後に帰らぬ人となる人も多かったので、日本中、どこでも戦場に向かう兵士を見送ったものでした。
家に帰ってみると、お母さんが土間で倒れていました。お母さんは数日後に亡くなってしまいました。それまで、お父さんが亡くなるとは思っていました。しかし、お母さんが亡くなるとは夢にも思わなかったことです。そのお母さんが亡くなったのです。天と地がひっくり返ったような驚きでした。人間は何をたよりに生きていったらよいのか、そのときの気持ちはうまく言い表すことはできません。そのとき以来、お寺の釣鐘が鳴ると、家にじっとしておれませんでした。私か聴聞を始めたのは十八歳のときからでした。
このように、この方は当時をふり返って申されたことがあります。
この方にとって、お母さんとの別れ、両親との別れという事実に、お念仏の教えに遇うことを通して、新しい意味が与えられたのです。あのお母さんとの別れがあったればこそ、お念仏の教えに遇わせていただいたと、感謝の生活をされています。
最近も八十数年の生涯をふり返って、若いときには乳呑み児を連れおむつを持って聴聞に出かけた。夫もそれを許してくれた。聴聞を続けることができたのは、こんな愚かな者を捨てられないという如来のお慈悲のおかげであったと、喜んでおられます。
両親と若くして別れるという事実はけっしてなくなりません。しかし、如来さまのお力によって、そのような出来事があったればこそと、力強く生きぬくことができるようになるのです。そのことが、この世において悪業を転じて善業と成すという味わいでしょう。
(黒田覚忍)