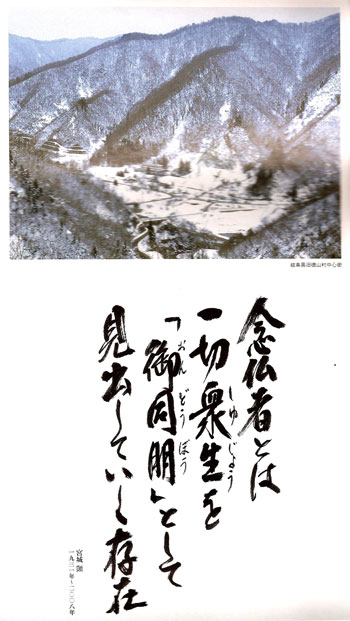 失われたつながり
失われたつながり
私たちは、いろいろなつながりのなかに生きています。関係性のなかに生きていると言っていいのかも知れません。家族のつながり、親子、兄弟、あるいは友だち、また地域、社会とのつながり、さらには自然とのつながりもあります。本当に、多種多様な関係性のなかに生きています。目には見えないけど、複雑に絡み合い、すべてがつながりのなかにあるということに、なかなか気がつきません。それどころか、つながっていることが面倒だからと、つながりを断ち切って、つながっていないことにしてしまっているのではないでしょうか。
どうして、つながりを断ち切っていこうとするのでしょうか。それは、一言で言えば、自分の思いどおりにならないからでしょう。他とのつながりのなかにいれば自分一人の思いどおりにはなりませんし、自分勝手なことはできません。助け合わないと生活できない時には、つながりを切ってしまうわけにはいきませんでした。みんな足りないところを補いながら、支えあってきました。しかし、少し余裕がでて生活が楽になってくると、そのつながりが面倒で、煩わしくさえなってしまうのです。隣近所の付き合いとか親戚付き合いがそうでしょう。それが、家族のなかでさえもそうなってきているところに、問題の深さがあります。
貧しくて生活に余裕のなかった頃に比べると、家族の関係もずいぶん変わってきたのではないでしょうか。いつの間にか、それぞれの部屋を持つようになり、専用のテレビがあり、携帯電話があり、部屋にこもってしまえば、家族であっても何をしているのかわからないというようなことになっています。都合のいい時だけつながり、都合の悪い時はそのつながりを断ちきってしまうことができます。自分の関心だけで、家族さえも見ていこうとしているのではないでしょうか。
悲しいことですが、家族のなかでも思いどおりにならないと、傷つけたり、殺し合うというような事件が、よく報道されるようになりました。一緒に生活していると、考えの違いや意見の対立があるのは当然でしょう。でもそこで、理解しようと努力したり、我慢したり、自分のことを本当に心配してくれていたと気づいたりしてきたはずです。そのことより、家族とのつながりを切り捨ててでも、自分の思いを通すことが強くなったのでしょうか。どこまでも自分の都合のみを守ろうとするのでしょう。自己中心の極みとも言うべきことです。このような極端なことだけではなく、いつの間にか自己中心の生き方というのが目立ってきたように思います。時代の流れのなかで、意識しないまま、煩わしい周りとのつながりを断ってきたのではないでしょうか。
御同朋とは
阿弥陀仏の本願を聞き、念仏申す私たちには、どのような世界がひらかれてくるのでしょうか。生活のなかで出会っていくあらゆる人たちを、自分の都合ではなく、その人として見ていくことができるのでしょうか。親鸞聖人は、お念仏のなかにともに生きる人びとを「同朋」「とも同朋」と言われています。今月の言葉は、宮城顗(しずか)師の著書『本願に生きる』のなかの言葉です。少し前後の文章を含めてご紹介してみます。
「御同朋」という言葉は、実は「一切衆生」、つまり、おおよそ人間をみる眼を言い表している言葉であって、あえていえば、念仏者とは一切衆生を「御同朋」として見出していく存在。念仏者が「御同朋」なのではない。念仏者の集いが「御同朋」なのでもない。念仏者とは一切衆生、一切の人間を「御同朋」として見出していく。そういう心をたまわったものであり、その歩みを開かれたものだというべきではないか。
(『本願に生きる』七七~七八頁)
本願を聞きひらき、念仏に呼びさまされながら生きるもの(念仏者)に開かれてくる世界は、自ずと一切の生きとし生きるものを、ともに生きるものとして見出されるものであることが述べられています。どこまでも、自分の思いや都合でしか周りの人を見ようとしない私に、どのようにしてこのような「御同朋」の世界が開かれてくるのでしょうか。「御同朋」とは、本願に出遇い呼びさまされて、初めて見出されてくる存在です。自分の関心のあるところでしか見ることのできない私か、一切衆生を見出していくことはとてもできません。本願には「十方衆生」と呼びかけられています。
本願が救わずにおれないものとして見出したのが、一切衆生なのです。本願に願われ呼びかけられている存在が私です。
本願に願われている存在、いや願われねばならない存在としての私に出遇う時、一切の衆生をともに願われているものとして受けとめ、見出していくことができるのでしょう。その時に、自分の関心や都合を超えて、一切衆生そのもの、周りの人をその人として見出し、出会っていくことができるのではないでしょうか。人を、物のように自分の都合のいいように利用するのではなく、人を人として見出していく、そこに「御同朋」の世界、人間が人間として生きるということがあるように思います。
人間であること
宮城先生は、多くの著作を遺しておられます。親鸞聖人の生涯を通して、その意味を尋ねるなか、人間の誕生、人間に生まれるということを、深く問われているところがあります。法然門下の先輩である聖覚法印(せいかくほういん)が著された『唯信鈔(ゆいしんしょう)』を書写されるなか、「人間」という言葉に左訓をつけて「ひとゝむ(生)まるゝをいふ」(『定本親鸞聖人全集』第六巻・写伝篇2・四〇頁)と説明してあります。そのことについて、
人間とは、ひととうまれたものをいうのだという左訓は、一見、同語反復のように思えます。しかもそのような左訓を宗祖がわざわざほどこされているということは、逆に、宗祖のご生涯というものが、人と生まれたという、そのことひとつを問いつづけられたご生涯であったということを物語っているとも思えるのであります。つまり、人間とは人と生まれたというその事実を生涯にわたって問いつづけてゆくものだという、そういうひとつのうなずきがそこにはこめられてあるかと思います。
(『宗祖親鸞―生涯とその教え(上)』一七頁)
と述べられています。人に生まれたとはどういうことなのか。人として生きるとはどういうことなのか。人間に生まれたら人間なのか。人間の姿はしているけれども、本当に人間として生きえているのか。さまざまな問いが出てきます。
人間として生きるとはどういうことなのでしょう。親鸞聖人は『涅槃経』の言葉を引いて、
無慚愧(むざんぎ)は名づけて人とせず、名づけて畜生とす。慚愧あるがゆゑに、すなはちよく父母・師長を恭敬(くぎょう)す。慚愧あるがゆえに、父母・兄弟・姉妹あることを説く。
(『註釈版聖典』二七五頁)
と示されます。自らを恥じることのないものは人とは言わないのです。それはあさましい生きものと言われる畜生と言うべきでしょう。いや慚愧という自らを恥じるところにこそ、目上の人を敬うことが出てくるし、恥じるということがあるから、父母とか兄弟というような本当の人間関係が生まれてくる。形だけは親子であったり、夫婦であったりするけれど、本当の親子、夫婦という関係性は、ただ自分の言いたいことだけを主張しているところにはありません。自らの自己中心性を恥じ、愚かさを、汚さを恥じるところにしか、本当の人と人とのつながりはないということでしょう。人間であることの証しを、人と人とのつながり、関係性の上に見ていかれたものとすることができるでしょう。何とも思わずに自分の都合でしか人を見ていなかったことに気づき、慚愧し、痛みとなり、悲しみとなっていくところに、人と人とのつながりが回復されていくに違いありません。
本願のまなざし
法然聖人は、阿弥陀さまが本願にお念仏ひとつを選ばれたことを、次のように示しておられます。
しかればすなはち弥陀如来、法蔵比丘(ほうぞうびく)の昔平等の慈悲に催されて、あまねく一切を摂せんがために、造像起塔等(ぞうぞうきとうとう)の諸行をもって往生の本願となしたまはず。
ただ称名念仏一行をもってその本願となしたまへり。(『選択集』『註釈版聖典(七祖篇)』 一二〇九~一二一○頁)
一切の生きとし生くるものを救いとるために、私たち人間の持っているすべての価値を超えたお念仏ひとつを選び取られたのです。そこには、「造像起塔」といった、財産のある者が仏像を造り、仏塔を起てて寄進して善を積むというような、私たち人間の持っている能力や価値を、一切排して見られたまなざしがあります。お金があるとか、才能があるとか、学問があるとか、立派な生活ができるとか、いのちの後からついてきたもので一切衆生を見られたのではありません。そういうものを、救うか救わないかの基準にはされなかったのです。
私たちは、どこまでも自分の関心によって、もっと言えば、煩悩という自分中心の欲を満たそうとする思いによって、周囲の人と関わりを持とうとしているのではないでしょうか。そうすると、その人のいのちそのものと出遇っているのではなく、後から付いてきた、表面的なものと出合っているに過ぎないことになってしまいます。私たちの人を見るまなざしはそのようなものですから、自分の思いにかなっている時はいいのですが、そうでなくなると、いつでも切り捨て見捨てることになってしまいます。そうして、つながりを断ちきっていくことになるのです。
本願のまなざしに触れることによって、小さな私の思いでしか人を人として見ることができなかったばかりか、人に嫌な思いをさせ、人を踏みつけにしてきたことに、気づかされるのではないでしょうか。それが、悲しみとなり痛みとなっていく時に、一切の存在を「御同朋」として見出し、ともに生きるということがあるように思います。
(後藤明信)
















