たまわりたる信心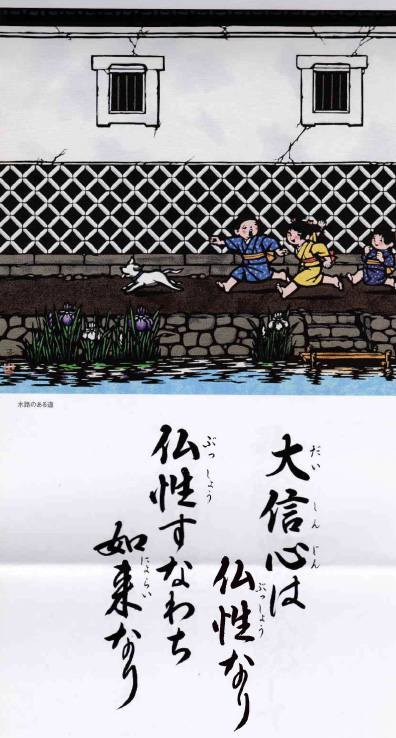
浄土真宗のみ教えで一番大切なことは「信心」であるといえます。蓮如上人の「御文章」に、
聖人(しょうにん)(親鸞)一流(いちりゅう)の御勧化(ごかんけ)のおもむきは、信心(しんじん)をもって本(ほん)とせられ候(そうろ)ふ
(五帖目第十通、「『註釈版聖典』一一九六頁」
とある通りです。
ですが、一番わかりにくいというか、合点がいきにくいのも浄土真宗の信心であるといえるかもしれません。
信心」という言葉を辞書で調べてみると、「神仏を信仰して祈念すること。また、その心」(「広辞苑」)とあります。神仏を信じるのですから、主語は衆生、つまり私です。ところがその説明には、次のように追加されるものがたくさんあります。
親鸞は(中略)信心は如来から与えられるものと考え、独特の理解を示した。
(『岩波仏教辞典』五七三頁)親鸞は(中略)本願力回向の信心を明らかにした。(『浄土真宗辞典』三九六頁)
どの宗教も信心を語らないものはありません。何をどのように信じるのか、そこにそれぞれの宗教の特徴があらわれているといえます、そのような中、辞書で特に追加の説明がなされているように、浄上真宗の信心を理解することは簡単ではないようです。
今月のことばは、親鸞聖人の『浄土和讃』の中、『諸経讃』と呼ばれる一首です。さまざまな経典の言葉を通して阿弥陀さまと浄ヒの功徳を讃嘆するもので、この一節では信心について示されています。
はじめに「大信心は仏性なり(大いなる信心は仏性である)」とあります。信心とは私が信じるのであって、私の心のことをいうのだとすると、そこに大の字がついて大いなる信心と表現されるのはおかしいのではないでしょうか。親鸞聖人が、自分の心をそのように立派なものとお示しになるとは、考えにくいように思います。
親鸞聖人は、私の心、すなわち凡夫のはからいによる思いがいかにたよりにならないものであるかを、明らかにしてくださいました。この私が信じるとか、信じないとかいった場合、いくら言葉を尽くして信じているといっても、あるいは確固たる信念で信じ続けるなどといっても、自分の考えで信じている以上、都合が悪くなると信じなくなってしまいます。
親鸞聖人がお示しになった信心とは、他力の信心です。阿弥陀さまから与えられる、たまわりたる信心のことです。阿弥陀さまから回向されるので大信心(大いなる信心)といえるのであり、金剛心や一心ともあらわされるのです。
阿弥陀さまは、たよりにならない私の心を自分で何とかせよとおっしゃるのではありません。私たち衆生が煩悩を身にそなえた凡人であることをはじめから知っておられて、救わずにおかないと大いなる慈悲の心で本願をおこされたのでした。
まことの心
阿弥陀さまの本願は、「仏説無最寿経」に説かれる四十八願の中、第十八願として誓われています。そこには信心について、「至心信楽(ししんしんぎょう)してわが国(くに)に生(しょう)ぜんと欲(おも)ひ(欲生我国)(よくしょうがこく)(『註釈版聖典』一八項)とあります。心から信じて仏の国(お浄土)に生まれたいと願う、それが信心であるというのです。
至心とはまことの心、信楽とはとは信じ喜ぶ心、欲生とはお浄土に往生しようと思う心のことです。一見すると、この信心は主語か私で、私かどのように信じるのか、その私の信じ方を示しているように見えます。
ですが、先はども申しましたように、私の中にまことの心や確固たる信念を求めることは難しいものです。お浄土よりも迷いの世界である今の生活に執着する思いがとても強く、救いを信じ喜ぶ心もおこりません。
喜ぶべきことを喜べない私、まことの心をもつことができない私を、阿弥陀さまはすべて見抜いたうえで、そんな私を救わずにおかないと他力の悲願をおこされたのです。
まことの心を持てるようになったら救おう、仏のさとりに近づいてきたなら迎え入れようというのでは、いつまでも闇の中で立ちすくんでいなければならなかった私です。そのような私の姿を自身の悲しみとし、願わずにおれなかった阿弥陀さまのやるせない思いが、本願でありました。
阿弥陀さまは、私たち衆生にかわって真実の心(至心)をおこし、この私を往生させようと願い(欲生)、救いとることに疑いのない心(信楽)を完成されました。その願いを南無阿弥陀仏の六字に込めて、私たちに与えてくださっているのです。
他力の信心とは、南無阿弥陀仏に込められた仏の願いが私の心に入り満ちてくださっとところに成り立ちます。
阿弥陀さまが「われに任せよ、わが名を称えよ、必ず浄土に生まれさせよう」と願われた心が私に届き、「そうですか、お任せいたします」と受けとめていくところに、他力の信心をたまわるのです。
言葉は人を育てる
私の勤めている相愛大学には、『日々の糧(かて)』という法語を収めた小さな冊子があります。それを毎週木曜日の昼休み、礼拝の時間に学生のみなさんと拝読しています。
その法語に次のようなものがあります。
言葉は心のあらわれ。心が荒れると乱れた言葉、心が豊かだと美しい言葉となる。見えない心も、言葉で見える。
この冊子は、もともと高校生や中学生に拝読してもらうように編集されました。ある卒業生は、礼拝の時間に拝読した法語が、その後の人生の節目に思い出されることがある、そのようにおっしゃっています。難しい言葉や宗教の専門用語は用いられず、日々の生活の中でさまざまに示唆を与えてくれる言葉の数々が載せられています。
自分の心や他者の心、人の心は本当に見えにくいものです。見えないことから誤解も生まれ、苦しくつらい思いをせねばならないことがあります。だからこそ、田心いやりを忘れてはならないし、人の思いが垣問見えた時には大切にしたいものです。
口をついて出てくる言葉は、人を傷つけることもあれば、人を救う言葉となることもあります。言葉は心のあらわれであり、見えない心を伝えてくれます。
一方で、言葉には限界があります。言葉にした時点で、実際の思いとはかけ離れていってしまう特徴をもちます。言葉が一人歩さして、思いもよらない事態になることもしばしば見受けられます。
煩悩にまみれた私の心から発せられる言葉には、まことを見出すことは難しいといえるでしょう。真実の言葉にふれてこそ、真実に気付かされるのです。
ふだんから美しい言葉に接していると、その言葉に育てられ、自然と美しい立ち居振る舞いが身に付いてきます。そういえば、食事の時に申している「食前のことば」「食後のことば」を通して、おかげを感じご恩を喜ぶありがたさに気付かされます。そして、手を合わすことによって、たくさんのいのちをいただいて生かされているわが身であることに思いを致すことができるのです。
『歎異抄』の有名な言葉が思い出されます。
煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)、火宅無常(かたくむじょう)の世界は、よろづのこと、みなもってそらごとたはごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておはします
(『註釈版聖典』八五三~八五四頁)
(わたしどもはあらゆる煩悩をそなえた凡夫であり、この世は燃えさかる家のようにたちまちに移り変る世界であって、すべてはむなしくいつわりで、真実といえるものは何一つない。その中にあって、ただ念仏だけが真実なのである『歎異抄(現代語版)』五〇頁)
真実の言葉である南無阿弥陀仏によって私の姿に気付かされ、仏とともに歩む人生へと導かれるのです。
願いが届いたところ
毎年一月に行われる大学入試センター試験で、感慨深い出来事にふれさせていただきました。
私の勤めている学校も試験会場となり、監督業務に携わらせていただきました。二百人ほどが入れる大きな教室に、間隔を空けて五十人が座って受験していました。私の受け持ちの列があって、前から順に問題冊子や解答用紙を配布いたします。その中、私か配布物を置いたり解答用紙を回収したりする、そのたびに必ず小さな声で、「ありがとうございます」とおっしゃる受験生がいました。シーンと静まりかえった教室ですので、その女の子の声は聞こえるか聞こえないかの小さな声でした。ですが、必ず何をした時も「ありがとうございます」とおっしゃるのです。
いつの間にか、私もその受験生の所に来ると、動作の時に少しだけ頭が下がってしまいます。もとより偉そうに行っていたつもりはありませんが、知らず知らずのうちに「こちらこそ」、あるいは「どうぞ」。そして「がんばってください」。私か声に出して言うことはありませんでしたが、そのような思いで頭を下げずにおれませんでした。
現代的な感覚でいうなら、そう言ったからといって試験に合格するわけではない。言っても何か得するわけではない。そんな時間があったら英単語の一つでも覚えたほうがマシ、そのようにいう人もあるかもしれません。
それでも、一言の「ありがとうございます」が、人の動きを変える力をもっていたのです。その方の言葉は私の心の底に、体の中に入り満ちたのです。
そして、その方はなぜこのように、「ありがとうございます」と言うようになったのだろうかと考えた時、想像でしかありませんが、その方がこれまでにかかわってきたたくさんの方々の願いが、そこにあるのではないかと思うのです。感謝することを忘れないでほしい、損得勘定や効率的・合理的な考えだけではない、恩を知る人になってほしいという願いをかけて接してこられたのではないだろうか。その方のことを大切に思っている人の願いが、その方の心の底、体の中に入り満ちて、「ありがとうございます」という言葉となってあらわれていたのではないか、そのように感じさせていただく出遇いでした。
阿弥陀さまの願いにふれ、まことの心をいただいて、お浄土を見据えた人生を歩ませていただくのです。それが大いなる信心をたまわり、如来とともに歩む念仏者としての心強い人生となるのです。
(佐々木隆晃)
















