はじめに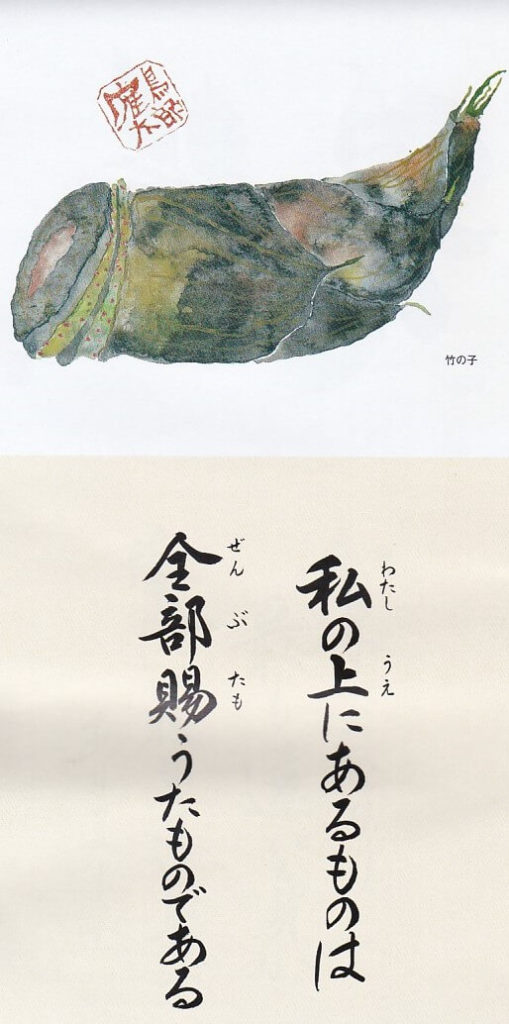
今月のことばは、細川巌師の言葉です。師は、一九一九(大正八)年に福岡県に生まれ、広島文理大学(現広島大学)化学科に進学。卒業後に、広島師範学校(現広島大学)、福岡師範学校(後の福岡学芸大学、現福岡教育大学)、東京水産大学などで教育と研究に携わり、一九九六(平成八)年にご往生されました。専門は「分析化学・地球化学」で、「浅海底土の化学的研究」で東京大学の理学博士号を取得されています。
端的に言えば、河川や海の土壌の研究をされた「科学者(化学者)」です。その一方で、戦後の福岡に帰ってからは、福岡学芸大学内で仏教、特に親鸞聖人の教えの勉強会を主催し、さらに座談会などで来聴者との質疑応答を大切にしつつ、自らの仏教理解を深めていかれたそうです。そのような会を通して、多くの方々に影響を与えられたことでも知られています。
たとえば、私と郷里が同じ田畑正久(元龍谷大学大学院実践真宗学教授・宇佐市佐藤第二病院院長)先生は、九州大学医学部時代に師の主催する勉強会で仏法に触れることになったそうです。私は、田畑先生を通して師の書籍をたくさんいただきました……恥ずかしながら、ボチボチとしか読めていません……。師の生涯については、二〇〇〇(平成十二)年四月十三日放送のNHKラジオ「宗教の時間」でテーマ「自力を尽くした果てに見えてくる愚かな者の救いの道」の中で触れられています。この「愚かな者」とは師ご自身のことを意図しています。
仏法との出遇い-不思議なご縁-
さて、師は今風に言えば理系でしたが、仏教に触れたのは進学した広島文理大学で金子大築先生の講義を聴講したのが最初でした。また、在学中に二十名ほどの学生を指導する立場となり彼らと共同生活を始めますが、その場所が郊外の真宗関係の会館であったことが浄土真宗の教えを聴聞する機会となりました。毎日の生活の中で、会館関係者に「希望者は朝の勤行に出てもよい」と言われたそうですが、最初は誰も出なかったそうです。しかし、間借りの体裁を繕う気持ちで出るようになり、朝の勤行が聴聞の最初の縁となるのです。当初は仏教の知識がなかったので法話の内容がわかりづらいところもありましたが、「真実のみが末通る」など、学生にもわかり易い表現を使ったお話を聞いているうちに、興味が湧いてきたといいます。
やがて初めての「報恩講」を迎え、一週間の法座に皆勤しかことが大きな仏縁になったそうです。そこでの同行さん(念仏者)と寝食を共にする中で、「人として生きること」についてさまざまな気付きと影響を受けられました。
しかし、最初の一年間にあった聴聞ごとの感動も、二、三年と経つと薄れてきたそうです。ある時、ご講師にその思いをぶつけると、そのご講師は『歎異抄』の、
念仏申し候へども、踊躍歓喜のこころおろそかに候ふこと、・……(以下略)
(『註釈版聖典』八三六頁)
云々という「唯円房の問い」こそが「あなたの問いそのものです」と指摘され、その問いは「すぐに解決しようとせずに、一生それを背負って、続けて聞いていきなさい」と諭されたそうです。その言葉が縁となり、広島在住の時代には、島根や山口へ時間を作ってば何度も聴聞に出向き、繰り返し同じご講師の法話を聴聞されたそうです。
求道の姿勢とは
戦前・戦中・戦後の激動期を生き抜かれた多くの方が体験しかように、師も世間的な価値観の激変に悩まれたのでしょう。そこに、普遍的で変わることのない「真実というものがあるのか」という問いが生まれてきたのです。そのような中で、学生時代に縁のあった『歎異抄』の親鸞聖人の言葉を聞いていくことになるのです。
しかし、専門が化学という理系であったためか、他人が言っていることでも、自分がわからないことや実証できないことを受け入れることは難しかったそうです。化学(理系)の確信とは、「自分」を横に置いて、実験で実証できるとおりで間違いないと確認していく営みです。一方、仏法の教えは、その理解し確信する自分、すなわち「私」を問題にします。たとえば、家庭や学校・社会の中で、教えられたとおりに実行できればよいのですが、理屈はわかっていても、それが実行できない「私」がいるのです。師は、否応なく、そんな「私」の姿を見つめることになり、苦悩し続けられました。
このように客観的に「もの」を観察していた科学者が、観察している「自分」を見つめることの大切さに目覚めるという出来事は、ままあることのようです。私の読んだ『科学者の説く仏教とその哲学』(学会出版センター・一九九二年)の著者である泉美治先生(武田化学薬品株式会社勤務を経て大阪大学教授や蛋白質研究所長などを歴任)も、その一人だと思います。そんな方々の言葉を読むと、漠然と日暮らししている自分自身の至らなさやいい加減さ、そして傲慢さを痛感させられます。
「七仏通戒偶」とその逸話
「仏法という教えは何か」、それを一言で説明することは難しいですが、『法句経』などに伝えられる偶文があります。それは「七仏通戒偶」と呼ばれる、
諸悪莫作(しょあくまくさ) 衆善奉行(しゅぜんぶぎょう)
自浄其意(じじょうごい) 是諸仏教(ぜしょぶっきょう)
というものです。端的に言えば、「すべての悪を作らないようにしましょう。できるだけ多くの善を行いましょう。そうすると、自分自身のこころは浄くなります。これが諸々の仏さまの教えです」ということです。
この掲文には種々の逸話がありますが、その一つは次のようなものです。中国唐代の詩人である白居易(白楽天)は禅を愛好していました。ある時、鳥衆道林という禅僧に「仏教とは何か」と質問したところ、禅師が先の偶文で答えたのです。そこで、白居易は「そんなことは三歳の子どもでも知っている」と言ったのに対して、その禅僧が「確かに三歳の子どもでも知っていよう。しかし、自分は五十年あまり仏法の教えに依って生きようと心がけているが、今まで一日たりともできたことがない」と応えたのです。この問答は史実とは認められていませんが、「仏教(仏法)とは何か」を象徴的に示す逸話として大切にされています。この逸話によって、より善く生きようとする「私」自身を見つめることの重要性と、まさに今を生きている「私」自身を見失いがちであることに、改めて気付かされます。
先人達のご苦労に感謝する
私たち凡夫は、自分の周りの「人」も「物」も自己中心的な眼で観察し、比較して理解しています。それも、一人ひとり一つひとつを唯一無二のものと見ることができず、漠然とした表面的な因果関係でもって、自分にとって「役にたつか否か、必要であるか否か」という功利的なご都合主義で見ています。そのような利己的な視点では、本当に大切なものを見落としてしまい、感謝の慶びを失っていきます。
さて、「私」たちは「知識がある」とか「知識がない」とか言います。この「知識」という言葉は仏教に由来する語で、本来「先生」を意味します。たとえば、「私には多くの知識がある」という場合、それは困った時に教導してくれる「先生」が多いという意味です。私たちは生まれてから種々のことを学び知識を得ますが、そこには必ず「先生」がいました。ノーベル賞に値するような業績を残しか方々も、その分野の先人たちが研究し続けた成果の上に積み上げた業績が評価された受賞なのです。その成果をもたらした先人やその成果が「知識」なのです。翻って、その成果を知っていることが「知識」と転用されるようになったのです。「自分には知識がある」という場合、それは自らが学び修得したものですが、それを伝えてくださった方々のご苦労に感謝することが大切です。しかし多くの場合、感謝すらなく、傲慢にも「自分には知識がある」と威張ってしまうのです。
「知徳報恩」の世界
一般には、「ありかとうと感謝の気持ちを大切に生きていきましょう」といわれます。考えてみると、そんなことは三歳の子どもでも知っていますが、皆さんはできていますか。恐ろしいことに、大人になればなるほどできていないのではないでしょうか。「人間は一人では生きていけない」と言いながら、誰の世話にもなりたくないと思っていませんか。また、毎日の生活を支える知力も体力も自分一人で得たものだと傲慢にも思っていませんか。そこには真の意味での感謝も慶びもありません。
親鸞聖人が詠まれた『正像末和讃』の一つに「恩徳讃」があります。
如来大悲の恩徳は
身を粉にしても報ずべし師主知識の恩徳も
ほねをくだきても謝すべし (『註釈版聖典』六一〇頁)
「如来大悲」とは、「南無阿弥陀仏」の親心のことであり、この煩悩具足の「私」のいのちを見放すことなく照らし続ける阿弥陀さまの智慧と慈悲です。「師主」とは、先生の中の先生で、その「智慧と慈悲(南無阿弥陀仏の功徳)」を私たちに説き示してくださったお釈迦さまのことです。「知識」とは、その「南無阿弥陀仏」の親心を解きほぐして伝えてくだった方犬特に浄上教伝統における七人の先生(七高僧)と、その方々が残してくださった成果(書物)を意味します。親鸞聖人の「恩徳讃」は、それらのはたらきに対する、自らの「知徳報恩」の言葉なのです。
私は、今月のことば「私の上にあるものは全部賜うたものである」をその「知徳報恩」に通じる言葉として味わっています。
(内藤 昭文)
















