上山大峻先生の生涯
三月のことばは「平等への視座ー対談・歴史的課題と教団ー』(本願寺出版社)に出てくる上山大峻先生のお言葉です。
上山先生は一九三四(昭和九)年に、山口県長門市にある浄土真宗本願寺派浄泉寺にてお生まれになりました。一九六二 (昭和三十七)年に龍谷大学大学院を単位修得退学された後、本願寺派宗学院で研鑽。その後、龍谷大学に奉職され、三十七年間にわたって仏教学を中心とした教育研究に従事されました。その間には海泉寺住職としてご門徒をご教化いただく傍ら、大学の要職を歴任され、一九九九(平成+一)年には学長として大学運営にもご尽力なさっています。また先生は大学を退官後も、宗派の教学伝道センター所長や筑紫女学園大学学長などの重責を担い、宗門内外に多大な貢献をなされました。
このように数多くのご功績を残された上山先生でしたが、二〇二二(令和四)年十二月十九日、ご家族が看取られる中で、眠るように静かなご往生を迎えられました。御年八十九歳のことでした。
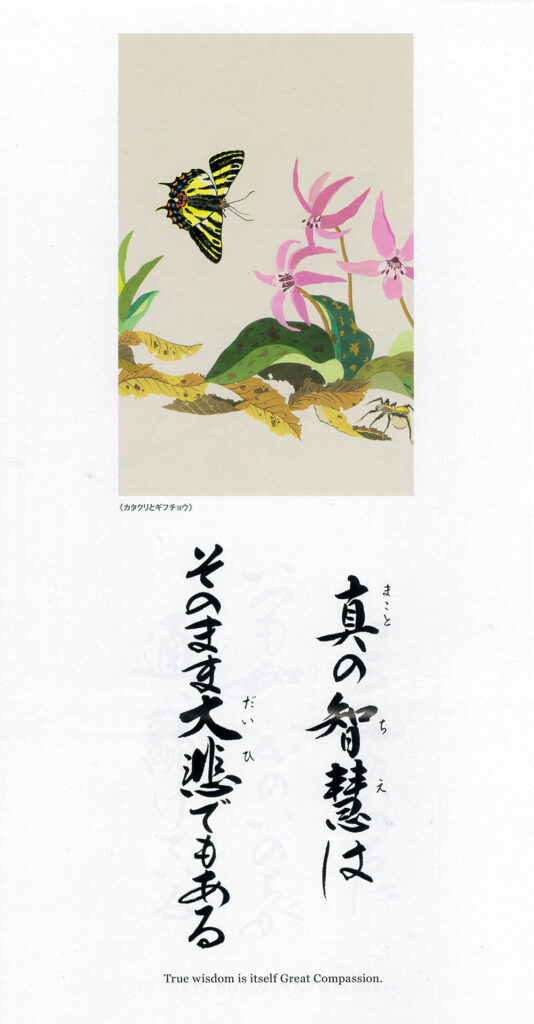
ことばの背景
先ず、この言葉の意味を知るために、言葉が出てきた背景を紹介します。この書物は副題が表すように、上山先生自らがご執筆されたものではなく、お二人の先生による対談を書籍化されたものです。対談のお相手は、元教学伝道センター所長であり、本願寺派勧学(真宗教学の最高学階)の梯實園先生(一九二七ー二〇一四)です。もう少し詳しくいえば、対談という体裁を用いてありますがその中身は、上山先生による梯先生へのインタビュー的な色彩が強い内容です。
以上のようなことから、三月の法語は、両者の間に通底するお考えを、上山先生が確認された言葉だと受け取った方がいいでしょう。また、この対談が企画された理由については、この本の前書きに簡潔に記載がありますが、その要点は次の通りです。
(前略)差別や戦争を容認し肯定してきた教学(み教えの受け取り方>の問題として、その枠組み全体を現代の視座から見直し、克服していく必要が生じました。さらには、むしろより積極的に「差別・被差別からの解放」をめざす教学を、また、戦争に協力してきたあり方を見直し、「平和を創造する教学」として、「御同朋の願いに応える教学(御同期の教学)」をたずねる必然性が出てきたのです ※<>内著者追加(同署十頁)
さて、この対談の企画意図が前述した通りであるため、その内容は書籍全体を通して、「真宗を学ぶ者へ新しい示唆を与える」ことを意識した内容となっています。
このような書籍作成の経緯を十分考慮しながら、今月の法語の意味を訪ねてみたいと思います。
智慧と大悲
法語の言葉は「真の智慧は、そのまま大悲でもある」ですが、ここでいわれる智
慧とは智(仏さまの智慧)のことです。また大悲とは、阿弥陀仏の惣悲心を略した言葉です。思徳識に出てくる言葉なので、ご存知の方も多いと思います。さて、この智慧と慈悲の関係について、対談では次のように語られています。
(真実の智慧の無い)私どもは、いつも自己中心的に物事を考え、自分の都合を相手に投影して、いいとか悪いとかと騒いでいますが、要するに自分の心の影に踊らされているのでしょうね。私どもの本当の「いのち」は、私の妄念の手垢の付かない向こう側に厳然と輝いているのでしょうが、残念ながらそれを妄念が隠してしまっているわけでしょう。(同書四五頁)
つまり、私の煩悩が自分を中心とした世界を作り上げ、自分と他人を区別して、本当のいのちの輝きや尊さを見えなくしてしまっているといわれるのです。自分の都合によって「いい人」「悪い人」「役に立つ人」「立たない人」などと勝手に作り上げ、愛欲と憎悪を繰り返しながら毎日を生きているのです。親鸞聖人はご自身のこととして
無明煩悩が激しくおこり、数限りない塵のように満ちわたっている。ほしいままに愛着や憎悪をいだくありさまは、まるでそびえ立つ高い峰や缶のようである。(「正像末和護』「三帖和議(現代語版)」一七)
と述懐なさっています。山の峰が高ければ高いほど、その谷底は深くなっていきます。このように、愛が深ければ深いほど、裏切られたときの憎悪は大きく、激しい炎となって自他のいのちを焦がしてゆくのです。これを虚不実の「わが身」だと嘆かれました。
真の智慧とは
このように、無明であるが故に、自分の妄念(分別心)によって描き出した世界を真実だと思い込み、そこに捕らわれながら日々の生活を繰り返している、私たちの悲しい姿があります。
しかし、そのような生死(迷い)の苦海に浮き沈みする私を呼び覚まし、真実に向かわせるはたらきこそが、真の智慧であるとおっしゃるのです。また、その智慧は必ず大悲心となって私のいのちに顕現してくださるのだとおっしゃっています。そのことについて
慈悲の慈とは(語の)マイトリの訳語であり、悲とはカルナの訳語だそうですね。マイトリは純粋な友愛、相手の幸せを心から願うことをいい、カルナは相手の悲しみをわがことのように痛む心ですから、要するに痛みの共感です。
とりわけ人の痛みを自らのこととして共感し響く心、これが仏教の本体なのでしょうね。その根底には、自他の隔てを超えた自他一如といわれるような智慧の領域、すなわちまことの「いのち」の領域が拡がっています。(同者四五頁)
と語られ、また、その智慧の領域は必ず「平等の大悲」としてはたらくのだともおっしゃっています。
平等とは
私たちは「平等」という言葉を何気なく使っていますが、よく考えるとこれはなかなか難しいことです。何故なら条件によって人間の平等は変わってくるからです。
例えば、ここにさまざまな人たちがいて、その人たちに「同じ量のパンを一人に一つずつ配分」すれば、これは確かに平等です。しかし、そこに「お腹を満たす」という条件が加わると、まったく平等ではなくなってしまうのです。赤ちゃんはそのままでは食べることはできないし、大食漢の人にとっては腹の足しにもならないでしょう。もともと平等の平とは秤(はかり)という意味だそうです。対談ではそのことについて、ジャータカ(お釈迦さまの前生譚)を引用してお話しされています。
飢えた鷹に追いつめられた鳩が、救いを求めてシビ王の懐へ飛び込んできました。そこで、シビ王は鳩を助けるために、鳩と同じ分量の自分の肉を鷹に与えて、(鳩と鷹の)両方を生かしていこうとします。しかし、シビ王が鳩と同じ分量の肉と思ってわが身から切り取って提供した肉も、天秤ばかりにかけますと鳩の方が重くて、釣り合いが取れません。そこで(最終的には)鳩を片方の秤皿に載せ、片方の秤皿にシビ王自身が乗ると、初めて秤は水平になり、重さが等しくなったという説話です。
そこでは、鳩の重さもシビ王の重さも鷹の重さもまったく等しいというのですから、その重さは物理的な重量ではなくて、「いのち」の重さを意味していたことは明らかです。(中略)仏教徒が「いのち」を考えるときには、常にこのシビ王のジャータカを思い起こして考えていったのでした。仏界とは「いのち」の重さが平等であるような領域なのです。(同善四〇頁)
真の智慧は、そのまま大悲である
阿弥陀仏が浄土を建立し、私を喚び続け、喚び覚まして、念仏の楽生へと成し遂げなければならない道理はここにあったのです。そのお心を親鸞聖人は、
阿弥陀仏が願いをおこされたおこころを尋ねてみると、苦しみ悩むあらゆるものを見捨てることができず、何よりも回向を第一として大いなる慈悲の心を成就されたのである。(「正像末和護』「三帖和議(現代語版)」一五二頁)
と詠われています。「回向を第一」というのは「仏さまが先手であった」ということです。私から拝まれるべき対象であった阿弥陀仏が、私を拝んでくださる、私の人生の主人公へと転じられたのです。これを回心といいます。
このような浄土からの智慧の念仏に喚び覚まされ、大悲のお心を信知させられたとき、絶対的に愚かなる私が、真実なる大悲の浄土を慕う私に育てられていくのです。
(田中 信勝)
















