救いの助縁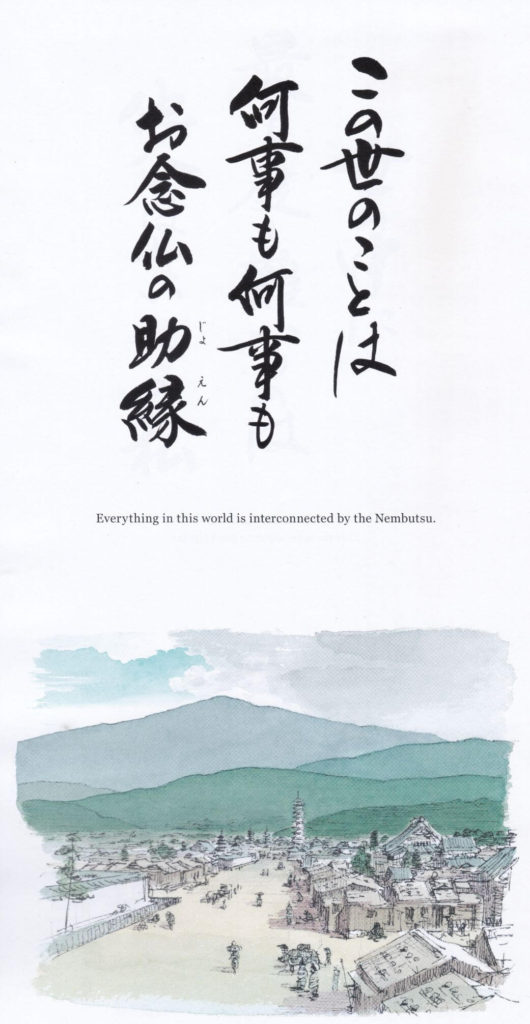
一月は、元龍谷大学学長の信楽峻麿先生(一九二六-二○一四)の「この世のことは、何事も何事も、お念仏の助縁」という言葉です。先生は、現在の広島県東広島市の浄土真宗本願寺派教円寺にお生まれになり、龍谷大学文学部、文学研究科と進まれました。一九五八(昭和三十三)年四月に龍谷大学文学部に奉職し、さらに真宗学ひとすじに研究と教育の歩みを進めていかれ、多くの研究成果を残し、有為な人材を育成されました。先生は、真宗教学の現代化と国際化に取り組まれつつ、臓器移植問題など、社会の諸問題に対しても積極的に発言、行動され、そのなかで常々に浄土真宗は「めざめの宗教」であり、信心とは「智慧を得ること」であることを、教えてくださいました。
一九九五(平成七)年に定年退職されて後には仏教伝道協会理事長として、国内外における仏教伝道活動に尽力されました。すでに大学ご在職中から浄土真宗本願
寺派の海外開教区の別院や寺院を幾度も訪問し、開教使や門信徒の要請に応じて親鸞聖人のみ教えの本義を語られました。先生は、真宗の教義が世界に通用するためには、大乗仏教の原理に立ち返りながら語ることが大事であることを強調されていました。そのことは、そのまま今の日本において、私たちが浄土真宗のみ教えを学び、お念仏の生活を送る上にも必要な視点であると思います。
この一月のことぼは、ご著書『この道をゆく』に掲載されています。先生が座右の銘とされていた言葉で、縁のあった学生が卒業するにあたって、何か書いてほしいと頼まれたときに、好んで書き続けてこられた言葉であるとうかがったことがあります。ご著書には、この言葉の由来となった法然聖人の次の文章を引用されています。
現世をすぐべき様は、念仏の申されん様にすぐべし。念仏のさまたげになりぬ
べくは、なになりともよろづをいとひすてべこれをとゞむべし。(中略)衣
食住の三は、念仏の助業也。 (『浄土真宗聖典全書』第六巻、六一一-六一二頁)
これは、法然聖人のお手紙や法語、伝記などが集録されている『和語燈録』(巻五)のなかの文章です。省略されている箇所も含めて、文意をいただいてみます。 法然聖人は、人生の目的はお念仏を申すことにあるから、お念仏を申しやすいように人生を送りなさい、ライフスタイルも一人ひとりにあった様式でよいともおっしゃっています。「衣食住の三は、念仏の助業也」というのは、衣食住は私たちの生活の基本です。その三つがお念仏を支えるための生業だと言われています。これは、お念仏を人生の第一義に、生活の中心にして生きることを薦められたものです。
念仏即生活、生活即念仏というお諭しです。法然聖人は、阿弥陀如来は煩悩具足の凡夫の浄土往生の行業として「称名念仏」 一行をお選びになったのであり、その他の諸行はお捨てになったことを明らかにされました。その称名念仏することが人生の第一義、生活の中心であるということには、どういう意味があるのでしょうか。
煩悩中心の自我教
少し視点を広くして、その意味をいただいてみたいと思います。世の中では、浄土真宗は宗教の一つだと考えられています。では、「宗教とは何か?」と問われると、その答えは一通りではありません。インターネットで検索すると、国語辞典などを出典にした定義が示されますが、そもそもキリスト教やイスラム教、その他、さまざまな名称の個別の教えをひとくくりにできる定義は存在しないのです。ただ一人の神を中心に成立している教えもあれば、多くの神を信仰することで成立している教えもあるし、そういった神の存在を前提にしない教えもあります。多種多様の様相です。昔から宗教学者が百人いたら百通りの定義があるとも言われるゆえんです。
先日ある宗教哲学の先生が、「宗教」という言葉を漢字のとおり、自分か「宗と
する教え」と解釈したらどうかというお話をされました。この場合の宗というのは、自分の考え方や行動を支配するもの、基準になるものという意味です。自覚的に信仰を持っている大は、その教えに黄づいて、たとえば食べるものや生活態度を決めています。こう言うと、現代の多くの日本人は、「私は無宗教者なので、そのようなものは持ち合わせていない」と答えるかも知れません。それに対して先生は、「自我教(自分教ともいう)」というものがありますよ、とおおせになりました。「自我教」つまり自我=自己中心の価値観がその人の考え方や行動を決めているということです。誰もが、それぞれの個性があるので、一見それは多様なように見えますが、仏教でいう煩悩をモノサシにしている点では共通していそうです。すべてを自分の都合の良し・悪し、損・得、快・不快、好き・嫌い、役に立つ・立たない等という価値基準で判断し、行動しています。自分にメリットをもたらすものはこれを際限なく求めようとし、気に大らないもの、デメリットをもたらすものは際限なく遠ざけ、排除しようとする、この煩悩が人生生活の基準になっているというのが自
我教、自分教の正体です。これでいくと、どうやら無宗教者という人は皆無に等しいようにうかがえます。
ところで、この自我教徒は他ならぬ私のことだと言えます。自信を持って言ってはいけませんが、否定はできません。正確に言うと、浄土真宗のみ教えに出遇う前の私の姿でありました。これもまた、言い直しが必要かと思います。お念仏のみ教えに生きるようになったからといって、自我教徒であることを免れたわけではありません。そのことを教えてくださったのが、信楽先生が大事にされた「生活念仏」です。先生は、真宗の仏道としての称名念仏とは、私か申すべき行為でありながら、それは決して私の行為に価値があるのではないことを強調されました。ただ南無阿弥陀仏と申す、その念仏の響きを通して、自身の心の奥底に聞こえてくるものに耳を傾け、それを味わうことが大切だとして、称名即聞名が親鸞聖人が明かされた念仏の肝要であると教えてくださいました。
念仏において、私自身が問われ、砕かれてゆくのです。すなわち、私から仏への方向において成り立つ称名念仏とは、またそのまま、仏から私への方向を持つところの聞名念仏、仏の呼び声を聞き、仏に念ぜられて生きる、ということ
へのめざめでなければなりません。仏を念ずるとは仏に念ぜられていることである。仏の名を呼ぶことは仏の呼び声を聞くことである。称名とは聞名である。
(『この道をいく』五〇-五一頁)
めざめ体験としての「信心」
教えを聞き始めた人にとって、自ら称える念仏が、ただちに阿弥陀如来の喚び声として聞こえてくるということはないでしょう。それは日頃のお聴聞、お仏壇へのお参り(勤行)、日々の称名念仏の相続によって、次第に阿弥陀如来の本願が、この私に向けて誓われたもので、いつの日か、その念仏が阿弥陀如来の私への喚び声と聞こえてくるのだと思います。まさに、仏さまの心が私に届き、仏に念ぜられていると感じるときがあるのです。そのような仏心に対する「めざめ」体験を「信心」といいます。その機縁やプロセスは人によってさまざまな違いがあるかも知れ
ませんが、信楽先生はその体験こそが真宗念仏の肝要だと示されました。
煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろづのこと、みなもってそらごとたはごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておはします
(『歎異抄』、『註釈版聖典』八五三頁)
在俗生活とは、自我教に生きる日々とも言えるでしょう。それが偽らざる事実かと思います。しかし、聴聞を重ね念仏申していく人は、そんな生活のなかに、仏の智慧と慈悲を依りどころとする生き方を願うのです。それは、あらゆるいのちあるものが自他ともに平和で心豊かに生きることができることを願う生き方です。煩悩に基づく自我教はどこまでも自己中心的で、「まことあることなき」教えです。人によっては、そのままで生き続けていく人もいます。しかし、仏教に縁をいただき、なおかつ在俗の生活(自我教)のなかに、智慧と慈悲を活かした生き方、真実の生き方を願う人には、「念仏のみぞまこと」という基準がいただけるのです。日々にお念仏申す一声一声に阿弥陀如来の心を意識して、不真実なる方向へ進みがちな自分の考え方や行動を常に軌道修正してもらう、そういった在俗の仏道が浄土真宗と言えるでしょう。繰り返し繰り返し、日々の生活のなかで「めざめ」をいただく。
それゆえに、念仏することが人生の第一義であり、生活の中心となることを強調されたのです。宗とすべきは、本願の心、お念仏なのです。
最後に、先生の言葉では「助業」ではなく、「助縁」となっていることについて、自ら味わっていらっしゃる言葉を引用してみます。
自分の人生生活の中で、どんなに悲しいことがあっても、どんなに腹が立つことに出あっても、それらはすべて、私に念仏を忘れないように、一声でも多くのお念仏を申すようにと、何かが働きかけているのだと、このように思いとって念仏せよ。そうすれば、どんな悲しみも苦しみも、きっと超えていくことができる。新しい道が開けてくる。 (『真宗の大意』七一頁)
誰しも人生の上に起こる順境は「おかけさま」とお念仏申すことができます。しかし、先生はそれだけではなく、逆境もまた、そこに仏法の真実、人生を味わっていくための大切な意味があるのだと言われています。これが親鸞聖人が浄土真宗を開いて、私たちに残してくださった、生活念仏のみ教えなのです。
(河智 義邦)
















