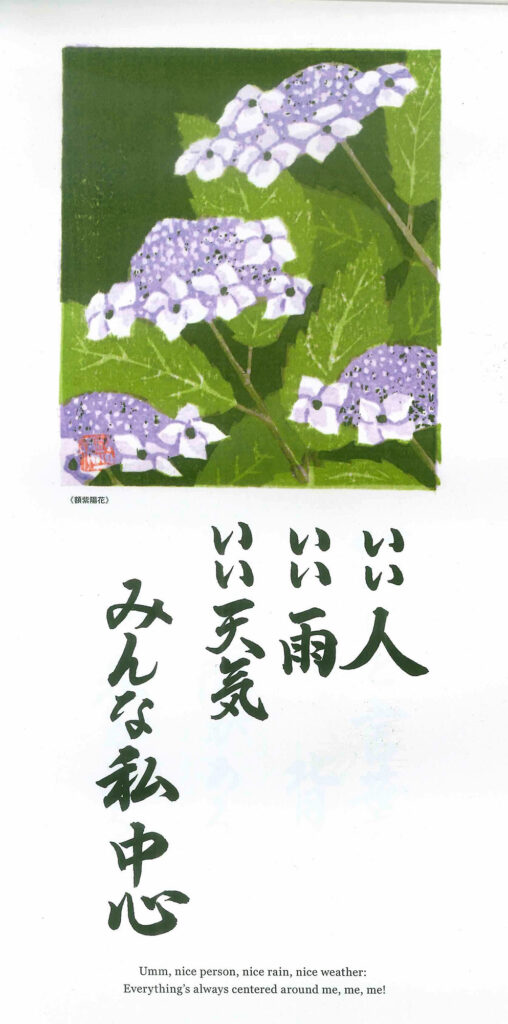五月のことばは、山本仏骨和上のお言葉です。
山本和上の俗名は山本清、一九一〇(明治四十三)年八月十五日、石川県金沢駅近くの浄土真宗の在家に末子としてお生まれになりました。しかし、世界中でまん延したスペイン風邪で、ご両親をはじめお兄さんたちをつぎつぎに失われ、小学生だった和上を残して、最後にお母さんがご往生されたそうです。ご家族を失い一人になって親類にあずけられた和上の学歴は、高等小学校卒業、行義校卒業です。しかし和上はその後、行倍教校教授、本願寺派勧学、龍谷大学教授、本願寺派伝道院院長を歴任され、大阪東淀川区にある定専坊住職を務められました。そして一九九ー(平成三)年二月六日午前四時頃、八十歳でご往生されました。和上のお人柄やエピソードなどについては、『一味638・639合併号・常照院仏骨和上追悼号」(一味出版)に先生方、お同行さま方によって紹介されています。
今月のことばは、『浄土真宗を語る』(本願寺出版協会・一九七八(昭和四十三)年出版)に掲載されている対談中のお言葉です。その頃、行教校で講師をされていた、京都大学の井上智勇先生、宮崎円連和上、利井興弘先生、山本仏骨和上、梯實圓先生、高田慈昭先生、岡邦俊先生が対談の出席者でした。
対談当時の世界情勢は、混迷を極めていたといってよいでしょう。ベトナム戦争は一九六四(昭和三十九)年に全面戦争に突入し、一九七五年アメリカ合衆国が負けて撤退し、戦争は北ベトナム軍が、南ベトナム軍の首都サイゴンを陥落するまで続きました。一九六七年に中国が水爆実験を行い、一九六八年にはアメリカ軍機がグリーンランド油に墜落し、水爆四個が行方不明になったともいわれています。日本では所得倍増計画・経済成長に伴う公害が深刻化していました。
そんな状況の中で、山本和上は、
他力にめざめるということは、さきほど梯君もいわれたように、相対的な人間のエゴイズムの対立する争乱の世界をやぶって、それを超えた仏の絶対の真実の世界に眼をひらかしめられることです。仏さまはその絶対平等の立場から、つねにあらゆるものをわけへだてなく平等につつみ、これらを完全に生かそうと働いておられるわけです。
そうした仏さまのめぐみに気づかされたものは、つねに浅ましい煩悩をおこす自分をはずかしく反省せしめられ、またこういう自分をかぎりなく大悲して救うてくださる御恩をよろこびながら、真実の人生を開いていくわけです。
こういうふうに人間のみにくいエゴイズムを深く恥じ、仏さまの智慧と慈悲にかえって、あらゆる人々を愛しつつ生きようとされたのが、親鸞聖人の他力のみ教えであって、このみ教えこそ混乱と斗争にあけくれる現代の社会にもっとも大切なものだというべきでしょう。
とおっしゃっています。現在の状況に通ずる大切なお言葉です。
その後、高田慈昭先生が話題をかえて、「心のことについてご意見を聞かせていただきたい」と提案されます。それに利井興弘先生が、
浄土真宗の心は、「安心せよ(南無)必ずたすける(阿弥陀仏)」という仏の仰せ(法)だから、それをいただく心(機)は「きっと助かる(阿弥陀仏)」と安心する(南無)ことだ、と仰せを聞き受ける倍心である
と答えられます。信心について、「必ず助ける(法)」を一人ひとりが「必ず助かる」といただくことだと、利井鮮妙和上よりの伝統の定義をされています。
その信心について山本和上が、
親鸞聖人は信心を「遇(あう)」とか「聞(きく)」という言葉で顕されていますね。だから信心ということは、仏さまの光に照らされて、私の心に明かりがつくことだというように味わうと、一ばん有難いんですよ。
とおっしゃいます。その山本和上のお言葉を梯賞園先生が、
なるほど「心に明かりがつく」という表現は、ありがたいですね。何かこう人生にほのぼのとした暖かみと明るさが感じられますね。
と恩師のお言葉を味わわれます。
親鸞聖人は、『正像末和」に
智慧の念仏うることは
法蔵願力のなせるなり
信心の智慧なかりせば
いかでか涅槃をさとらまし
(「註釈版聖典」六〇六頁)
仏さまの智慧の結晶である念仏を私が称えることは、法蔵菩薩の本願が力となって、はたらいているということです。
智慧である念仏をいただくのが居心ですから、心も智慧でありました。その儲心なくしては、どうして本当の安らぎを実現することができるでしょう。
(著者意訳)
無明 長夜の燈炬なり
智眼くらしとかなしむな
生死大海の船筏なり
罪障おもしとなげかざれ
(『註釈版聖典」六〇六頁)
(そのような智慧の念仏。心の智慧は、真っ暗な絶望の長き夜にあって、消えることのない大きな灯火です。
智慧の眼がひらけないから希望なんかどこにもないと悲嘆しないでください。
念仏をいただく個心は、生死の苦しみの海を渡り超えてゆく船や筏のようです。
自業自得だと絶望することはありません。
(著者意訳)
と心を讃えられます。『頭浄土真実教行証文類』総序にも、
無礙の光明は無明の闇を破する恵日なり
(「註釈版聖典」一三一頁)
何ものにもさまたげられない光明は、私の根深い暗闇を破ってくださる暖かな恵みの太陽です。
(著者意訳)
とお書きになっています。
山本和上の「人間に花ひらく」(八~十二頁)(永田文昌堂)には、「星がうつる」と題された文章があります。日中戦争を舞台とした小説『麦と兵隊」を書いた火野葦平の文章に感した、と書かれたものです。戦後すぐの廃墟の都市にいた戦争孤児の少年が、クツみがきをしながら生きのびてゆく姿を描いていて、その少年はクッをみがきながら「ぼくのみがいたクツには、天上の星がうつるんだよ」と活きいきと目をかがやかしていたというのです。
和上は、その少年の生き方はあわれかもしれないけれどとされながら、
しかし、彼の小さい手で、一生けんめいにみがくそのクツに、大空にまたたく星がうつっているというところに、彼の手と天上とむすばれるものがあり、そこに誇りを感じ、希望が湧き、そして、みすほらしいと見える中にも、大きな生きがいにはずんでいたのでしょう。
お念仏をする心にも、これに通じるものがあると思うのです。誰も知らぬ仕事場の中に、ひとり夜道を帰る町の灯の下に、しずかにお念仏を称えるとき、そこに、仏の心が通い、仏の心がうつっているのです。そこにこそ、ひろびろとしてはてしない、宇宙の真実ありだけをはらんで、わたしのためにねがいをかけてやまない、仏の全生命が流れそそがれているのです。
お念仏は単にお寺や、お仏壇の中にだけあるものでなく、こうして一人、一人の、70いかなるささやかな生活の中にも、生きているのであり、光っているのです。
と味わっておられます。
きっと山本和上は、クツみがき少年に、一人はっちで生きてきたご自身の姿を見られたのでしょう。和上のお母さんは、肺炎をおこして人生を終わってゆかねばならぬなか、十一歳の我が子を前に、
「わたしは死にません。お浄土に生まれさせていただくのです。おさとりの身にしていただいて、この子の一生をまもりつづけます。みんなに可愛がってもらいなさいよ」
と言い残してご往生されたそうです。
山本和上は、一人ぼっちになって生きのびてゆかねばならなかった自分と、孤独に生きねばならぬ人々に、優しく言い聞かせておられるのでしょう。
「一人ではあるけれど、お前には母さんが遺してくれた念仏がある。念仏の温もりは母さんの温もりだよ。お前を支えているものの温もりだよ」「苦労をしても、ひがんだり、ごうまんにならないようにお育てくださるのが、如来さまである」
といつも和上はおっしゃっていたそうです。
(濱畑 僚一)