十一月の法語は
真宗大谷派の僧侶である仲野良 俊先生の講義録 『 浄土真宗―往生と不退―』( 東本願寺出版)からの一節です
仲野先生は一九一六 ( 大正五)年に京都市の真宗大谷派専念寺でお生まれになり大谷大学文学部をご卒業の後
大谷大学講師、大谷専修学院講師、真宗大谷派北海、道教学研究所長
真宗大谷派真宗教学研究所長などを歴任され一九八八 ( 昭和六十三)年一月にご往生されました。
『 浄土真宗 ―往生と不退―』は
一九八三 ( 昭和五十八)年十一月から翌年の十二月にかけて行われた名古屋東別院での五回にわたる研修会の講義録です
あとがきによりますと
先生はこの研修会の前後から体調を崩されたため講義録としては最晩年のものとなったのだそうです。
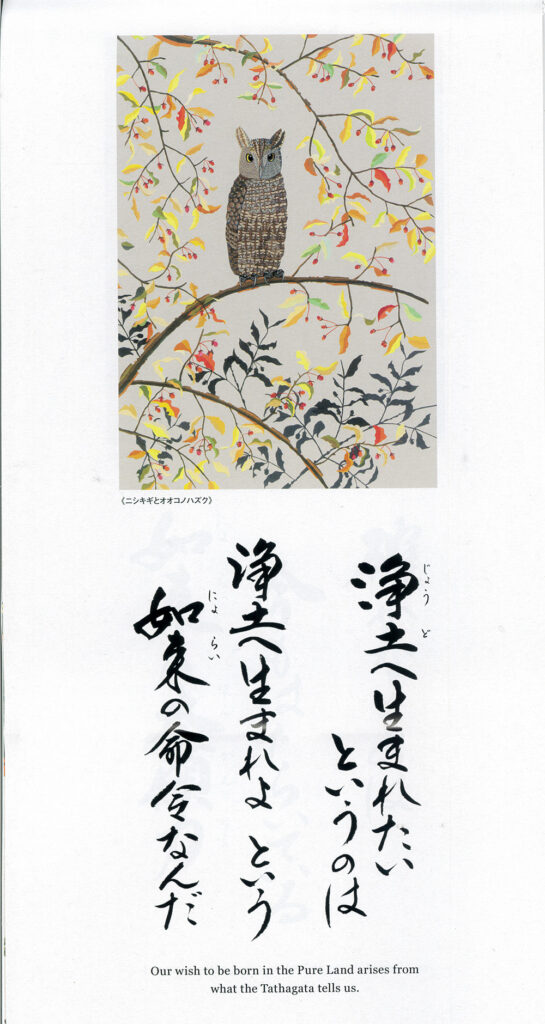
全編を拝読しますと、まとまった生涯をご教化に尽くされた先生の力強いお声が聞こえるようでした
さて今月の法語から私はふと
「 すなの しろ」という仏典童話を思い出しました。
白く美しい砂浜に子どもたちが駆けてきて、喧嘩をしながら場所取りを始めた。
やがてめいめいの場所が決まると子どもたちは思い思いの城や家を作った。子どもたちはみな自分のものを大事に守り、他の子に触らせなかった。ところが一人の子どもが他の子の城をうっかり踏み潰してしまい、また争いが始まった。
いつの間にか夕暮れ時になり、松林の向こうから「ゆうごはんだよ。はやく、かえっておいで」と母が呼ぶ声が聞こえてきた。その声の方に子どもたちは駆けだした。大事にしていた城も家も踏み潰していることにも気づかずに帰っていった。子どもたちが帰った後、波が寄せてきて城も家も残らず崩してしまった。
その様子をずっと見ていた男が言った。
「人間のしていることと、そっくりだ」
「ほとけさまのありがたい説法だ。うかうかしては、いられない」
(花岡大学「仏典童話全集七」二〇〇一二〇六頁、著者要約)
仲野先生も、
浄土に生まれたいというのは、浄土へ生まれよ、という如来の命令なんだ。
(仲野良俊「浄土真宗 1往生と不退ー』一五六頁)
というお言葉に続けて、ただ自分の都合のいいようにしたいと願っている私たちが浄土へ生まれたいなどとは到底思ってはいない、そんな心が発るというのが不思議なのだ、と語っておられます。
私たちはみな、前出の子どもたちのように、生きている間は欲や怒り、愚痴の心を燃やしながら、生きることに必死の日々を送っています。先生がご講話の中で度々言われるように、都合のいいこと(生)が好きで、都合の悪いこと(死)が嫌いなのが私たちの有りようです。
私事ですが、私は臨終間際の父から、そのことをよくよく知らされました。
私の父は、二〇〇三 (平成十五)年五月に六十五歳で往生しました。四月に急性肝炎で入院したのですが、良くなることなくひと月足らずで今生の縁を終えました。
私は父の入院の報せを聞き、すぐに家族で島根まで里帰りをして父を見舞いました。
肝臓の病気なので辛そうではありましたが、父は私たち家族の訪問を喜んでくれて、起き上がって病状などを話してくれました。
「わしは六十五年もこの肝臓を腹の中へ据えとったが、肝臓や腎臓が体の毒をきれいにしてくれておったとは少しも思わずにおったなぁ」
と言い、
「体の毒は肝臓や腎臓が働いてきれいにしてくれるし、それがだめなら、治療や薬できれいにもなるだろう。でも心の毒というものは、死ぬるが死ぬるまで、この身からもこの心からも離れることはないけえのう」と話してくれました。その時はまだ私も、おそらく父も、まさかひと月も経たぬうちに今生のお別れをしなければならなくなるとは思ってもいませんでしたので、父の話も何気なく聞いていたのでした。けれど後から、あの時父は親鸞聖人のお言葉を病の身に実感しながら自分の言葉で語ってくれたのだと気づきました。その親鸞聖人のお言葉とは、
「夫」といふは、無明、殲われらが身にみちみちて、欲もおほく、いかり、
はらだち、そねみ、ねたむこころおほくひまなくして、脇約のごにいたる
まで、とどまらず、きえず、たえずと、製処二酒のたとへにあらはれたり。
(『註釈版聖典」六九三頁)
いちねんたねんもんい」
という「ご文意」のお言葉です。父の言う心の毒とは、食欲・眼憲・愚類の三毒の煩悩です。この身に満ち満ちている煩悩は、死の瞬間まで消えることも離れることもないというのです。まさに煩悩具足の凡夫であることを、病の身をもって知らされたのでしょう。
その後、父の容態が悪化し、医師からも今夜が危ないと告げられる日が来ました。
父のもとに駆けつけた私は、病室で父の六十五年の人生最後のお夕事をしようと思いつきました。父に、
しょうしんげ
「お父さん、お正信のおつとめをしようかねぇ」と言い、小さな声で、
「帰命無量寿如来南無不可思議光渋蔵書成位時様地自在玉佐所..」
と「正園」のおつとめを始めました。父は島根県の山間のお寺で生まれ、幼くして父親が戦死したため、龍谷大学を卒業後すぐに住職継職して以来四十年余り、ご門徒や青少年への教化をひたすらにつとめてまいりました。私たち姉弟にもご法座の時には本堂でお参りするように厳しく言っておりました。そんな父ですから、自らの人生最期のひと時に家族と「正傷」のおつとめをすることをきっと喜んでくれると私は思ったのです。ところが、父は苦しそうに顔をしかめて、「はぁ、そがあな難しいことはいい…」(もうそんな難しいことはいらない)
と言ったのです。私は父が「正信偈」を跳ね除けたことに驚き、とても残念に思いました。けれど、父の様子を見ると残念な気持ちも消えました。生と死とのせめぎ合いの中で、死の瞬間を迎えるその時まで、生きたい、生きたい、生きよう、生きようと父の体は戦っているのです。そのせめぎ合いの真最中には、到底「正」を喜ぶことも、お念仏を称えることも、お浄土を成うこともできないのだと、父は身をもって教えてくれました。まさに、親鸞聖人のお言葉通りでした。
親鸞聖人は先掲の「一会多念文意」のお言葉の後に、導犬前の「観経強」「散鬱業」から三瀬が道の比喩を出されるのですが、そこでは、このような嘆かわしい私たちも、食欲をあらわす大水の河と志をあらわす大火の河に挟まれた一筋の白道を一歩二歩と歩いていくなら、何ものにもさまたげられない阿弥陀さまの光明に携め取られ、かならずお浄土に往生することができる、とお示しになられています。ここから、我欲に溺れ、怒りの炎を燃やしながらの私たちの生きざまや歩みが、もうすでに白道に喩えられる阿弥陀さまのご本願の中だったと窺えます。
善導大師は「散善義」に、
また西の岸の上に人ありて喚ばひていはく、「なんぢ一心正念にしてただちに
来れ。われよくなんぢを譲らん。すべて水処の難に癒することをれざれ」と。
(「註釈版聖典(七祖篇)」四六七頁)
と阿弥陀さまが大慈悲心をもって、「なもあみだぶつがあなたをお浄土へ生まれさせます。だいじょうぶ、もう二度と迷いの世界へ沈ませはしません」
と召喚してくださっていると説かれています。阿弥陀さまのお喚び声が聞こえたなら、そのまま帰ってゆけるのです。安心して帰ってゆけるのです。「すなのしろ」の子どもたちのように。
ほどなく臨終を迎える父ですが、その前に少しだけ状態が安定した時間がありました。その時、父は、
あんにょうじょうど
「この身このまんまで、安養の浄土へ参らせてもらうだけぇ(参らせていただくのだから)、安心、安心」
と、付き添っている私たちに言ってくれました。
「正園」も跳ね除けてしまうこの身、一声のお念仏も称えられなくなったこの身、生きたいと願い続けるこの身、心の毒が離れることがないこの身です。父に限ったことではありません。私も同じです。この身をひっさげた私のまるごとそのま
まが、阿弥陀さまの機取不橋のおはたらきのまん中に抱かれて、安らけきお浄士へと生まれさせていただくのだから、安心、安心、と父はほんとうの安心を教えてくれました。
いよいよ臨終間近、もう話すこともできなくなった父に、お見舞いに来てくださ
った隣寺のご住職が、
「ご院家さん、長いことお世話になり、ありがとうございました。またお会いし
ましょう」
と声をかけてくださり、父は小さく頷きました。
今まさに臨終を迎えようとしている人に対して「また会いましょう」と言うのは、一般常識ならおかしな話です。けれど、お念仏をいただき、お念仏のみ教えに生きる者同士であれば、いつであろうともお互いに「また会いましょう」と言えるのです。何故なら、みな等しく阿弥陀さまの御手の中にあり、かならずお浄土に生まれ
させていただけるからです。
私たちは誰しもが愛しい人、大切な人を、何人も何人も見送ってまいります。そのたびに深い悲しみの底に沈みます。空っぽになった手を合わせ、灰かな温もりを探します。会いたくて会いたくて、この胸が打ち展えます。けれども「また会いましょう」と言える世界があるということを、その人たちが教えてくれるのです。仏さまとなって教えてくれるのです。
仲野先生のお言葉をお借りすると、都合のいいこと(生)が好きで、都合の悪いこと(死)が嫌いな私は、お浄土とは真反対の生き方しかできませんが、お浄土に生まれて、あなたに会いたい…そう思う心もそのまま阿弥陀さまのおはたらきの中、「かえっておいで」という、頼もしくやさしいお喚び声だったのだと知らせていただきました。
さあ、うかうかしてはいられません。南無阿弥陀仏のお心を聞かせていただきましょう。
(徳平亜紀)
















