浄土真宗で一番大切なのは素人感覚
六月は、近田昭夫先生のお言葉です。まず先生のお姿を知るために住職を務められていた寺院をお訪ねしました。東京都豊島区南池袋の閑静な場所にあり、二代目のご住職であった近田昭夫先生が、まったく何もないところに、本堂など全部仕上げられたそうです。本堂には浄財された方の名が多く掲示されていました。先生が念仏者として、内にも外にも躍動感あふれる活動をされたことを、本堂に座りながら感じることができました。三代目で現住職の近田聖二さまには、突然の訪間にも関わらず、先生のお話をお聞きかせいただきました。
近田先生は、一九三一(昭和六)年に東京都浅草でお生まれになりました。法政大学経済学部経済学科を卒業され、一九五五(昭和三十)年より真宗大谷派顕真寺住職になられました。その間、真宗本廟総会所教導や同朋会館教導を歴任され、去る二〇一八(平成三十)年十月二十六日に、八十六歳でご往生されました。
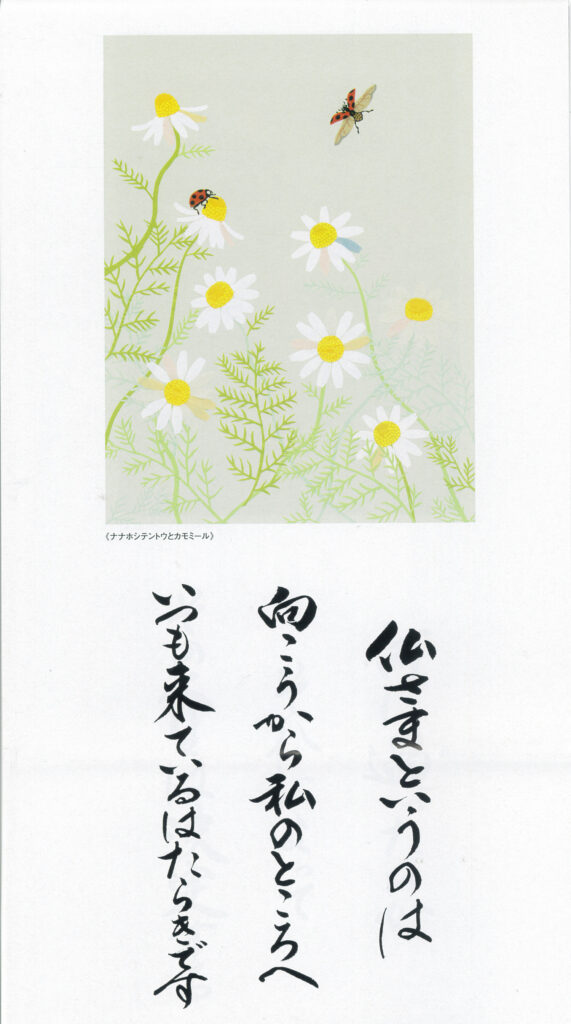
近田先生は「浄土真宗で一番大切なのは素人感覚だ」と言われました。素人感覚とは、「わかったことにしない」ということです。
小さい子どもは「どうして」「なぜ」と連発します。ですから子どもの世界は新鮮なのです。大人になると、わからないことをわかつたことにしてしまうから、驚きもなく感動もないのです。
確かに浄土真宗のお話は「なぜ」と考えるところから、新鮮なお念仏の味わいが出てくるように思います。
真宗の本尊はなぜ絵像・木像
巻頭の言葉は、二〇〇八(平成二十)年三月二十二日に真宗本廟(東本願寺)春季永代経総経において、「なぜ、絵像・木像の阿弥陀如来を本尊とするのか」という講題でお話をされた講演録の中に出てくるお言葉です。
親鸞聖人は「南無阿弥陀仏」という六字の名号を、あるいは「帰命尽十方無碍光如来」という十字名号などをご本尊として礼拝されていました。ところが現在はなぜか、浄土真宗の本山をはじめ、どこのお寺でも木像の阿弥陀さまをご本尊とされています。またご門徒宅のお内仏は、絵像の阿弥陀さまです。親鸞聖人は名号をご本尊とされていたのに、今はなぜ阿弥陀さまの木像。絵像がご本尊とされているのでしょうか。
浄土真宗本願寺派の本山である本願寺の阿弥陀堂に安置されているご本尊の阿弥陀さまはお木像で、蓮の台の上にお立ちになっている立像です。しかし知恩院をはじめ、浄土宗の阿弥陀さまはお座りになっています。なぜ浄土真宗では立ち姿なのでしょうか。
阿弥陀さまは仏の座(お浄土)から、今まさに降り立とうとするお姿で、少し前かがみになっています。人間の迷いの世界のど真ん中に、阿弥陀さまは降り立たれ、煩悩のあやうさや浅ましさを知らせ、呼び覚ましを与えてくださるのです。
なぜ絵像。木像のご本尊なのかというと、あのお姿を拝することによって、「阿弥陀さまは私の姿をご覧になって、仏の座に落ち着いてはおられなかったのだ」と気づかせるためです。そのことを私たちに知らせるため、お立ち姿をご本尊としてお敬いするのです。
言葉となった仏さまが招き喚ぶ
この後に
仏さまというと私たちと懸け離れた尊いお方とお敬い申しあげるけれどもそれは尊敬しているといっても、実は敬遠しているだけなのです。生きた仏さまのはたらき、おこころというものが全然わかっていないわけです。(乃至)実は、仏さまというのは、向こうから私のところへいつもきているはたらきです。
と言われています。
お寺にある木像の阿弥陀さまやお内仏の絵像は、仏の座を降りて、この泥にまみれた娑婆世界にお出ましになります。仏さまらしい姿形をまったく滅し去って、言葉となった仏さま「南無阿弥陀仏」の六字の姿なのです。「いつでも、どこでも、だれでも」と出遇ったらならば、平等に目覚めることができる、これこそ生きた仏さまです。その仏さまというものを、お釈迦さまが『仏説阿弥陀経』に語り遺されたのが「言葉となった仏さま。南無阿弥陀仏」であるといわれました。
「南無阿弥陀仏」は中国語で「帰命尽十方無碍光如来」と翻訳されました。 一般的に「帰命」とは私たちがおこす信心のことで、仏のみ名とはしません。しかし親鸞聖人は「帰命」ということまで仏のみ名とされ、無碍光如来は、その智慧・慈悲のお徳から私たちの信心まで施し与えてくださる仏さまと仰がれたのです。この私に阿弥陀さまの方から先手をかけて、何もかも整え、どうか救われてくれよと願ってくださったのです。
このような仏さまであるから「帰命尽十方無碍光如来」と呼ぶようになったのであり、またこの名のあるところには、いつでも、どこでも、だれにでも、阿弥陀さまはいきいきとはたらいて、私を摂取してくださるのです。
親鸞聖人の「行文類」の六字釈に「帰命は本願招喚の勅命なり」(『註釈版聖典』一〇七頁)といわれています。「南無阿弥陀仏」というのは、仏さまが私を招き、喚び覚まし続けている勅命であるとおっしゃっているのです。
この「招」というのは「まねく」ということです。私を阿弥陀さまの方へ招いてくださり、私は阿弥陀さまから「わが国に生まれ来たれ」と招かれている人間なのだということです。
「喚」は「よぶ」という字ですが、親鸞聖人はこの「喚」を「ヨバウ」と読んでおられます。「ヨバウ」は「よぶ」という動詞に、「ウ」という動作の継続をあらわす助動詞を付けておられます。つまり阿弥陀さまは、私を喚び続け、招き続けているのです。 一回だけではなく継続して喚び続けている相が、私が「南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏」とお念仏を相続している相なのです。だから念仏を相続しているということは、阿弥陀さまのはたらきが私に至り届いていることなのです。
それを明治時代の仏教学者であり、僧侶の原口針水和上は、われ称え、われ聞くなれど、南無阿弥陀仏、連れて行くぞの親の呼び声と言われました。
阿弥陀さまの私を喚ぶ仕事を、私がさせていただくのです。阿弥陀さまのお仕事を、阿弥陀さまに代わって私がさせてもらつて、そして阿弥陀さまのお言葉を私が聞かせてもらっているのです。これはありがたいことです。
磁石の警えなほ磁石のごとし、本願の因を吸ふがゆゑに。
(『註釈版聖典』二〇一頁)
と親鸞聖人は阿弥陀さまの救いを磁石で喩え、磁石が鉄釘を吸いつけるようなものだと言われています。普通の鉄釘は絶対に動きません。ところが磁石を近づけた時に、鉄釘は磁石の方に向かって動いていきます。これは鉄釘が磁場の中に入ると、外面はただの鉄釘ですが、内面は変貌して磁石になっているからです。同じ鉄釘でも、磁気を帯びた鉄釘と磁気を帯びない鉄釘とでは、鉄の原子は同じなのですが、原子の配列が違ってくるのです。親鸞聖人はそれを、阿弥陀さまの本願の救いの模様を顕わすのに使っておられます。
阿弥陀さまの本願力というのは磁石のようなものです。「本願の因を吸うがゆゑに」(『註釈版聖典』二〇一頁)と、阿弥陀さまが救おうとされた救いの対象を、自らに吸いつけていくというのです。磁石に引っついている鉄釘に、他の鉄釘を引っつけると、その鉄釘が引っつくのです。これは鉄釘が既に磁石になっている証拠です。電子顕微鏡で見ると、磁気を帯びると原子の配列が瞬間に変化します。そうなると単なる鉄ではなく、磁石になっているのです。
内面的な大きな変革
本願を聞き、そして本願を信じたということは、その意味で外面は煩悩具足の凡夫のままの姿なのですが、内面に大きな変革を受けているのです。どんな変革を受けるかというと、阿弥陀さまと同質のものになっていくので、阿弥陀さまの方に向かって親しみ近づく親近性をもつようになるのです。そして仏さまに向っていくような人間に育てられるのです。錆びた釘も曲がった釘も磁石に引き付けられるように、阿弥陀さまの本願も、賢かろうが愚かであろうが罪深きものであろうが、無条件に引き付けてくださるのです。
どのような変化が起こるのかというと、第一に、教えを聞くことを少しずつ楽しむようになっていきます。私たちは教えを聞くことを嫌がり、聴こうともしなかったけれど、少しずつ教えを聞くことが楽しくなって、教えに対して親近性が出てくるのです。
第二に阿弥陀さまのみ名を称え、阿弥陀さまを思い、浄土を思う人間になっていきます。これは内面に変革を受けている証拠です。鉄釘が磁石に変わっていくように、外見は少しも変わりませんが、内面には大きく変革しています。曲がった鉄釘も折れた鉄釘でも、磁気を帯びた鉄釘は、他の釘を吸いつける能力を持ちます。
そのように阿弥陀さまの教えを聞き、そして阿弥陀さまに向かった存在に変化をうけます。また有縁の人たちを阿弥陀さまの方に向きを変えていくようなはたらきをする人間に変わっていきます。このように大きな変革が行われていくのです。
救われるということは、外面はあまり変わりがないように見えますが、内面が質的に変わっていくのです。質的に変われば、もちろん外面にも変化はあるでしよう。
教えを聞いて慶ぶ人間
まずは教えを聞いて慶ぶ人間になります。そして人々に「共にこの教えを聞いて、共に阿弥陀さまの子であることに目覚めていきましょう」という呼びかけも出てくるようになります。そして阿弥陀さまの教えにしたがって、「行ってはいけない」
「言ったらダメだ」「思ってはいけない」と、身にも口にも心にも慎んでいこうという嗜みがおこってきます。ここに変革を受けている姿が出てきます。
煩悩具足の愚かな者を、そのままで救おうと思し召す阿弥陀さまの教えに触れた時に、私たちは大きな変革を受けます。磁石は折れた鉄釘でも曲がった釘でも、鉄ならば引きつけます。阿弥陀さまの本願もその通りで、賢かろうと愚かであろうと罪業深き者であろうと、その人が、クいのちクあるものであるが故に、阿弥陀さまは無条件に引きつけてくださるのです。そして阿弥陀さまと同質のものに仕上げてくださいます。そのはたらきが、阿弥陀さまの救いなのです。
そして阿弥陀さまの本願を聞いて、教えをいよいよ慶ぶ人間になり、教えを聞くことを楽しむ人間になって、そして仏さまに親しみ深くなって来るのです。
阿弥陀さまにお礼を申し、お念仏を申すようになって、阿弥陀さまに対する馴染みが深くなっていくのです。
「南無阿弥陀仏」
(大野孝顕)
















