一、今月のことばについて
今月のことばは、燃器太恵子(一九三九〜二〇二三)さんのご苦者である「心のポケットに~言葉の花束を~」(本願寺出版社、二〇〇二)から選ばれました。外松さんは、青少年問題カウンセラーとしてご活躍され、福岡県いじめ問題対策審議会委員、福岡県「心のふれあい教育相談」推進委日会委員などを任されました。また、福岡県仏教連合会女性の会会長もされていることから、仏教にも深い閉わりのある方です。
「大のなかに大慈悲のなかに確かにこの私がいます」は、外松さんが「私は何に見えますか」と題して書かれた随学の中の結びのことばになります。この随筆の日頭には、詩人であり、国家でもある昆野台盤(一九四六~二〇二四)さんの「花の詩画集 鈴の鳴る道」(成社、一九八六)にのせられている時を引用され、その詩を外松さんが感動されたことからはじまります。
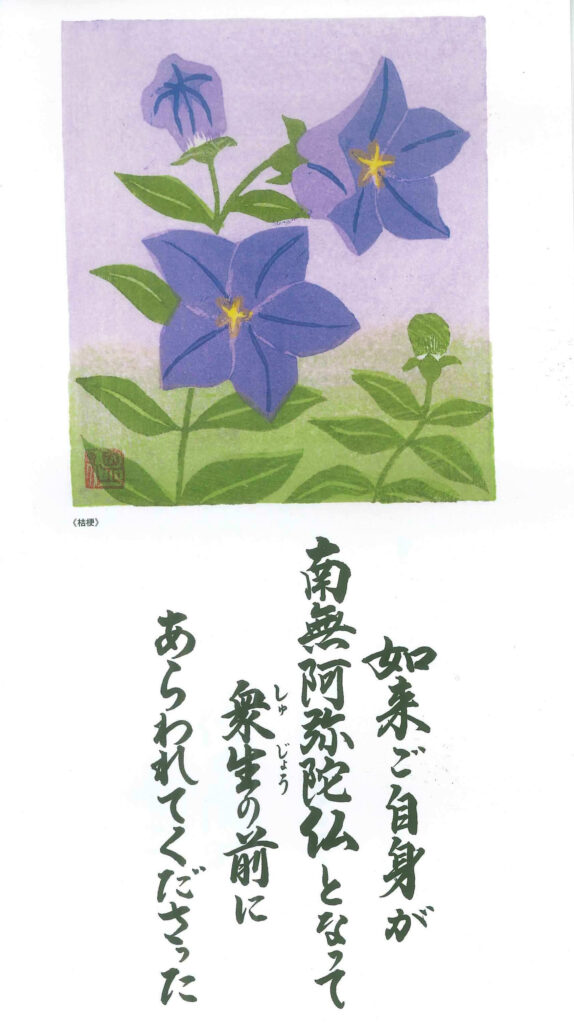
星野さんの詰は、「よ/その草が/木に見えるか/その石ころが/岩に見えるか/焼よ/私は/何に見える」というものです。同じものを見ていたとしても、その存在の遠いや立場によって見え方は異なるものであり、またこの見え方が絶対的に正しいというものはないということを伝えているのでしょう。
この部を目にした外松さんは、常に自分からの視点、自分のものさしで考えながら生きてきたことに気付かれます。そして、自分の身のまわりの犬や猫や小鳥たちに、「私は何に見えますか?私は今まで小さな生きものを殺したり、読めたりはしていませんよ、優しい人間に見えていますか?」とたずねます。しかし、鶏や卵、牛、豚、魚など多くのいのちをいただいて生かされていることに気付いた外松さんは、「何と、慢な、何と不遜な私の姿」が見えたと述べられています。私を私の中から見るのではなく、犬や、猫や小鳥など他者から見た時に、それまで見えなかった自分の姿が見えてきたというのです。
二、他者を他者のほうから理解しようとする想像力
ところで、哲学者の鷲田清 一(一九四九~)先生が、大阪大学の総長を務められていた時、二〇一一年度の入学式告辞の中で以下のようなことを述べておられます。
「幸福とは何か?」この問いは、逆説的にも、得たものの大きさではなく、失ったものの大きさによって深まっていきます。あるいは他者が失ったものへの想像力の密度に比例して、深まっていきます。
(鶏田を一「路の前にいる君たちに~総田港一式辞集~」(朝日出版社、二〇一九)、一三八~一三九頁)
この年の三月十一日は東北地方太平洋沖地が発生し、本震とそれにともなう大津波、福島第一原子力発電可事故など、東日本大天災によって多くのいいのちが奪われました。この大災の傷がそのままのこる中、熊田先生が新たに大阪大学に入学した学生に向けて書られました。
この告辞で総田先生は、「幸福な生活」について話をされています。幸福になるためには、快楽や名誉や声、そして知恵や技能は望ましいものではあるけど、失業や名誉や宝、そして知恵や技能を手に入れることが幸福とは言えない、と述べています。
これに続いて、右に引用したことばが述べられるわけですが、幸福は、失ったものへの思い、つまり他者への想像力に比例すると述べているところが、総田先生の選識と呼べるところでしょう。そして、次のように田先生のことばが続きます。
そういう意味で、みなさんにいつも持ち合わせてほしいのは、この(他者への想後力)です。…..・他者への想後力)とは、ふつう思いやりと言われますが、要するに他者を他者のほうから理解しようとすることです。その意味では、想像力とは、自分が抱いているイメージをさらに減げることではなく、自分をここではなく、別の場所から見る力のことだと言うべきです。
(鶏田(二〇一九)一三九百)
三、石がいのちの中にある
他者とはいったい何ものなのでしょうか。これについてイギリスの人類学者・テイム・インゴルド(一九四八~)が興味深いことを述べています。インゴルドは、人間と勤物、進化という概念、人間にとっての環境の意味など、従来の文化人類学の枠組みを大きく越える黒を続け、世界的にも注目されています。
インゴルドの著作の中で、「人類学とは何か』( 奥野克巳・宮崎幸子訳・亜紀書房 二〇二〇)は、他者と向き合い、ともに生きるとはどういうことか、世界が直面する危機にどう立ち向かうべきか、これらの問いに対して、人類学と人類の未来について考える一冊です。
他者とともに生きるといわれると、自分自身を出発点として考えているようで、鷲田先生が述べることとは違うように感じます。しかし、インゴルドが述べるのはもっと大きなものからの視点です。その点で驚田先生の理解と通じるものといってよいでしょう。
インゴルドは「人類学とは何か」の中で、人類学者だった八・アーヴィング・ハロウェル(一八九一~一九七四)が、一九三〇年代に北部カナダの先住民アニシナアベ(オジブア)の人々の調査を行っていたことについて考察を深めています。(イ
インゴルド(二〇〇)二三~三三頁)ベレンズ川のアニシナアベの首長ウィリアム・ベレンズが語った「生きている石」について、インゴルドは、いのちが石の中にあるということではなくなる。むしろ、石がいのちの中にあるのだ。人類学では、この(モノの)存在論は、アニミズムとして知られる。アニミズムはかつて、モノの開への間違った付仰の上に楽かれた最も原始的な宗教として打ち捨てられたのだが、今日では、実存の完全性の理解において、科学を浅認する、生の時学であるとみなされている。それは、他者を真剣に受け取ることから帰結する。
(インゴルド( 二〇二〇)三〇頁)
「アニミズム」とは精金信仰のことをいいますが、これを宗教の原始的な姿として取り上げたのは、宗教学者のエドワード・B・タイラー (一八三二~一九一七)でした。ダイラーは、人間精神の深層に横たわるもろもろの的存在についての僧仰をアニミズムと名付けました。そして、人間以外のものにも魂があるとしました。
このタイラーのアニミズムの問題は、人間と人間以外の存在を愛別し、人間以外の存在の中に人間同様の魂があるとし、人間以外の存在に対し人間同様の性質を投影しようとする、二元論的な思考だったことです。
これに異を唱えたのがインゴルドでした。インコルドが主張する要点を述べるとこういうことです。人間の生(いのち)そのものとの対話は、単に世界との対話ということではなく、人間のみならず、石もまた動的な存在として含む世界そのもの(他者)からの対話ということを述べているのです。注意しておきたいのは、インゴルドのアニミズムに関する見方を述べているのであって、決してそれを信じるとか、付じないかという話をしているわけではありません。
このインコルドの述べるところをみた時、親葉迎人が仰る「自然」のことを想起せずにはおれません。
四、自然法間
親鷲望人の八十六懐のお手の中に「自然法解料」というのがあります。このお手紙の最後に、
ちかひのやうは、「無上低にならしめん」と話びたまへるなり。無上他と出すは、かたちもなくまします。かたちもましまさぬゆるに、自然と申すなり。かたちましますとしめすときには、無上副菜とは申さず。かたちもしましまさぬやうをしらせんとて、はじめて気に傷と出すとを、ききならかて悩み。弥陀は自然のやうをしらせん潤なり
( 『 註釈版聖典』七六九頁)
とあります。姿やかたちもない阿弥陀仏は、自然の姿(やう)を知らせるためのかて(料)であると述べておられます。
「自然」とは行者のはからいではなく、もとからそうさせるという意味であり、わかりやすくいうなら、「あるがまま」ということになるでしょう。
私たちが理解する「自然」は、通常、山川、海、草木、動物、季候などmatureの意味でしょう。この場合の「自然」は「シゼン」と読みます。これは人(人開世8)と「シゼン」を対立機造的に捉えている視点になります。この視点のままではどこまでいっても「私」という枠から抜け出すことはできません。ところが「自然」を「ジネン」と読んだは意味が変わってきます。「ジネンーは「あるがまま」の世界を意味するのですから、もっと大きなものを意味します。この世界の全体といってもよいかもしれません。また、それはいのちと理解してもよいでしょう。そうすると、人間だけでなく、この世界のすべてのものがみな、自然の中に平等にこの世にあることに気付かされるのです。
五、大悲のなかで
外松さんは、「野に咲く小さな花が、私を人間に見てくれるなら、それは仏法に返えたから」と述べておられます。他者の立場から他者をおもうことができるのは、仏法に出返えたからだというのです。続けて、「この救いようのない私を、阿弥陀さまはじっとみていてくださっています。その眼差しのなかに、確かにこの私がいます」と述べ、最後に「大悲のなかに、大慈のなかに、離かにこの私がいます」と結んでいます。
大、大慈悲とは、阿弥陀如来のはたらきのことであり、すべてのいのちを隔てることなく包摂し、私たちすべてを救おうとする阿弥陀如来の本のお心を示しています。
「教行道」の行巻のおわりに、親禁型人は「感分化側(信編)」をつくられています。その鳳(九四二~一〇一七)学において、
梅事の感はただ他を続すべし。われまたかの摂取のなかにあれども、混、眠を感へて見たてまつらずといへとも、大態、絶きことなくしてつねにわれを照らしたまふといへり
( 『 註釈版聖典』二〇七頁)
と述べておられます。私たちはどこまでも投欲にとらわれた、悩具足の愚かな存在でしかありません。私たちの目には阿弥陀如来の本頃のお心は見えなくても、その大夫、大慈恵は常に私たちを照らしているのです。
伝灯奉告法要でご門主さまがお示しくださった「念仏者の生き方」の最後にも述べられておられます。
…仏さまのような熱われのない完全に清らかな行いはできません。しかし、それでも仏法を依りどころとして生きていくことで、私たちは他者の喜びを自らの喜びとし、他者の苦しみを自らの苦しみとするなど、少しでも仏さまのお心にかなう生き方を目指し、精一杯努力させていただく人間になるのです。
まさにこのようなことでしょう。念仏者として生きるということは、「大悲のなかに、大慈恵のなかに、猫かにこの私がいる」とを感じることであり、自他の別、人間と自然を対立を超えた生き方ということになるのです。
(井上盟)
















