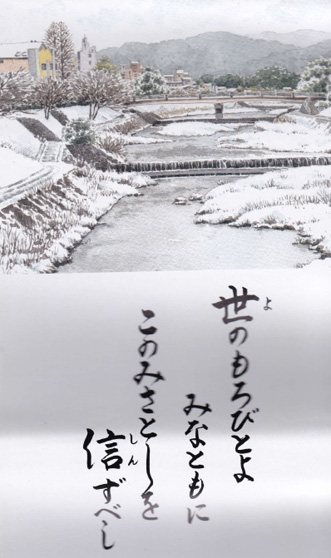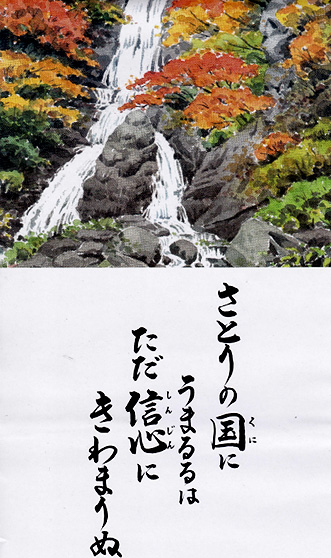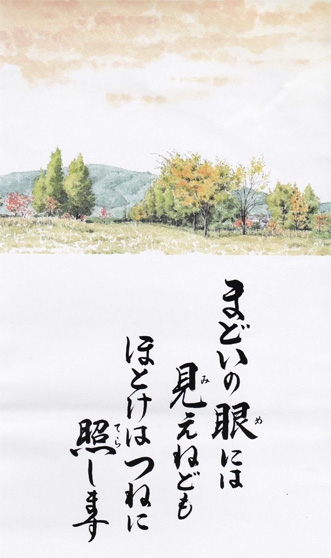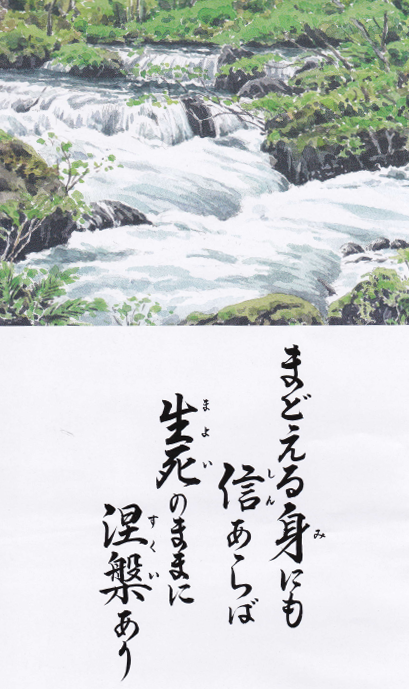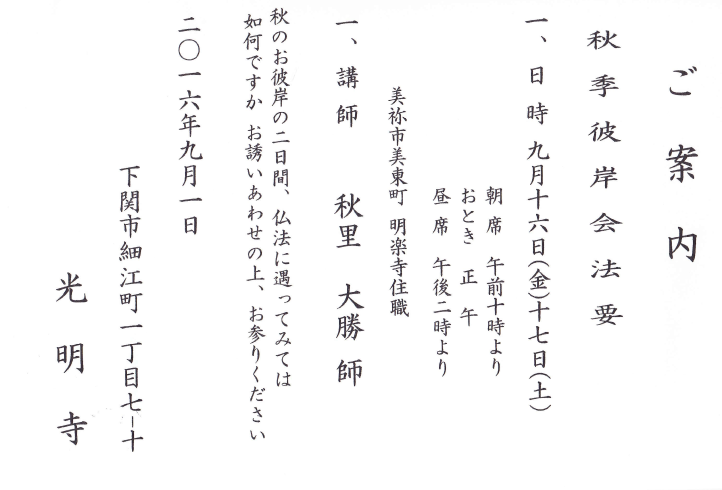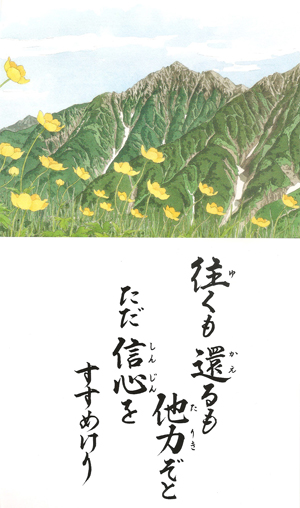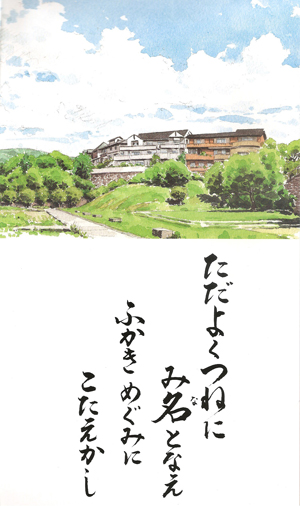「ひかりといのちきわみなき 阿弥陀ほとけを仰がなん」からはじまった「和訳正信喝」は、いよいよこの法語をもって締めくくられていきます.
ここは本文最後の二句「道俗時衆共同心(どうぞくじしゅぐどうしん) 唯可信斯高僧説(ゆいかしんしこうそうせつ)」〔道俗時衆(づぞくじしゅ)ともに同心(どうしん)に ただこの高僧(こうそう)の説を信ずべしと.〕
(『註釈版や典』一.0じ頁)
の意訳になります.
「このみさとしを信(しん)ずべし」とは、これまで「正信偶」で述べられた「仏説無量寿経」の法義、インド(直樹・天親)、中国(曇鸞・道棹・稗導)、日本(源信・源空)の七人の高僧方の教法におしたがいしましょう、という意味です。
ここでは釈尊が出世された本意はひとえに阿弥陀如来の本願真実を説かんがためであり.『にごりの世にしまどうもの おしえのまこと 信ずべし」(「五濁悪時群生海(ごじょくあくじぐんじょうかい) 応僑如来如実言」)(おうしんにょらいにょじつごん)と示された言葉にも対応し、この世のすべての人びとにたいし、高僧方の導きによって「おしえのまこと」である『仏説無量寿経』に説かれる本願を信じ念仏申す身となり、出家(道)も在家(俗)も.時の人(時衆)みなともに(共同心)、浄上に往生させていただきましょう、と勧められ、百二十句の渇文を結ばれるのであります.
親鸞聖人が教法を学ぶ姿勢は、「御伝紗」(ごでんしょう)の「愚禿(じとく)すすむるところ、さらに私(わたくし)なし」(「註釈版聖典」 一〇五じ頁)や「御文章」の「親鸞(しんらん)めづらしき法(ほう)をもひろめず」
(『註釈版聖典』一〇八四貝)
と述べられますように、あくまでも伝統の祖師方の教法に依られました.
もちろん聖人独自の経典理解や他には見られない教義の展開がありますが、祖師方が一切の経典の根本意趣を「仏説無量寿経」に説かれる本願念仏の救済と見定められたこと、また光寿無量の阿弥陀如来に帰順し浄土を願生されたこと、さらにそれぞれの時代と人間に相応した教法を樹立されたことなど、まさに命がけのご苦労があって教えが伝わってきたことを仰がれ讃えられるという一貫した態度が窺(うかが)えます。
「仏説無量寿経」には、法蔵菩薩が本願を建立し、一々の誓いが永劫(ようごう)の修行によって遂に完成され阿弥陀如来となり、その名は誓いの通りに喚び声となって一切の世界に響きわたり、しかも時はすでに十劫というはかり知れない歳月が経過している、と説かれています。それは私自身が。「無始(むし))よりこのかた」といわれるように果てしなく生死流転(しょうじるてん)を繰り返し、如来の願いに背を向け続けてきた時間の長さをも意味しています。しかしながら今生まれ難くして父母の縁によって仏法の聞こえる世に生まれ、通い難くして本願と出遇い、仏の仰せに信順し念仏巾す人生を恵まれたことは、まことにしあわせなことといわねばなりません。
今日一日のいのち
ところで、私の手元に「死の宣告をうけて 竹下昭寿こ坦書」(竹下哲編)と題された竹下昭寿さんという方の手記の写しがあります。
この方は若くしてガンを患い、昭和三十四年に三十歳で往生の素懐を遂げられました。同年一月六日にガンを告知され、三月二十五日にはすでに不治の病状であることを医師に宣告されます。
そしてその日から四月十二日まで日記を書き、病苦をかかえた日々の心境をありのままに綴られています。その内容は、まさに昭寿さんが歩まれてきた人生を締めくくる法悦の記録ともいえるものでした。
冊子の冒頭には担当であった高原医師が、
…その日が来た。思い切って船のともづなをふりはなして、船出の口がいよいよ迫ってきたことを告げる口である。病状は…胃ガンである。すでに不治の状態であることを宣告した。あと幾月か幾日かと数えるよりも。今日一日限りと心得て、今日一日を頂いて生きて行くべきことを語った。-何もかも我一人のためなりき 今H一日のいのちたふとし’―これは昭寿君に贈った一位である、君は何等動ずることなく、平然として私の宣告を受けとられた。人ならぬ大きな力に抱かれた君の姿に、私はただお念仏申すのみであった。この日から君の生活は明るくなり、念仏と感謝の生活になった。
…ただ徒に人生航海の日の長いことが幸福ではない。喜びも悲しみも乗り越えて、一路お浄上を目ざして誓願の大船に乗托して、名残惜しくも雄々しくも船出された君こそ、人生最大の勝利者である
{「遺書をいただいてI」)
という一文を寄せておられます。
故人は篤信の家庭に育ち、遺書を編集された実兄の竹ド哲さんや念仏者であった高原医師をはじめ、法義篤き人びとに囲まれながら生涯を終えられたのでした。
竹下哲さんは、
愛する弟昭寿は、お念仏を申しながら静かに息を引き取りました。静かな、静かな往生でした。親思い、兄弟思いのやさしい弟でしたが、とうとう三十年五か月の生涯を閉じてしまいました。何だか夢のようです。あとに残された私どもは、片腕を失ったような、限りない寂しさと悲しさでいっぱいです。このや
るせなさと悲しさは、とてもことばで一胃い表すことはできません。でも、何かその底にはしみじみとした喜びがあります。深い安らぎがあります。それは、弟が如来の人悲を讃嘆し、静かに念仏しながらお浄土に召されていったからだ、と思います
(弟のことII)
と記されています。
白道を歩いていく
医師から不治である旨を告げられた日、
…これからさき、どんな病苦にのたうちまわるかも知れない。…この世を去る以外にないのだ。しかしその宿業の果てには、親鸞聖人や唯円房が渡っていられる処があるのだ。そして、十五年前往っておられるお父さんも。この世の人
間の愛情の、なんと濃やかな中に、自分は生かされていたことだろう。三十年間の愛の火の中で。しかも何よりも、仏縁に恵まれていたことの良かったこと。すべては大慈悲の唯中に、いままでもいまも生かされているのだ。…
また五日後には、
お念仏の世界こそ、寂しいこの人生の明け幕れの中での落ち着ける場所ですから。ほんとに人生とは寂しいところ、名残おしいところです。愛別離苦という言葉もしみじみと味わわれます。でも、なつかしいお浄土が川意されてあるのです、限りなくなつかしい浄土-
四月九日には、
白道を歩いていく お母さんや兄ちゃんたちの やるせなき愛情を総身に浴びて それでもひとり白道を歩いていく いつかその道がつきたとき そこにはお浄土が開けている 多くの仏さまたちが時っていて下さる おお御苦労だっ
たと如来さまが 抱きとって下さろう もうそのときは仏の一員 病、衣、食、住の執着のないところ 無執着の世界-浄上 そこでほんとうに大切なことだけを 無限にやらせていただけるのだ
と、念仏に出遇うことのできた人生の意味について書いておられます。
そして翌日の四月十二日、
…一本願の船に乗せて頂いているという、大安心の上でのやっさもっさだ、大いにじたばたしても、往生は間違いなし 如来の願船のびくともしないことのありがたさ
という言葉で「遺書」は終わっています。
常住の世界への夜明け
親鸞聖人は『一念多念文意』に「念仏の人をば、上上人・好人・妙好人・希有人・最勝人とはめたまへり」
(「註釈版聖典」六八一。貞)
と述べられ、念仏する人は分陀利華(白蓮華)であり、五種の誉れがある人にほかならないと讃えられています。なぜなら蓮華は泥の中でしか咲かず、泥に根を張りながら泥とは真反対の美しい花を咲かせるからです。そのように念仏の人は煩悩の濁りに身を沈めながら濁りに染まることなく、必ず浄土に往生する美しき人であるといわれるのです。
昭寿さんは如来に抱かれ、諸仏に讃えられ、朋友に励まされて浄土へと往かれました。白道を歩む人とは煩悩の苦をかかえ孤独の中にあって苫や孤独に沈まず、生死の事実に処してなお生死を超える念仏を賜った人であるといえるでしょう。
兄の哲さんは記録を編集される中で、
人生は一応五十年の契約。しかし、家主が不意に出て行ってくれ、と言うことがある。そのとき、田舎に自分の家がある者は、「これまでお世話になりました。ありがとう。」と言って出て行ける
と書いておられます。
この世はたえず変化しとどまることがなく、煩悩に満ちた世界です。この世で生きていく限り、私たちの惑い、苦しみ、悩み、悲しみは尽きることがありません。
しかしながら、尽十方無擬光の如来(煩悩にさえられずに十方を照らし尽くす光の仏)はこの世に来って生死を照らす光となり、苦悩にうちひしがれ孤独に涙するものの灯火となり、帰すべき郷里へと必ず導いてくださいます。光を信じ御名を称えることは暗き人生の暁となり、むなしく命終わることなき常住の世界への夜明けとなるのです。
阿弥陀如来は「安心して帰せよヽわが世界に至れよ」と一人ひとりの苦悩の人生に
喚びかけられています。そして私が称える念仏には、親鸞聖人をはじめ三国の祖師方、さらに浄上に往生された幾多の念仏者の願いがこもっていることが知られます。
この「正信喝」は自信教人信の書であるといわれます。本願のまことは「親鸞一人がため」(自信)と聖人によって受けとめられ、さらに「十方衆生みなもれず往生すべし」(教人信)とすべての人々に開かれた救いでありました。親鸞聖人は自ら信じたよりとされたこの「みさとし」を、すべての人びとに「どうか信じてください、お念仏申してください」とよびかけられているのです。
すべて命あるものは、幸福であれ、安穏であれ、安楽であれ
(「スッタニパータ」 一四五濁)
仏陀は生きとし生ける者すべてを安楽、安穏の境地に至らしめたいと願われました。