2012年4月8日、下関は霊鷲山(りょうじゅせん)にて花まつりが開催されます。
検索したい語句を入力
光明寺について
ご参拝・法要ガイド
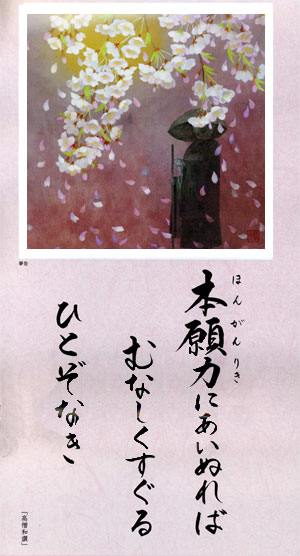 浄土真宗のお救い
浄土真宗のお救い
今月の法語のご和讃は、
本願力にあひぬれば
むなしくすぐるひとぞなき
功徳の宝海(ほうかい)みちみちて
煩悩の濁水(じょくすい)へだてなし(『註釈版聖典』五八〇頁)
阿弥陀さまのお救いのはたらきのなかで生きている人で、この世を空しく過ごす人はいません。それは阿弥陀さまの功徳がその人に海のように満ち溢れるようになるからです。汚れた水のような煩悩も、そのはたらきを遮ることはないのです。
という、『高僧和讃』「天親讃(てんじんさん)」のなかの一首の前半部で、『浄土論』「不虚作住持功徳(ふこさじゅうじくどく)」の、
仏の本願力(ほんがんりき)を観ずるに、遇ひて空しく過ぐるものなし。
よくすみやかに功徳の大宝海(だいほうかい)を満足せしむ。(『註釈版聖典(七祖篇)』三一頁)
という偈文がもとです。この偈文は、お名号を聞信(もんしん)すると、即時に阿弥陀さまの功徳が私の心に満ちて、必ず往生浄土できるという趣旨です。この法語は、「少しでも早く阿弥陀さまの願いとはたらきに気づいてください。<自分のいのちのゆくえ>を知った人の人生は、安らかで豊かな人生ですよ」という、親鸞聖人の思し召しです。
このお心をたずねてみましょう。
阿弥陀さまは私を救うとおっしゃいますが、どのように私を救っていてくださっているのでしょうか。そのことについて、『往生礼讃』には「光明名号摂化十方」(光明・名号をもつて十方を摂化(せっけ)したまふ 『註釈版聖典(七祖篇)六五九頁』)と示されています。
また、『高僧和讃』では、
無碍光如来(むげこうにょらい)の名号(みょうごう)と
かの光明智相(こうみょうちそう)とは
無明長夜(むみょうじょうや)の闇(あん)を破(は)し
衆生の志願をみてたまふ(『註釈版聖典』五八六頁)
阿弥陀さまのお救いのはたらきであるお名号と、その智慧の光明は、無明である私の迷いの闇を破っています。ありがたいことに、阿弥陀さまのお名号は、すべての衆生の願いを満たしてくださっているのです。
と、阿弥陀さまは光明で衆生を摂取不捨し、お名号で衆生を招喚(しょうかん)していると、親鸞聖人がお示しになっています。
浄土真宗のお救いは光明と名号にあります。阿弥陀さまの衆生救済のはたらきを本願力といいますが、これはお慈悲・仏力・名号ともいいます。風が吹いても、私の体にあたらないと、風の涼しさを感じることができません。阿弥陀さまのはたらきがなければ、私からお念仏がでるはずがありません。私からお念仏がでるのは、阿弥陀さまのはたらきがあるからです。私には「本願の名号をもつて十方(じっぽう)の衆生にあたへたまふ」(『一念多念文意』『註釈版聖典』六七八頁)と、お名号によるお救いがかかっているのです。「本願力にあひぬれば」の「あひ(あい)」は「遇う」で、これはまったく予想していない出会いをあらわしている字です。本願力に遇えば、「本願力を信ずる」(『同』六九一頁)身となり、「むなしくすぐるひとなしといふ」(『同』)人生になってきます。これは「信心あらんひと、むなしく生死(しょうじ)にとどまることなしとなり」(『同』)と、お浄土に向かって生きるようになるという意味です。
人生の大事
人生の大事は念仏に遇うことであると教えているのが浄土教です。それは、
一切の群生海(ぐんじょうかい)、無始(むし)よりこのかた乃至(ないし)今日今時(こんにちこんじ)に至るまで、穢悪汚染(えあくわぜん)にして清浄(しょうじょう)の心(しん)なし、虚仮諂偽(こけてんぎ)にして真実の心(しん)なし。
(『教行信証』「信文類」『註釈版聖典』二三一頁)
という存在の私だからです。「ここをもつて如来、一切苦悩(いっさいくのう)の衆生海(しゅじょうかい)を非憫(ひびん)して」(『同』)、と、苦悩の衆生を救いたいと願いをたてて、お名号を成就したのが阿弥陀さまです。すべての人を「必ず救う」と誓い願った阿弥陀さまが、その願い通りに衆生を救済しているはたらきがお名号です。『教行信証』「行文類」に、『往生論註』の、
願(がん)もつて力(りき)を成(じょう)ず、力もつて願に就く。願徒然(とねん)ならず、力虚設(こせつ)ならず。力・願あひ符(かな)ひて畢竟(ひっきょう)じて差(たが)はざるがゆゑに「成就」といふ。
(『註釈版聖典(七祖篇)』一三一頁)
というご文を引用して、お念仏は阿弥陀さまの願いと救済力がぴたっとひとつになって、私を救ってくださっていると示されています。『教行信証』「行文類」一乗海釈の最後で、「まことに奉持(ぶじ)すべし、ことに頂戴すべきなり」(『註釈版聖典』二〇二頁)といわれるように、招喚の勅命を「疑心あることなし」(「信文類」『同』二五一頁)にいただくばかりです。
曇鸞大師(どんらんだいし)は、『往生論註』で三依(さんえ)(何所依・何故依・云何依 『浄土真宗聖典(七祖篇)―原典版―』六三頁、参照)から、阿弥陀さまはまちがいない仏と証明をして、阿弥陀さまが真実だから帰依をするといわれています。阿弥陀さまの真実心を不顛倒(ふてんどう)といい、分けへだてがない仏さまだと説明をして敬っておられます。
煩悩を転じる
そこで、「一乗海釈」の二教対(にきょうたい)・二機対(にきたい)をみてみましょう。親鸞聖人は、念仏行は易く諸行は難しいと、四十七通りに念仏と諸行を比較しておられます。要は、阿弥陀さまのお慈悲は、強くて・深くて・広くて・速くて・優れて、これ以上の仏さまはいないといわれています。私を救ってくださる仏さまは阿弥陀さま以外にはいないと結論をされました。
ここで注意したいのは、阿弥陀さまのお救いを海に喩えておられるところです。お名号を海に喩えられているのは、海には同一鹹味(どういつかんみ)の潮に変えなす力があるからです。
そこで、お名号は有漏の身を仏に転じる力があると、海の転成(てんじょう)の力を阿弥陀さまの本願力に転用されているのです。それを「如衆水入海一味(にょしゅしいにゅうかいいちみ)」(「正信偈」『日常勤行聖典』一二頁)(衆水(しゅすい)海に入りて一味なるがごとし『註釈版聖典』二〇三頁)とか、
弥陀(みだ)智願(ちがん)の広海(こうかい)に
凡夫(ぼんぶ)善悪の心水(しんすい)も
帰入(きにゅう)しぬればすなはちに
大非心(だいひしん)とぞ転ずなる(『正像末和讃』『註釈版聖典』六〇七頁)
阿弥陀さまの広大なお慈悲には、転成の力があります。衆生救済のはたらきである本願力に、善悪を沙汰する凡夫が帰依すれば、ちょうど海に川の水が流れ込み溶け合ってひとつの塩辛い水になるように、凡夫のさまざまな心は、阿弥陀さまの大慈悲へと変わってしまうのです。
といっておられます。
また、善導大師は、
浄土対面してあひ忤(たが)はず 無量楽(むりょうらく)
弥陀の摂(しょう)と不摂(ふしょう)とを論ずることなかれ 願往生(がんおうじょう)
意(こころ)専心にして回(え)すると回せざるとにあり 無量楽(『般舟讃(はんじゅさん)』『註釈版聖典(七祖篇)』七三三頁)
といっておられます。この文意は、<私は阿弥陀さまに救ってもらえるのだろうか、それとも救われないのだろうか>と、心配したり悩む必要はない。それよりも、私がお浄土にむかって生きているかどうか、今の生き方が大切なことだ、というお示しです。親鸞聖人はこのご文を大事にされています。『教行信証』の「信文類」と「化身土文類」にこの文を引用され、その心を『高僧和讃』に、
金剛堅固(こんごうけんご)の信心の
さだまるときをまちえてぞ
弥陀の心光摂護(しんこうしょうご)して
ながく生死(しょうじ)をへだてける(『註釈版聖典』五九一頁)
阿弥陀さまのお慈悲を領受すれば、どのような状況になっても、不退転の信心に定まります。そうなれば、阿弥陀さまの慈悲の光明に護り摂め取られた身になりますから、いつまでも生死の迷いから離れることができるのです。
と説かれています。
さらに善導大師は、「恵みの雨をえても朽ちた林には芽がでてこない。また大きな石の中までは潤うことがない」(『観経疏(かんぎょうしょ)』「玄義分(げんぎぶん)」取意)と誡めておられます。
ここでは、善導大師が、朽ちた木やかたい石に、花が咲いたり水が潤うことはありえませんが、私たちには回心(えしん)があるので心の向きを変えなさい、とすすめておられるのです。そこで、『教行信証』「行文類」は、『観仏三味経』の伊蘭(いらん)と栴檀(せんだん)の喩えを引用し、念仏の功徳の広大さをお示しになりました。それは、悪臭がする伊蘭の林に栴檀が生えてくると、伊蘭の悪臭は消えてはいないが、そのまま栴檀の芳ばしい香りにつつまれてくる、という喩えです。
蓮如上人は、これを、
一念の信力にて往生定まるときは、罪はさはりともならず、されば無き分なり。
命の娑婆にあらんかぎりは、罪は尽きざるなり。(『蓮如上人御一代記聞書』第三十五条 『註釈版聖典』一二四四頁)
といわれています。煩悩具足の身であるが、お名号の功徳によって<無き分なり>の世界に転じられ、生きるようになるといわれています。海が衆水を同一鹹味(どういつかんみ)の潮に変えなすように、栴檀が伊蘭の悪臭を芳ばしい香りに変えなすように、煩悩だらけの私を仏になる身に転じてくださるのが、本願力の大いなるはたらきなのです。
お慈悲のどまんなか
阿弥陀さまのお救いを聞くか聞かないかに、私の救いの人生がかかっています。このことに少しでも早く気づいて、阿弥陀さまに近づく人生にきりかえるべきです。私を導いてくださるのは、教えであり、善知識です。
よき人の仰せにききてみ名を呼べば
喚ばはせたまふみ声きこえぬ(『仏と人』三五九頁)
と池山栄吉先生が詠んでいます。先生は、講演会で「なんぢ一心正念(いっしんしょうねん)にしてただちに来(きた)れ。われよくなんぢを護らん」(『観経疏』「散善義」『註釈版聖典(七祖篇)』四六七頁)という、善導大師の「二河白道(にがびゃくどう)の譬(たとえ)」の言葉をよく引用されていたそうです。
そして、池山先生は、次のように申されていました。
念仏の心意気は、「一心正念直来(いっしんしょうねんじきらい)」の言葉のなかによく現れている。これを流浪の旅を続ける一人子の帰りを、ふるさとに待ちわびる母の心に喩えるなら、「直来」をスグキテオクレヨと訓じ、「一心正念」にオネガイダカラと仮名をふってそう見当はずれではあるまい。「オネガイダカラ、スグキテオクレヨ」。この哀情が、相手の心にしみいり感銘した極促が、やがてそのまま内からしみでて帰心ともなり、念仏もうさんとおもいたつ心ともなるのである。
煩悩をのけた念仏は便所のない別荘だ。どんな立派な座敷でも便所がなくちゃ住めない。煩悩めあての念仏でこそ、われわれの安住所である。
このように言われることが先生の口癖で、このお話からたくさんの人を導かれたと恩師から聞いたことがあります。
音信不通の母を思い出した時に、思わず「お母ちゃん」とつぶやいたことがありませんか。親を忘れて暮らす私ですが、親はいつも私を心配しつづけています。阿弥陀さまを忘れて日暮しをしていても、阿弥陀さまは私をいつも心配しています。これを知れば、「ナンマンダブ ナンマンダブ」とお念仏がこぼれてきます。聞けば聞くほど、「どうか救われてくれよ」とたのまれている私だと知らされるのです。知れば知るほどもったいないことです。
浅原才市さんが、
うれしいか ありがたいか
ありがたいときゃ ありがたい
なっともないときゃ なっともない
才市 なっともないときゃ どぎゃぁすりゃ
どがあもしようがないよ
なむあみだぶつと
どんぐり へんぐり しているよ(梯實圓著『妙好人のことば』一六五頁)
と詠っています。私はこの心情に共感をおぼえます。ありがたい、ありがたくないというのは、私の心の問題でしょう。お念仏には、阿弥陀さまのお慈悲のありったけがこもっています。阿弥陀さまのお心すべてを疑いなく、「ありがとうございます。ナンマンダブツ」と、お念仏している才市さんです。お念仏は法体全顕(ほったいぜんけん)の称名なので、お念仏は阿弥陀さまが私に回向してくださるお慈悲そのものといえます。阿弥陀さまのてもとでは名号といい、名号が私の心にとどけば信心といい、それが私の口からでれば念仏といいます。言い方はちがっても、名号・信心・念仏は同一のものがらです。
才市さんは、教えを覚えて、それを理解をしてから、お念仏をしているのではありません。才市さんは阿弥陀さまの御心にとびこみ、安心しきってお念仏しているのですね。まるでお母さんが両手で迎えているその姿に、幼子が飛び込んでいっているようです。なんのくったくもなく、お母さんのふところで生きているような才市さんです。阿弥陀さまとともに生きている喜びだけが伝わってきます。お慈悲のどまんなかで、うれしそうにお念仏している才市さんの姿があります。
お念仏の功徳
親鸞聖人は『教行信証』「行文類」で、「大行(だいぎょう)とはすなはち無碍光如来(むげこうにょらい)のみ名を称するなり」(『註釈版聖典』一四一頁)と、私が称えている念仏がどういうものかを明らかにしておられます。お念仏が私の往生行となるのは、お念仏に阿弥陀さまのすべての徳がそなわっているからです。これを、「化身土文類」には「この嘉名(かみょう)は万善円備(まんぜんえんび)せり」(『註釈版聖典』三九九頁)とか、「正信偈」に「本願名号正定業(ほんがんみょうごうしょうじょうごう)」(本願の名号は正定の業なり『同』二〇三頁)とお示しです。お念仏には仏徳のすべてがこもっているので、お念仏する人はお浄土に往生ができ、阿弥陀さまと同じ徳をもつ仏さまになれるのです。そうだから、才市さんはいつもうれしいのですね。
本願を信じ念仏するしか仏になりえない私であることを、知らされるばかりです。
(鎌田宗雲)
 光明寺のホームページ開設1周年にあたり、期間中ホームページからお問い合わせいただいた方にささやかではございますが、記念品をご用意しております。皆様のご意見を元により良いホームページを作っていきたいと思います。どうぞ今後とも宜しくお願いいたします。
光明寺のホームページ開設1周年にあたり、期間中ホームページからお問い合わせいただいた方にささやかではございますが、記念品をご用意しております。皆様のご意見を元により良いホームページを作っていきたいと思います。どうぞ今後とも宜しくお願いいたします。
【期間】2012年3月1日~2012年3月31日
【記念品発送】2012年4月末~5月上旬予定
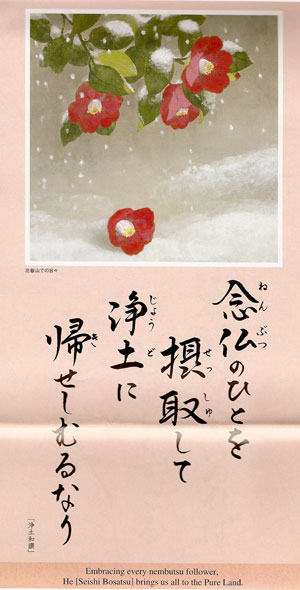 勢至菩薩の勧め
勢至菩薩の勧め
今月は、『浄土和讃』の一節から、親鸞聖人のお心を味わってみたいと思います。
まず、その言葉を掲げてみます。
念仏のひとを摂取して
浄土に帰せしむるなり
大勢至菩薩(だいせいしぼさつ)の
大恩(だいおん)ふかく報ずべし(『註釈版聖典』五七七頁)
(勢至菩薩は、今、この娑婆世界で、)念仏を称える人を浄土に往生させようと、護りはたらいてくださっています。阿弥陀さまに救われることによって、このような勢至菩薩の恩に深く感謝し報いなければなりません。
という和讃の前半部が、今月のご文になっています。
この和讃は、一つ前の和讃と一連のものになっています。ですから、二つの和讃を一緒に読みますと、よく理解されてきます。また第一句は、龍谷大学蔵の蓮如上人による文明五(一四七三)年の開版本、いわゆる文明本では、「念仏のひとを摂取して」とありますが、もともと国宝本(真筆本)では、「念仏のひとを摂してこそ」というご文になっています。
では、まず摂取についてでありますが、ここでは阿弥陀さまが摂取するという意味とは異なります。それは、摂取の主語が大勢至菩薩であるからです。この和讃は、「勢至讃」八首のなかの一首ですが、その冒頭には「『首楞厳経(しゅりょうごんぎょう)』によりて大勢至菩薩和讃したてまつる」(『註釈版聖典』五七六頁)とあり、文末には「源空聖人御本地(げんくうしょうにんごほんじ)なり」(『同』五七七頁)とあります。勢至菩薩の智慧の念仏が源空聖人という念仏者となって現れるという意味ですから、その言葉によっても、ここでは勢至菩薩の摂取をいわれているということがわかります。
さて、今、阿弥陀仏の摂取とは違うということを申しました。そこで、ここでの摂取とはといいますと、念仏を勧め、往生浄土の道をはずれないように護ることを意味しています。それは、
弥陀(みだ)・観音(かんのん)・大勢至(だいせいし)
大願(だいがん)のふねに乗じてぞ
生死(しょうじ)のうみにうかみつつ
有情(うじょう)をよばうてのせたまふ(『正像末和讃』『同』六〇九頁)
阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩の方がたは、本願の船に乗船して、生死の迷いの海に浮かびながら有情を呼び続け、本願の船に乗せてくださるのです。
と、讃詠されている和讃にも示されています。大願の船によって生死の海を渡るのが弥陀の摂取であり、有情に船に乗るように勧められるのが大勢至菩薩であります。それは言い換えると、大勢至菩薩が本願の信を勧めておられるということなのです。
影と形
勢至菩薩の摂取は、影の形に添うように随逐影護して浄土に帰せしめるはたらきであるといわれます。また、浄土に往生させるはからかであるといわれます。立ち上がっても、勝手に私は影と離れることはできません。私が行くところに影はついてきます。どこまでも影と一緒です。影の方からは形に寄り添って護っているようにみえます。そのようなはたらきを、「浄土に帰せしむるなり」といわれているのです。
また、影という文字は影現という熟語として用いられることがあります。
無礙光仏(むげこうぶつ)としめしてぞ
安養界(あんにょうかい)に影現(ようげん)する(『浄土和讃』『註釈版聖典』五七二頁)
無礙光仏という姿となって、安養浄土に現れてくださいました。
釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)としめしてぞ
迦耶城(がやじょう)には応現(おうげん)する(『浄土和讃』『同』)
お釈迦さまという人間界に応じた姿となって、迦(伽)耶城に現れてくださいました。
というように、安養界には影現といい、伽耶城には応現と使い分けておられるのも、興味深いものがあります。
『唯信鈔文意』には、
観音・勢至はかならずかげのかたちにそへるがごとくなり。
(『註釈版聖典』七〇一頁)
などと、影が形に添っていることを、仏法を護ることに喩えたり、阿弥陀仏の名を信受する者を護るということに喩えられています。
親鸞聖人の譬喩
親鸞聖人は、譬喩を多く用いて、教えを分かり易く示されているように思います。たとえば、如来の世界も衆生の世界も、海で表されています。「正信偈」に、
唯説弥陀本願海(ゆいせつみだほんがんかい)
五濁悪時群生海(ごじょくあくじぐんじょうかい)
応信如来如実言(おうしんにょらいにょじつごん)(『日常勤行聖典』一一頁)
(ただ弥陀(みだ)の本願海(ほんがんかい)を説かんとなり。
五濁悪時(ごじょくあくじ)の群生海(ぐんじょうかい)、
如来如実(にょらいにょじつ)の言(みこと)を信ずべし。
『註釈版聖典』二〇三頁)
と詠われているのがそれです。仏の世界も凡夫の世界も海だということは、何を示されているのでしょうか。それは、阿弥陀さまのはたらき場所が、この娑婆世界にあるということをいっておられるのだと思われます。この私を離れて阿弥陀さまはないということを明らかにしようとされているのだといえます。
また、『教行信証』行文類末の「一乗海釈」では、弘誓の一乗海を表すのに、二十八の喩えが示されています。その一つの例に磁石の喩えがあります。
なほ磁石のごとし、本願の因(いん)を吸ふがゆゑに
(『註釈版聖典』二〇一頁)
という言葉です。本願の因とは、煩悩にまみれたわれわれ衆生のことを指します。それで、磁石は鉄を吸い付けます。それは、磁石が鉄のなかに入っている状態です。鉄の方から動いているように見えますが、鉄が吸い付けられているのです。磁石が仏で、鉄が衆生と考えれば、磁石が遠くにあって、鉄が「こちらへこい」といっているわけではありません。磁石の方から鉄に入りこんでいるのです。このような状態は、摂取不捨とか他力ということを示していると窺えます。
他にも、親鸞聖人は譬喩をいくつか用いられ、教説のなかに彩りを添えておられるように思われます。
違いを認める
さて、勢至菩薩は念仏の人により添って浄土に帰せしむるという、その浄土について少し考えてみたいと思います。今、和讃に浄土の世界について、
清風宝樹(しょうふうほうじゅ)をよくときは
いつつの音声(おんじょう)いだしつつ
宮商和(きゅうしょうわ)して自然(じねん)なり
清浄薫(しょうじょうくん)を礼(らい)すべし(『浄土和讃』『註釈版聖典』五六三頁)
お浄土で、宝樹の間を清風が吹く時には、宮・商・角・徴・羽の五つの音色が自然に調和して響き渡っています。このような清浄な薫りの浄土の主である阿弥陀さまを礼拝しましょう。
と述べられているなか、「宮商和して」という語に注目してみたいと思います。お浄土は、もともと不協和音である宮と商の音が和する世界だといわれるのです。これは、違いがあってこそ存在する意義があるという、考えにつながっているように思います。浄土の世界は、違っているまま、それぞれが輝いているのです。『阿弥陀経』のなかの、
青色(しょうしき)には青光(しょうこう)、黄色(おうしき)には黄光(おうこう)、赤色(しゃくしき)には赤光(しゃくこう)、白色(びゃくしき)には白光(びゃくこう)ありて
(『註釈版聖典』 一二二頁)
とある文は、そのことをあらわしています。
私たちは、なかなか違いをそのまま認めようとしないところがあります。よく対話するということを申します。対話には、お互いの違いをはっきりと認め合うということが、基本的な前提としてあります。説得になってはいけないということです。言葉でもそうです。たとえば、溢れるとこぼれるという二つの言葉がありますが、こぼれるは溢れるではありません。また、溢れるもこぼれるではないのです。美しいときれいという二つの言葉もそうです。しかし、また同時に、共通の現象を想像することができます。どちらの言葉も根底のところではひとつだということです。
このような立場に立って考えますと、お互いほめ合っている姿が思い浮かびます。先の『阿弥陀経』の言葉も、それぞれが輝いているという根底には、ほめ合っているということがあると思います。
『阿弥陀経』には、浄土には共命(ぐみょう)の鳥がいるとあります。頭が二つで、胴体が一つの鳥です。一身に両頭を有するというものです。このような鳥が生存するためには、互いの頭がけんかしたり嫉妬していては生きていけません。こういう話があります。
それは、どちらもきれいな声で鳴くのですが、いずれも自分の方が勝っていると言ってゆずらない。ある時、一方の鳥がもう一羽の方がいなければということを考えました。寝ている時に、毒を飲ませます。死んでいく様子を見ていたその鳥も、やがて毒が回って死んでしまったということです。だから、こういう鳥が存在するということは、お互いきれいな声だとほめ合っているということでしょう。
覚りの世界
ところで、親鸞聖人の浄土観はどのようなものでしょうか。よく知られた『御消息』のなかの文が浮かんでまいります。
この身は、いまは、としきはまりで候へば、さだめてさきだちて往生し候はんずれば、浄土にてかならずかならずまちまゐらせ候ふべし。
(『親鸞聖人御消息』『註釈版聖典』七八五頁)
とありますように、親鸞聖人がお弟子の有阿弥陀仏(ゆうあみだぶつ)という方に、「お浄土でかならずお待ちしています。お会いできることを楽しみにしていますよ」とおっしゃっておられます。私たちは、この世で親子や夫婦と会っていると思っています。しかし、それは仮の出会いといえるようです。本当に出会うのは、お浄土においてであえるといえましょう。
また、親鸞聖人は、浄土の世界を覚りの世界として説明されています。覚りの世界だから救うということが成り立つのです。帰って行く世界を持たせていただくことは、誠に尊い、これこそ本当の幸せということであります。
そういう浄土への道をはずれないように念仏を勧めてくたさるのが、大勢至菩薩であり、念仏を申して生きていくということは、生きる方向性がはっきりしていくということです。先哲の歌に、
一輪の花を飾りて今日もまた
浄土へ帰る旅を続けん
というものがあります。一輪の花とは、お念仏のことと味わうことができます。一歩一歩がお浄土への旅だということは、歩む方向がはっきりしているということです。
あるお寺の掲示板に、
一泊の旅は楽しい
永遠に帰れない旅もある
油断すべからず
とありました。帰る家があるから一泊の旅は楽しいのであり、「水遠に帰れない」とは、迷い続けなければならないことをいっているのです。
「報ずべし」の「べし」は命令形でありますが、ここではそれを、自己の誓いとして受け止めておられるといえます。今、大勢至菩薩は法然聖人の本地でもありますが、大勢至菩薩が念仏する人をよく摂め護って弥陀の浄土へ帰入できるようにしてあげたいといわれた大恩に、深く感じ報わなければなりません。
(大田利生)
 障りと徳
障りと徳
今月は、『高僧和讃』「曇鸞讃」のなかの一節をとりあげて、そこに現されている深い心に聞いていきたいと思います。
まず、そのご和讃を取りあげてみましょう。
罪障功徳(ざいしょうくどく)の体(たい)となる
こほりとみづのごとくにて
こほりおほきにみづおほし
さはりおほきに徳おほし
(『註釈版聖典』五八五頁)
罪や障りが覚りのもととなります。氷と水の関係のなかで、氷が多ければ水も多いように、障りが多ければ、覚りの徳も多いのです。
この和讃の第三句・第四句目が、今月のご文として引用されています。
最近、親鸞聖人の真筆として世に出ました『信微上人御釈(しんびしょうにんおんしゃく)』(本願寺蔵)のなかに、
障り滅れども去なる所ろ無し、冰り解て水と為るが如し、冰多れば水多し、障り多れば徳多し。
(『浄土真宗聖典全書』第二巻、九八三頁・原漢文)
という言葉があります。障りがなくなるといっても、どこかに消えていってしまうのではありません。それは、ちょうど氷が解けて永となるようなものです。形は変わっても、その本質はひとつであるということです。そして、次の文は今の和讃の言葉と同じであります。氷は煩悩に、水は菩提に喩えられます。ですから、氷が解けて水になるということは、煩悩がそのまま菩提になるということで、煩悩を離れて菩提はないし、菩提は煩悩と体ひとつだということになります。また、煩悩の氷が多ければ多いだけ、解けた水も多くなる。氷の分量と水の分量が比例するということです。このような関係を思ってみますと、煩悩が起こっている私のところにこそ、阿弥陀さまのはたらく場があると味わわれます。煩悩が多ければ多いだけ、仏の力というものもそれにつれて多くなるということです。
ある方が、「われわれの罪や煩悩が、そっくりそのまま覚りの種だ」と言っておられました。心に残っている言葉であります。ある方は、「『さはりおほきに徳おほし』と言い切れる世界が開けた人は、豊かな人生を生きられるでしょうね」と言われておられました。人生には、さまざまなつらいこと、苦しいことが、また障りが起こってきます。なぜ、こんな苦しい人生を生きねばならないのだろう、と思うこともあります。そんな時、「さはりおほきに徳おほし」という言葉が、どのように響いてくるでしょうか。障りを通して徳が昧わえるような視野が開かれていくのが「信心の智慧」だ、ということだと思われます。
ずいぶん前のことになりますが、妙好人(みょうこうにん)を訪ね、有福(ありふく)の善太郎さんのお寺にお参りしたことがあります。その時、ご住職から次のようなお話をうかがいました。
善太郎さんはもともと”毛虫の悪太郎”と嫌がられ、残された手記によりますと、
善太郎は父を殺し、母を殺し
その上には盗人をいたし、人の肉をきり
その上には人の家に火をさし
その上には親には不孝のしずめ
(菅真義著『妙好人 有福の善太郎』二〇頁)
と告白しています。そういう善太郎さんが、お念仏を喜ぶ身となっていかれたということをお聞きしながら、親鸞聖人の今の和讃が心に浮かんできました。恐ろしい顔つきのクチビルがいつの間にかモグモグ動いて、静かな念仏の声が出るようになったといわれています。まさに、「さはりおほきに徳おほし」の言葉どおりの姿を見るようであります。
「二河白道の譬」
この和讃を味わう時、今一つ思い出されるのは、煩悩のなかに清浄な往生を願う心が生ずるという、有名な善導大師の『観経疏(かんぎょうしょ)』「散善義」の「二河白道(にがびゃくどう)の譬(たとえ)」です。 その内容を少し辿ってみることにします。
その冒頭には、
人ありて西に向かひて百千の里を行かんと欲するがごとし。
(『註釈版聖典(七祖篇)』四六六頁)
とあって、その旅人は旅の途中で二つの河に出合います。一つは火の河、今一つは水の河です。善導大師は、同じく「散善義」のなかで、
「水火二河」といふは、すなはち衆生の貧愛(とんない)は水のごとく、瞋憎(しんぞう)は火のごとくなるに喩ふ。
(『同』四六八頁)
と示されています。そして、
二河おのおの閥さ百歩、おのおの深くして底なし。南北辺なし。
(『同』四六六頁)
と続きます。この「深くして底なし」というのはわれわれの煩悩の底が限りなく深く暗いということを表しています。『歎異抄』の、
さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまひもすべし
(『註釈版聖典』八四四頁)
という言葉が思い浮かびます。人間の限りない暗さと悪への可能性を読み取ることができます。さらに、「南北に辺なし」という文が深い意味を添えます。深さだけではなく、広がりをもって煩悩を表しています。
ついで、
まさしく水火の中間(ちゅうげん)に一の白道あり。闊(ひろ)さ四五寸ばかりなるべし。
(『註釈版聖典(七祖篇)』四六六頁)
とあり、水の河・火の河の中間に、四・五寸ばかりのわずかな幅のIつの白道がありますと述べられています。
その白道について、善導大師は、
衆生の貪瞋(とんじん)煩悩のなかに、より清浄(しょうじょう)の願往生心(がんおうじょうしん)を生ずるに喩ふ。
(『同』四六八頁)
といわれていますが、このなかの「煩悩のなかに」といつ文に注目したいと思います。
それは、煩悩を離れて清浄願往生心はないということです。煩悩が清浄願往生心を起こさしめているということです。
泥中の蓮華
よく知られている『維摩経(ゆいまぎょう)』のなかに出てくる、煩悩の泥中に咲く蓮華の話もそうです。
讐えば高原の陸地は蓮華を生ぜず、卑湿(ひしつ)の淤泥(おでい)は乃ち此の華を生ずるが如し。(中略)煩悩の泥中に乃ち衆生有りて仏法を起こすのみ。
(『維摩詰所説経』『新国訳大蔵経』文殊経典部二、一〇一頁)
とありますように、蓮華が淤泥に染まらず、淤泥のなかから美しく咲いています。もちろん、ここで淤泥は煩悩に、そして蓮華の花は菩提に喩えられます。煩悩こそ仏道を成り立たしめている素材ということになります。
煩悩にそのような意味があるとすれば、闇と明かりの関係で考えますと、闇、そして暗いところはダメで、明るいところが肯定され価値が認められるという見方は、少し考え直さなければならないといえるでしょう。たとえば、こんな話を聞いたことがあります。朝顔は、朝、太陽の光に当たって咲きます。確かにそうだと思っています。しかし、夜の長い時間をくぐりぬけ、そして朝の陽に当たって咲くのだという見方もできます。もし、そのように考えることができるとすれば、闇に対する考え方を少し変えなければならないと思います。親はわが子のため涙を流しながら、長い夜を通り過ぎて、初めて本当の親になるのだといわれます。現代は、どこか暗いところを切り捨て、かえりみることをしなくなった時代のように思えてなりません。
智慧のはたらき
ところで、障りが功徳に転換するといわれる場合、その転換は智慧のはたらきによるものです。智慧は知識とは違います。知識には行き詰まりがあります。さますまな出来事が起こり、それを解決しようとすれば、知識では解決できない問題も生じてきます。もっとも生きていく上においては、知識も必要です。豊かな生活を送るためには、知識がなくてはなりません。ですから、けっして知識がいらないといっているのではありません。
仏の教えは、何ものにもさまたげられない行き詰まりのない世界を知らせてくださるのです。その仏さまの教えによって新しい領域に気付かされ、救いにあずかるということができるのです。それは智慧の眼をいただくということです。肉眼(にくげん)・天眼(てんげん)・慧眼(えげん)ということがいわれます。私たちがいかに物を見ているようで見ていないかということを思い知ることができます。障子一枚向こうは誰が何をしているのか分からないのですから。
高性能の望遠鏡によって、五十億光年という遠くの星が観測できるようになったといわれています。しかし、それは、宇宙全体からみれば全天の一点にすぎません。また、精度の高い電子顕微鏡によって、十の十八乗分の一の世界が見られるようになったともいいます。しかし、それ以上の極小の世界は、見ようとして光のエネルギーをあてますと、かえって見えなくしてしまうということを聞きます。いずれにしても、私たちの眼で見える世界には限界があるのです。
このような人知を超え、智慧の眼をいただくということがなくては、転換は成り立ちません。それが信心の智慧をいただくということです。
渋柿の渋がそのまま甘味かな
という歌のごとく、転成(てんじょう)とは、渋がなくなって甘くなるのではなく、太陽の光を受け養分を取って、渋のままが甘くなるのです。大きな力によって転じられていくのです。
氷もその本質は水でありますから、熱を加えれば水に転ずることができます。この煩悩成就の凡夫がそのままで、如来の本願力によって救われていくということです。
信心の利益
親鸞聖人は、曇鸞大師(どんらんだいし)を讃えられる和讃のなかで、
本願円頓一乗(ほんがんえんどんいちじょう)は
逆悪摂すと信知して
煩悩・菩提体無二と
すみやかにとくさとらしむ
(『高僧和讃』『註釈版聖典』五八四頁)
すべての教えが円かで速やかに備わっている、優れた本願のみ教えは、五逆や誹謗の者を摂取すると信じ知らせ、煩悩と覚りとが本来ひとつであるということを、即座に覚らせるのです。
無礙光(むげこう)の利益より
威徳広大(いとくこうだい)の信をえて
かならず煩悩のこほりとけ
すなはち菩提のみづとなる
(『高僧和讃』『同』五八五頁)
阿弥陀さまの無限の障りのないはたらきによって、すばらしい信をえることができれば、必ず氷のような煩悩も解けて、そのまま水のような功徳に満ちた覚りになります。
などと詠って、「信知して」、あるいは「信をえて」とあるように、どこまでも信心の利益として、「煩悩・菩提体無二」とか「煩悩のこほりとけ すなはち菩提のみづとなる」といわれるのです。私たちは、つい利益の方に、氷と水の喩えの方にと、眼が向きがちですが、和讃一つひとつにたとえ信心の語がなくても、いただかれた信の上に立って、それぞれが詠われていることに注意すべきであります。曇鸞大師は、信心の内容を詳しく説かれています。それを受けられた親鸞聖人も、たとえば次のように詠われています。
論主(ろんじゅ)の一心ととけるをば
曇鸞大師のみことには
煩悩成就のわれらが
他力の信とのべたまふ
(『高僧和讃』『同』五八四頁)
天親菩薩が「一心」とお説きになった信心を捉えて、曇鸞大師は「煩悩にまみれた私たちのための他力の信心である」とお述べになりました。
このように和讃を通して、お念仏の教えに触れさせていただきたいものです。
(大田利生)
親鸞聖人のお徳を偲び、西本願寺・大谷本廟納骨参拝と京都サクラの名所春爛漫の京都をゆっくりと満喫いたしましょう。
お友達お誘いあわせの上ご参加ください。
画像をクリックすると申込書がダウンロードできます。