A. お供物はおさがりとして持ち帰りましょう。
お茶やお水は供えません。
お茶やお水は供えません。
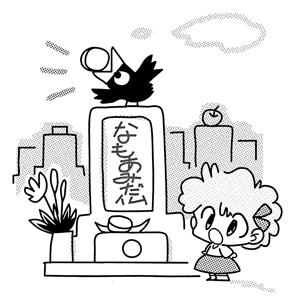 碑の意味は、記念碑ということでしょう。その人が確かにこの世に存在したという証。遺族にとってはお墓を縁として故人の徳をしたい、お念仏を申して会いまみえるところです。
碑の意味は、記念碑ということでしょう。その人が確かにこの世に存在したという証。遺族にとってはお墓を縁として故人の徳をしたい、お念仏を申して会いまみえるところです。
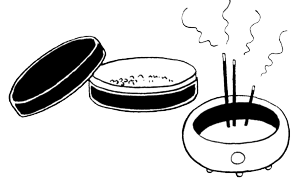 線香は線状の細長いもので、抹香は香の材料を小さく刻んで調合されたものです。
線香は線状の細長いもので、抹香は香の材料を小さく刻んで調合されたものです。
ご法事などのように人数が多い場合は「抹香」を用意しておきましょう。また、香はお浄土の清浄な香りも意味しますので、できるだけ香りの良いものを使いましょう。
その他には塗香といって粉にしたものがあります。これは、儀式の時に体に塗って浄める意味に使われます。したがって一般には使われません。また、香を切らさないということで「巻香」かおりますが、浄土真宗で使われることはほとんどありません。
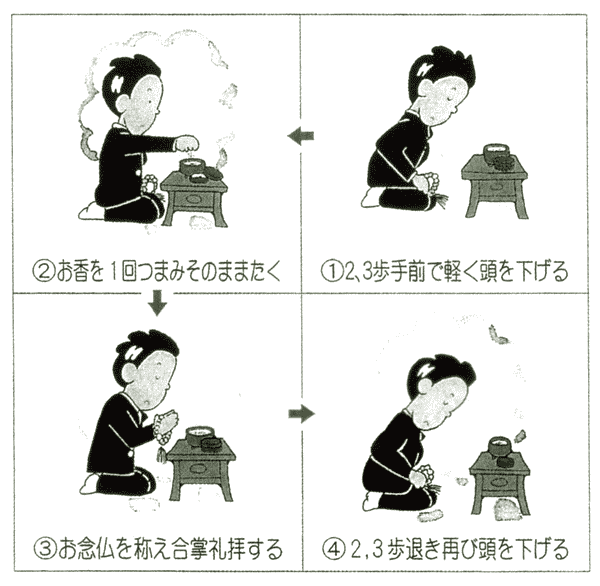
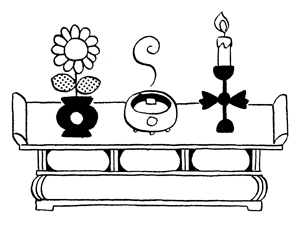 お仏壇の横にお骨を置く壇を作ればいいのです。
お仏壇の横にお骨を置く壇を作ればいいのです。
◇あくまでお仏壇が中心ですので、そちらがおるぞかにならないように。
◇お骨や法名の前にお菓子とかお水とかのお供えはしません。(お水はどこにも供えません。)
遺産なき母が唯一のこととして
残しゆく死を子らよ受け取れ
と気持ちを歌に託していかれたお方がありました。どのように受けとめていくか、残された者に投げかけられている大きなことがらと思います。
別れは身を引き裂くように悲しいことでございますが、故人はいのちをかけて、このわたしに仏縁をくださったのだといただいていくところに、尊い世界と深い感謝の思いが開かれてくるのではないでしょうか。
◇今まで朝夕の読経の習慣のなかったお方は、ぜひ始められるようお勧めします。何をおつとめしたらよいか、ご住職の意見を参考にされてお参りを始めてみてください。
先立った者も残った者も、共に抱いていてくださる如来さまでありますと御恩報謝のお勤めであります。
 報恩講
報恩講
御開山親鸞聖人のご命日のご法事です。一月十六日がご命日ですが、一般寺院では繰り上げて勤めることが多いです。お念仏を伝えてくださった聖人のご恩に報いる法要だから報恩講といいます。
永代経法要
ご門徒の総法事です。このお寺が永代にわたってお経が勤まり、おみのりが伝えてゆかれることを願い、全門徒あげて勤められる法要です。
宗祖降誕会
親鸞聖人のご誕生をお祝いする法要です。その他、次のような法要・法座があります。
元旦会 彼岸会 歓喜会 除夜会
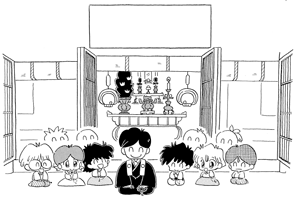 そしてご講師のお話を聞きます。お話は特別に堅苦しいものではありません。誰でもが気がねなく、一緒に聞ける和やかな雰囲気です。
そしてご講師のお話を聞きます。お話は特別に堅苦しいものではありません。誰でもが気がねなく、一緒に聞ける和やかな雰囲気です。
懇志の額に決まりはありません。
 普段の服装で結構ですが、門徒式章を持っておられる方はぜひ着用しましょう。
普段の服装で結構ですが、門徒式章を持っておられる方はぜひ着用しましょう。