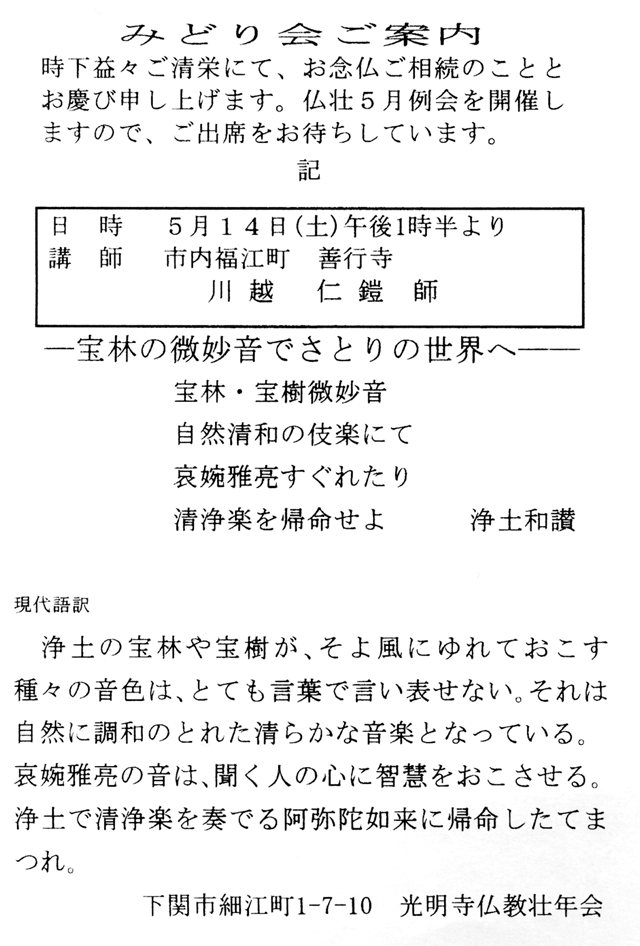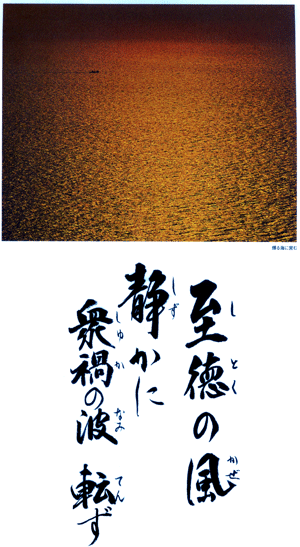
「海」の譬え
この言葉は、『教行信証』行文類「行一念釈」を結ばれるにあたり、念仏の道を歩む者が大悲の光明に摂め取られさとりを聞かせていただくことを、譬喩(ひゆ)を用いて讃嘆されたものです。あらためて全文を出させていただくと、
しかれば、大悲の願船(がんせん)に乗じて光明の広海に浮びぬれば、至徳の風静かに衆禍(しゅか)の波転ず。すなはち無明の闇を破し、すみやかに無量光明土に到りて犬般涅槃(だいはつねはん)を証す、普賢の徳に遵ふなり、知るべしと。
(『註釈販聖典』 一八九頁)
と讃嘆されていて、「至徳の風」も「衆禍の波」も、「大悲の願船に乗じて光明の広海に浮びぬれば」という言葉を受けて述べられたものであることがわかります。
ここに「光明の広海」という言葉がありますが、親鸞聖人は「海」という譬えを用いて、ときには「本願海」「功徳大宝海」など、如来のはたらきを示される場合もあれば、一方で「群生海」「愚痴海」など、苦しみ悩む衆生を示される場合もあります。あるいは、「生死海」「無明海」などと苦しみや迷いの境界そのものを指して用いられる場合もあり、その使われ方はさまざまです。このように「海」をもってたとえられるのは、『浄土論』や『往生論註』といった書物に用いられた譬喩が元になっていると考えられますが、一方で「本願海」「信心海」など聖人特有のものもあったり、また善導大師の『観経疏(かんぎょうしょ)』に一度だけ用いられている「一乗海」の語を、「一乗海」「本願一乗海」「弘誓一乗海」「一乗大智願海」等と広くさまざまに用いられているところにも、聖人の「海」という語に対する思い入れが表れているように思います。
「海」という言葉が、如来のはたらきを示すような場合にも、苦しみ悩む衆生の境界を示すような場合にも、どちらにも用いられているのは、「海」という言葉自体がどのような特質を持っているからなのでしょうか。
一つには、その広大さがあげられるでしょう。「本願海」や「功徳大宝海」といった言葉は、その徳の広さを示しているでしょうし、また「群生海」や「愚痴海」などの言葉も、迷いの世界にある衆生が限りなく存在することや、またその迷いの深さを物語っているように思います。
二つには、それが静止した世界ではなく、動きがあり、はたらきがあるということです。この点については、親鸞聖人が『教行信証』行文類「一東海釈」で、
「海」といふは、久遠(くおん)よりこのかた、几聖所修(ぼんしょうしょしゅ)の雑修雑言(ざっしゅぞうぜん)の川水(せんすい)を転じ、逆謗闡提恒沙無明(ぎゃくほうせんだいごうじゃむみょう)の海水を転じて、本願大悲智慧真実悟沙万徳(ほんがんだいひちえしんじつごうじゃまんどく)の大宝海水(だいほうかいすい)となる。これを海のごときに喩ふるなり。(中略)願海は二乗雑善(にじょうぞうぜん)の中下の屍骸を宿さず。
いかにいはんや人天の虚仮邪偽(こけじゃぎ)の善業、雑毒雑心(ぞうどくざっしん)の屍骸を宿さんや。
(『註新版聖典』 一九七百項)
と説明されていることからもわかります。これは、『往生要集』や『往生論註』の解釈によって「海」という言葉の待つ意味を表しておられるのですが、さきはどの「本願海」や「功徳大宝海」という言葉の持つ「徳」とは、その衆生の煩悩にまみれたありようが、如来大悲の智慧によって功徳に転ぜられるというはたらきを意味しているのです。また、「信心海」という言葉も同様の意味を持つものでしょう。
一方、「無明海」や「生死海」という言葉も、迷いの世界をめぐり続けているという私たちのありようを示すものです。
三つには、「海」はさまざまなものを受け入れるということです。たとえば、川の水は海へと流れていきますし、私たちも海へと入っていくことがあります。「願海に流入せしむ」「願海に入りて」などの言葉や、「生死海に入りて」「生死海に漂没して」、あるいはっ大信心海ははなはだもつて入りがたし」などの言葉は、海が何ものも受け入れず、そこへ入り込むことができなければ成り立たない表現です。
四つには、その海の向こう側に、まだ見ぬ世界があるということです。言葉を換えれば、「海」はそれを超え渡るべきものであって、しかもその広さと深さのゆえに泳いで渡ることはできません。また、その海が穏やかなものではなく、荒れ狂う波が逆巻くようであれば、小舟で渡りきることも不可能です。大きくて丈夫な船だけがその海を渡ることができるのです。
「難思(なんじ)の弘誓(ぐぜい)は難度海(なんどかい)を度する大船」(『教行信証』総序『註釈版聖典』一三一項)、「一切智船に乗ぜしめて、もろもろの群生海に浮ぶ」(『同』行文類 『註釈版聖典』ニ〇一~二〇二項)といった表現は、さとりの岸へと渡ることができない私たちを、如来の大きなはたらきによって渡していただくことをたとえたものです。
如来の智慧の光明に照らされて
親鸞聖人が用いておられる「海」という言葉の譬えを見てまいりましたが、今月の言葉のもととなった「しかれば、大悲の願船に乗じて光明の広海に浮びぬれば……」という文は、私たちが本願のはたらきによって浄土へ往生し、還相のさとりを聞かせていただくことを、「海」の譬えをもって讃嘆されたものであり、特に美しく描かれているように思います。
まず、「大悲の願船に乗じて」とあるのは、ご本願のはたらきを受け、「南無阿弥陀仏」とお念仏させていただく私たちのすがたを表しています。「光明の広海」とは、海が光そのものであるということではありません。海自体はやはり、「衆禍の波」が立つ生死の苦海であって、さまざまな悩みや苦しみに満ちた私の人生なのです。しかしながら、「大悲の願船に乗じ」たからには、その苦海には本願のはたらきが行き渡り、如乗の智慧の光明に照らされぬところはないというのです。
その光明のはたらきを「至徳の風静かに衆禍の波転ず」と表されているのですが、この「至徳」という言葉は、如来のはたらきに対して用いられているものであり、至極の功徳という意味であって、如来のこの上ない智慧と慈悲の徳を言います。また、「円融至徳の嘉号」「至徳の尊号」等と言われているように、「南無阿弥陀仏」の六字のみ名を讃嘆されるところで用いられるものです。そして、
「この徳号は一声称念(いっしょうしょうねん)するに、至徳成満(しとくじょうまん)し衆禍みな転ず」(『教行信証』化身土文類 『註釈版聖典』三九九頁)
と言われていることからも、「至徳の風静かに衆禍の波転ず」とは、私たちが本願のはたらきを受けお念仏申すなかに、人生におけるさまざまな禍(わざわい)の波も、如来の智慧のはたらきによって、人生を豊かに生き抜くものに転ぜられていくという意味であることがわかります。あるいは、「風」は船を進ませるはたらきを言われているのかもしれません。そうすると、本願の大船に乗じた私の人生は、如来の智慧のはたらきを風として帆にいっぱいに受けて、穏やかに力強く進んでいくことを言われているようにも思います。
そして、「すなはち無明の闇を破し、すみやかに無量光明土に到りて大般涅槃を証す」とあるとおり、私を包んでいた無明煩悩の闇は如来の光明に破られて、もはや迷いの世界を生死流転することなく、すみやかに限りない光の浄土へ往生し、この上ないさとりに到ることができる、そうした人生を私は歩ませていただくのです。
ここで「普賢の徳に遵ふなり」とありますが、「普賢」とは普賢菩薩のことで、お釈迦さまの慈悲のはたらきを表す菩薩であり、智慧のはからかを表す文殊菩薩とともに、お釈迦さまの両脇に侍する菩薩(普賢菩薩は向かって左側です)です。お釈迦さまは、この娑婆世界において八十年の生涯をかけて人びとをさとりへと導かれましたから、「普賢の徳」とは、娑婆世界における仏の慈悲のはたらきを表しています。ですから、「普賢の徳に道ふなり」とあるのは、浄土に往生して聞かせていただくこの上ないさとりとは、ふたたび浄土よりこの世界に還り来て、大悲心をもって苦しみ悩むすべての者を救いとる普賢菩薩のように、有縁の人びとを救いとる還相のさとりであることを示しています。
現生の利益
さて、親鸞聖人が「海」をもって如来のはたらきや苦しみ悩む衆生の境界を表されるとき、『浄土論』や『往生論註』などの七祖の聖教に用いられた譬喩を元にしておられると申しました。しかし、この「至徳の風静かに衆禍の波転ず」という譬えは聖人独自のものです。そして今見てきたとおり、この言葉は如来の本願のはたらきを讃嘆されるものなのですが、この譬えの中身は、「信文類」に示された「現生十益(げんしょうじゅうやく)」の第二・第三の利益にあたるとも言われます。
現生十益とは、現世に生存しているなかで受ける十種の利益ということなのですが、その第二は「至徳具足の益」、第三は「転悪成善(てんあくじょうぜん)の益」です。「至徳具足の益」とは、如来のこの上ない智慧と慈悲の功徳が、私たちの信心に具足しているということです。また、「転悪成善の益」とは、さきに見た「行文類」 一乗海釈で言われる徳が、そのまま私たちの信心の徳となってはたらいているということです。つまり、私たちの信心に具わる徳は、そのまま如来の智慧のはたらきの徳であるということになります。
そして、このことが現生の利益として言われるということは、如来のはたらきを受けているのが、今、まさにこの瞬間ということなのです。そうすると、本願名号の至徳の風が私の人生の衆禍の波を転じてくださるのは、今この時より他にはないということを知らせていただいていると言えるでしょう。
眼前に広がる海
親鸞聖人の九十年に及ぶ生涯のなかで、海が間近にあったのは流罪にあわれた北陸の地でありました。眼前に広がる日本海は、ときに激しく波を海岸に打ち寄せ、ときに穏やかに沈みゆく夕陽を映したことでしょう。聖人の目に映った海のすがたが、「大悲の願船に乗じて光明の広海に浮びぬれば、至徳の風静かに衆禍の波転ず」と示された、この美しい譬えを生んだのかもしれません。そのようなことを思いながら、あらためて聖人のご苦労を偲ばせていただくことです。
(安藤光慈)
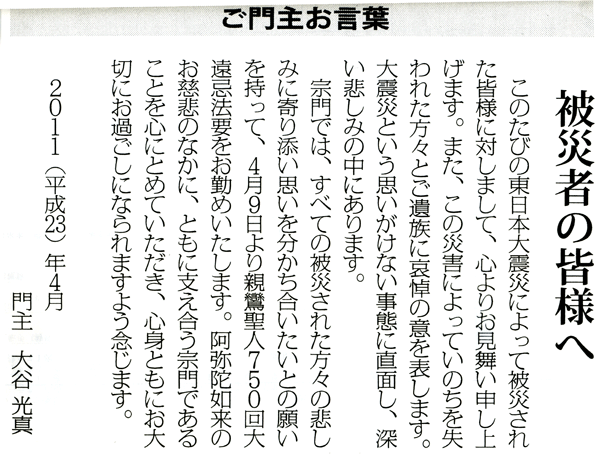
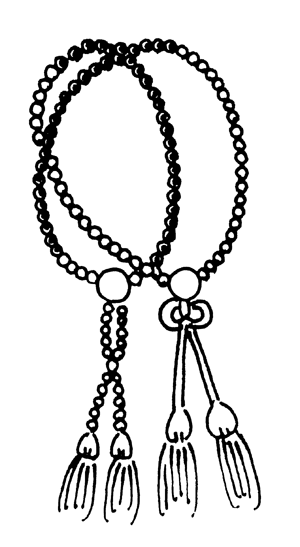 「暑さ寒さも 彼岸まで」という先人のことばに、汗して働く生身の人間を感じるのは、私一人ではないと思います。
「暑さ寒さも 彼岸まで」という先人のことばに、汗して働く生身の人間を感じるのは、私一人ではないと思います。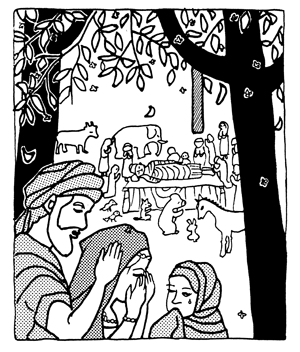 私たち人間がこの地球上に誕生してから、随分長い歴史を経てきました。
私たち人間がこの地球上に誕生してから、随分長い歴史を経てきました。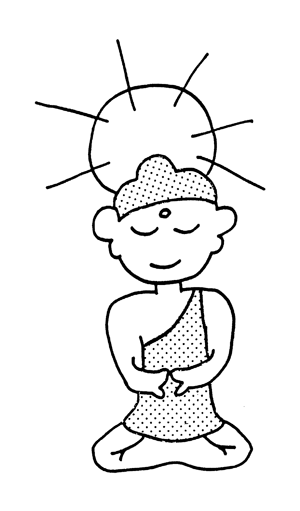 お墓は一般的には死者の霊安所とか、また祖先崇拝の場としてとらえられている場合が多いようですが、しかし、仏教は本来、空・無我を説く教えですから、一般的にいわれている霊の存在を否定いたします。したがってお墓は霊安所的な考え方をしないのが仏教徒の正しいあり方です。それでは何のために墓碑を建てるのかということになりますが、浄土真宗では墓碑を建てるとき、その題字に「南無阿弥陀仏」とか、また「倶会一処」という文字を刻かのが通例です。これはこの文字、つまり七名号によって示されますように、お墓はご法義相続の場であることを表わしているからです。これは「ときをもいはず、ところをもきらはず念仏申す」場として在るのです。
お墓は一般的には死者の霊安所とか、また祖先崇拝の場としてとらえられている場合が多いようですが、しかし、仏教は本来、空・無我を説く教えですから、一般的にいわれている霊の存在を否定いたします。したがってお墓は霊安所的な考え方をしないのが仏教徒の正しいあり方です。それでは何のために墓碑を建てるのかということになりますが、浄土真宗では墓碑を建てるとき、その題字に「南無阿弥陀仏」とか、また「倶会一処」という文字を刻かのが通例です。これはこの文字、つまり七名号によって示されますように、お墓はご法義相続の場であることを表わしているからです。これは「ときをもいはず、ところをもきらはず念仏申す」場として在るのです。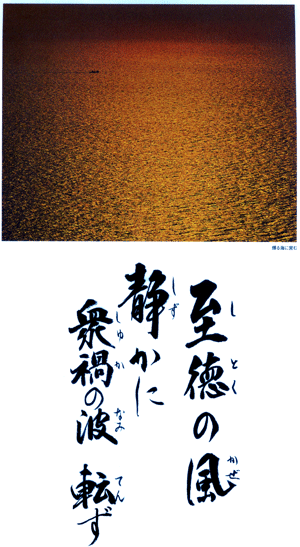
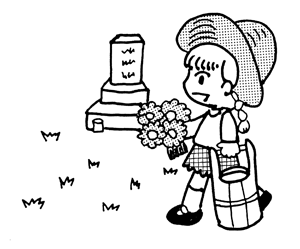 どんなにキビシイ寒さであっても、また、いく日も続いたウダルような暑さも、お彼岸のころになると、すごしやすくなるという意味のことばなんだよ。
どんなにキビシイ寒さであっても、また、いく日も続いたウダルような暑さも、お彼岸のころになると、すごしやすくなるという意味のことばなんだよ。
 百人の大学生に、「あなたには四人の祖父母がおられますね。その四人のお名前を、いま、ここで全部書けますか」と質問してみました。書けると答えた人はわずかに二人。
百人の大学生に、「あなたには四人の祖父母がおられますね。その四人のお名前を、いま、ここで全部書けますか」と質問してみました。書けると答えた人はわずかに二人。 弔辞の多くは、「安らかにお眠り下さい」と結ばれます。慣用の表現であり、病気で 苦しまれた方などへの言葉として用いられるのも、自然な感情の現れとも言えましょう。
弔辞の多くは、「安らかにお眠り下さい」と結ばれます。慣用の表現であり、病気で 苦しまれた方などへの言葉として用いられるのも、自然な感情の現れとも言えましょう。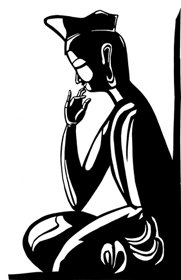 阿弥陀仏が主(あるじ)
阿弥陀仏が主(あるじ)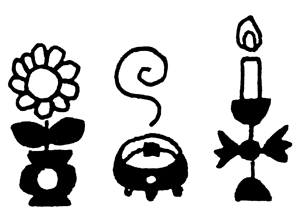 どうして、このような間違いがおこってくるのでしょうか。
どうして、このような間違いがおこってくるのでしょうか。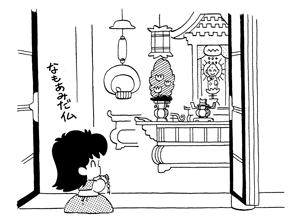 浄土真宗のお仏壇は、文字通りご本尊てある阿弥陀仏をご安置する壇てあります。
浄土真宗のお仏壇は、文字通りご本尊てある阿弥陀仏をご安置する壇てあります。 あるご婦入が、劫い時を回想していわれました。
あるご婦入が、劫い時を回想していわれました。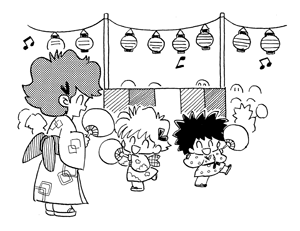 夏のお盆が近づくと、「亡くなった方が、帰ってこられるよ」「ひょっとすれば、トンボやチョウになって帰って来られるから、生き物をとってはダメよ」と、よくいわれたことがありました。
夏のお盆が近づくと、「亡くなった方が、帰ってこられるよ」「ひょっとすれば、トンボやチョウになって帰って来られるから、生き物をとってはダメよ」と、よくいわれたことがありました。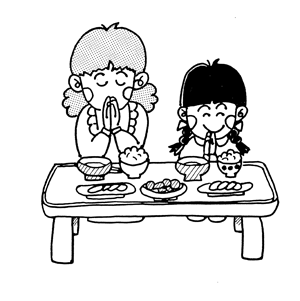 毎日の生活のなかで、なにげなく言っていることばや、掌をあわせるしぐさに「たくさんの”いのち”のつながりのなかで、私の”いのち”は今、与えられているのですよ」と、教えられてきたようです。
毎日の生活のなかで、なにげなく言っていることばや、掌をあわせるしぐさに「たくさんの”いのち”のつながりのなかで、私の”いのち”は今、与えられているのですよ」と、教えられてきたようです。 A .そのとおりです。浄土真宗門徒として、心から阿弥陀さまを敬い、そのみ教えに生きることを表明する儀式を「帰敬式」と言いますが、この帰敬式に際して、ご門主さまより「おかみそり」を受け、いただくのが「法名」です。
A .そのとおりです。浄土真宗門徒として、心から阿弥陀さまを敬い、そのみ教えに生きることを表明する儀式を「帰敬式」と言いますが、この帰敬式に際して、ご門主さまより「おかみそり」を受け、いただくのが「法名」です。 A 違います。ここをハッキリと理解しないと、仏事はどの宗派でも同じものと思ったり、字数が多いほど値打ちがあると誤解したりするのです。
A 違います。ここをハッキリと理解しないと、仏事はどの宗派でも同じものと思ったり、字数が多いほど値打ちがあると誤解したりするのです。