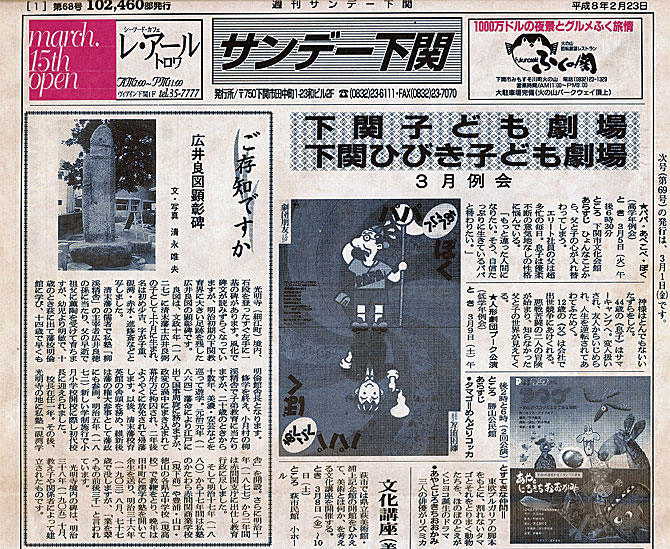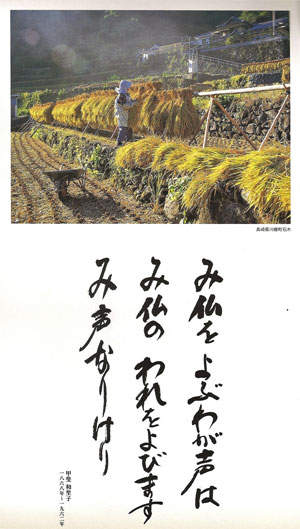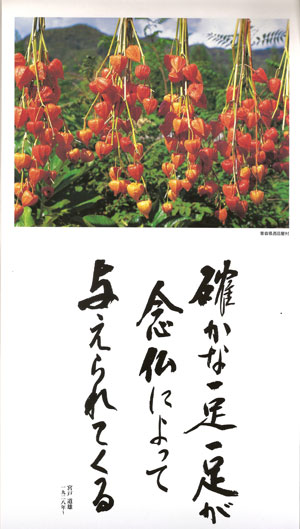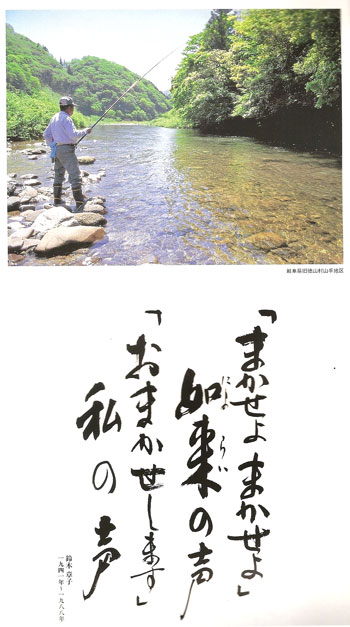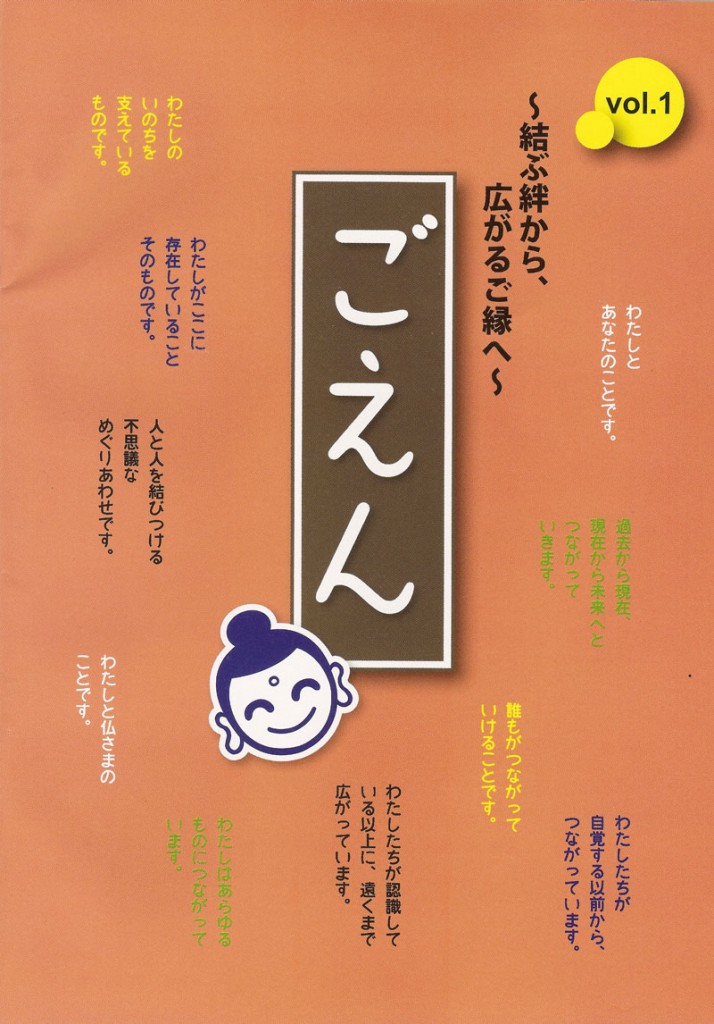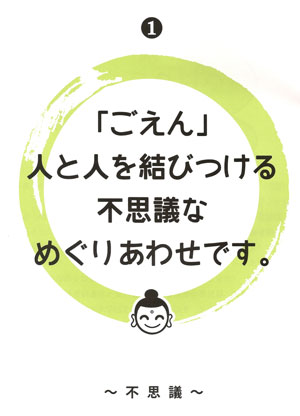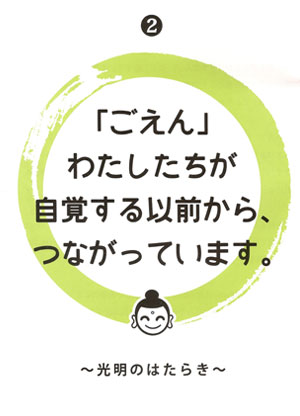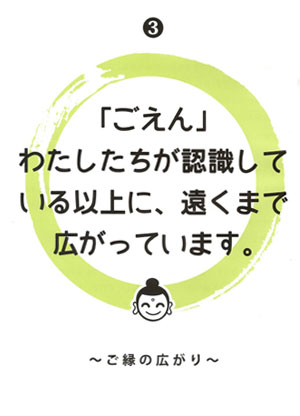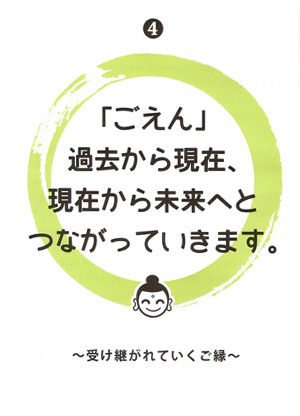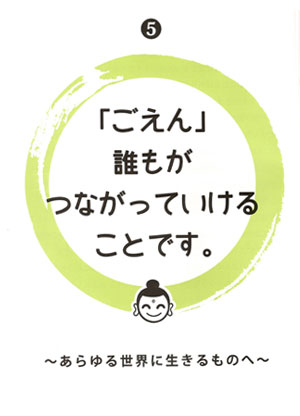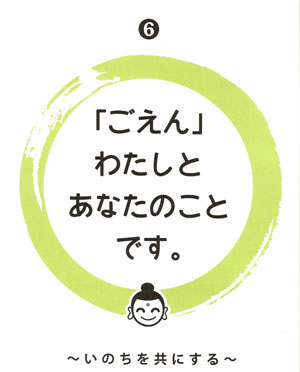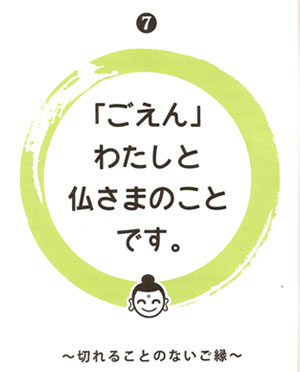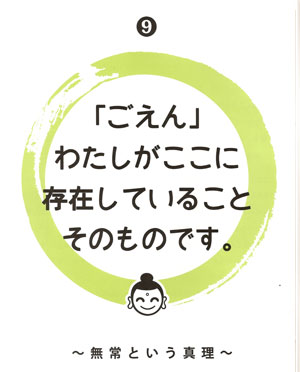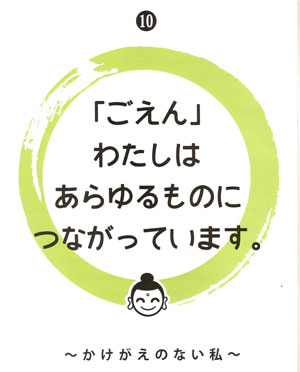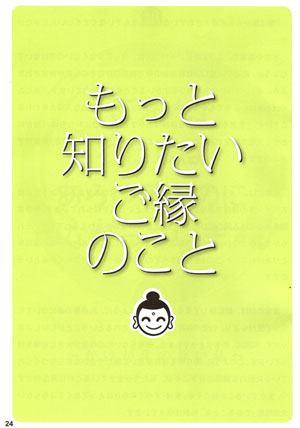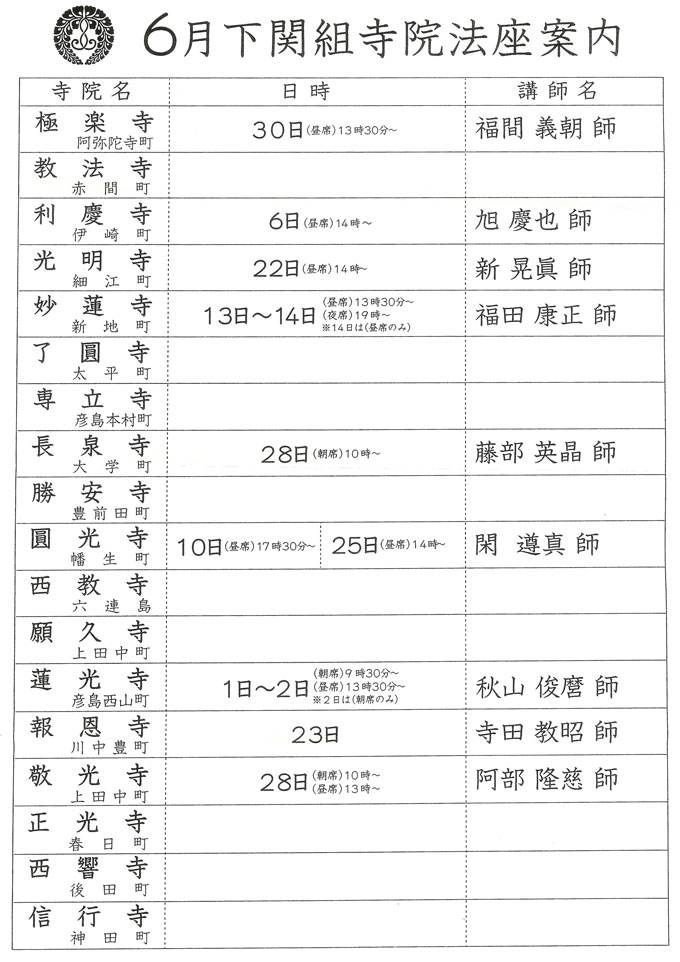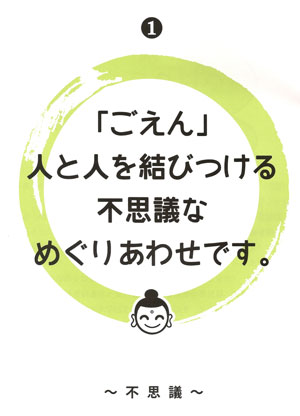 私たちには、さまざまな縁(原因)がはたらいています。そして、そのことを、知り尽くすことができません。今、ここで起きている事柄は、数え切れない無限の原因が積み重なった結果です。私たち人間の浅はかな考え方では、到底、理解し尽くすことができません。
私たちには、さまざまな縁(原因)がはたらいています。そして、そのことを、知り尽くすことができません。今、ここで起きている事柄は、数え切れない無限の原因が積み重なった結果です。私たち人間の浅はかな考え方では、到底、理解し尽くすことができません。
一方で、因果関係でものを見ることは、私たち人間に特徴的な思考方法でもあります。しかし、私たちには、ほんとうの因果関係を正しく見極めることができず、自分の都合で因果関係を見てしまいます。これは誤った認識であり、それによって誤った行為が生み出され、悲しみや苦しみの要因ともなります。
縁起を見抜くことができず、自己中心的な考えで、結果に対して誤った原因を見てしまう私たちは、仏さまに出あい、その智慧をともしびとしなければ、私自身をきちんと見つめることさえできません。
仏さまが示された「縁起」とは、物事の正しい因果のことです。この教えをよりどころとして、思い込みや自己中心的な因果関係を見てしまわないよう、常に注意しなければなりません。
あなたと私も、そして仏さまと私も、人間のはからいでは知り尽くせない多くのご縁でつながって、不思議なめぐりあわせがあって、ここに出あっているのです。
———————————————————
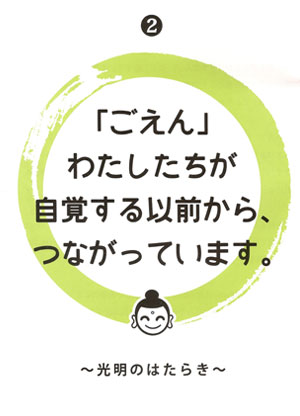 「袖振り合うも多生の縁」(※1)という言葉があります。「多生」を「多少」と書き間違える人もいますが、「多生」でなければ、この言葉の正しい意味にはなりません。往来で行き交う人の着物の袖先が、軽く接するようなささやかな関係であっても、何度も生まれ変わる中で生じた貴重な縁であることを意味しています。
「袖振り合うも多生の縁」(※1)という言葉があります。「多生」を「多少」と書き間違える人もいますが、「多生」でなければ、この言葉の正しい意味にはなりません。往来で行き交う人の着物の袖先が、軽く接するようなささやかな関係であっても、何度も生まれ変わる中で生じた貴重な縁であることを意味しています。
しかし、長い時間の中で育まれたご縁であることを意識することは、なかなか難しいことです。直接的な原因について思いをめぐらすことはできても、遠い過去からの原因を自覚し続けることは本当に困難です。
親鸞聖人(※2)は、『教行信証』(親鸞聖人の主著)の「総序」で、
ああ、弘誓(ぐぜい)の強縁(ごうえん)、多生にも値(もうあ)ひがたく、真実の浄信、億劫(おくごう)にも獲がたし。
たまたま行信を獲ば、遠く宿縁を慶べ(『註釈版聖典第二版』132頁)
と仰っています。阿弥陀さま(※3)からの願いである大いなる本願は、いくたび生を重ねてもあえるものではなく、まことの信心はどれだけ時を経ても得ることは難しい。思いがけず、真実の行と信(※4)を得たなら、遠い過去から、阿弥陀さまの光が、育み続けてくれていたご縁を感謝しよろこぶべきであると、親鸞聖人はお示しくださっています。
私たちは、心配し続けてくれている人、願い続けてくれている人がいても、当たり前のようにそのことに気付かなかったり、ついつい忘れてしまったりしています。そうした縁が途切れた時、心配してくれていた人がいなくなった時に、やっと、その大切さに気付くということも少なくありません。
阿弥陀さまの光明は、私たちの気付かない遠い過去から、すべての人々を照らし続けています。そのことが、貴重なご縁となって、今、救いに出あっているのです。
※1 「袖振り合うも多生の縁」は、「袖すり合う」「袖触れ合う」「他生の縁」といった表現のものもあります。
※2 「親鸞聖人」浄土真宗の宗祖1173-1263
※3 「阿弥陀さま」浄土真宗のご本尊、阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)
※4 「行と信」仏教一般では、行はさとりに至るための修行を意味しますが、浄土真宗では、浄土往生の行は信と同じく阿弥陀さまより衆生にふり向けられ、あたえられたものとして、大行といわれます。
———————————————————
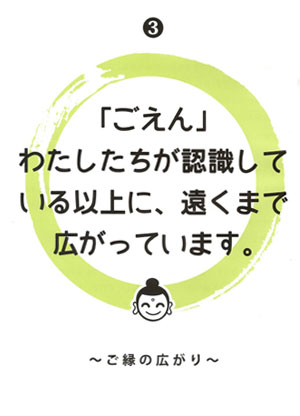
質問です。名前しかわからない、まったく見も知らぬ遠くの人へてがみを届けなくてはなりません。何人を仲介すれば、目的の人に、その手紙は届くでしょうか?
これは、アメリカで1960年代に実際に行われた実験です。1600キロ離れた土地に住むビジネスマンに、自分より関係の深そうな方に手紙を渡すという方法で、人づてに手紙を送ろうとします。すると、平均して、たったの6人を介するだけで目的の人物に届くのです。これはアメリカ国内での実験でしたが、2003年には、世界規模で同様の実験を行いました。すると、やはり同じく6人で届いたそうです。
私たちは、広い世界の中で、ばらばらに生きているように思いがちです。遠くにいる人であれば、まったく無関係に生きているように感じてしまいます。しかし、誰もが、たった6人を通してつながり合っていける世界、「スモールワールド」に生きているということを、これらの実験は証明したのです。インターネットが急速に発達している現代では、世界は、さらに小さなものになっていくことでしょう。
しかし、私たち人間は、私と外の世界を切り分けて認識する習慣を持つため、つながりを断って、世界を認識してしまいがちです。それによって、自己中心的な視点に縛られ、自己へのとらわれから離れられなくなり、つながっていても、また、つながる可能性があっても、そのことを自覚することができないでいます。個別に独立した存在として切り離された関係をつくり、お互いに、ねたみ、怒り、非難の心で見てしまうのが、私たちのありさまなのであり、疎外される人々を生み出す私たちの社会のありのままの姿です。
遠い、近いという感情は、私たちの心が作り出すものです。自他を隔てることのない仏さまの智慧を鏡とするとき、自己のとらわれから離れられない私たちに、分別するあり方を省みて、互いにつながりあっていける可能性が、開けてくることでしょう。
———————————————————
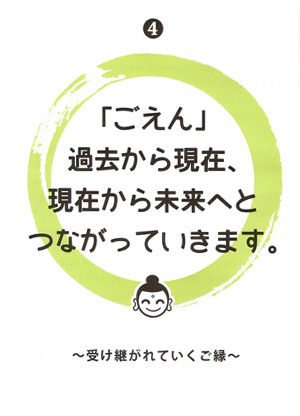 吐く息が白くなるような寒い冬の日、暖かなお風呂に入ると、「あ~ありがたいなあ」と思わず声が漏れることがあります。「ありがたい(有り難い)」とは、「有ることが難しいこと」、つまり極めてまれなことに感謝をする言葉です。もちろん、お風呂に入ったときだけではありません。仕事や恋愛など日常生活の中で直面するさまざまな困難の中で思わぬ支えに出あったとき、口に出さなくても私たちはありがたさを心から実感することがあります。
吐く息が白くなるような寒い冬の日、暖かなお風呂に入ると、「あ~ありがたいなあ」と思わず声が漏れることがあります。「ありがたい(有り難い)」とは、「有ることが難しいこと」、つまり極めてまれなことに感謝をする言葉です。もちろん、お風呂に入ったときだけではありません。仕事や恋愛など日常生活の中で直面するさまざまな困難の中で思わぬ支えに出あったとき、口に出さなくても私たちはありがたさを心から実感することがあります。
さて、お釈迦さまから始まった仏教の教えは、約2500年の時を経て、現代にまで受け継がれてきました。しかし、その歴史は決して平坦なものではありませんでした。中でも仏教が国家に受容された中国・日本などの東アジアでは、いくたびかの深刻な弾圧や迫害によって、その教えが途絶えそうになったことが多くの歴史書に記されています。そうした困難の中で仏法をなんとか伝えようとしてきた人々がいたからこそ、私たちは今、その教えに出あうことができているのです。
親鸞聖人は、法然聖人(※1)など自らを導いてきた人々の教えを通して阿弥陀さまの救いに出あえたことをよろこび、ご著作の最後に、次の言葉を引用されています。
前に生れるものは後のものを導き、後に生れるものは前のもののあとを尋ね、果てしなくつらなって途切れることのないようにしたいからである。
(『教行信証』化巻、『現代語版』646頁)
ここには、み教えを伝えてくれた先人への感謝と共に、自らも途切れることなく人々に伝えていこうとする親鸞聖人の決意をうかがうことができます。過去から現在へと多くの困難の中でみ教えを伝えてきた方々の「有り難い」ご縁の積み重ねによって、今、私たちが阿弥陀さまの教えに出あうことができているのです。私たちの手によって、未来へとその教えをつなげていきたいものです。
※1 「法然聖人」浄土宗の宗祖、親鸞聖人の師、1133-1212
———————————————————
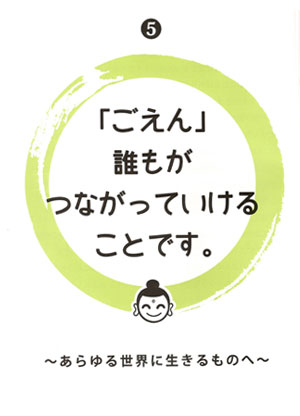 毎年お正月になると、初詣の参拝者で多くの神社や仏閣はにぎわいます。
毎年お正月になると、初詣の参拝者で多くの神社や仏閣はにぎわいます。
中でも、若者たちに人気なのが、「縁結び」のご利益です。「今年こそは素敵な人と出あいたい」と、「良縁成就」のお守りを求めて長蛇の列ができる風景は、この時期の風物詩といえるでしょう。このように、私たちが求める「ご縁」は、「悪い縁」をとりのぞき、「良い縁がほしい」「自分の思い通りの異性が見つかれば良い」という思いが反映された、いささか都合の良いものであることが多いようです。
しかし、私と仏さまとの間にある「ご縁」は、こうした私たちが求める「縁結び」とは、全く違うものです。曇鸞大師(6世紀に活躍した中国の僧)は、慈悲について述べる中で、阿弥陀さまの慈悲を「無縁、これ大悲なり」(『往生論註』上巻、『註釈版聖典七祖篇』62頁)と示しておられます。「無縁」とは、仏教では「つながりがない」という意味ではなく、「特定の対象(縁)を選ぶのではない」ということを意味します。つまり、阿弥陀さまから結ばれた私との「ご縁」は、どのようなものに対しても向けられる大悲(私たちを慈しむ心)のはたらきそのものなのです。このことが、『仏説無量寿経』には「十方衆生を救う」と誓われています。「十方衆生」とは、あらゆる世界のいのちあるものという意味です。
阿弥陀さまの普遍の救いに出あうとき、自分中心の世界に生きていた私が、仏さまにつながっている世界、仏さまの慈しみに包まれている世界の中にあると、気付かされていくのです。縁のよしあしを気にして思い悩む私たちに対して、阿弥陀さまのほうからすでに、全ての者に対する「ご縁」が結ばれています。この仏縁を通して、私たちが、互いに阿弥陀さまの大悲に等しく包まれているもの同士であったことが知らされていくのです。
| はじめに | 「ごえん」①~⑤ | 「ごえん」⑥~⑩ | もっと知りたいご縁のこと |