二月のご案内
仏教壮年会 二月例会
二月 九日(土) 午後二時より
講座 十五回「みんなで学ぶ ご絵伝」
宇部市東須恵中野 蓮光寺住職
講 師 伊 東 順 浩 師
二○一三年 二月 一日
下関市細江町一丁目七番十号
光 明 寺
二月のご案内
仏教壮年会 二月例会
二月 九日(土) 午後二時より
講座 十五回「みんなで学ぶ ご絵伝」
宇部市東須恵中野 蓮光寺住職
講 師 伊 東 順 浩 師
二○一三年 二月 一日
下関市細江町一丁目七番十号
光 明 寺
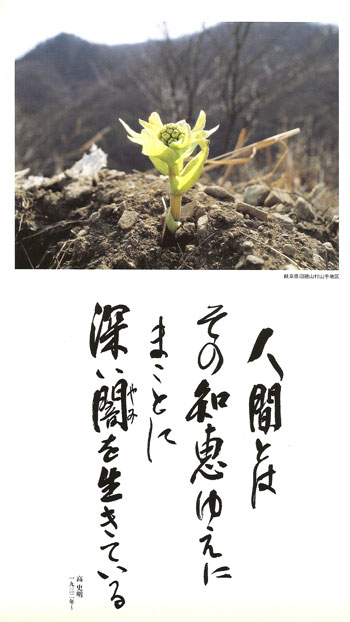 十二歳の息子の死
十二歳の息子の死
二月の法語は、高史明(コサミョン)さんの言葉をいただきました。
人間とは、その知恵ゆえにまことに深い闇を生きている
(『悲の海は深く』七七頁)
私ども人間の知恵がいかに深い闇のなかのものであるかを語られるものですが、ここには、高さんの深い人生観が窺われます。
高さんの独り子の息子さんは、十二歳の春を迎えた時、自らこの世を去られます。
高さんは、この最愛の子の突然の自死に出遭って、目の前が真っ暗になられました。
息子さんが鋭い視線で多くの詩を書き残していたことを知って、それまで息子のことを何も知らずにいたことにがっくりされました。中学生となった息子さんに、「これからは、何事も自分で責任をもって歩んでゆくことだ」と、激励のつもりで語りかけた、その直後の自死でした。
ご白身が、何も本当のことをわかっていない「無明」のなかにある、わが子も「無明」のなかにある、ともに深い暗黒の淵に落ち込んでいるという思いでおられました。そのような時に、『歎異抄』と真剣に対面するようになり、『歎異抄』の声が聞こえてきたと言われます。
初めのうちは、『歎異抄』を読んでも、頭のなかに何ら入ってくることはありませんでしたと言われます。小学校を出て以来初めて墨をすり、「南無阿弥陀仏」という文字を、毎日毎日書いていたが、それにどういう意味があるのか説明できないけれども、そうせずにおれなかったと、当時のことを語られます。
そして、連れ合いの岡百合子(ゆりこ)さんが「仏さまの顔を見に行きたい」と言うので、一緒に奈良を訪ね、田んぼのなかの道を歩いていた時のことだそうです。周囲が黄金色に輝く光景に出遇ったその時に、夕日の輝きのなかで、「生きているんだ」と気づかされたと言われます。『歎異抄』第五条の「まづ有縁(うえん)を度(ど)すべきなり」(『註釈版聖典』八三五頁)という言葉がどういう教えであるか、言葉としても整理して考えられるようになったとのことです。
浅はかな人間の知恵
息子さんの自死によって『歎異抄』に向き合うようになった高さんは、人生の絶望、暗黒の淵を体験されて、人間の知恵がいかにたよりないか、浅はかなものであるかを思い知らされたということでしょう。
『歎異抄』の結びの部分(後序)に、
煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)、火宅無常(かたくむじょう)の世界は、よろづのこと、みなもってそらごとたはごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておはします
(『注釈版聖典』八五三~八五四頁)
とあります。すなわち、「私どもはあらゆる煩悩をそなえた凡夫であり、この世は燃えさかる家のようにたちまち移り変わる世界であって、すべては虚しく偽りで、真実と言えるものは何一つない。そのなかにあって、ただ念仏だけが真実なのである」とあるとおりである、と実感されたのです。
私ども人間の世界は、いまや科学技術の急速な発達のおかげで、たいへん便利な生活ができるようになっています。そして、私たち人間は有能で、世界を支配しつつあるというような驕(おご)りの思いすら、持ち始めていると言えるでしょう。しかし、それは人間中心の思考の上に乗っての営みであり、さらには自己中心の思考に支配されている驕慢(きょうまん)の姿と言わざるを得ません。
人間中心の科学的な知識にしても、人間の欲望を満足させようとする思考にしても、根本的に「無明」(真実が見えていない無知)の世界のことであるという深い洞察が、高さんの言葉に窺われます。
『正像末和讃』には
末法五濁(まっぽうごじょく)の有情(うじょう)の
行証(ぎょうしょう)かなはぬときなれば
釈迦(しゃか)の遺法(ゆいほう)ことごとく
竜宮(りゅうぐ)にいりたまひにき
(『註釈版聖典』六〇一頁)
と詠われています。すなわち、親鸞聖人は「末法の五濁の闇にある私ども人間には、修行も覚りもかなわない時(時代)であるから、釈尊が遺された教法もみなこの世から隠れて、竜王の宮に入ってしまわれた」と言われるのです。この和讃を拝読されて高さんは、人間の自己中心の知恵は、その根っこに「五濁」の深い闇が横たわっているが、そこでは修行も覚り(証)もかなわぬといわれている、と受け止められたのです。
ただ念仏のみぞまこと
『仏説阿弥陀経』には、
釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)、よく甚難希有(じんなんけう)の事(じ)をなして、よく娑婆国土(しゃばこくど)の五濁悪世(ごじょくあくせ)、劫濁(こうじょく)・見濁(けんじょく)・煩悩濁(ぼんのうじょく)・衆生濁(しゅじょうじょく)・命濁(みょうじょく)のなかにおいて、阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)を得て、もろもろの衆生のために、この一切世間難信(いっさいせけんなんしん)の法を説きたまふ
(『註釈版聖典』一二八頁)
と、すなわち「釈迦牟尼仏は、世にもまれな、きわめてなしがたい尊いことを成し遂げられた。この娑婆世界は濁りきり、悪に満ちていて、時代は汚れ、思想は乱れ、欲望をはじめ、さまざまの煩悩は激しく、人びとは堕落し、生命を損ない、大切にしていない。そのなかにありながら、この上ない覚りを得て、人びとのために、この世のすべてのものたちには信じがたい尊い教えをお説きになった」と説かれています。このように、『仏説阿弥陀経』に、諸仏がたが釈尊の不可思議の功徳をほめ讃えておられることが説かれていることを、高さんは深く受け止められます。
そして、法然聖人、親鸞聖人が、人類史の地殻に潜む暗黒を露わにされていることを、さらには、その地獄のただ中を生き抜いて真実のみ教えを捉え返され、「ただ念仏のみぞまことにておはします」(『歎異抄』後序 『註釈版聖典』八五四頁)の道を、さらに深くお示しくださったと言われています。
まさに、高さんがいただかれたように、私たちは、人間中心の営み、自分中心の知恵の「深い闇」のなかにあって、如来の大悲のおはたらきに出遇わせていただいているのであると言えるでしょう。
(佐々木恵精)
 妙好人
妙好人
「妙好人(みょうこうにん)」とは、お念仏をいただいた篤信の念仏者を讃える称讃の言葉として用いられます。もともとは、善導大師(ぜんどうだいし)が用いられたのが最初でした。『仏説観無量寿経』に、釈尊が篤信の念仏者を讃えて、
もし念仏するものは、まさに知るべし、この人はこれ人中(にんちゅう)の分陀利華(ぶんだりけ)なり。
(『註釈版聖典』一一七頁)
と説かれています。分陀利華(芬陀利華とも表記されます)とは、泥田にありながら清浄な華を咲かせる白蓮華(びゃくれんげ)のことです。これを善導大師は註釈されて、経に分陀利華と讃えられたことは、
すなはちこれ人中の好人なり、人中の妙好人なり、人中の上上人(じょうじょうにん)なり、人中の希有人(けうにん)なり、人中の最勝人(さいしょうにん)なり。
(『観経疏』「散善義」『註釈版聖典(七祖篇)』四九九~五〇〇頁)
と言われ、言葉を尽くして念仏者を称讃されました。
特に、「妙好人」という言葉をもって篤信の念仏者を表すようになったのは、江戸時代の真宗学者・実成院仰誓(じつじょういんごうぜい)師からで、その後、次第に一般に使用されるようになり、今や海外でも「Myokonin」で通用するようになっています。
源左さんの苦悶
一月の法語は、その妙好人の一人として讃えられる足利源左(あしかがげんざ)さんの言葉から選ばれました。
源左さんは、本名を足利喜三郎と言いますが、一般に源左衛門と言い、略して「源左」で通っておりました。鳥取県の浜村温泉に近い気多郡(けたぐん)山根村の生まれで、根っからのお百姓さんでした。頑強な体格で気性も荒く、喧嘩や賭博もした青年期であったようですが、勤労には精を出し、分け隔てなく人びとの難儀を助ける性格だったとのことです。
源左さんが聞法を始めたきっかけは、十八歳の時に、父親が当時流行していたコレラにかかり急死して、動転したことでした。父親がわずか半日のわずらいで亡くなるのですが、その直前に、「おらが死んで淋しけりゃ、親をさがして親にすがれ」と言い残した遺言が心にとどまり、死とは何か、親さまとは何かを考える毎日でした。そして、願正寺を訪ねて住職の芳瑞(ほうずい)師の導きを受けて、聞法生活を始めたのでした。
さらに、二十一歳で結婚して、五人の子どもを授かりますが、いずれも死別するという、世の無常をつくづく思わされて、近隣の法座に出向き、本願寺にも足を運んで求道し続けます。しかし、死について、親さまについて、わからない苦悶の日々が続いていました。
ふいっとわからしてもらったいな
三十歳を過ぎたある夏の朝、「ふいっとわからしてもらったいな」と、源左さんが語る出来事が起こります。
源左さんは、いつものようにまだ夜の明けやらぬうちに、牛を連れて、裏山の城谷(じょうだん)へ草刈りに行きました。朝日が昇る頃、刈り取った草を幾つかに束ねて牛の背に担がせ、帰ろうとする時に、全部乗せては牛が辛かろうというので、一把(わ)だけ、自分が背負って帰ろうとしました。
ところが、疲れていたのでしょうか、急に腹が痛くなってどうにもならないので、背負っていた草の束を、牛の背に負わせました。自分はスーツと楽になった、その瞬間に心が開けたのです。
ふいっと分らしてもらったいな。
(柳宗悦・衣笠一省編『妙好人 因幡(いなば)の源左』三頁)
と、源左さんは後々までこのように語っております。「おれが背負っていかねば」と、気張っていた草の束を、牛の背にまかせたとたんに、手ぶらとなった自分は、ウソのように楽になった。その時、わたしのこの生と死のすべてをしっかりと支えて、「お前の生死はすべてこの親が引き受けたぞ」と喚び続けていてくださる阿弥陀さまがましますことを、全身で「ふいっと」気づかせてもらった、というのです。
その後は、「デン(牛)がおらの善知識だあ」とよろこび、なおいっそう牛を大事にしています。自分には(人間には)背負いきれない深重なる罪業を、阿弥陀さまがすでに背負ってくださっていた、その他力のご恩に気づかされたということができるでしょう。
おらなあ、親さんが、源左助けるって云はれっだけえ、ようこそゝよりほかにゃないだいなあ
(『同』九九頁)
ようこそゝ、なんまんだぶゝ
(『同』四頁)
このように、口癖のように語り、多くの人びとにお念仏のよろこびを伝えたのでした。
とにかく お慈悲は ぬくいでなあ
(『山陰 妙好人のことば』二三頁)
これが一月の法語です。ここに、源左さんが、苦しい、悲惨な人生を味わいながらも、大慈悲の温もりのなかにあることをしみじみと語られた言葉と、いただくことができるでしょう。
よろこびと安堵の言葉
『仏説観無量寿経』に「仏心(ぶっしん)とは大慈悲(だいじひ)これなり」(『註釈版聖典』一〇二頁)とあります。阿弥陀さまは、煩悩や苦悩、悲嘆のただなかにある私たちのあるがままの姿を見通し、常にはたらきかけて、摂取不捨されています。どのようなことがあっても、とらえて離すことなく見捨てることがない、如来の大慈悲です。そこに、言い知れぬ「温もり」を味わうのです。源左さんが、如来の大慈悲をひしひしと感じている、その心が深く味わわれます。
親鸞聖人は、『教行信証』行文類に、
大悲(だいひ)の願船(がんせん)に乗(じょう)じて光明(こうみょう)の広海(こうかい)に浮(うか)びぬれば、至徳(しとく)の風静かに衆禍(しゅか)の波(なみ)転ず。
(『註釈版聖典』 一八九頁)
と説かれています。すなわち、「本願の大いなる慈悲の船に乗り、念仏の衆生を摂め取る光明の大海に浮かぶと、この上ない功徳の風が静かに吹き、すべての禍(わざわい)の波は転じて治まる」と示されています。
そのとおりに、如来の大慈悲の船に乗せていただいていることのよろこびと安堵が、源左さんの言葉からいただかれます。
(佐々木恵精)
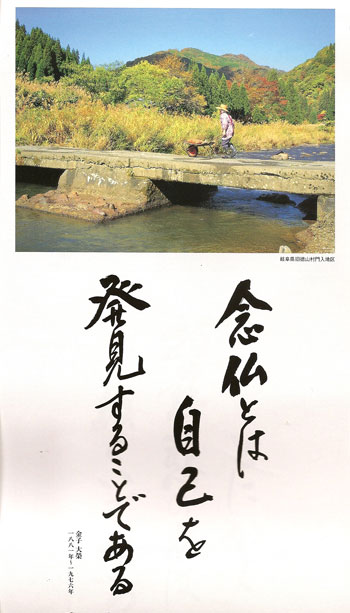 智慧と慈悲
智慧と慈悲
二〇一三(平成二十五)年の法語カレンダーは、「智慧(ちえ)と慈悲」をテーマとしています。
ブッダ・釈尊は真実に目覚められて、最初の説法で「四聖諦(ししょうたい)」(あるいは「四諦八正道(したいはっしょうどう)」)を説かれたと言われます。その「四聖諦」の第一が「この世は苦である」という真実であり、第二が「その苦の原因は(自己中心の)愛欲、すなわち煩悩である」という真実である、と説かれました。
『歎異抄』にも、私どもの姿を「煩悩具足の凡夫」と示される親鸞聖人のお言葉が述べられていますが、そのようなご教示によって、私たちは自らをたよりとして自己中心的な振る舞いしかできず、覚りを目指す実践がまったくかなわないものであると、つくづく知らされます。実際には、私たちは、何かに失敗した時とか、大きな災害に出遭った時などには、自分の愚かさや人間の無力さをいくらか感じますが、自分中心の思いを持ち、自分中心の眼(まなこ)でものを見ること以外にない存在で、なかなか自己をまともに見つめることができないものであります。
釈尊のみ教えに出遇(あ)って、やっと少し自分の姿に気づかされ、さらに、真実の覚りそのものである如来の、あらゆるものを平等にご覧になる真実の智慧と、すべてにへだてなくはたらく大慈悲に照らされてこそ、愚かなる「私」の姿が見えてまいります。
それが、煩悩具足の凡夫であると知らされるということになります。
この法語カレンダーには、如来の智慧と慈悲に照らされて、自己を見つめ、自己の愚かさを知らされるとともに、大悲にいだかれたよろこびをかみしめる。そのようなお言葉を、先達のご著述などから選んでいます。ともに味わいつつ、日々を過ごしたく思います。
自己の発見
表紙に、金子大榮(かねこだいえい)師のお言葉をいただきました。
念仏とは 自己を 発見することである
(金子大榮著『歎異抄』四六頁)
「念仏」とは、浄土教では私どもの口元で「南無阿弥陀仏」と称えさせていただく「称名念仏」のことですが、本来、真実の覚りそのものである如来を心に念ずることが「念仏」であり、仏を念ずることによって覚りへの道を歩む、すなわち仏道を歩むことになる、ということになります。しかし、親鸞聖人は、「この私」が迷いのなかの凡夫であることを厳しく見つめられ、真実の覚りである阿弥陀さまの本願によってこそ、救われる道が開かれているということを説かれました。
阿弥陀さまが「あらゆるものを救わずにはおかぬ」と願われ、「南無阿弥陀仏」の名号(みょうごう)を完成され、如来の大智と大悲を円かにそなえた救いのはたらきそのものである名号となって、「この私」に喚びかけてくださっている。その本願を信じ、名号をいただき、称名念仏するところに、救われていく道が開かれることになります。
親鸞聖人は、称名念仏の道を歩むについて、その根底に、如来の智慧と慈悲のおはたらきにいだかれて、そのはたらきにたよりきる心、「信心」があることが大事である、と示されました。師である法然聖人は、「ただ念仏して、弥陀にたすけられまゐらすべし」(『歎異抄』第二条 『註釈版聖典』八三二頁)とおっしゃられたと言われているように、唯円房(ゆいえんぼう)がまとめられた『歎異抄』にも、しばしば「念仏する」ことが説き示してあります。
『歎異抄』には「念仏」が三十九回使われていて、「念仏によって往生する」と説かれているのです。すなわち、念仏するところに、如来の本願を信じ、如来の智慧と慈悲のはたらきをいただく。そしてそのことは、「この私」の煩悩具足の姿を知らされつつ、如来の大いなるはたらきにいだかれる世界が開かれることであると、うかがわれるのであります。
金子大榮師が、念仏とは「自己を発見すること」であると語られるところには、念仏するなかに、阿弥陀如来の本願のはたらきをいただき、「この私」をあるがままに見つめさせていただく世界が広がっていることが示されているものと、うかがうことができるでしょう。
お念仏とともに生きる、お念仏のなかに生活するということは、お念仏するなかで、お念仏を通して、仏・如来に対面し、自己をあるがままに見つめる、そしてお念仏のなかに如来の大慈悲をよろこばせていただく、ということになるでしょう。
念仏のなかの生活
これは、阪神大震災の一年余り前のことですが、浄土真宗本願寺派の総長を長く務められた豊原大潤(だいじゅん)師が語ってくださった話です。
ある祝賀の会合で話されたのです。お祝いの言葉を述べられた後に―、
「私は、耳が遠くなり、自宅にいても家族の話がろくに聞こえず、まったく孤独な毎日です。そのようななかでも、ひとりでにお念仏を称えている、お念仏申すばかりの生活です。
ありかたいことに、自分か称えるお念仏だけは聞こえるのです、耳元でお念仏が響いてくださる。これが尊い、ありかたいことです。私か称えさせていただいているお念仏をいただきながら、お念仏のなかに生活させていただいています」
と加えられて、挨拶を結ばれました。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 なまんだ―ぶ…… とお称えする
このお念仏するなかに、「愚かなるこの私」がお念仏のなかに生かされている、お念仏とともに歩む身となっているということを、深いよろこびのなかで感じとり、ご自身を見つめておられる、そういうお姿を、豊原大潤師の挨拶のなかに拝見させていただいたのです。
金子師のお言葉のとおり、このような「自己発見」の場がお念仏なのだ、といただくことができます。
(佐々木恵精)
一月のご案内
御正忌報恩講法要
一月十三日 午前十時 午後一時半
十四日 午前十時 午後一時半
十五日 午前十時 午後一時半 午後六時
十六日 午前十時 午後一時半
講師 宇部市大字東万倉 明山寺住職
山名 学慈 師
おとき 十六日 正午
(十三日より十五日間、昼食を用意しています)
仏教壮年会 一月例会
一月十五日(火)午後六時より
講師 宇部市大字東万倉 明山寺住職
山名 学慈 師
暖かい支度をしてお参りください
 親鸞聖人の説諭
親鸞聖人の説諭
今月の法語は、『歎異抄』のなかに記された親鸞聖人のお言葉より頂戴しています。
『歎異抄』は、親鸞聖人のお弟子である唯円房(ゆいえんぼう)が書かれたものとするのが一般的な説ですので、「いよいよ大悲大願(だいひだいがん)はたのもしく、往生は決定(けつじょう)と存じ候へ」(第九条『註釈版聖典』八三七頁)と説諭された相手ば唯円房であろうと思われます。『歎異抄(現代語版)』では、
大いなる慈悲の心でおこされた本願はますますたのもしく、往生は間違いないと思います。
(一六頁)
と意訳されています。
いったい、唯円房は聖人にどのようなことを言われたのでしょうか。同じ意訳を読んでみましょう。
念仏しておりましても、おどりあがるような喜びの心がそれほど湧いてきませんし、また少しでもはやく浄土に往生したいという心もおこってこないのは、どのように考えたらよいのでしょうか
(『同』一四頁)
この問いに対し、親鸞聖人はお答えなさいます。
おどりあがるほど大喜びするはずのことが喜べないから、ますます往生は間違いないと思うのです。喜ぶはずの心が抑えられて喜べないのは、煩悩のしわざなのです。そうしたわたしどもであることを、阿弥陀仏ははじめから知っておられて、あらゆる煩悩を身にそなえた凡夫であると仰せになっているのですから、本願はこのようなわたしどものために、大いなる慈悲の心をおこされたのだなあと気づかされ、ますますたのもしく思われるのです。
(『同』一五頁)
このように、浄土に往生することが決まっているのに喜べないのは煩悩のせいであると、聖人はおっしゃいます。
慶喜と歓喜
そもそも、親鸞聖人ほど喜びについてお考えだった方はあまりおられないように思います。時に、喜びを「慶喜」と「歓喜」とに分けておられます。
まず、『唯信鈔文意』に、
信心をうるを慶喜(きょうき)といふなり。(中略)慶はよろこぶといふ、信心をえてのちによろこぶなり。喜はこころのうちによろこぶこころたえずしてつねなるをいふ。うべきことをえてのちに、身にもこころにもよろこぶこころなり。
(『註釈版聖典』七二一頁)
と「慶喜」をご説明になり、そして、『一念多念文意』には、
「歓喜」(かんぎ)といふは、「歓」(かん)は身をよろこばしむるなり、「喜」(き)はこころによろこばしむるなり。うべきことをえてんずとかねてさきよりよろこぶこころなり。
(『同』六七八頁)
と「歓喜」をご説明されます。
整理してみますと、「慶喜」は必ず往生できる身に定まったことを喜ぶのであり、「歓喜」は必ず往生できることを待っている喜びであります。
卑近な例で申し訳ないのですが、たとえば、私か学校や会社に入るために受験をしたとします。それで念願の合格をしますと、私の心には、入学や入社できることに対する喜びが湧くことでしょう。先の「慶喜」は、入られることが決まった喜びであります。そして、「歓喜」は、入って学生や社員になることを待っている喜びであります。
さて、このような喜びの説明は卑近な例ですからイメージが湧きますが、浄土の仏になるということは凡夫の身ではイメージが湧きません。なぜかといえば、学生も社員も私たちの世界で目の当たりにすることができるからです。なりたいと思っている人がそばにいるのです。なれると決まったら喜びもひとしおでありましょう。また、はやくなりたいと待っている喜びもありましょう。しかし、仏になることは…、どうもイメージが湧きません。それは自身が煩悩のある身ですから、煩悩のない身をイメージすることができないのです。
清浄の身と煩悩の身
煩悩のない身とはどのような身なのでしょうか。もちろん、煩悩がないのですから智慧の身ということができます。
しかし、智慧の身といわれても智慧のない身にはわかるはずもありません。そこで、親鸞聖人が他にどのように示してくださったのかを考えてみたいと思います。
このたびの親鸞聖人七百五十回大遠忌法要のために、「宗祖讃仰作法」という作法が制定されました。この作法は、親鸞聖人の和讃を十八首用いて作られています。その最後、回向文に相当する箇所の和讃に、次の一首が選ばれています。
南無阿弥陀仏をとけるには
衆善海水(しゅぜんかいすい)のごとくなり
かの清浄(しょうじょう)の善身(ぜんみ)にえたり
ひとしく衆生(しゅじょう)に回向(えこう)せん(『註釈版聖典』五九九頁)
南無阿弥陀仏のみ教えが説かれるところには、すべての善が海水のように満ちています。念仏の清浄の善を身に得たならば、同じようにその功徳を他の衆生にも施しましょう。
『高僧和讃』の結びの和讃ですが、ここに仏になるとは清浄の善を身に得ることであると示されています。考えてみますと、阿弥陀さまには多くの別名があります。そのなかで清浄と付くお名前の多いことは、七高僧のお一人、曇鸞大師の『讃阿弥陀仏偈』にも「清浄光(しょうじょうこう)・清浄大摂受(しょうじょうだいしょうじゅ)・清浄楽(しょうじょうがく)・清浄薫(しょうじょうくん)・清浄人(しょうじょうにん)」(『浄土和讃』『註釈版聖典』五五六頁、参照)と多く挙げられることから、知ることができます。
煩悩のない身とは、阿弥陀さま同様の清浄な身なのであります。ただし、私たち凡夫の世界で清浄というと、健康に害のない清潔なことの意味で用いられることが多いのですが、そのような意味ではありません。具体的には自己中心的な欲望がまったくないことであります。
昨年、日本は未曾有の災害に襲われました。東日本大震災であります。多くの方がたがお亡くなりになられ、また、避難を余儀なくさせられました。復興にどれほどの時間と経費が必要になるのかと世界中の人びとが心配をし、日本各地はもちろんのこと、外国からも多くの義損金が寄せられました。本当にありかたく尊いことであります。
しかし、その寄付をなさった方すべてが、自身の立場を忘れてまったくの無私の心から寄付をされていた、と言い切れるでしょうか。「誰それがいくら寄付をしたが、足りないのではないか」とか、「寄付の仕方が悪いのではないのか」とか、善意からの行為にもかかわらず、批判や意見が寄せられることがありました。
それらの批判的な報道に接する時、私も内心複雑な思いをいだきました。なぜならば、わずかばかりしか寄付をしていない私が、どのように使われるのだろうか、本当に被災者に届くのであろうか、と余計な心配をしていました。
いや何よりも、自分の生活に影響の及ばない範囲での浅ましい心での寄付でありました。誠にお恥ずかしいことです。煩悩具足の私のすることであります。
この自己中心的な欲望に支配される私のような心を、仏教では貪欲といい、瞋恚・愚痴とともに、三毒の煩悩の一つに数えます。この貪欲があるかぎり、人間には苦しみがついてまわるのです。そこで、阿弥陀さまはこの浅ましい心を取り除き幸せな心にさせてやろうと、凡夫を浄土で仏にしてくださるのです。その仏の身を清浄な身と申すのです。
大悲大願の心
汚穢不浄(おえふじょう)な身を清浄な身にさせようというのが、阿弥陀さまの本願のお心であります。これこそが大きなお慈悲の心であります。この心より「南無阿弥陀仏」の名号が私にはたらいてくださるのであります。
親鸞聖人は『弥陀如来名号徳』に、このはたらきを次のようにお示しくださいます。
つぎに清浄光(しょうじょうこう)と申すは、法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)、貪欲(とんよく)のこころなくして得たまへるひかりなり。貪欲といふに二つあり。一つには婬貪(いんとん)、二つには財貪(ざいとん)なり。この二つの貪欲のこころなくして得たまへるひかりなり。よろづの有情(うじょう)の汚機不浄を除かんための御ひかりなり。婬欲・財欲の罪を除きはらはんがためなり。このゆゑに清浄光と申すなり。
(『註釈版聖典』七二八~七二九頁)
自己中心的な欲望を除くことのできない私であります。また、その欲望を本心から否定もできない私であります。そのような愚かな、浅ましい私をかねてご存知であるからこそ本願をお建てになったのが、阿弥陀さまです。法語に、「いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じ候へ」と親鸞聖人のお言葉が掲げられていますが、ますますありかたく、このお言葉を頂戴させていただくようなことであります。
まことに頼もしく、ありかたい聖人の仰せでありました。
(北塔光昇)
あとがき
親鸞聖人ご誕生八百年・立教開宗七百五十年のご法要を迎えた一九七三(昭和四十八)年に、真宗教団連合の伝道活動の一つとして「法語カレンダー」は誕生しました。門信徒の方がたが浄土真宗のご法義をよろこび、お念仏を申す日々を送っていただく縁となるようにという願いのもとに、ご住職方をはじめ各寺院のみなさまに頒布普及のご尽力をいただいたお陰で、現在では国内で発行されるカレンダーの代表的な位置を占めるようになりました。その結果、門信徒の方がたの生活の糧となる「こころのカレンダー」として、ご愛用いただいております。
それとともに、法語カレンダーの法語のこころを詳しく知りたい、法語について深く味わう手引き書が欲しいという、ご要望をたくさんお寄せいただきました。本願寺出版社ではそのご要望にお応えして、一九八〇(昭和五十五)年版から、このカレンダーの法語法話集『月々のことば』を刊行し、年々ご好評をいただいております。今回で第三十三集をかぞえることになりました。
真宗教団連合各派において、二〇一一(平成二十三)~二〇一二(平成二十四)年と親鸞聖人七百五十回大遠忌を迎えますことから、聖人のいただかれた聖典のお言葉を中心に法語が取りあげられることになり、特に二〇一二(平成二十四)年には、親鸞聖人が書かれた「正信偈」や和語のご聖教を中心に、ご門徒にとっても身近な法語が選定されました。この法語をテーマにして、四人の方に法話を分担執筆していただき、本書を編集いたしました。繰り返し読んでいただき、み教えを味わっていただく法味愛楽の書としてお届けいたします。
本書を縁として、カレンダーの法語を味わい、ご家族や周りの方がたにお念仏のよろこびを伝える機縁としていただき、また、研修会などのテキストとしても幅広くご活用ください。
二〇一一 (平成二十三)年八月
本願寺出版社