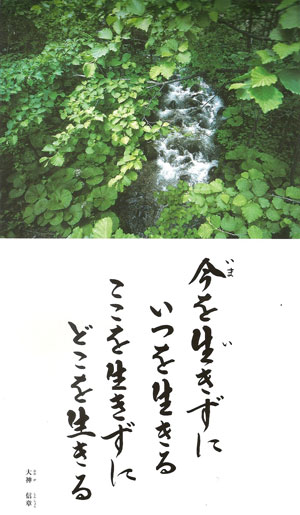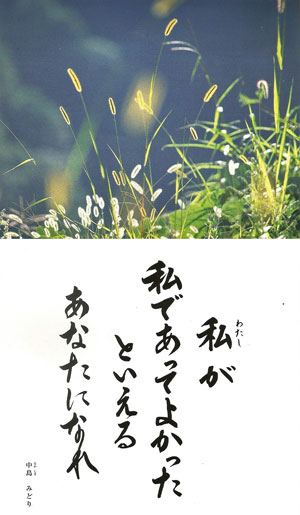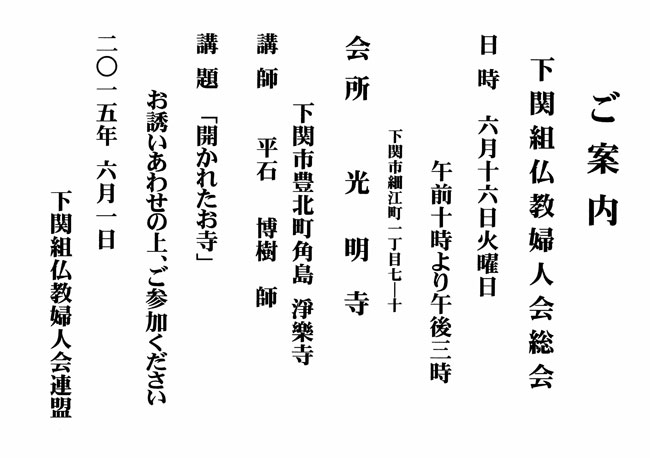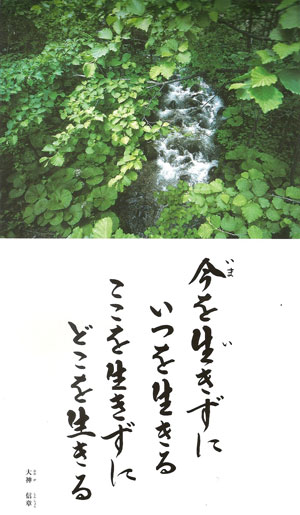 お寺の前の掲示板
お寺の前の掲示板
八月といえば、私の郷里の福岡ではなんと言ってもお盆です。「例年以上の猛暑です」という毎年恒例のニュースにぐったりしつつ、意を決して外に出てみれば、強烈な日差しと濃い影。盛大な蝉しぐれと入道雲。たちまち吹き出す汗に貼りつく白衣、そんな中を原付バイクにまたがってお参りする私。そして久しぶりに集まった家族や親戚と連れだってお寺参りされる方々。里のお盆の毎年の風景です。
ところでお寺の前を通りかかると、しばしば門前の掲示板に、味わい深い法語が書かれています。あれは掲示伝道といいます。門前を通りがかった人が、歩き過ぎるまでに読める程度の言葉かずで、真理を伝える言葉や、ぬくもりを伝える言葉などが示されています。目にすれば「なるほど」と思わずうなる言葉や、忘れがちな大切な事実を思い起こさせてもらいます。しかし掲示伝道を自分でやってみるとなると結構、大変です。長すぎたり難しすぎたりで、具合のいい言葉を選び出したり案出したりすることは、そう簡単にはいきません。
今月の言葉は、大神信章氏の『学仏大悲心 ほとけのおしえ 詩と言葉』(探究社)という書物からです。この一冊には、大神氏が生涯をかけて創作し続けた法語や短文が満ちあふれています。氏は、いわば法語伝道の達人といえましょう。
大神氏は一九四九(昭和二十四)年にお生まれになり、二〇一三(平成二十五)年二月十八日にご往生されています。しかしページをめくって氏の紡ぎ出した法語に触れ続けていると、おもしろいもので、会ったこともない氏の人格に濃厚に触れる気がします。ご法義が身に染みついた人が発する言葉とは、そういうものなのかもしれません。今月のお言葉も、そんな氏が残された力強いお言葉です。
無量光・無量寿のこころ
さて阿弥陀さまの「阿弥陀」とは、「無量光」「無量寿」を意味するインドの言葉「アミターバ」「アミターユス」がもとになっているといわれます。特に両方に共通する「アミタ」の部分は「無量」、すなわち私たちには「量り知ることができない」という意味です。そしてその後に続く「アーバ」は「光」、「アーユス」が「寿」です。
仏教のお話を聞いていると、しばしばこの「光」というのが登場しますね。仏教で光というのは、詳しくは「光明」といいます。真理を明らかに見通した仏さまの智慧をあらわしているのです。一方で、仏教では私たちのもっている根源的な自己中心性(煩悩)のことを「無明」、すなわち闇として表現します。つまり光と闇の対比で、仏さまと私たちの関係性を表しているのです。
私たちは人生を生きていくのに、それぞれに構築した価値観をたよりに生きています。しかしこの無明という表現は、仏教の教えに触れることなく構築された価値観とは、実は「闇」に身を置くようなものであると言っているのではないでしょうか。闇に身を置くと、自分がどのような姿で、どちらを向いているのか、まるでわかりません。しかしそこに一条でも光が差し込めばどうでしょうか。おのずとみずからの姿を知らされ、行くべき方向を知ることになります。
つまり阿弥陀さまはご自分の名前に、どのような場所に生きる、どのような者の闇であっても、かならず光を与えていく如来であることを「無量光」の意味をもって「阿弥陀」と知らせているのです。また、その広大な活動は時をえらばず、常に私を照らし護り続けるのだということを「無量寿」(量り知れないいのち)の意味を込めて「阿弥陀」と名告られたのでした。
阿弥陀さまのこうした強力なはたらきは、遥かなる過去から私一人をあたかも狙い撃ちにするようになされてきました。私はいま図らずも、お浄土の阿弥陀さまを、そして先人を心に思い浮かべ、お念仏するようになっていますが、この姿こそ、そうしたはたらきが私の身の上に結実した何よりの証なのです。お念仏する者とは、阿弥陀さまによって育てられた者であり、そのはたらきを知らされた者に他なりません。
ところで私が法事の席などで、たとえば「阿弥陀さまのお救いは、お名前の通り、無量光・無量寿のお救いです。それは端的には、〈いつでもどこでも〉のお救いということです」といったような法話をすることがあります。すると法事が終わって私か着替えをしていたら、ご門徒さんがすっと寄ってこられ、
今日のはなし、ようわかった。いつでもどこでもの如来さんで、ほんによかったばい。私も今は元気ばってん、いずれは、いつかどこかで阿弥陀さんの世話にならないけんもんね
と言う方がおられます。――いやいや。そうではないのです。実は、「いつでも」というのはいつも「今」なのです。「どこでも」というのは「ここ」のことです。つまり「いつでもどこでも」と聞けば、「いつかどこかで」と聞かずに「今ここで」阿弥陀さまに値遇していくのであると昧わっていただきたいのです。
「味わう」ということ
浄土真宗ではお聴聞が大切であると強調しますね。しかしだからといって、お聴聞を重ねて知識を増やし賢くなれと勧めているわけではありません。また、聞くことで煩悩を減らしなさいと言っているわけでもありません。もし知識を得て賢くなるために聞いているのなら、同じような話を何度も聞く必要はありませんし、試験でもすればよいのです。また煩悩が減っていくのならば、長年お参りされている方は仏さまのような在り方に近づいているはずですが、私のお寺では見たところ、ここだけの話ですが、そうでもないようです。では何度も何度もお参りされる方は、なぜお参りされているのでしょうか。
あれは、実は本堂の阿弥陀さまの前に座ってお慈悲を味わっておられるのです。
阿弥陀さまのお慈悲を味わうことが心地よいから、何度でも参るのです。ですから、昔からお聴聞してご法義に触れることを学習ではなく、味わいといいます。つまり食事ですね。食事は一度食べたから、もう十分というわけではありません。またしばらくたてば食事をして味わいますし、それが極上の味ならなおさらです。そういえば先輩の布教使さんが、「お酒の味をすでに知っているからといって、もう晩酌は必要ありませんというわけにはなかなかいきませんでしょう」と譬(たと)えておられたことを思い出しました。やや不謹慎かも知れませんが、おっしゃりたいことはとてもよくわかりますね。
お聴聞をしておりましたら、「私の全人生をつつみ込む阿弥陀さま」といった表現をしばしば耳にします。しかしいくら全人生といってみても、それは結局、いつも「今」の自分以外にはないのではないでしょうか。久遠劫来の過去を経ながら、いま現に迷いの世界に存在し、未来へと歩みを続けるのは、他の誰でもなく、いつも「今」の私だからです。ですからお念仏しては、いつもわが身を離れない阿弥陀さまを確認し、またご法義を聞いては阿弥陀さまのお慈悲に身を浸します。それはいつも「その時その場」でやっていくのであり、その人にとっては「今ここ」でお念仏しているのです。そしてどの「今ここ」であってもかまわない。「無量光」だからどこでだっていいし、「無量寿」だからいつだっていい。そしてご法義は味わうのだから「何度でもよい」ということです。その意味において、私たちは阿弥陀さまに全人生を包まれています。
「いま」と「すでに」
親鸞さまは、阿弥陀さまのことが説かれた経典や、その真意を明らかにされた七高僧さまとの出遇いについて、『教行信証』の「総序」に、
ここに愚禿釈(ぐとくしゃく)の親鸞、慶(よろこ)ばしかな、西蕃(せいばん)・月支(げっし)の聖典しょうてん)、東夏(とうか)(中国)・日域(じちいき)(日本)の師釈(ししゃく)に、遇ひがたくしていま遇ふことを得たり、聞きがたくしてすでに聞くことを得たり。
(ここに愚禿釈の親鸞は、よろこばしいことに、インド・西域の聖典、中国・日本の祖師方の解釈に、遇いがたいのに今遇うことができ、聞きがたいのにすでに聞くことができた)
(『註釈版聖典』 一三二頁)
と述べておられます。ここで注目すべきは「いま」と「すでに」という部分です。
この文章を書いた時点では、それらの方々に出遇われたのは過去のはずですから「すでに」という表現が当てはまるはずです。しかしながら、それを「今」という表現を離さずにお書きになっている。これは「遇ふ」ことと「聞く」こととが別の時に行われたというわけではありません。ならば一方で「今」と書き、一方で「すでに」と書けば矛盾しているように感じますが、そこに親鸞さまの真実があるように感じます。私はこの表現にこそ、経典や祖師方と、いつも「今」遇い続けていらっしゃった親鸞さまのお姿を垣間見るような気がするのです。
今月の言葉を、いま一度味わってみてください。
(井上見淳)
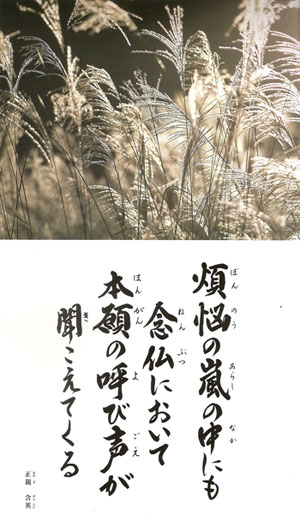 南無阿弥陀仏の喚び声
南無阿弥陀仏の喚び声