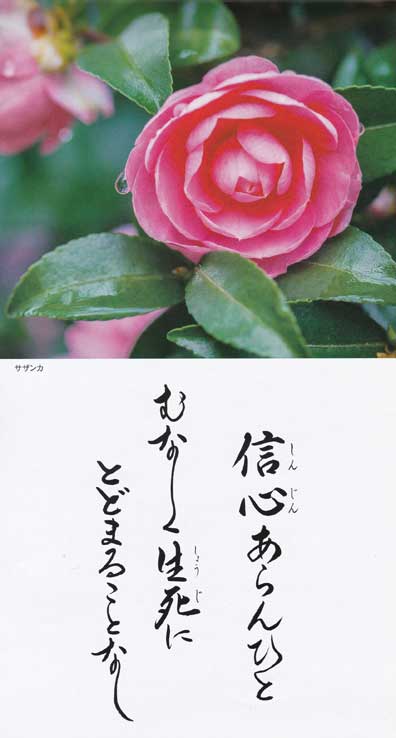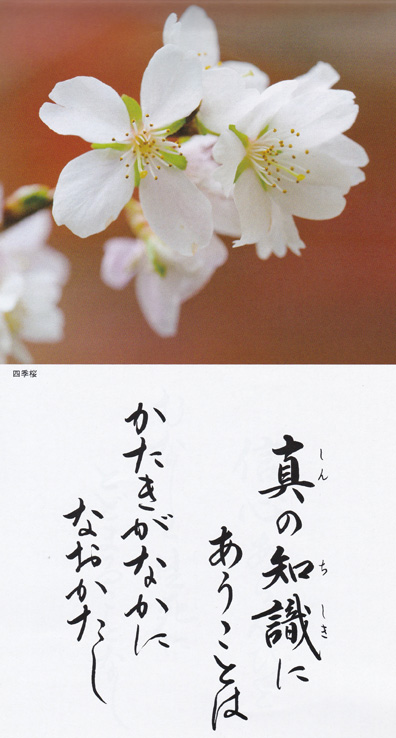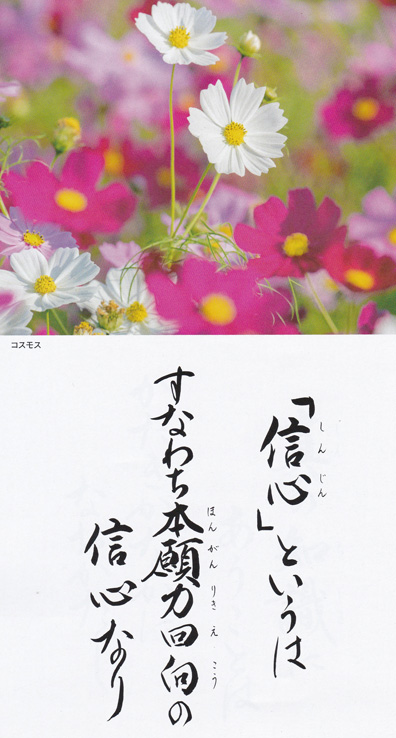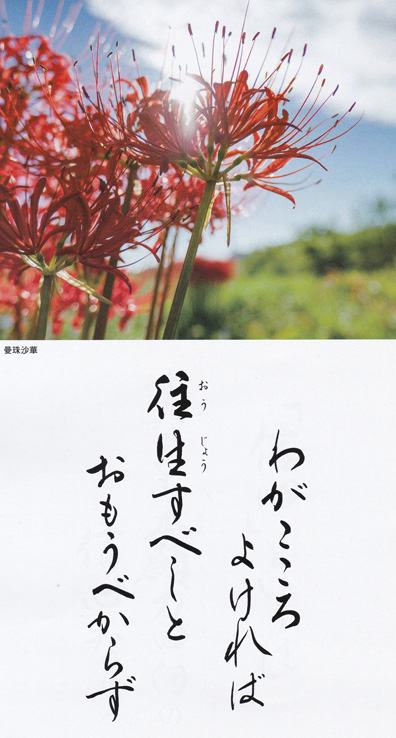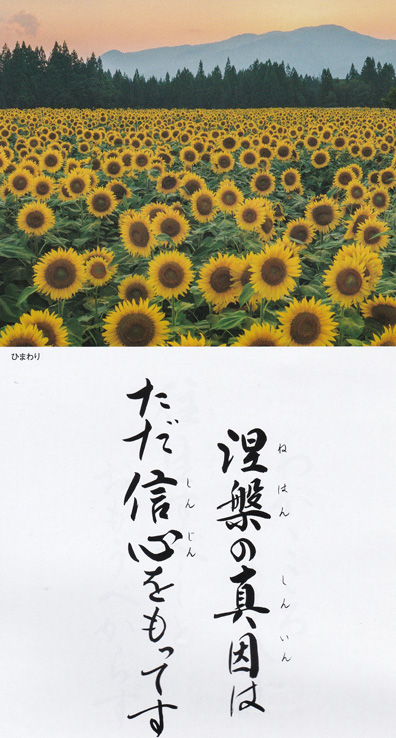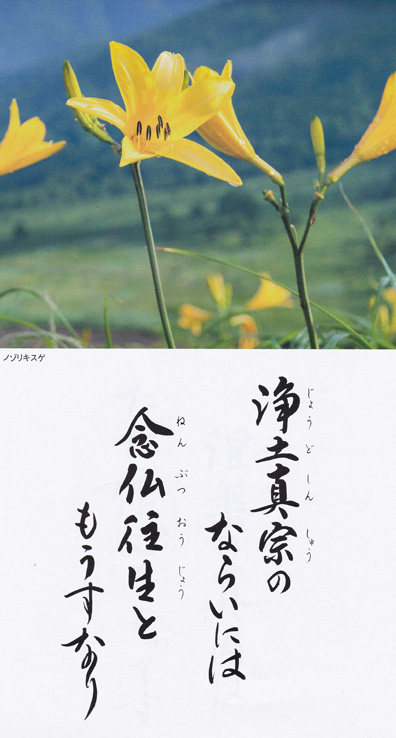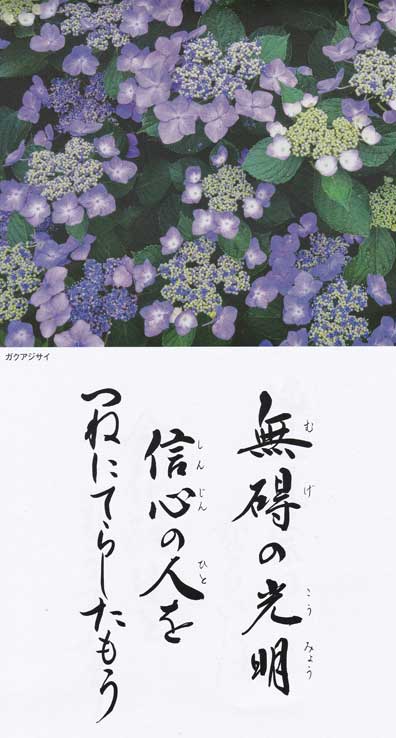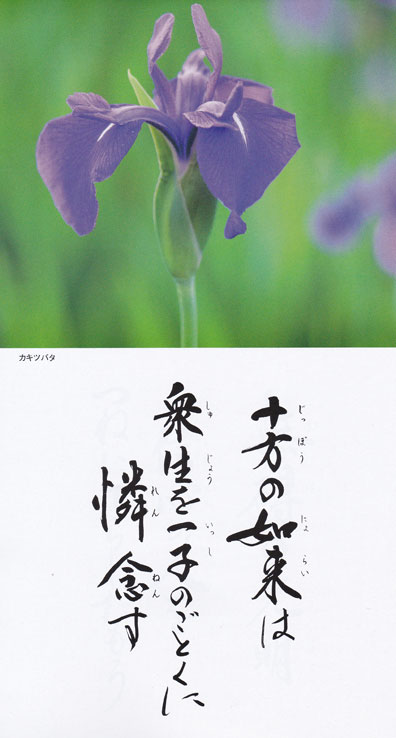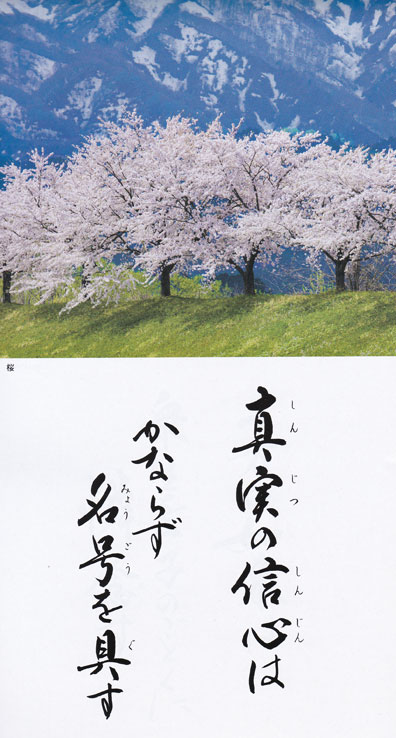先生との思い出
毎年、真宗十派が加盟する真宗教団連合によって「法語カレンダー」が出版されています。
去る二〇一九年五月一日、元号がそれまでの「平成」から「令和」に代わりまし
た。この「令和」は、『万葉集』に載っている文から選ばれたものです。したがっ
て、二〇二〇年版「法語カレンダー」は令和二年版になります。もう少し早くから
次の元号が決められていたならば、スムしスに移行できて混乱を生じさせることも
なかったと悔やまれます。
表紙のことばは、京都女子大学名誉教授であった瓜生津隆真先生の著『仏教から真宗ヘー仏教用語散歩-』(本願寺出版社)から引用されたものです。
瓜生津先生は一九三二(昭和七)年九月に生まれられ、二〇一五(平成二十七)年二月に往生されました。八十二歳でした。文学博士で、滋賀県犬上郡にある浄土宗本願寺派法城寺の住職をされていました。ご著書には、『龍樹(ナーガールジ
ュナ) 空の論理と菩薩の道』『信心と念仏』『親鸞聖人に学ぶI無我と他力』『聖典セミナー 阿弥陀経』など、多数があります。
この「法語カレンダー」との関わりでは、先生は、二〇〇七(平成十九)年、二〇〇八(平成二十)年と続けて、カレンダーの解説書である『月々のことば』の表紙のことばを担当されていました。二〇〇七年は、
仏心というは大慈悲これなり (『観無量寿経』)
そして二〇〇八年は、
世のなか安穏なれ 仏法ひろまれ (『親鸞聖人御消息』)
という法語について、文章を書かれています。
たまたま二〇〇八年の「法語カレンダー」に私も関わり、四月は、
真なるものははなはだ少なく 偽なるものははなはだ多い
(『教行信証』化身土巻)
という法語の解説を、そして五月には、
仏の国土は清く安らかな涅槃の世界である
(『教行信証』証巻引文、『無量寿経』上巻)
六月には、
仏の智慧をほめたたえ その功徳を人々に伝えよう
(『浄土和讃』「讃阿弥陀仏偶和讃」)
という法語の解説を担当いたしました。
瓜生津先生とのご縁のなかで思い出すのは、二〇〇二(平成十四)年度の浄土真
宗本願寺派布教講会です。これは布教使の研修会で、九月二日から六日まで西本願寺聞法会館で開かれました。先生は教講を務められ、四日問、「大乗菩薩道と真宗」の題名で講じられ、私も副講の任を与えられ、三日問、「真宗和語聖教―一念多念文意・唯信紗文意・尊号真像銘文を中心として」の題名で講述しました。
真の仏弟子
それでは、法語[悲しみの深さのなかに立]のよろこびがある」のご文を味わってみましょう。
私たちの人生には「悲喜こもごも」と言われるように、悲しみと喜びが交互にや
ってきます。まさしく山あり谷ありです。しかし、念仏生活によって深い悲しみの
なかに真の喜びが生じてきます。
親鸞聖人は、浄土真宗の教えに出遇った人は信心をいただいた喜びから「真の仏
弟子」であるといわれますが、瓜生津先生は、まずその主著『教行信証』信巻
(末)にある、この「真の仏弟子」について言及されています。
「真の仏弟子」(散善義四五七)といふは、真の言は偽に対し仮に対するなり。
弟子とは釈迦・諸仏の弟子なり、金剛心の行人なり。この信行によりてかな
らず大涅槃を超証すべきがゆゑに、真の仏弟子といふ。
(『註釈版聖典』二五六圭一五七頁)
ここでは、「真実」の語は「邪偽」と「権仮方便」に対する語で、「弟子」とは「釈迦・諸仏の弟子」である。また、金剛心(信心)を獲得した行人(念仏者)で
ある。すなわち信心と念仏によって、浄土に往生してかならず大涅槃のさとりを得
るから、これを真実の仏弟子という、と述べられています。そして、ひたすら阿弥
陀如来の真実心を仰ぎ、如来のこころに生きる人は、どのような苦悩や悲しみに出
会っても、それにうちひしがれることなく、またどのようなさまたげにもくじける
ことがない、と述べられています。
「真仏弟子釈」の終わりには、
仮といふは、すなはちこれ聖道の諸機、浄土の定散の機なり。
(『註釈版聖典』二六五頁)偽といふは、すなはち六十二見・九十五種の邪道これなり。 (同頁)
とも述べられています。仮とは聖道門の人々であり、浄土門の定善・散善の人で
あり、どちらも自力の教えです。また、偽は釈尊当時の異教徒の総称で、仏教以外
の教えのことをいいます。
智慧と慈悲
また「真仏弟子釈」の後には、『無量寿経』の第三十三願(触光柔軟の願)と第
三十四願(聞名得忍の願)が連引されています(『註釈版聖典』二五七頁)。これに
ついて瓜生津先生は、阿弥陀如来の光明に照らされれば、心身ともに柔軟になる。
また、「聞名」とは名号を聞くということであり、如来の喚びかけを通して如来の
真実の智慧が凡夫である私にはたらくことである。また「得忍」とは、無生法忍、
すなわちすべての存在の本質が空であるという真実を知る智慧を得ることであり、
私の上に阿弥陀さまの真実が智慧となってはたらくことである、と述べられていま
す。
さらに瓜生津先生は、
智慧の念仏うることは
法蔵願力のなせるなり
信心の智慧なかりせば
いかでか涅槃をさとらまし (『註釈版聖典』六〇六頁)
という『正像末和讃』を引いて、
念仏は智慧であり、したがって信心も智慧であることがたたえられている。この智慧は自己(罪悪性)にめざめ、如来(真実功徳)を知るという働きをもつ。
自己にめざめることは、自己の罪悪深重を知ることであり、それは「愚にかえる」ことなのである。如来を知るとは、如来の真実を知ることであって、この自已にめざめ如来を知るということが、同時に成り立つところに、この智慧の
特質がある。 (『仏教から真宗ヘー仏教用語散歩-』二四二圭一四三頁)
と述べられています。
続いて、瓜生津先生は、信心の行人(念仏者)として「正信偶」の四句を出され
ています。
一切善悪几夫人
聞信如来弘誓願
仏言広大勝解者
是人名分陀利華 (『日常勤行聖典』 一五頁)
二切善悪の几夫人、如来の弘誓願を聞信すれば、仏、広大勝解のひととのたまへり。この人を分陀利華と名づく。『註釈版聖典』二〇四頁)
第三効目の「広大勝解者」は、「真仏弟子釈」に引用される『無量寿経』異訳の経典である『如来会』にあり、また第四劫目の「分陀利華」とは、真実信心に生きる人のたとえである白蓮華の意で、『観無量寿経』の終わりに述べられています。
さらに、瓜生津先生は、道緯禅師の著『安楽集』に引用される『大悲経』の「大悲を行ずる大」の言葉に注目されます。
『大悲経』にのたまはく、〈いかんが名づけて大悲とする。もしもつぱら念仏相
続して断えざれば、その命終に随ひてさだめて安楽に生ぜん。もしよく展転
してあひ勧めて念仏を行ぜしむるは、これらをことごとく大悲を行ずる大と名
づく〉と。 (『註釈版聖典』二六〇頁)
このように『大悲経』には、どのようなことを大悲と名づけるのであろうかという問いに対して、もし念仏を続けて止めなければ、いのちを終えると必ず浄土に往生する。もしも、次々と念仏を人々に伝えていくならば、このような人をすべて大
悲を行じる人と名づけるのである、と説かれています。
栃平ふじさんの歌
次に、瓜生津先生は、鈴木大拙師の名著『妙奸人』に掲載されている、石川県
奥能登在住の栃平ふじさん(一八九六~一九六五)の歌を一句紹介されています。
親さまの智慧と慈悲とをいただいて
ねるもおきるも、なむあみだ (『仏教から真宗ヘー仏教用語散歩-』二四四頁)
この栃平ふじさんの歌を、
念仏に生きる人生を見事に示しているといえよう。如来の智慧と慈悲をめぐまれて、人生を生きぬくところに、念仏者の人生があって、それこそ真の人生であることを簡潔にのべている (同頁)
と、先生は讃えられています。
私は、二〇一八(平成三十)年三月三日に、本願寺金沢別院で開催された中央仏教学院の「石川地区つどい 本部派遣学習会」に出講した後、午後四時に金沢駅前からバスに乗り、四時間ほどかけて一路、能登半島北端の珠洲市宝立町の栃平ふじ
さんゆかりの地を訪れました。出発する前に、あらかじめ『妙奸人 千代尼』を刊行された、珠洲市飯田町にある真宗大谷派西照寺の西山郷史住職に連絡していましたので、終着駅に着いたときには彼が迎えに来てくれていました。翌朝には、宿
の近くにある、西山さんから聞いていた、鈴木大拙師が若い頃に下宿されていた家も拝見することができました。
栃平ふじさんは、真宗大谷派往還寺のご門徒でした。西山さんの車で一緒に栃平さんの家を訪れ、玄関前で写真を撮らせていただきました。いまは親族の方が時々来られる程度で、ご不在でしか。帰途、かほく市にある哲学者の西田幾多郎先生の
出生地や墓地の近くを通り、金沢駅まで送ってもらいました。
妙奸人・栃平ふじさんの他の歌を紹介しましょう。
おやさまの智慧と慈悲とを戴いて、ゆくも帰るも六字かな。南無阿弥陀仏。
(『妙奸人』二五二頁)
おやさまの ふところ住まいと 知らなんだ ああありがたや しやわせじゃ
なむあみだぶつ (『同』二五五頁)法蔵とは どこに修行の 場所あるか みんな私の むねのうち なむあみだ
ぶつ あみだぶつ (『同』二五六頁)今日も日ぐれで 大晦日 あすは夜明けで 御正月 なむあみだぶつ (同頁)
実は、お世話になった西山師とは、珠洲市で初めてお会いしたのです。ところが、
いまから二十四年前の一九九五(平成七)年、新人物往来社から発行された『蓮如
のすべて』(早島鏡正編)のなかで、ともに原稿を寄せていたことが判明したので
す。題名については、彼が「現代に生きる蓮如-蓮如と北陸」で、私は「蓮如上人
と『御文章』」でした。まさに蓮如上大がとりもつご縁でした。
人間性のめざめ
最後に瓜生津先生が注目されたのは、「真仏弟子釈」が、次の親鸞聖人の悲嘆の
言葉によって結ばれていることでした。
まことに知んぬ、悲しきかな愚禿鸞、愛欲の広海に沈没し、名利の太山に迷惑して、定衆の数に入ることを喜ばず、宿六証の証に近づくことを快しまざるこ
とを、恥づべし傷むべしと。 (『註釈版聖典』二六六頁)
この悲嘆は、如来の真実に出遇った喜びと離れないものです。悲しみは喜びであり、悲しみの深さのなかに真の喜びがある。「まことに知んぬ」には、如来の真実に出遇った感動と、如来の真実によって照らし出され知ったものへの驚きが、述べられています。
如来の真実による深い人間性のめざめIそれは如来の真実を知り、自己の罪悪・虚仮を知ることですIが、このことが宗教的生の根源であり本質であることを、親鸞聖人の悲嘆の言葉はよく示されています。如来の智慧によって自らの心が明らか
になり、如来の慈悲によって新たないのちを生きるところに、「真仏弟子」すなわち「信心の行人」(念仏者)の道があると述べられているのです。
(林 智康)