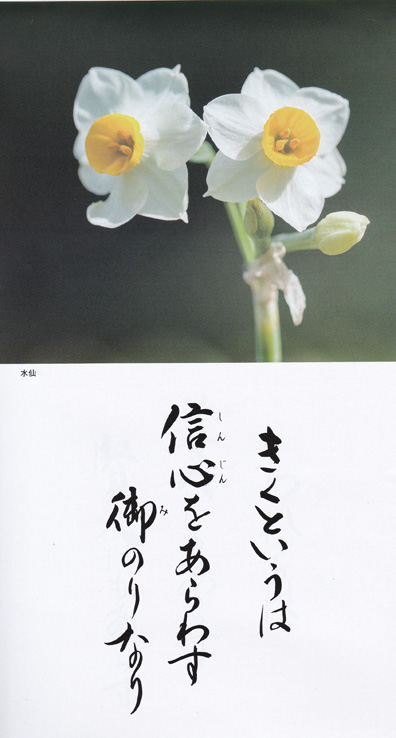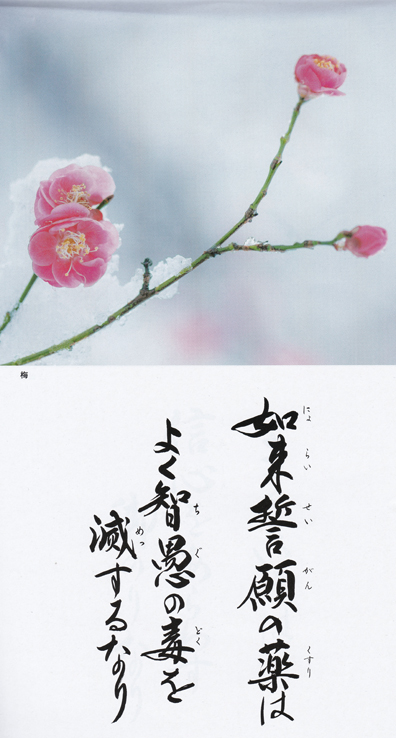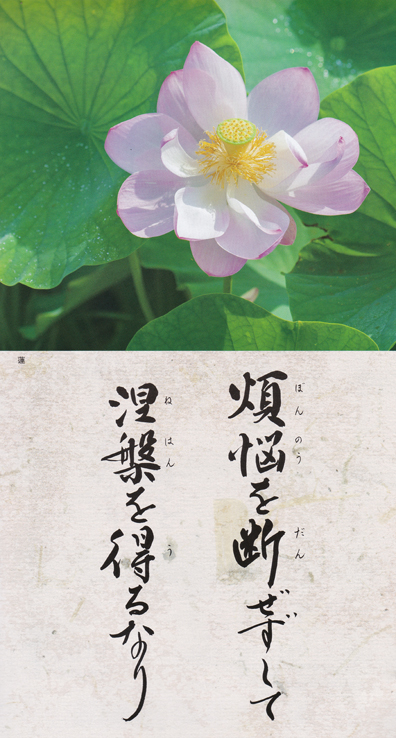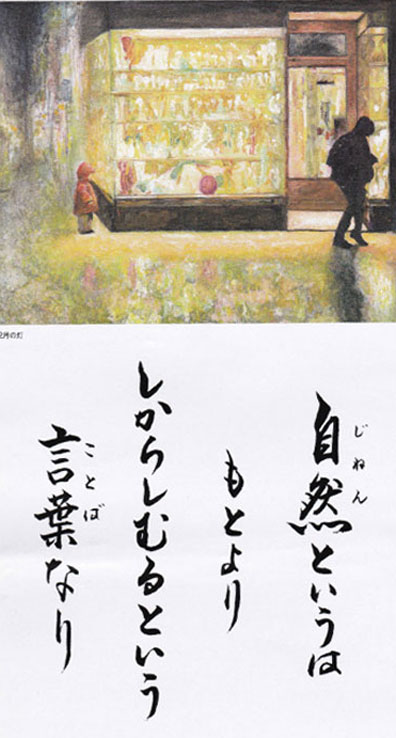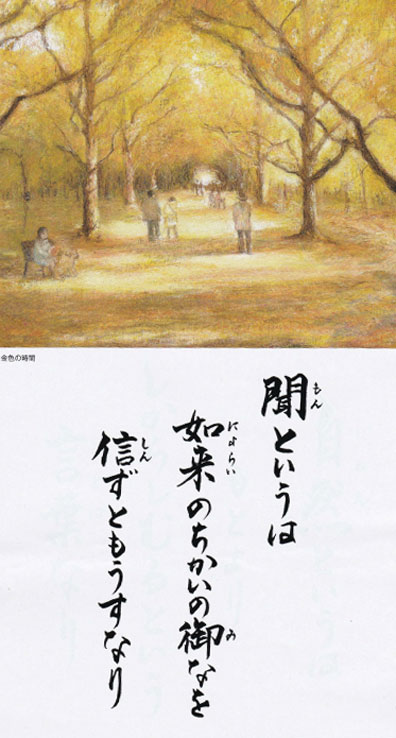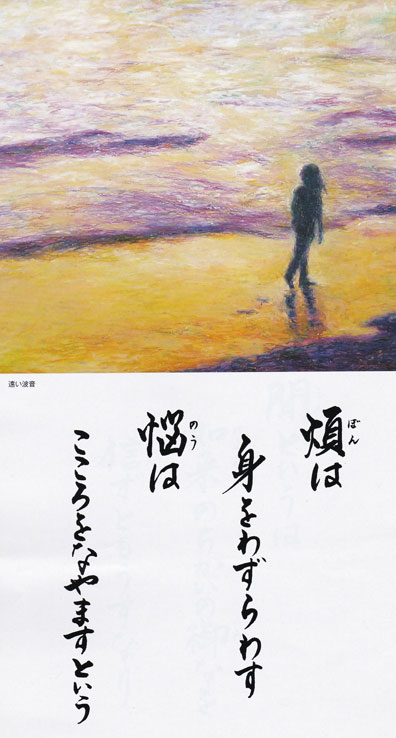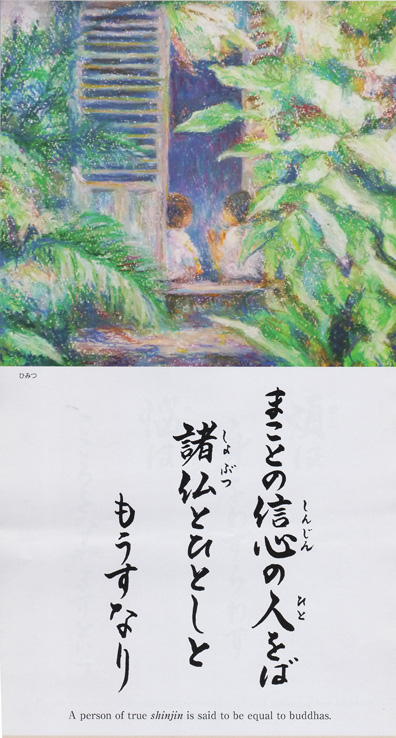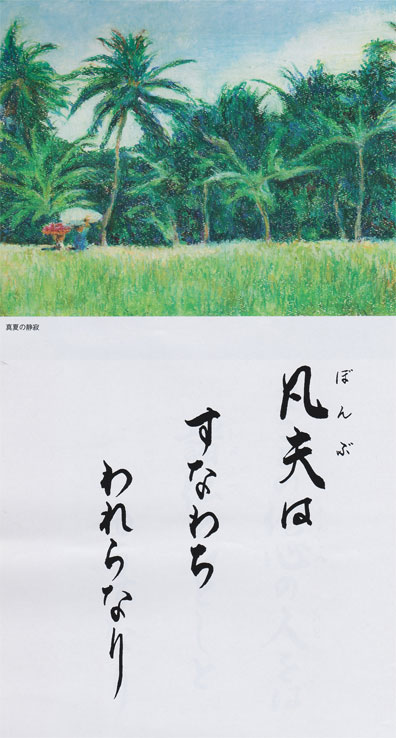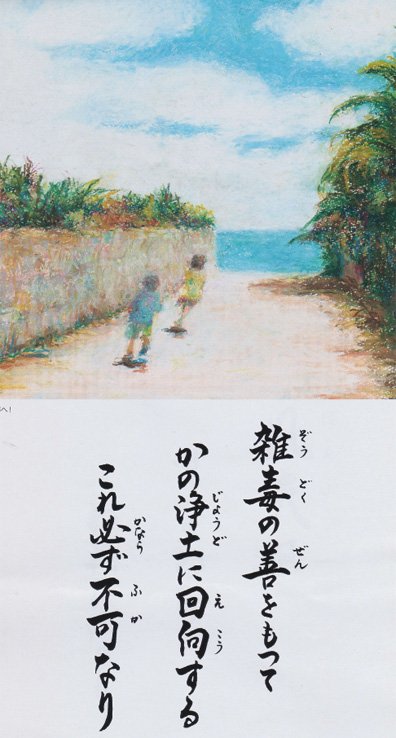「賢善精進」の深意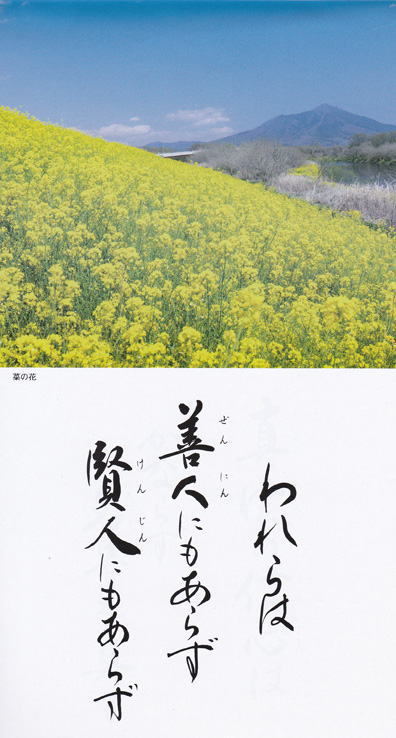
三月のことばは、親鸞聖人の『唯信炒文意』というご著作のなかにあります。
親鸞聖人が聖教を拝読されるにあたって、ときに独自の訓点によって大胆な訓み替えをなさったことは、よく知られています。なかでも、その代表格ともいえるのが、善導大師の「散善義」の文の訓み替え(『顕浄土真実教行証文類(教行信証)」信文類、『註釈版聖典』一二七頁)ですが、この『唯信炒文意』では、それを一語一語
細かく区切ってご解釈くださっており、今月はそのなかの一文です。
まず、もともとの善導大師の「散善義」の文を見ておきましょう。原文は漢文体です。
不得外現善精進之相内懐中虚仮
(『浄土真宗聖典全書』‥』三経七祖篇、七六一頁)
とあります。この文を普通に読み下せば、
外(ほか)に賢善精進(けんぜんしょうじん)の相(そう)を現(げん)じ、内(うち)に虚仮(こけ)を懐(いだ)くことを得(え)ざれ。
『註釈版聖典(七祖篇)』四五五頁)
となるでしょう。「外面」だけ賢そうにして、内側が虚仮不実であるようなことであ ってはならない」といった意味になります。
これを、親鸞聖人は、
外(ほか)に賢善精進(けんぜんしょうじん)の相(そう)を現(げん)じ、内(うち)に虚仮(こけ)を懐(いだ)けばなり
「(『教行信証』信文類、『註釈版聖典』一七頁、()内引用者)
と読み下されています。「内側が虚仮不実であるのだから、外面を賢そうに振る舞っ てはいけない」といった意味になるでしょう。
似ているようで、少し意味が違ってきます。善導大師の場合は、外見が賢善精進 のすがたを取るのであれば、内面が虚仮不実であってはならないという、内外の不 一致を問題とされているのに対し、親鸞聖人の場合は、内側が虚仮不実の身である ことは動かしようがないので、外見を賢そうに振る舞ってはならないとされ、さら に厳しい自己内省が徹底されているように思われます。 「この文脈に沿って、細かく善導大師の文を解釈されていくなかに標題の一文があり、「私たちは、善人でもなければ、賢人でもない」と示されています。だから賢善精進の相を示すことなどできないのです。
智者のふるまひをせず
この大胆な訓み替えのベースには、「一枚起請文」に記された、法然聖人のお心が あるのではないかと想像しています。現代風にいえば、「念仏者の誓い」とでもいう べき規範です。
もろこし(中国)・わが朝に、もろもろの智者達の沙汰しまうさるる観念の念に もあらず。また、学文をして念の心を悟りて申す念仏にもあらず。ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して、疑なく往生するぞと思ひとりて申すほかに 別の子細候はず。(中略)このほかにおくふかきことを存ぜば、二尊の あはれみにはづれ、本願にもれ候ふべし。念仏を信ぜん人は、たとひ一代の法 をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無智のともがら におなじくして、智者のふるまひをせずして、ただ一向に念仏すべし。
(『註釈版聖典』一四二九頁)
中国(「もろこし」)から仏教が伝来して以来、多くの高僧方による理解では、「念 仏」の「念」とは、精神を統一して邪念を雑えず、心に波風をたてず、浄土や阿弥 陀仏のすがたをありありと想い浮かべる、「観念」とされてきました。しかし、私たちのような心の散乱する凡夫において、乱れ心なく精神を統一することは、およそ 不可能です。ご法事のときでさえ、「焼香を早く回せや」、「料理はまだ来ないのか」 などと、すぐに雑念が湧いてきます。
「十方衆生」と阿弥陀さまが喚びかけられた、すべての者を等しく救いとろうと誓 われた本願の「乃至十念」の「念」が、特別の者しかなしえない、精神を統一した、「観念」の念仏のはずはありません。心の散乱する凡夫になしうる「念仏」とは、ロにお称えする「称名念仏」以外にはありえないのです。
わずかばかりの知識を持っているといっても、仏さまの智慧に比べると、何ほど の価値もありません。仏智の前では、ひとりの患者に過ぎないのがお互いです。そのような凡夫・悪人を救いの目当てとされた阿弥陀仏に対して、自らの智慧に頼り、 自らの智慧を誇ることは、むしろ背信行為であって、仏智の前では、ただ愚者であ り凡夫・悪人であるのが、私という存在です。
人間の怖さ
しかし、私たちは、ついつい善人の側に立とうとします。 ロングラン・ドラマだった「水戸黄門」では、必ずと言っていいほど、悪代官と悪徳商人が登場します。「こんな悪い奴は、早くこらしめてやれ」と、私たちの心が 叫びます。善人の側に立っているということですね。 数年前に流行った「半沢直樹」というドラマでは、銀行という組織の不条理に対 し、「やられたら、やり返す。倍返しだ」の決めぜりふで、相手を土下座させていま したが、それを痛快に喜んでいるのが私たちです。また、「忠臣蔵」での赤穂浪士の仇討ちに拍手喝采するのが私たちです。
「テレビのニュースを見ていると、毎日のように凶悪な犯罪が報道されます。そん なとき、「こんな犯人は厳罰にしろ」と裁くのが私たちです。しかし、同じような縁 に触れたら同じことをしたかも知れないという、自分自身の怖さに気付いているでしょうか。
法然聖人は、幼い頃、深夜、近くの賊に襲撃され、お父さんの漆間時国は命を落とします。瀕死の重傷を負ったお父さんは、いまわの際に、幼子であった法然聖人 に、「仇討ち」をしてはならないと諭されます。仇を討てば、今度は自らが仇討ちの 対象になり、恨みの連鎖が永遠に続くと諭されたのです。「やられたら、やり返す」 では、恨みの連鎖にしかなりません。
覚如上人が書かれたお書物に、『拾遺古徳伝」という、法然聖人の事跡を紹介され た伝記があります。極悪人として知られた耳四郎が、法然聖人のご教化に出遇う場 面の締めくくりに、
今時の道俗、たれのともがらかこれにかはるところあらんや。
「(『浄土真宗聖典全書』相伝篇上、一六五ー一六六頁)
と述べられています。こういわれると、「私は、耳四郎ほど悪人ではありません」と
弁解したくなりますが、
つくるもつくらざるも、みな罪体なり。おもふもおもはざるも、ことごとく妄 念なり。
『同』一六六頁)
と続くのです。悪いことをしたのが悪人で、しないのが善人という単純な話ではあ りません。マムシやハブのような毒蛇は、噛んだから毒蛇なのではありません。人 間の見方からすれば、噛もうが噛むまいがマムシは毒蛇なのです。そして、私たち も縁に触れたら何をするかわからない同じものを持っているということです。
また、こんなこともあるでしょう。近所の人との会話のなかで、「私は、つまらな い人間で」と言ったときに、「やっぱり、そうでしたか」と言われると、腹が立ちま す。「うちの子は、私に似て出来が悪くて」と言ったときに、「そりゃ、そうでしょう ね」と言われたら、「この人とは、二度と口をきかない」という気になります。口で は「あさましい」「罪深い」と言っていても、結局は、善人や智者の側に身を置いているのです。
機の深信・法の深信
法然聖人は、また、
浄土宗の人は悪者になりて往生す(『親鸞聖人御消息』、『註釈版聖典』七七一頁)
とも述べられています。私たちは、この「愚者になる」ということがむずかしいの かも知れません。すぐに善人になりたがる習性があるからです。
しかし私は、そんなにむずかしいことでもないように思います。それは、つねに 仏さまとお話をすればよいと思うからです。仏さまの智慧の前では、私は、愚者以 外の何ものでもないからです。仏さまの智慧に出遇ったとき、患者という私の本当 のすがたが知らされます。浄土真宗では、それを「機の深信」と称しています。
決定して深く、自身は現にこれ罪悪生死の凡夫、臓却よりこのかたつねに没しつねに流転して、出離の縁あることなしと信ず。
(『観経疏』「散善義」、『註釈版聖典(七祖篇)』四五七頁)
と示されます。いつから迷い始めたのかわからないほど、長い長い間、迷い続けて
きたのが私たちです。そこには、自分に誇る思いは微塵もありえません。しかし同
時に、
決定して深く、 の阿弥陀仏の、四十八願は衆生を摂受したまふこと、疑な おもんぱか」 く慮りなくかの願力に乗じてさだめて往生を得と信ず。
(『同』)
という「法の深信」、ご本願によって救われていくよろこびに支えられた身でもあるのです。
「われらは善人にもあらず、賢人にもあらず」(『註釈版聖典』七一五頁)
この「愚者」 の自覚こそは、「機の深信」という厳格な自己内省です。そして、それは、「法の深信」というよろこびに支えられた歩みでもあるのです。これこそは、仏さまの智慧
に出遇った者が恵まれる、尊い生き方です。
(満井 秀城)