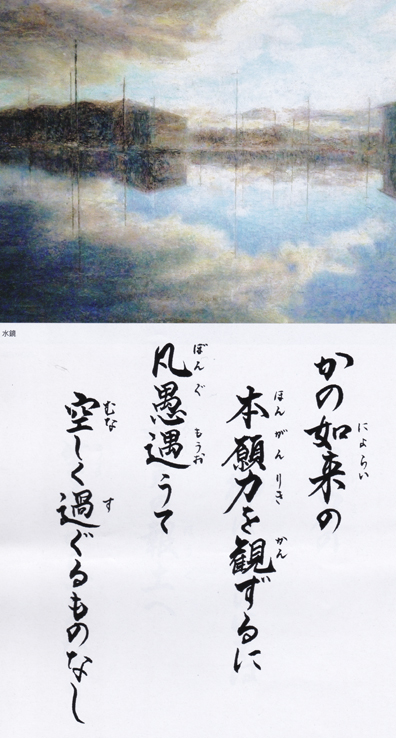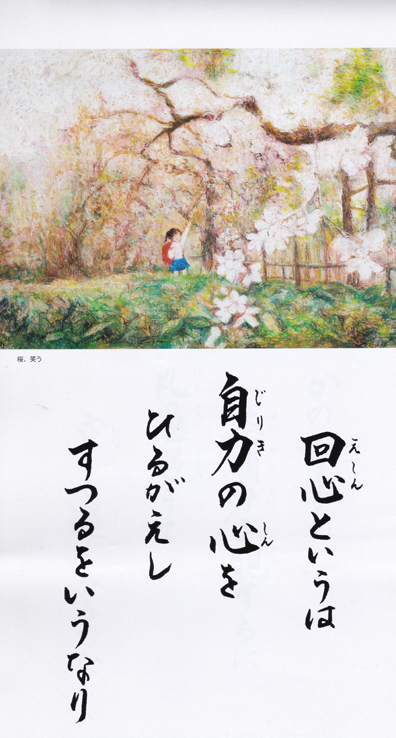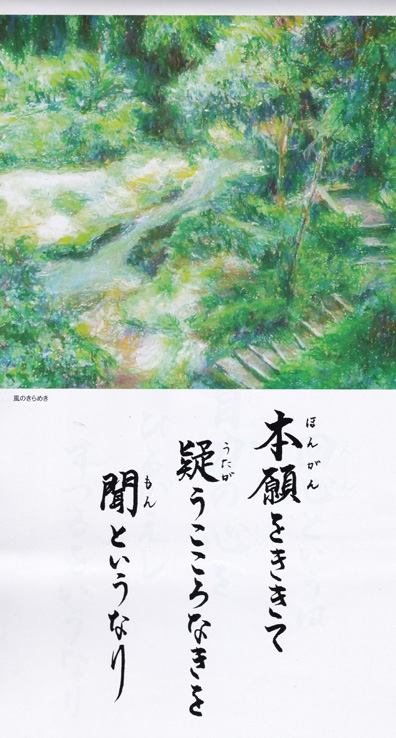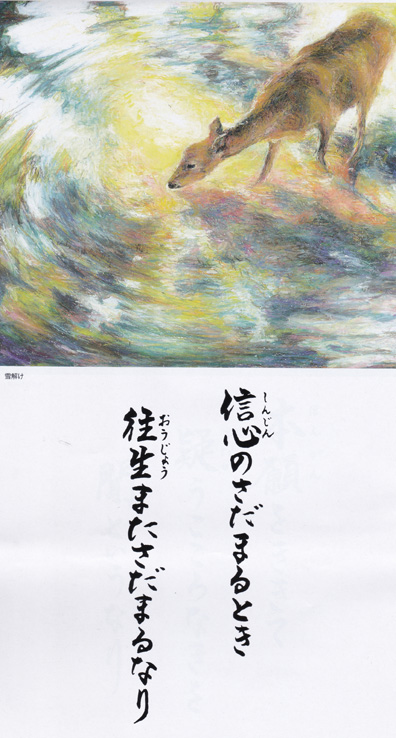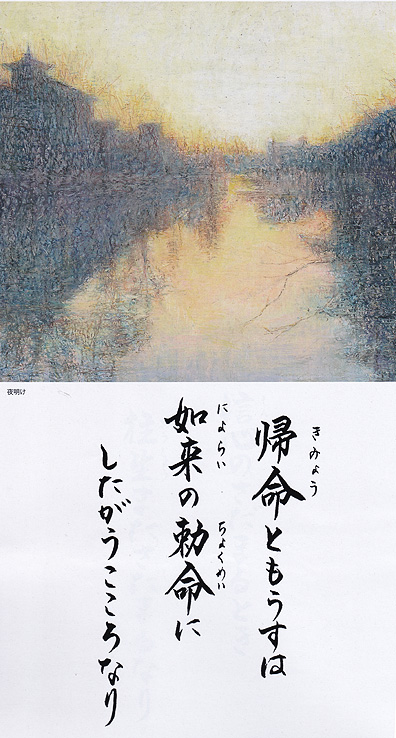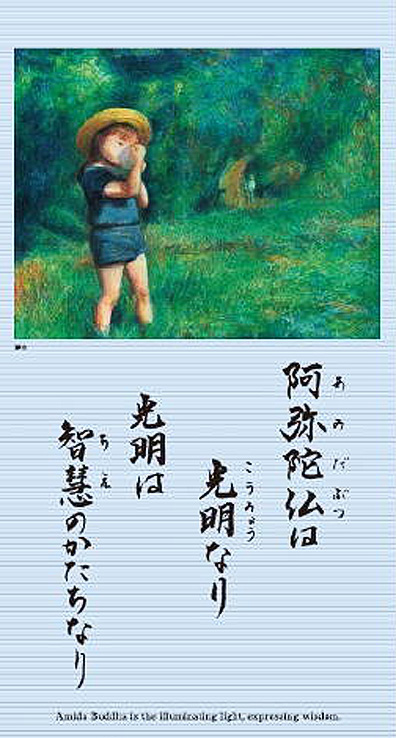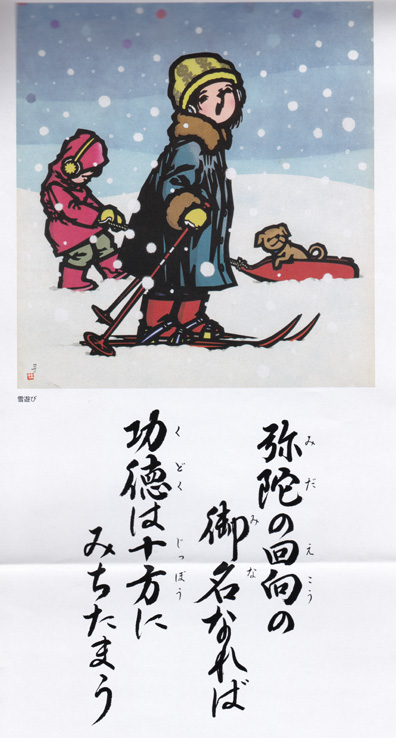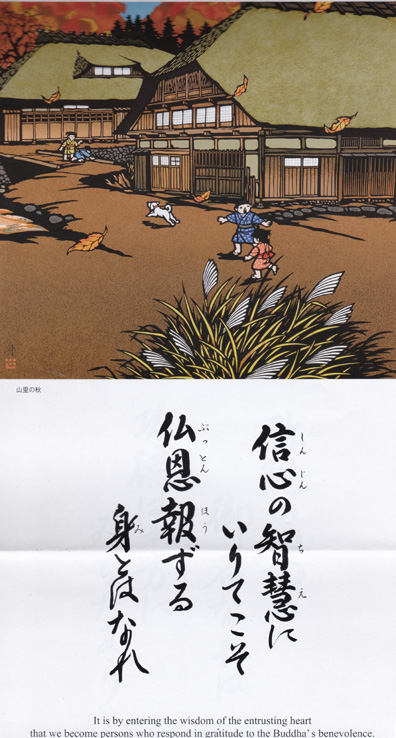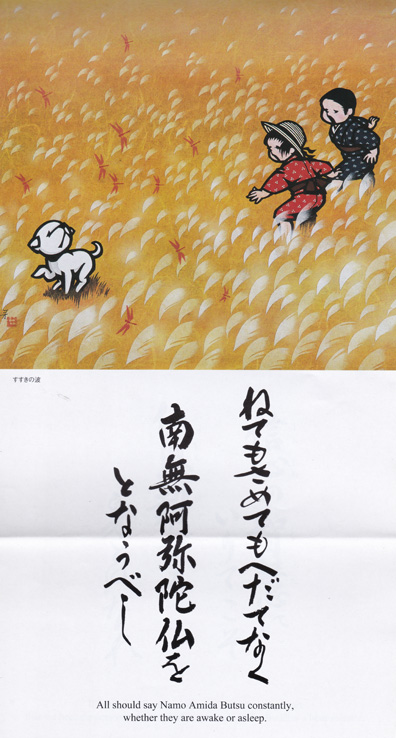浄土真宗を理解するために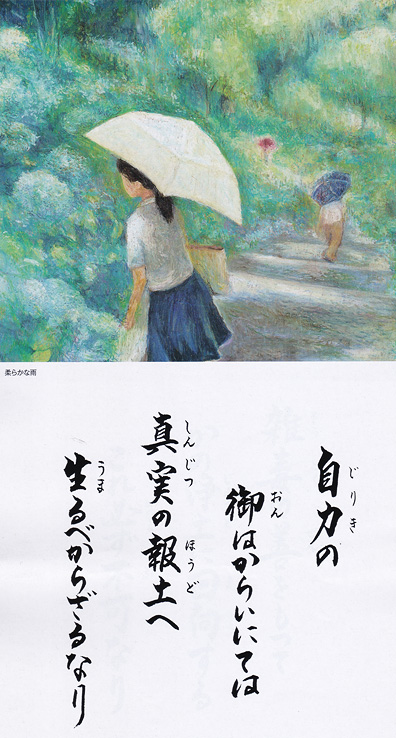 今月は、親鸞聖人が関東の門弟に宛てて書かれたお手紙(御消息)の中にある言 葉です。 このお手紙には、「笠間(かさま)の念仏者(ねんぶつしゃ)の疑(うたが)ひとはれたる(疑い聞かれたる)事(こと)」(『註釈版聖典』七四六頁)という題がつけられています。おそらくこのお手紙の最初に書かれている「自力・他力」ということは、親鸞聖人から念仏の教えを聞いてきた関東の門弟たちにとって、もっとも重要な疑問の一つだったからでしょう。ですから、親鸞聖人もこのお手紙の中で、門弟たちの疑問に答えるかたちで、「自力・他力」ということについて、詳しくていねいに解説されているのです。 さて、親鸞聖人はこのお手紙の最初に、
今月は、親鸞聖人が関東の門弟に宛てて書かれたお手紙(御消息)の中にある言 葉です。 このお手紙には、「笠間(かさま)の念仏者(ねんぶつしゃ)の疑(うたが)ひとはれたる(疑い聞かれたる)事(こと)」(『註釈版聖典』七四六頁)という題がつけられています。おそらくこのお手紙の最初に書かれている「自力・他力」ということは、親鸞聖人から念仏の教えを聞いてきた関東の門弟たちにとって、もっとも重要な疑問の一つだったからでしょう。ですから、親鸞聖人もこのお手紙の中で、門弟たちの疑問に答えるかたちで、「自力・他力」ということについて、詳しくていねいに解説されているのです。 さて、親鸞聖人はこのお手紙の最初に、
それ浄土真宗のこころは、往生(おうじょう)の根機(こんき)に他力あり、自力あり。このことすでに天竺(印度)の論家(ろんげ)、浄土の祖師の仰せられたることなり。(『親鸞聖人御消息』、『註釈版聖典』七四六頁)
と書いておられます。これによって、「自力・他力」ということは、すでに龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ)や天親菩薩などインドの祖師方の時代にも、さらには時がくだり、曇鸞大師、道棹禅師、善導大師といった中国の浄土教の祖師方の時代も、つねに問題にされてきたことである、ということがわかります。実は、浄土真宗の教えを理解できるかどうかは、「自力・他力」ということを正しく理解できるかどうかにかかっている、といってもいいほどの大切な問題なのです。そこで、今回は親鸞聖人のお手紙の言葉に耳を傾けながら、今月のことばについて味わってみたいと思います。 自力の否定 まず、親鸞聖人はこのお手紙の中で、「自力」ということについて、
自力と申すことは、行者のおのおのの縁にしたがひて、余の仏号(ぶつごう)を称念(しょうねん)し、余の善根を修行して、わが身をたのみ、わがはからひのこころをもって身口意(しんくい)んkみだれごころをつくろひ、めでたうしなして浄土へ往生せんとおもふを自力と申すなり。(『註釈版聖典』七四六頁)
と書いておられます。 すなわち「自力」とは、行者ひとりひとりが出会った教えにしたがって、いろいろな仏さまの名を称えたり、さますまな善行を積み重ね、それらの修行に励んだという自分自身を頼りとし、また自分の善悪の判断にもとづいて、つねに身のふるまいを正し二百葉遣いに気をつけ、ヽ心が乱れたらそれを取り繕い、立派にするように心がける。そうして、このような生き方をしている自分であれぼさっと往生できるだろうと期待すること、これを「自力」というのです、といわれています。 このように、「悪をつつしみ善をなしていく」という行為と、それによって自分の身を立派に調えていくということは、仏教の原則からいっても、社会通念上から考えても、実にまっとうな生き方であるといえるでしょう。 ところが親鸞聖人は、この後に
自力の御はからひにては真実の報土へ生るべがらざるなり。 (『同』七四七頁)
と、自力による往生を否定されているのです。いったい、それはどういうわけなのでしょうか。 阿弥陀さまの本意 その疑問について考える前に、親鸞聖人が「自力」に続いて、「他力」ということについて解説されていますので、もう少し聖人のお手紙を読み進めていきましょう。 親鸞聖人は「他力」ということについて、
また他力と申すことは、弥陀如来の御(おん)ちかひのなかに、選択摂取(せんしゃくせっしゅ)したまへる第十八の念仏往生の本願を信楽するを他力と申すなり。如来の御ちかひなれば、「他力には義なきを義とす」と、聖人(汪然)の仰せごとにてありき。義といふことは、はからふことばなり。行者のはからひは自力なれば、義といふなり。他力は、本願を信楽(しんぎょう)して往生必定(おうじょうひつじょう)なるゆえに、さらに義なしとなり。(『註釈版聖典』七四六頁)
と書いておられます。すなわち親鸞聖人は、阿弥陀さまの(四十八の)お誓いの中で、「あらゆる行を選び捨て、ただ念仏一行を選び取って往生決定の行とする」と誓われた第十八願(念仏往生の願)を、疑いなく聞き入れて喜ぶことを「他力」という、といわれています。 さあ、どうでしょうか。一般的には、念仏}行を修するよりも、さますまな行を積むことの方がすぐれており、そのようなすぐれた行を行ずる者をこそ、仏さまは救ってくださるのだ、と考えるのが普通でありましょう。実際、阿弥陀さまのお誓いの中、第十九願には諸行往生が誓われており、これこそが阿弥陀さまの本意であると考えた人もおられたのです。 それに対して、親鸞聖人が浄土真宗の七高僧と仰がれた方々は、念仏往生を誓われた第十八願こそ阿弥陀さまの本意の願である、とご覧になりました。もともと阿弥陀さまの四十八願は、すべて「因位(菩薩の位)の誓願」という意味で「本願」ではありますが、第十八願こそが四十八願の要であり、根本の願であるとご覧になりました。特に、法然聖人は「四十八願の中の根本の願」という意味で、第十八願のことを「本願」とよばれ、この願は、あらゆる行を選び捨て、ただ念仏一行を選び取って往生決定の行とされているというので、第十八願を「選択本願」と名づけられました。そして、親鸞聖人も法然聖人のお心を受けついでおられるのです。 それではなぜ、浄土真宗の祖師方は、第十八願こそが阿弥陀さまの本意の願であると考えられたのでしょうか。また、そもそも阿弥陀さまは、なぜ第十八願において、諸行を捨てて念仏一行をもって往生の行とされたのでしょうか。 その理由について、法然聖人は『選択本願念仏集』という書物の中で、第十八願にこそ、阿弥陀さまの「すべての人びとを救いたい」という「平等の慈悲」があらわれているからである、ということを明らかにされました。それは、第十八願に誓われた念仏行は、救いの条件として提示されたものではなく、すべての人びとを平等に救いたいという慈悲の心があらわれたものであると、法然聖人は見抜かれたということなのです。 阿弥陀さまは、平等の慈悲の心をもって、「どうしたらすべての人びとをもらさず救いとることができるか」ということを深く深く考えぬかれ、戒律や禅定、造像、起塔などは、限られた人しか救われない難しい行であるから選び捨てられ、もっとも行じゃすくたもちゃすい称名念仏一行こそが、すべての人びとを救いとることのできる方法であるとして、これを「選び取る」という本願をおこされたのである、といわれるのです。こうして法然聖人は、この第十八願は「すべての人びとを救おう」と誓われた阿弥陀さまの大悲のお心があらわれた誓願であるから、阿弥陀さまの救いについて、私たちがあれこれとはからうことではない、とあっしゃったのです。 他力とは阿弥陀さまの救済力 ここまで読み進めてくると、親鸞聖人のおっしゃる「自力・他力」ということが、おぼろげながらも見えくるのではないでしょうか。 親鸞聖人のおっしゃる「自力・他力」とは、一般に考えられているように、「自の力・他の力」という意味ではなかったのです。『教行信証』「行文類」に、
他力といふは如来の本願力なり。(『註釈版聖典』 一九〇頁)
といわれているように、「すべての人びとを救おうと願い立たれ、今その願いのとおりに、すべての人びとを救いつつある阿弥陀さまの救済力」のことを、「他力」といわれているのです。それに対して、自分のはからいをもって往生を願うことを「自力」といわれていました。 こうして、「自力・他力」ということを詳しく述べられた上で、
しかれば、わが身のわるければ、いかでか如来迎へたまはんとおもふべからず。凡夫(ぼんぶ)はもとより煩悩具足(ぼんのうぐそく)したるゆゑに、わるきものとおもふべし。またわがこころよければ、往生すべしとおもふべからず。自力の御はからひにては真実の報土へ生るべがらざるなり。「行者のおのおのの自力の信にては、塀慢・辺地の往生、胎生疑城の浄土までぞ往生せらるることにてあるべき」とぞ、うけたまはりたりし。 (『親鸞聖人御消息』、『註釈版聖典』七四七頁)
と結んでおられます。まことにもったいないことですが、阿弥陀さまのお浄土は、私が願って往く世界ではなく、阿弥陀さまに願われ招かれて往く世界だったのです。
親鸞聖人が『高僧和讃』「善導讃」に、
願力成就の報土には
自力の心行いたらねば
大小聖人みなながら
如来の弘誓に乗ずなり 『註釈版聖典』五九一百)
といわれていることを、よくよく味わいたいものです。
(藤潭信照)