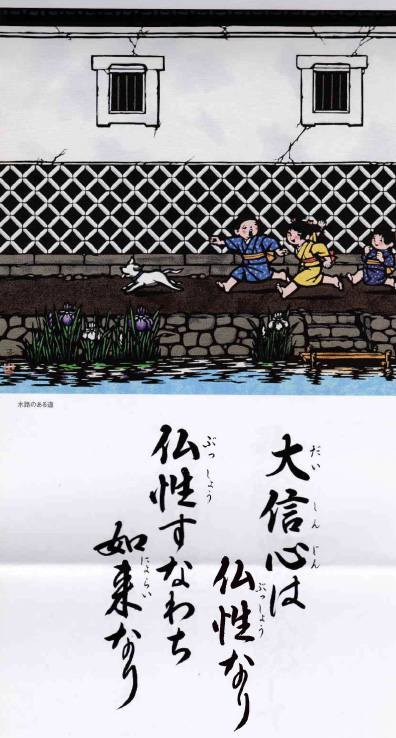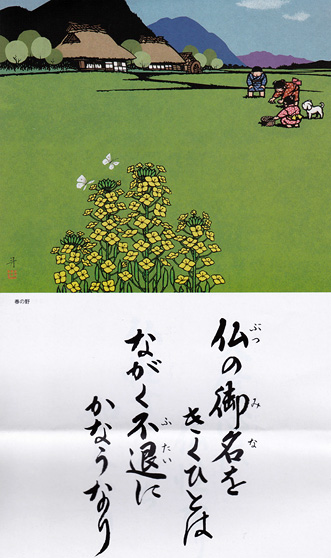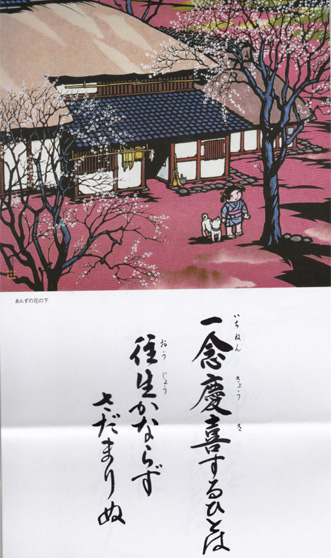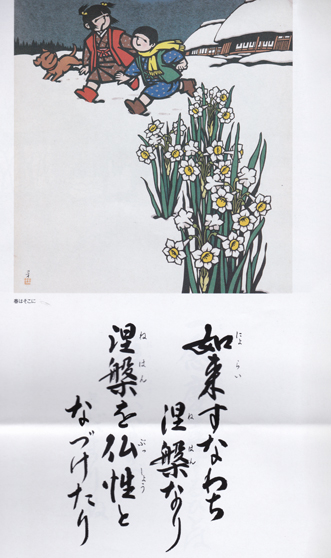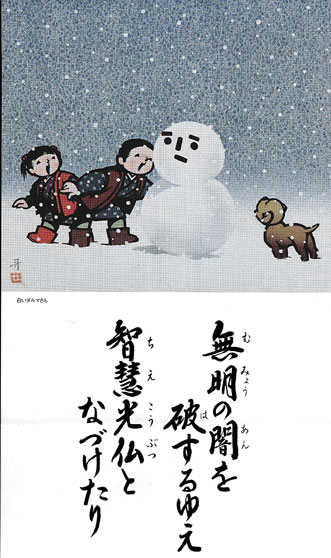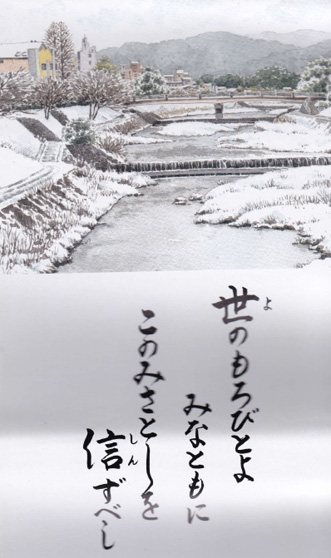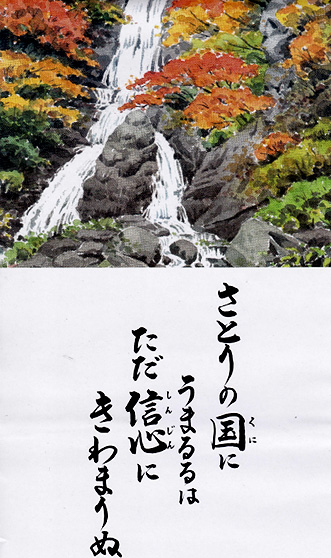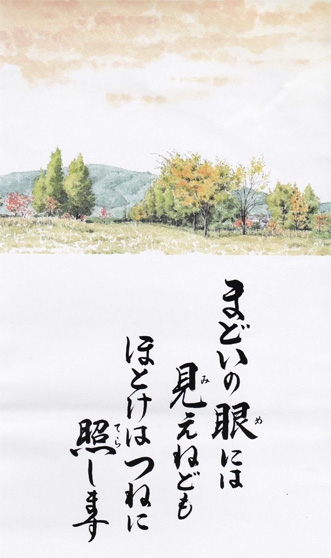浄土真宗では、朝夕にお仏壇の前に座って手を合わせ、ご法座やご法事の機会にお聴聞をするということが伝えられてきました。
ところが最近は、仏事をしたり、お寺へお参りしましょうということを、皆さん、特に若い世代の方々にお勧めすることが、難しくなってきました。
ご法事をお勤めすることの意味について考える時、このように思う方はいらっしゃらないでしょうか。
「死んだ人が化けて出てこないように、お経を読んでもらっておく」
このような思いでご法事に参加するのでは、非常に残念な気がします。なぜなら、この言い方には二つの失礼なところがあるからです。
まず一つは、亡くなった方に失礼なのではないでしょうか。故人となった方は人生の先輩であります。年齢が上ばりとは限りません。同世代や年下の場合もあります。これまで私たちが見送ってきた先人は、この娑婆世界を精一杯生き抜き、私たちよりも一足先にお浄土へ生まれていかれました。生前さまざまなことを教えてくださった先輩が、この娑婆世界で最後に見せて教えてくださったのが、いのちある者が死にゆく姿です。儚くももろい、だからこそかけがえのないいのちを生き抜いたお姿です。その先輩に対して、「出てくるな」ではずいぷんと失礼なのではないでしょうか。
そしてもう一つは、亡くなった方と縁のあった方に失礼なのではないかと思うのです。故人とのお付き合いの度合いは人それぞれです。挨拶を交わす程度の人もいたでしょう。ですが、その方と常に寄り添い、ともに生きた人もいます。その方の死をいまだに受け容れられず、もう一度会いたい、顔を見たい、声だけでも聞かせてほしい、どのような形でもよいからもう一度姿を見せてくれないかと、いくら涙を流しても忘れられない人もいるかもしれません。そのような遺族に対して、失礼な言い方になってしまうのではないでしょうか。
死が他人事であると、私たちは平気で人を傷つけるようなことを言ってしまうのかもしれません。
「浄土真宗」という言葉は、往生浄土、つまりこの私がお浄土に往き生まれていくことを問題としています。
葬儀の折りの挨拶などで、「故人が生前、たいへんお世話になりました」という言葉を聞くことがあります。これは存命中のこと、つまり亡くなる前のことを言っていますので、本来ならば「死前(死の前)」(そんな言葉はありませんが)というべきでしょうか。この生前という言葉は、亡くなった後に生まれていく世界があることを前提としています。最近は、天国やあの世という言い方のほうが思い浮かべやすいのでしょうか。お浄土ということが意識されないまま、それでも次に生まれていく世界について言及しているのです。
往生浄土とは、この私のいのちの行く末を問題としています。他人事ではありません。そのことを私に教えてくれる真実、(真)の教え(宗)を、親鸞聖人は浄土真宗といわれたのです。
浄土真宗という道
今月のことばは、親鸞聖人の『高僧和讃』の中、曇鸞大師のお示しについて述べられた一首です。浄土往生について、それが阿弥陀さまのはたらきである他力によって私たちに恵まれているのだということを、曇鸞大師の『往生論註』などのお言葉を通してお示しくださっています。
私たちは阿弥陀さまのはたらきによって、浄土に往生して仏さまになることができるのです。そして、迷いの世界に還って縁のある方々を救う活動をします。この往相(浄土に往く様子)と還相(浄土から還ってくる様子)とを、ともに阿弥陀さまから恵まれるのです。
阿弥陀さまからたまわることを本願力回向といいます。回向とは、回はめぐらす、向はさしむけることで、自分のおさめた善行の功徳を他にふりむけることをいいます。
身近なところで何か欲しいものがあるとします。たとえば新しい車が発売され、それを欲しいと思った時、ただ欲しいだけでは手に入りません。使うお金を節約し、一生懸命働いて得たお金を蓄えて、欲しいものと同じ価値(値段)にまで貯めることができたら、それをお店に持って行って車を得るためにふりむける、役立たせることで欲しいものが手に入ります。
他のご宗旨で厳しい修行をしたり、滝に打たれるなどの荒行をするのも、何も体を鍛えたり、水に強くなることが目的ではないでしょう。行によって身心に得られた鍛錬を、さとりを開くためにふりむけ役立たせる。それを自力回向といいます。
浄土真宗では、阿弥陀さまが本願力をもって、その功徳を私にふりむけることを回向といいます。阿弥陀さまが本願のはたらきとして、南無阿弥陀仏にその功徳のすべてを込めて私たち衆生にふりむけてくださっているのです。それを他力回向、本願力回向といいます。
町で回転寿司のお店をよく見かけます。私は、ここにいつも感慨深い思いをもつのです。ご存じの通り、回転寿司は職人さんが私たちのためにつくってくれたお寿司が店内を回転します。グルーッと
めぐって私たちの席にまでさしむけられますので、私たちはお寿司を取りに行く必要も、また難しい技術を身につけてお寿司を握る必要もありません。ただ私たちのもとに届けられたお寿司を受け取って、口に運ぶだけです。おいしいお寿司を味わいながら浄土真宗の他力回向に思いをめぐらしていると、回転寿司の看板ですら、「えてんずし」と読みたくなってしまいます。
還相のはたらきの中に
私たちが死の痛みを感じる、その大きな機会の一つに、大切な方を見送るということがあります。私たちはこれまで、たくさんの方々を見送ってきました。それは一つ一つの傷となって、私たちの心に刻み込まれています。
その痛みを通して、私たちはいのちを見つめることになるといえるでしょう。
ある研修会で、ご一緒した四十代の女性に教えられたことがあります。
仏教にふれる入門的な学びの機会でした。私か言葉の説明をしたり、味わいを申しあげたりするたびに、真剣に受講しておられるその女性の表情からは、何かつらいご経験をなさったであろうことが伝わってきました。
会が終わり、他の受講生の方が帰られた後、小さな声で聞いてこられました。
「亡くなった人は、お浄土でどのように過ごしているのでしょうか?」
お浄土では仏さまになって、穏やかに人々を導く活動をなさっていることが、お経に示されています。仏さまのはたらきをお手伝いしてくださっているということですから、現に私たちの周りにも、それを感じることができるのかもしれませんね。そのようなことをご一緒に味わわせていただきました。
その女性は、二年前、十五歳のお嬢さまを病気で亡くされたとのことでした。静かに、そして強く、お嬢さまのことを今も思い続けていらっしゃる様子に、見えなくとも感じることのできる世界があることを教えられました。
「死んだらおしまい」という言い方をよく聞きます。
今あるいのちの大切さを重く受けとめる必要はもちろんあります。生きていてこそ、健康であってこそ、思い通りに活動できてこそ、というのは誰もが求める大切なことです。
生きることの意義は、軽んじられるべきではありません。ですが、だからといって、死んだらおしまいなのでしょうか。本人にとっては死んだらどうにもできない、生きているうちにしておかなければならないことがたくさんある、というのはわかります。
でも、周りの方にとっては死で終わりではないのです。その人の死とかかわって生きていかなければなりません。他者の死によって心に傷をうけ、他者の死の後もそのいのちを思い続けるのです。
浄土とは、死を通していのちをみつめ、そこに向かって歩む生き方を考えることを教えてくれるのです。
仏に導かれていた私
四月の法語の中で申しあげた実父の十三回忌の法事で、施主であり父の後を継いで住職となっていた兄が、次のような挨拶をしました。
「日々の生活では父のことを思い出すことが少なくなりました。ほとんど思い出すことはないと言っていいくらいです」
弟の私は、そこまで言わなくてもいいのではないかと思いながら聞いていました。長男というのは父親とぶつかり合うものだと改めて感じながら、続きを聞きました。
「父のことを考えようとしない私や、それぞれの生活をそれぞれの場で過ごしている親戚、ご門徒のみなさまが、父の法事という機会に仏さまの前に座って、一同に手を合わす時間を過ごさせていただきました。仏さまとなった父に導かれて、自身のいのちの行く末を見つめる場に座っていました。念仏とともに今のいのちを精一杯生き抜き、お浄土へ生まれて来てくれよと、父が願っていてくれたのではないか、そのような仏さまの願いにふれさせていただく十三回忌の法事となりました」
死んだ人のために法事を勤めているのではなく、亡くなった方から導かれて、仏さまのはたらきによって願われて、手を合わす私になっていたのだということに気付かされました。
これまで、私たちはいろいろな思いをもちながら身近な方を見送ってきました。
何とかならないのか、何かしてやれることはないのか。この思いは見送った後も続きます。あれでよかったのだろうか、こんなこともしてあげたかった、など。
今度は、私たちが見送られる側になっていきます。その時、遺していかねばならない愛する者たちに、いろいろな思いをもつのでしょう。
ということは、これまで見送ってきた方々も、遺る私たちにいろいろな思いを持ちながら、お浄土へと生まれていかれたことに気付きます。仏さまとなった先人の願いに導かれて、阿弥陀さまのはたらきによって私もお浄土へ参る身であることをしっかりと受けとめさせていただき、歩んでまいりたいと思います。
(佐々木隆晃)