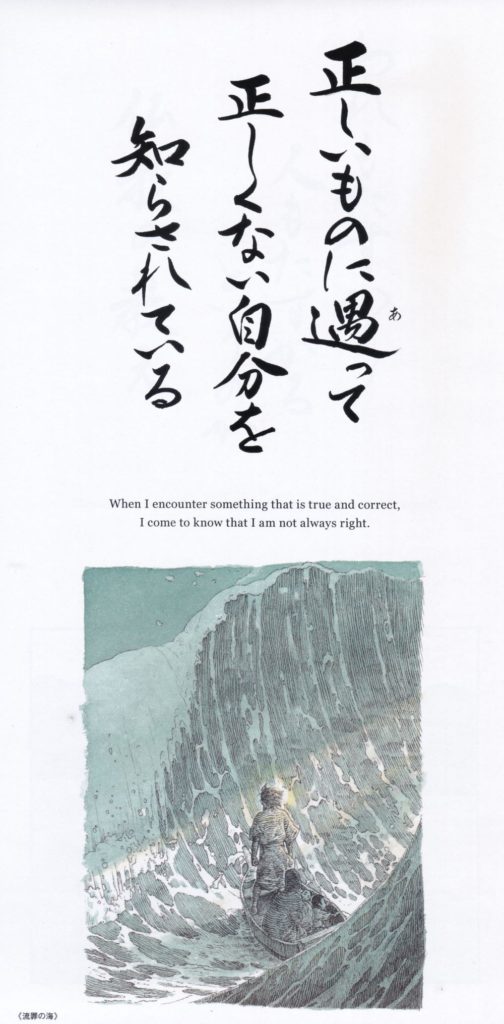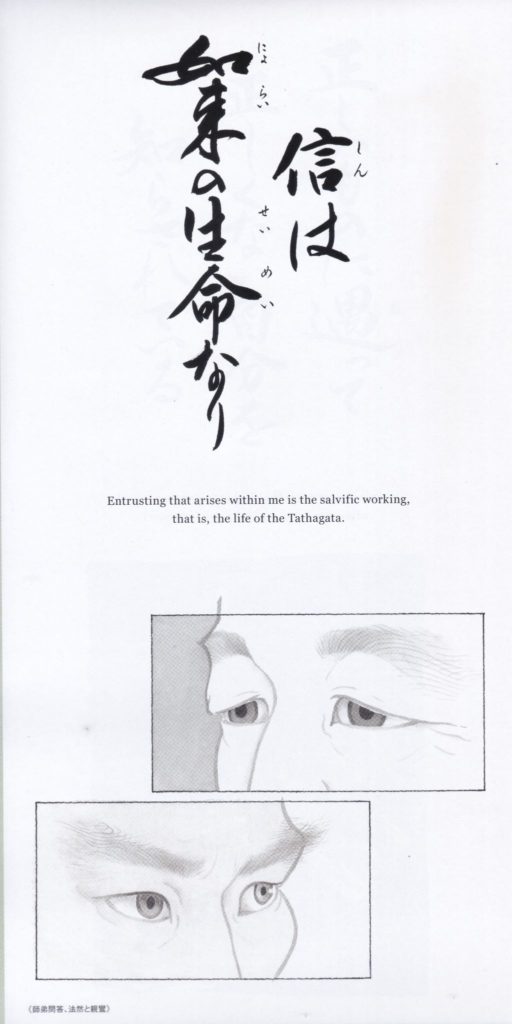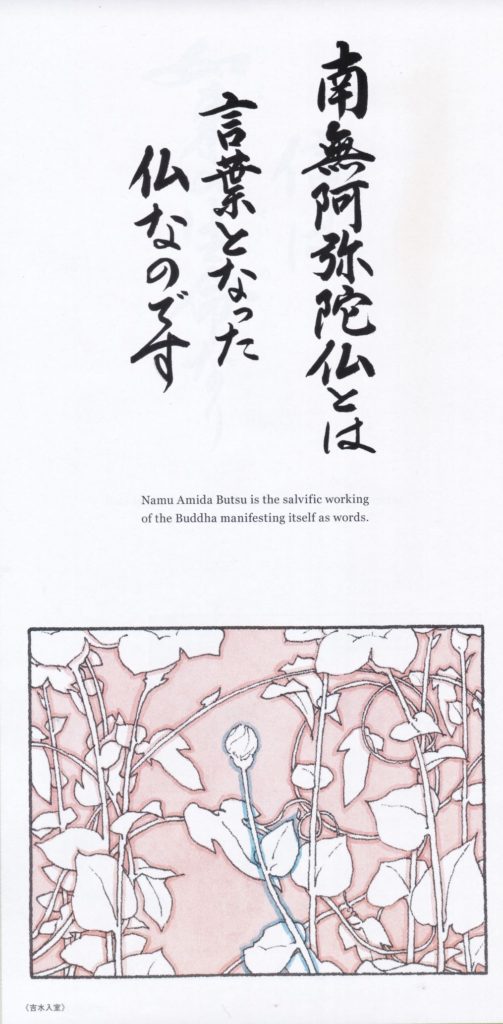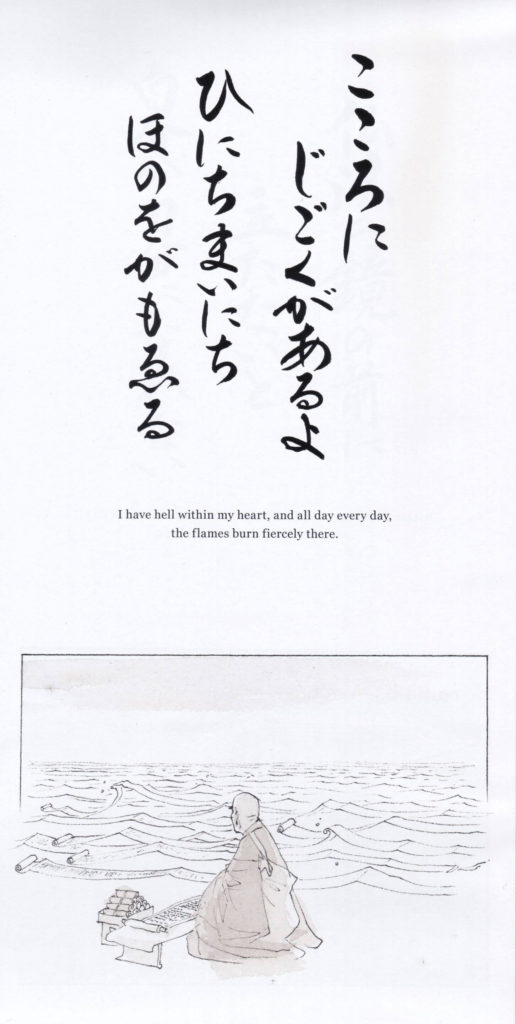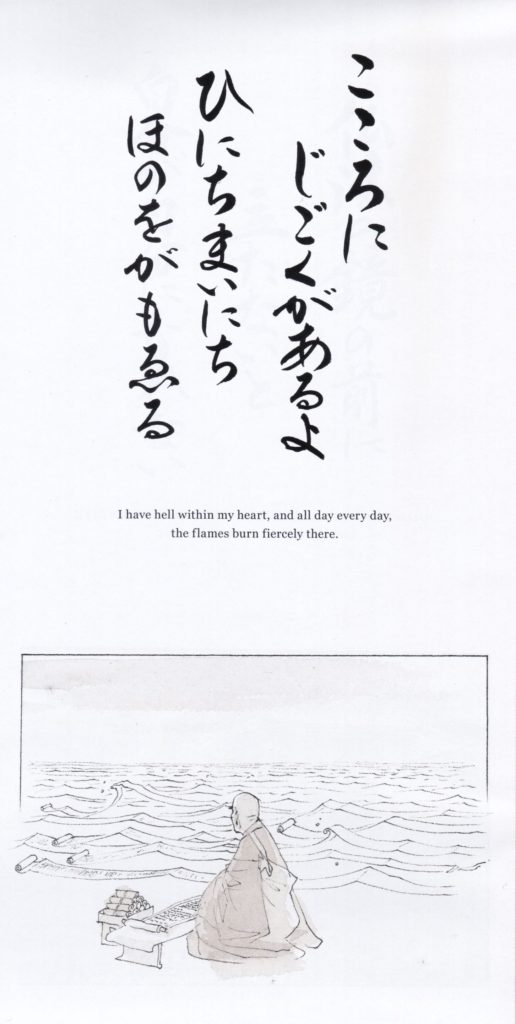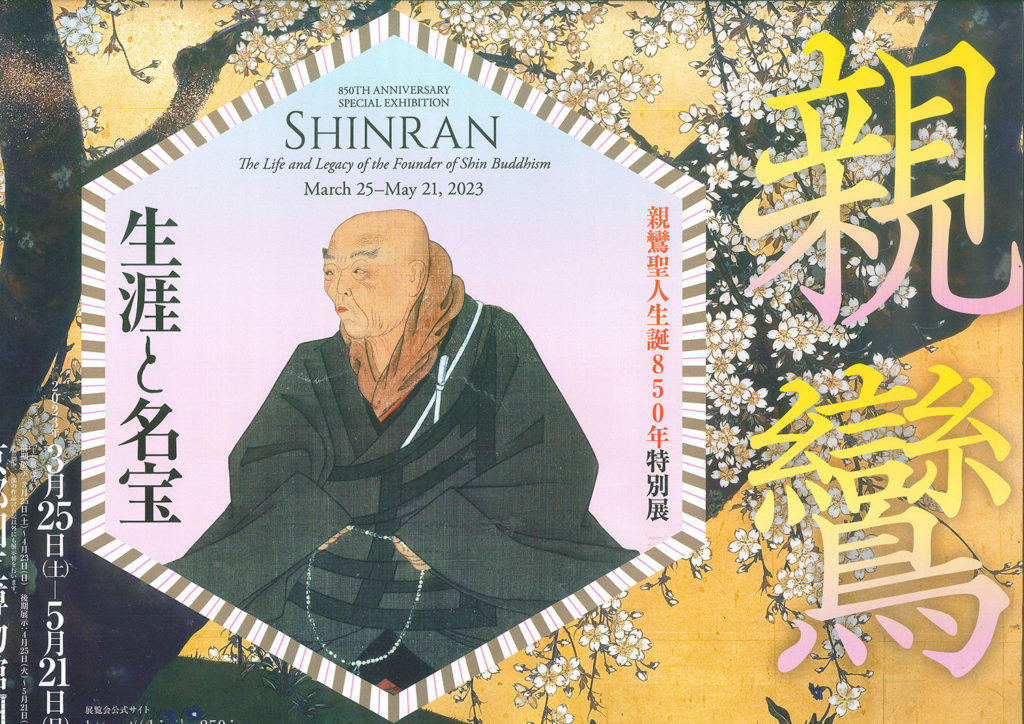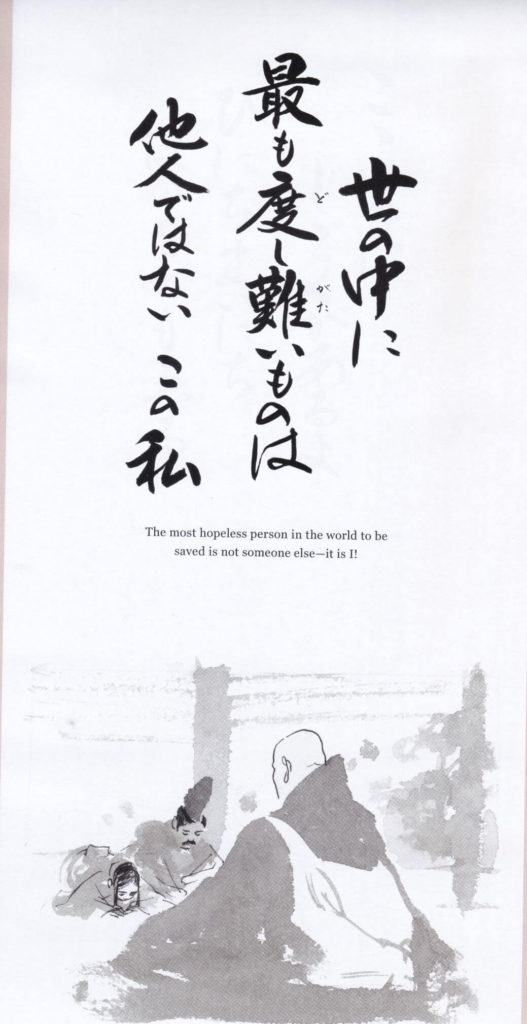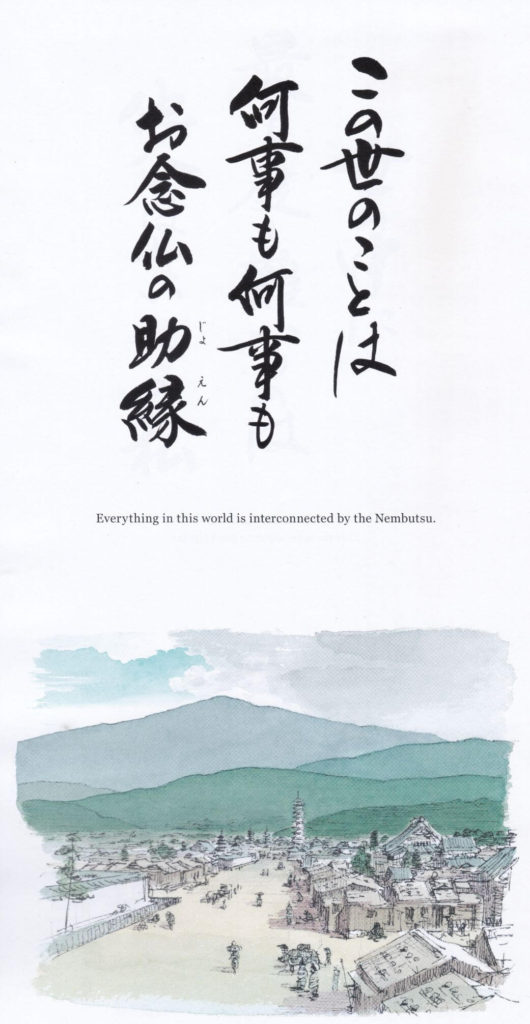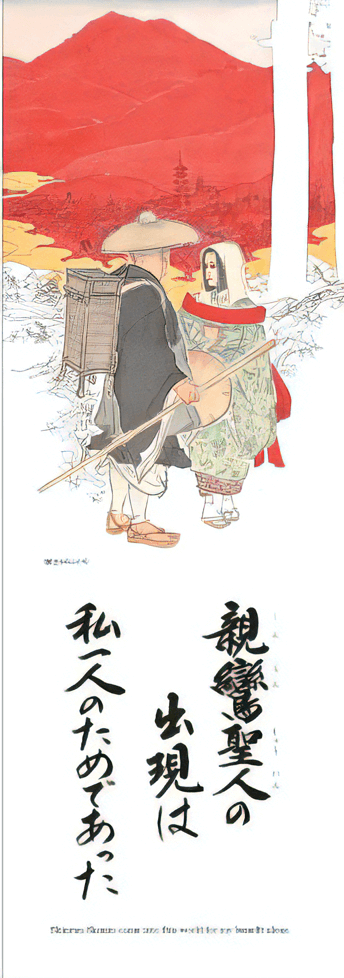阿弥陀さま中心の生活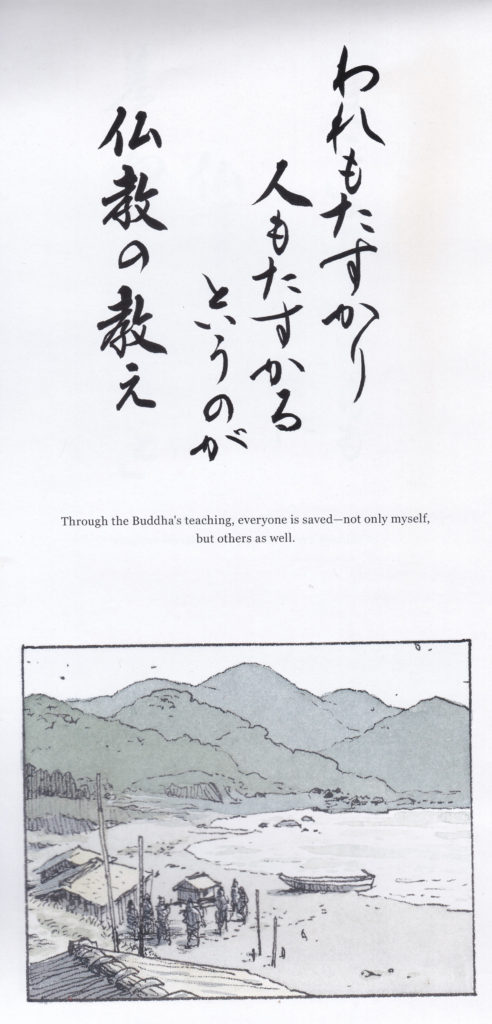
八月のことばは、曽我量深先生(一八七五ーー九七一)のお言葉です。曽我先生は明治から昭和にかけて大谷大学教授、また学長として活躍され、たいへん多くの著作ものこされました。そして、先生はするどい感性と独自の表現をもって真宗教義を解釈され、その思索に満ちた言葉の数々は、今なお多くの人びとを惹きつけています。今月のことばである「われもたすかり、人もたすかるというのが仏教の教え」とは、私たち凡夫は自らの力で往生の種を作ることはできず、あらゆるものの救済を誓われた阿弥陀さまのご本願により、われも人も救われていくということを述べられたお言葉です。
阿弥陀さまは、煩悩にまみれた凡夫であるこの私をなんとしても救いたいと、立ち上がってくださいました。そして、「必ず救う。まかせてくれよ」と、南無阿弥陀仏のお念仏となって喚び続けてくださっています。曽我先生はご著書のなかで、私たちは阿弥陀さまに願われたいのちを生きている」ということを強調しておられます。「願われたいのちを生きる」ということは、阿弥陀さまのご本願を聞き、阿弥陀さまを中心とした生活をさせていただくということにほかなりません。
先日、お参りにいったあるお宅のご門徒さんが、「夫が亡くなり、子どもたちも都会に出ていますから、私は一人で暮らしています。その上、新型コロナウイルスで老人会もないので、最近は人と話をする機会が減って寂しく過ごしていました。
しかし、先日の朝、いつものようにお仏壇の阿弥陀さまにお仏飯をお供えしてお念仏していたら、「そうだ、阿弥陀さまとお話しさせていただこう」と思い立ち、そのままお仏壇で阿弥陀さまにいろいろと話を聞いていただきました。今では毎朝、阿弥陀さまに自分のさまざまな思いを聞いていただいています。そして、夕方、病院や畑仕事から家に帰ると、お仏壇の前に座って阿弥陀さまに一日のご報告をさせていただくのです。愚痴や人にはなかなか言えないことも、阿弥陀さまに聞いていただきます。日々の喜びも悲しみも、私のすべてを受けとめてくださる方がいるということは、なによりもありがたいことですね」とおっしゃいました。そのお話を聞き、この方はまさに阿弥陀さまを中心とした生活をしておられるのだなと感じました。
ともに喜びともに悲しむお慈悲の声
さて、私には二人の娘がいます。長女は以前、本願寺のすぐ隣にある幼稚園に通っており、幼稚園バスの見送りや迎えはいつも妻がしてくれていました。娘は帰りのバスから降りてくると、今日は幼稚園であれをしてこれをして、こんなことがあって嬉しくて、でも〇〇ちゃんとおもちゃの取り合いをしてしまって、というように、いつもその日の報告をしてくれるのだと、当時、妻が教えてくれました。そして、ちょうどその頃、妻が二人目の子どもを妊娠し、だんだんとつわりがひどくなっていきました。そこで、私が大学から早く帰ることのできた日に、妻の代わりに娘の幼稚園バスの迎えに出ました。私は娘が幼稚園での出来事を私にたくさん報告してくれるだろうと思い、とても楽しみにしてバスを待ちました。
いよいよバスが娘を乗せてマンションの前に到着し、私は「おかえり」と言いながら娘を出迎えたのですが、バスから降りてきた娘の第一声は今日の出来事の報告ではなく、「お母さんはどうしたの」でした。「お母さんはちょっとお腹がしんどくて、お家にいるよ」と言うと、娘はマンションに向かって駆け出しました。私も急いで娘の後を追いかけてマンションに入り、一緒にエレベーターに乗り込みました。
部屋は八階ですから、到着するまでに十数秒はかかります。その間にエレベーターのなかで、「今日は幼稚園で何をしたの」と何度も尋ねたのですが、娘の耳に私の声は届いていない様子でした。エレベーターが八階に到着すると、娘は部屋のなかに駆け込み、奥で横になっていたお母さんを見つけるやいなや、「あのね、今日は幼稚園で鬼ごっこしてね、〇〇ちゃんが鬼だったよ。給食はからあげが出てね、ふりかけも付いててね・・・・・」と、堰を切ったように今日一日の報告を始めました。私はあっけに取られてその様子を眺めていました。
その数日後、妻のつわりが引き続きひどいため、再び私が幼稚園バスの迎えに出る機会がありました。私は今度こそ娘から一日の報告を聞きたいと思ったのですが、前回同様、娘はお母さんのいるマンションに向かって駆け出し、エレベーターのなかでも私の問いかけには応えず、マンションの部屋に入るとすぐにお母さんに向かって、「あのね、今日はカスタネットでたくさん遊んで、すごく楽しくね・・・・・・」と、また一日の報告をしていました。娘が私には報告をしてくれなかったことはちょっと寂しかったのですが、娘のすがたを見ていると、毎日の嬉しいことも悲しいことも何でも報告できる相手がいるということはとてもありがたいことだなと感じました。先ほど紹介させていただいたご門徒さんの、「日々の喜びも悲しみも、私のすべてを受けとめてくださる方がいるということは、なによりもありがたいことですね」というお言葉を、娘のすがたとかさねながらあらためて味わわせていただきました。
日々の暮らしのなかでなにか嬉しいことがあったとき、お仏壇で阿弥陀さまにご報告すれば、「私も一緒に喜んでいますよ」と阿弥陀さまも一緒に喜んでくださいます。「こんな辛いことがあったのに、この悲しみを誰もわかってくれません」とご相談すれば、「私はあなたの悲しみをわかっておりますよ」と一緒に泣いてくださいます。そしてもちろん、お仏壇の前にいるときだけではなく、いつでもどこでも、南無阿弥陀仏というお念仏を通して阿弥陀さまからの「いつでも一緒ですよ」というお慈悲の声が、この私に届き続けてくださっています。
願われたいのちを生きる
さて、数年前にお参りにいったあるご門徒さんのお宅での話です。そちらのお宅には、高齢の女性が一人で暮らしておられます。お参りが終わると、コーヒーとケーキを出してくださいました。私の住んでいる町はのどかな田園地帯で、主な交通手段はバスになります。しかし、そのご門徒さんのお宅は、町の中心部からかなり離れており、現在はバスも走っていません。車の免許も持っておられないこのご門徒さんが、どのようにしてケーキを買ってきてくださったのだろうか、と気になりました。「このケーキはわざわざどこかで買ってきてくださったようですが、どうやって買いに行かれたのですか」と尋ねると、「タクシーで行ってきました」とおっしゃいました。そちらのお宅から最寄りのケーキ屋さんまでは少し距離がありますから、往復で数千円のタクシー代をかけてケーキを買ってきてくださったことになります。しかも話を聞けば、「自分は洋菓子は苦手なので、お寺さん用のケーキを一個だけ買ってきました」とおっしゃいます。
数百円のケーキをタクシーで数千円かけて買ってきてくださったわけです。「それは申し訳ないですよ。次からは、わざわざタクシーで買いに行っていただかなくても大丈夫ですからね」とお伝えしました。するとそのご門徒さんは、「気にせんでいいんですよ。私は若さんが喜んで食べてくれればそれが嬉しいんじゃから」と笑いながらおっしゃいました。
数百円のケーキー個を数千円かけて買いに行くということは、一般的には割に合わない行為であるといえます。しかし、そのご門徒さんは、あなたに喜んでもらえればそれでいいと、笑顔でおっしゃってくださいました。その表情とお言葉には、損や得というものを超えた温かいものを感じました。以前、自坊にお説教においでくださった布教使さんから、百円で買った野菜を都会で一人暮らしをする子どもに千円かけて宅配便で送る母親のすがたに、損得勘定を超えた温かい親心をみることができる、というお話をお聞かせいただきました。先ほどのご門徒さんの「若さんが喜んで食べてくれればそれが嬉しいんじゃから」というお言葉にも、まさにその親心に通じる温かさを感じます。
さて、この親心ということについて、時々お参り先で、「うちの親は阿弥陀さまのことを親さまと呼んでいました」と聞かせていただくことがあります。阿弥陀さまは、私たちを救うために果てしないご苦労をされ、南無阿弥陀仏という名号を完成し、お念仏を通して「必ず救う」と喚び続けてくださっています。衆生をわが子のように思ってくださる阿弥陀さまのお慈悲の温もりから、昔の方がたは阿弥陀さまを親さまと呼んでおられたようです。
しかし、阿弥陀さまは親のように常に私たちのことを思い続けてくださっているにもかかわらず、ときに私たちは阿弥陀さまのお心のこともすっかり忘れて、世事に追われて生きています。あるいは、できるだけ阿弥陀さまを中心としたお念仏の生活をさせていただいたとしても、最後にはこの体は衰え、病気にもなり、それまでの生活がままならなくなるときがやってきます。
うちのお寺に二十年以上も勤めてくださっていた法務員さんが、数年前に急な病気で入院されました。私が妻と一緒に病室にお見舞いに行くと、法務員さんはベッドに横たわって目を開けておられました。「〇〇さん、お具合はいかがですか」と声をかけると、「若さん、ありがとうございます。このたびの病気で、いろいろと味わいが深まりました。病気で横たわっているこの私にも、南無阿弥陀仏が届いてくださいます。私がこのまま寝たきりになったとしても、それでも阿弥陀さまは変わらず私のところに届いてくださいます。お念仏に出遇わせていただいた人生でよかった」と目に涙を浮かべておられました。私もそのおすがたとお言葉に涙が流れました。
「願われたいのちを生きる」ということは、「我もたすかり人もたすかる」というその阿弥陀さまのご本願を、人生を通して仰ぎ続け、そして、たとえこの身が老いや病によってどのようになろうとも、私は阿弥陀さまのお救いのなかにあるのだと、感謝の内にお念仏申して生きていくことをいうのでしょう。
能美潤史