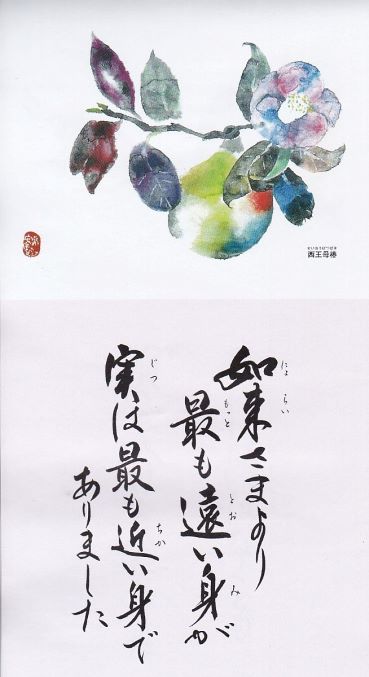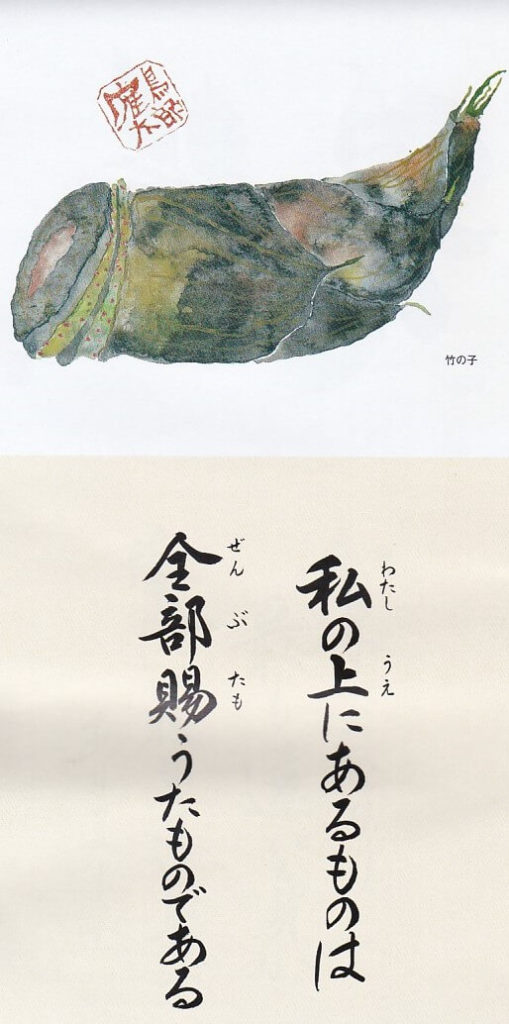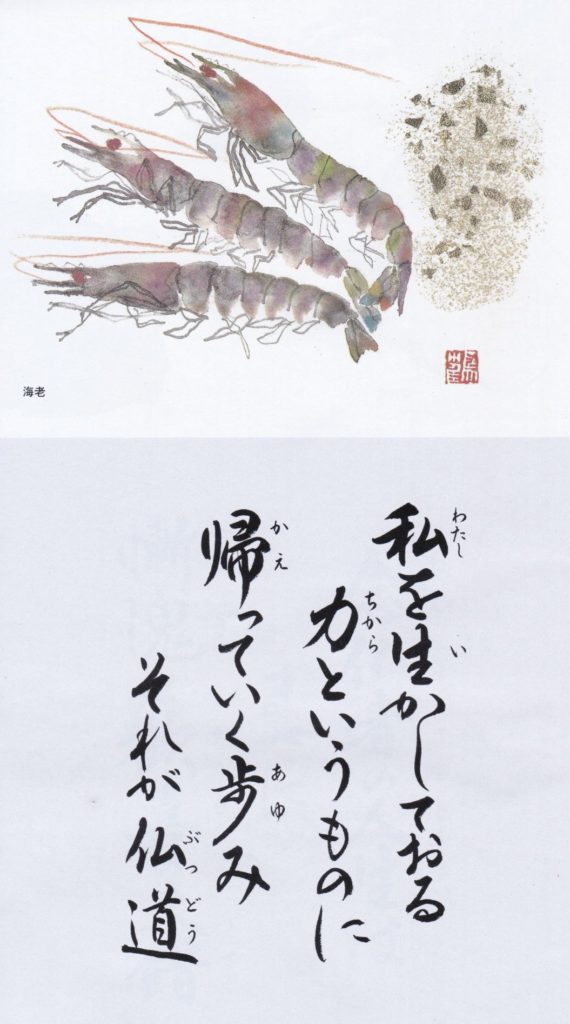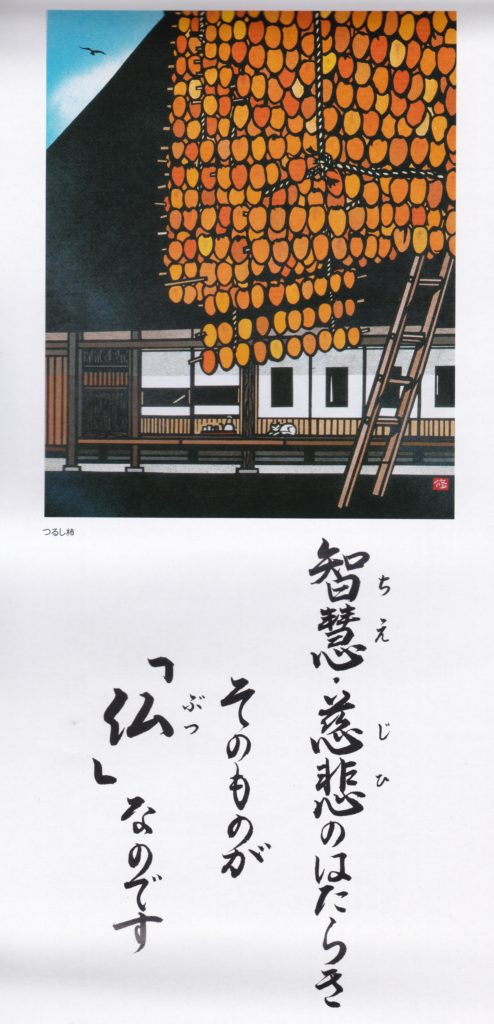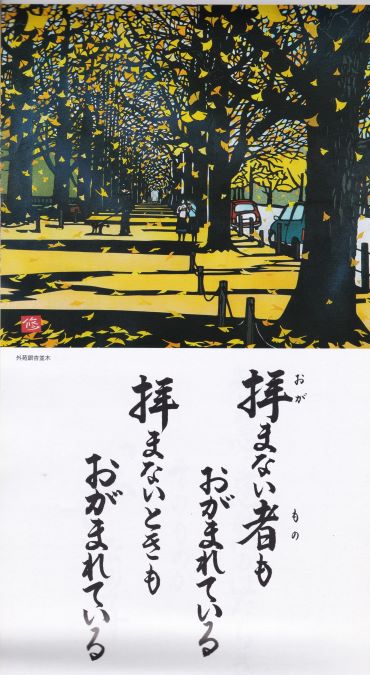「常によく考えなさい」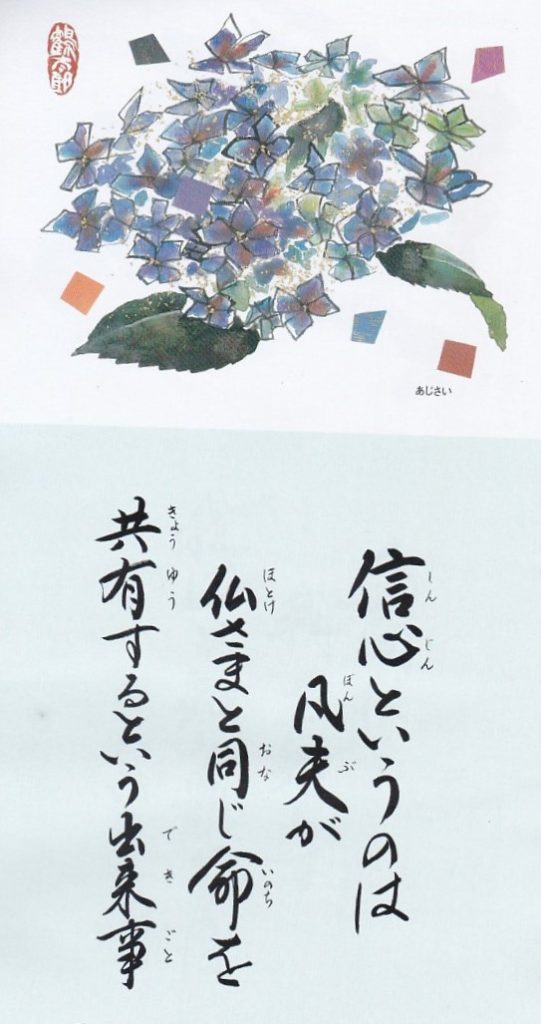
今月のことぼけ、大峯額先生の著書『生命環流 浄土和讃を読む 下』(本願寺出版社、以下、『生命環流』と表記します)に出てきます。
大峯穎先生が住職を務められた、奈良県の浄土真宗本願寺派専立寺は、吉野山を望む自然豊かな場所にあります。
一九二九(昭和四)年生まれの先生は、京都大学に進まれて哲学を専攻されます。
大学院文学研究科博士課程を修了された後、四十二歳から二年間は文部省在外研究員として、ドイツの(イデルベルク大学に留学されます。当時の思いを、
哲学というものは、世間一般の常識に満足しないでものをどこまでも考える仕事です。阿弥陀さまがおられるとはどういうことなのか、お浄土は今生きているこの世と私たちの世界とどういう関係にあるのか、そういうことを徹底的に究明したいと思っていました。 (二〇九頁)
と、述べておられます。毎日毎晩、このことを考えておられたそうです。毎日毎晩、ひたすら阿弥陀如来の救済について考える人はどれほどいるでしょうか。先生の言葉から私自身が問われているように感じます。浄土真宗の教えは他の誰かのための教えではない、私自身が教えに問い学ぶ中から聞こえてくるものなのでしょう。
先生は一九七六(昭和五十一)年に、論文「フィヒテの宗教哲学」によって京都大学で文学博士となられます。また、大阪大学名誉教授、龍谷大学教授などを務められます。また、今は浄土真宗本願寺派総合研究所とよばれる浄土真宗教学研究所の所長や顧問を歴任されました。その間、多くの著書をのこされ、二〇一八(平成三十)年一月三十日にご往生されました。
私も龍谷大学で先生の講義を受講したことがありましたが、授業の中で学生に「常によく考えなさい」とおっしゃっていたことが懐かしく思い出されます。
独りぼっちではない
今月のことば「信心というのは凡夫が仏さまと同じ命を共有するという出来事について考えるために、もう少し先生のことを紹介させていただきたいと思います。
俳句の世界でも著名な先生は、「毎日俳壇」の選者を務められ、数々の賞を受賞されました。『生命環流』に、先生の俳句とその情景が述べられていますのでご紹介いたします。
虫の夜の星空に浮く地球かな (『夏の峠』花神社)
という私の旧作があります。ある秋の夜、自宅の庭で、松虫や鈴虫が鳴いている声を聞きながら満天の星空を眺めていたら、自分かいるこの地球もいろいろな虫たちと一緒に星空の真っただ中に浮いているのだという感じが急に迫ってきたので、それを詠んだのです。 (三二〇頁)
俳句は世界で最も短い五七五の十七文字からなる短い詩です。俳句について先生は、「十七文字の中に、全宇宙がこもるような場合がある」と説明されています。先はどの俳句にも、無限とも思える宇宙の広がりの中で孤独ではない私の存在の不思議さについて触れられています。
私たちの地球は、無限の星空の真っただ中にあるのです。空は頭の上だけでな く、大地の下にも底抜けの空かあります。地球を會んだ太陽系は銀河系の中にありますが、宇宙にはそれ以外にもたくさん銀河系があるわけです。無数の太
陽があって、無数の銀河があり、そういう無数の星群の中の小さな惑星の一つである地球という所に、どうしてだが私たちは今いるわけです。そして、百年ほどの命を生きて、宇宙のどこかへ消えてゆくのです。けれども、この俳句をお読みになったら、ちょっと安らかな気持ちになりませんか。孤独で暗い気持 ちにはならないはずです。人間界の騒音がなくてにぎやかな宇宙です。
(二三一頁)
そして、このにぎやかな宇宙に生きている姿という受けとめから、浄土真宗の世界観として、親鸞聖人の『浄土和讃』「現世利益和讃」の一首を引用されます。
南無阿弥陀仏をとなふれば
十方無量の諸仏は
百重千重囲続して
よろこびまもりたまふなり (『註釈版聖典』五七六頁)
「現世利益和讃」は、他力信心の行者がこの世に生きている間(現世)からいただく現生正定聚などの利益について、親鸞聖人が讃嘆されたものです。
信心をいただいて南無阿弥陀仏を称える身になると、すべての世界の数限りない仏さま方が百重にも千重にもそのものを取りかこんで、喜んでお護りになるという内容です。これは現生において得る利益の一つで、諸仏が護ってくださる「諸仏護念」の利益といわれています。信心の人を幾重にも取り囲んで護ってくださるのですから、私は独りぼっちではなく、南無阿弥陀仏を称えると、いつも仏さま方が私と共に歩んでくださっていることを知らされます。
仏教は死後の世界のためだけにあるもの、信心や念仏はそのためのものと思っている人がいるかもしれません。しかし、この和讃を読むと、南無阿弥陀仏の教えはそのようなものではなく、今この世界に生きている私の人生に深く関わるものであることを教えてくださいます。
先生は、この和讃のおこころと、先はどの俳句を重ねて、私たちの地球というこの惑星は、独りぼっちではなくて無限の星の中にあるの です。そうしますと、南無阿弥陀仏を称える人は無数の仏さまに取り巻かれ、護られていることになります。死んでから護られるのではありません。今ここで護られるのです。 (一言二頁)
と、味わっておられます。宣(つ暗な闇にポツンと浮かぶのではなく、無数の太陽があって、無数の銀河があり、そういう無数の星群の中にある地球と受けとめる時、孤独で暗い気持ちではなく、どこかにぎやかで安らかな気持ちになるように、阿弥陀如来をはじめ、お釈迦さまや諸仏に護られて今生きているという事実が、私に安心を与えてくださるのです。
同じ命を共有する
今月のことばに「信心というのは凡夫が仏さまと同じ命を共有する」とあります。凡夫と仏さまが同じ命を共有するとはどういう意味なのでしょう。
先生の俳句に、「虫の夜」という言葉があります。夜は暗いため、周りがよく見えません、でも虫の夜とあります。夜の闇の中にその姿は見えないはずです。虫の音がそこにいる虫の存在を知らせ、孤独ではないことに気づかされているのではないかと思います。虫の音や満天の星のように、外からのはたらきかけによって孤独が打ち破られているのです。
親鸞聖人は、南無阿弥陀仏は阿弥陀如来の喚び声であると仰せになられました。
『教行信証』「信巻」には「弥陀の悲心招喚六『註釈版聖典』三天頁)とあり、阿弥陀如来の慈悲の心から発せられるものであるとお示しなのです。
「招」は招待の招です。披露宴など招待をされたら、招く側か来てくださいとお願いをしているので、遠慮なく参加します。阿弥陀如来は私たちに来て欲しいと願い招いてくださっていると受けとめることができるのです。「喚」は、普段私たち加人を呼ぶ時には使用しません。「喚」には「よびつづける」今よばふ」『同』二二五頁・脚註)という意味があると親鸞聖人は示されています。
『正像末和讃』には、
弥陀・観音・大勢至
大願のふねに乗じてぞ
生死のうみにうかみっつ
有情をよばうてのせたまふ (『註釈版聖典』六〇九頁)
とあります。阿弥陀如来は、大悲の観音菩薩、智慧の勢至菩薩を伴って、生死の迷いの苦海に沈没している私のところまでやって来て、招き喚びっづけ、私たちを大悲の願船に救いあげ、安らかなさとりの世界へと迎えいれてくださるというのです。
「有情をよばうて」とありますように、南無阿弥陀仏は私たちを喚び続けておられるという悲心の切なる様相なのです。このように、私の方から浄土真宗の教えにてあったのではなく、阿弥陀如来の切なる願いが南無阿弥陀仏の声となって喚び続ける中に、縁あって私はその喚び声に気づかせていただいたのです。たった六文字ではあるけれども、その六文字に阿弥陀如来の大悲の願心がこもっていると聞こえてくるのです。
こうして「必ずたすける」という阿弥陀如来の喚び声と、その声に喚び覚まされて仰せのままにおまかせする私の声が、一つに溶け合って響いているのが南無阿弥陀仏というお念仏なのです。ご信心は、私か勝手に起こす思いではなく、この喚び声を聞いて安心して生きていくことを表しているのです。
ですから、「信心というのは凡夫が仏さまと同じ命を共有するという出来事」とある今月のことぼけ、私か共有しているのではなく、阿弥陀如来のはたらきかけによって「共有する」出来事が生まれてくるのです。
今月のことばは『浄土和讃』にある、
信心よろこぶそのひとを
如来とひとしとときたまふ
大信心は仏性なり
仏性すなはち如来なり (『註釈版聖典』五七三頁)
のおこころについて述べられた中に出てきます。
この和讃に言われているように、阿弥陀如来を信じお念仏をよろこぶ人は如来に等しいのです。煩悩具足罪悪深重の凡夫であっても阿弥陀さまにまかせたら、その人の心は如来さまと等しい。これはつまり、その人は死なない命をいただいているということです。阿弥陀さまがそのようにおっしやっているのです。
信心というのは、凡夫が仏さまと同じ命を共有するという出来事です。共生と言ってもいいでしょう。われわれが生きているというのは、実は如来さまの命を生きさせてもらっているということです。如来さまは如来さまの無限の命を 生きていても、私は一人で死ななければならないと思うのであれば、それは信心ではなく疑い心であります。 言一一七上二一八頁)
南無阿弥陀仏の大悲の願いに喚び覚まされることによって、その無限のいのちに生きていくものとしての歩みが誕生するのです。その歩みは、これまでのように独りぼっちで寂しいものではなくなります。無数の太陽があって、無数の銀河があり、そういう無数の星群の中の小さな惑星の一つである地球と気づくように、諸仏に護られ歩む、たしかな大いなる南無阿弥陀仏の道なのです。
(和気 秀剛)