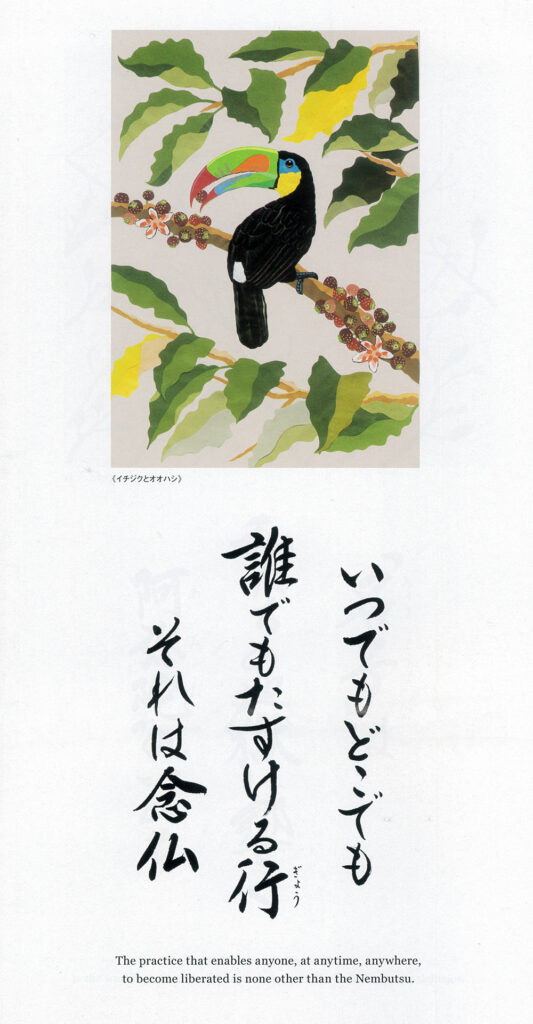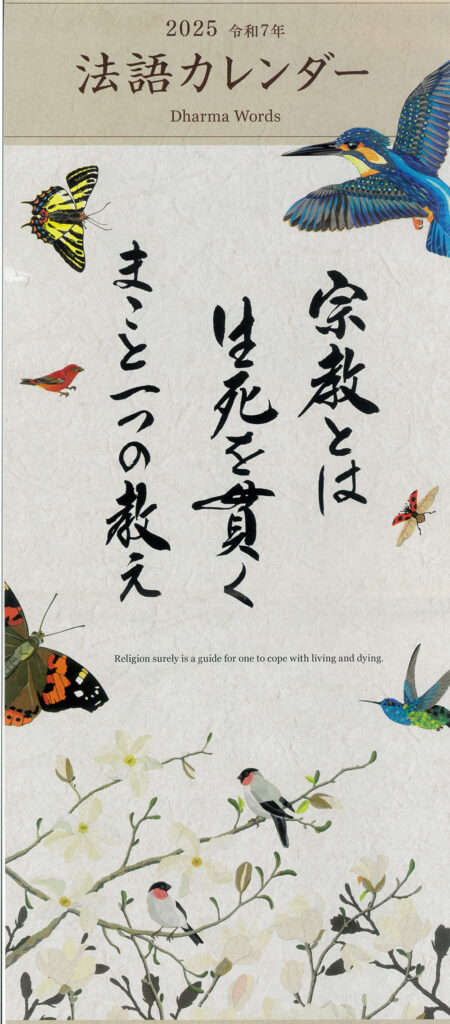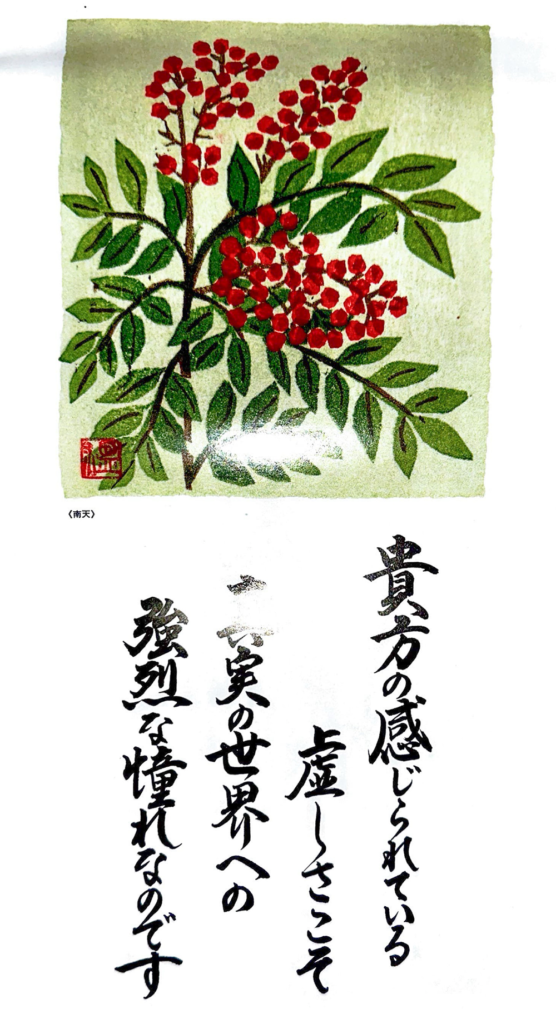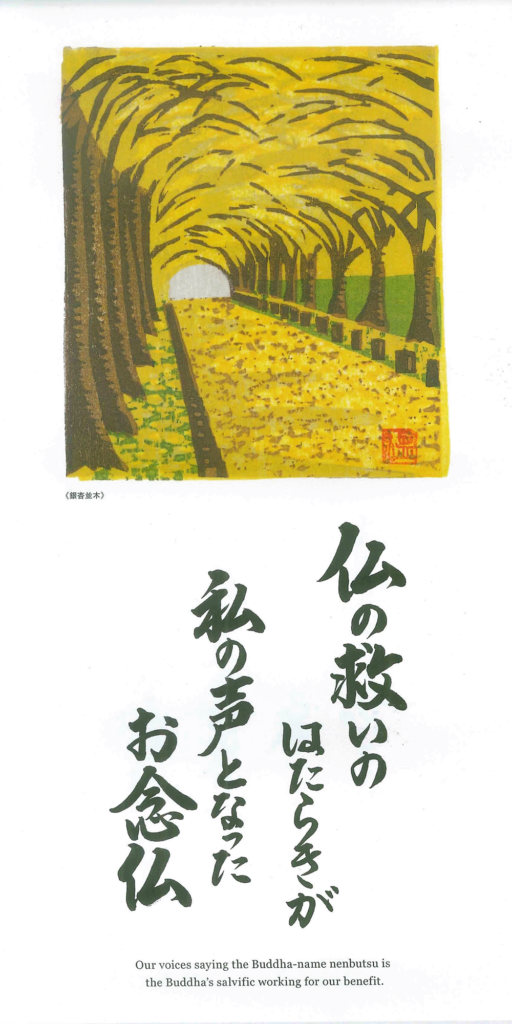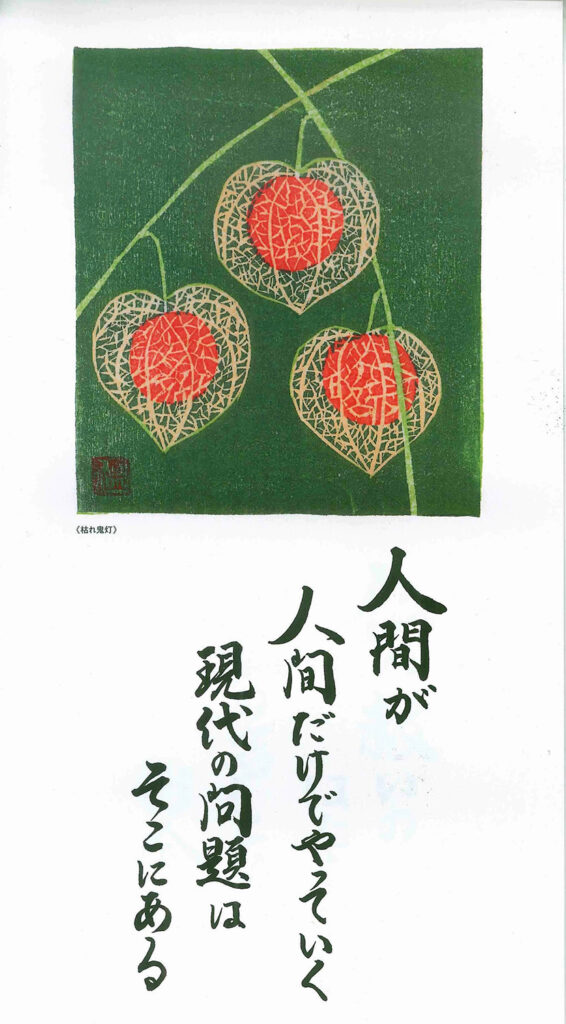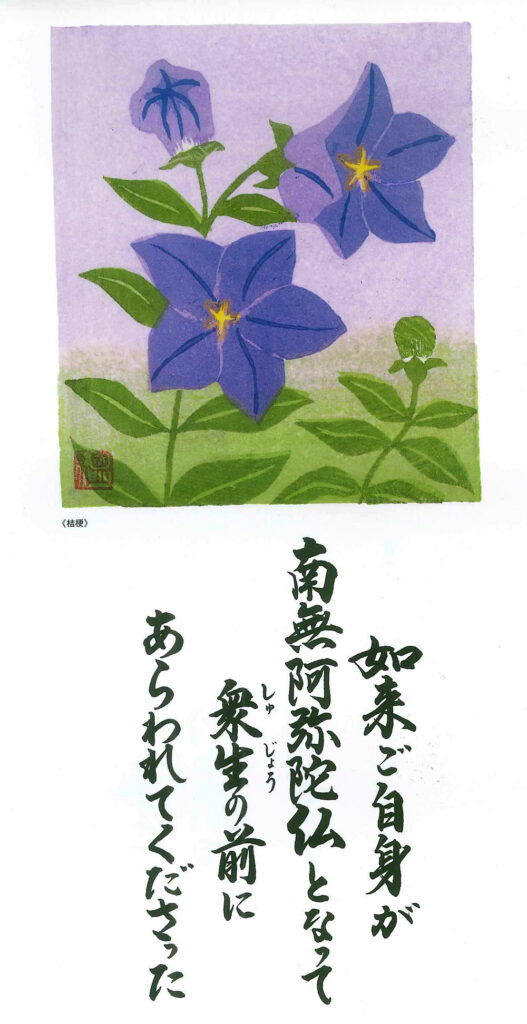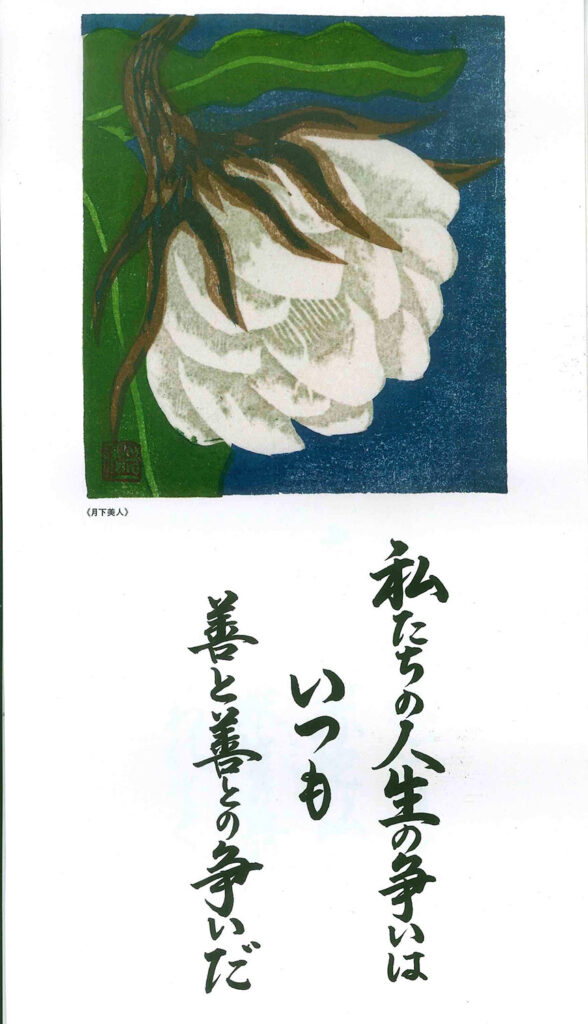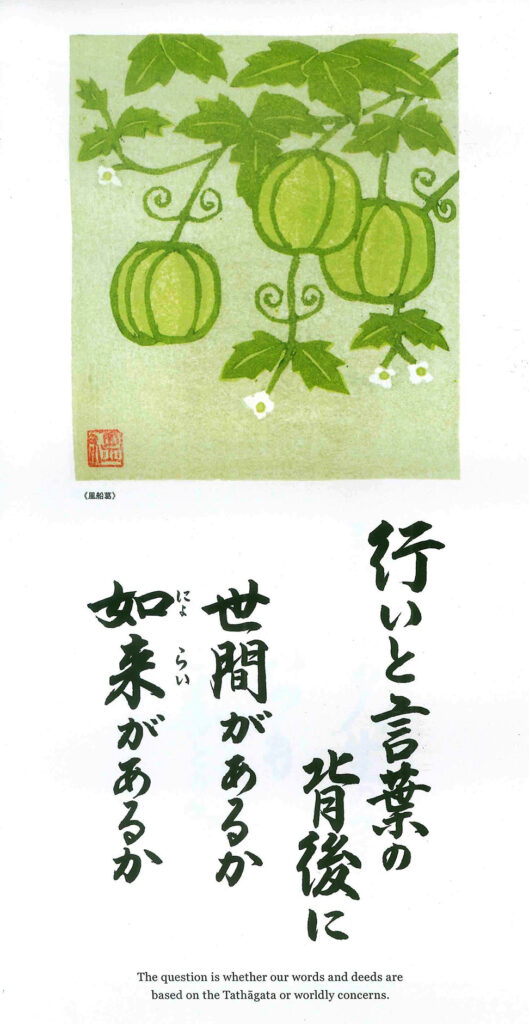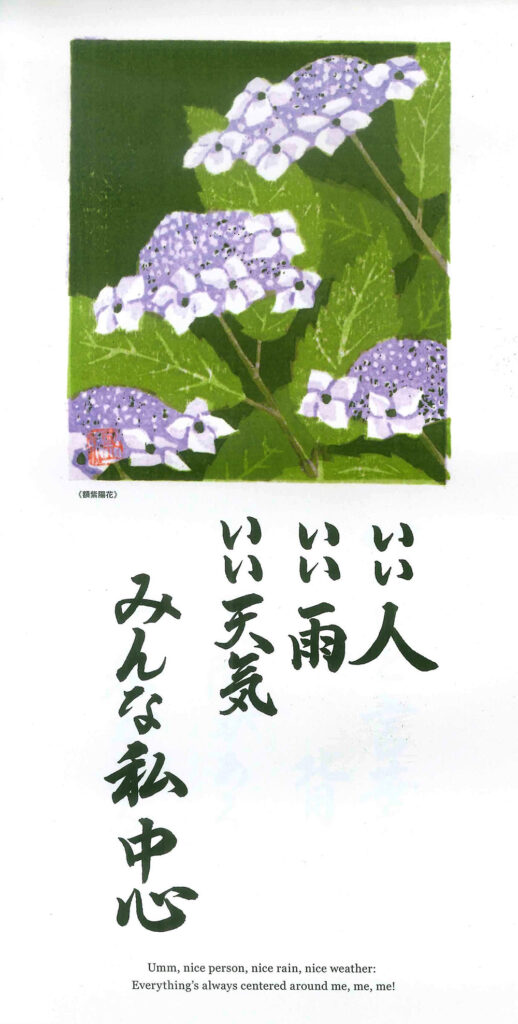亮先生の生涯
二月のことばは「悲の海は深く』(東本願寺出版)に出てくる高史明先生のお言葉です。
先生は一九三二 (昭和七)年に、山口県の下関市にて誕生されました。三才のとき母親と死別され、高等小学校を中退後、さまざまな職業を経ながら独学にて文学を会得。元来より持ち合わせておられた、いのちを見つめる深い洞察力とその表現力によって、作家としての道を歩み始められたのです。一九七五(昭和五十)年には一人息子の真史さんが十二才で自死をするという深い悲しみの中に、「戦異掛」を縁として親鸞聖人の教えに出遇い、海土真宗に導かれたのでした。数多くの作品や講演会などを通して、あまたの人々に真のいのちのあり方や生きる意味を問い、阿弥陀仏の願いに生きることの尊さを伝え続けてこられた先生でしたが、二〇二三(令和五)年七月十五日、神奈川県の自宅にて、お念仏の中に往生されたのでした。御年九十一才のことです。
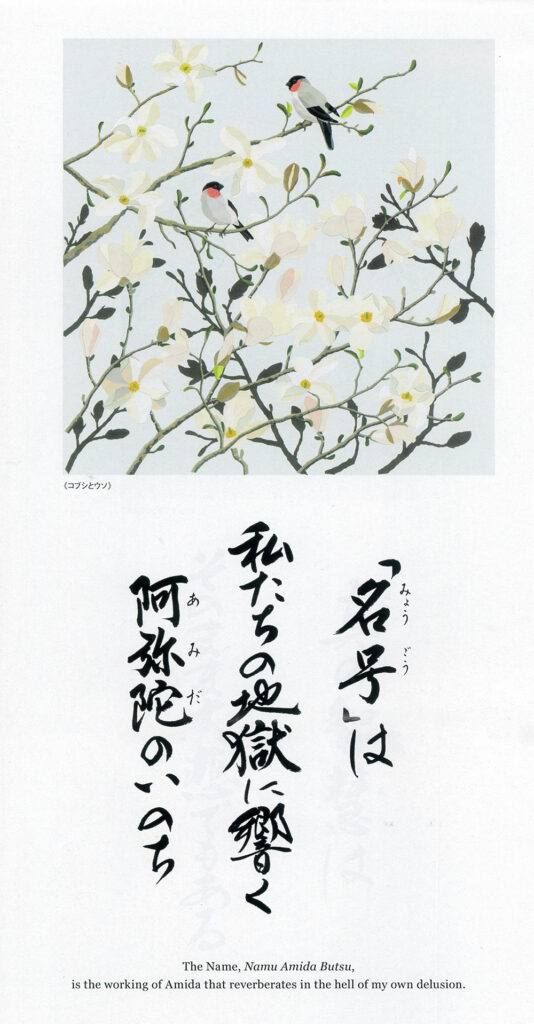
ただ弥陀をたのむこころ
この書籍は、真宗大谷派佐世保別院報恩講でのご法話をまとめられたものです。
このご法話全体を通して語られていることは、自力(自分中心の世界)に固教して人間が暗闇を作り続けることの罪業の深さ、そしてそれに対する阿弥陀仏による絶対他力の救済です。先生はそのキーワードとして道知上人の「御安童」(大谷派では「御文」)を用いられておられます。少し長い文章なので、肝要な部分を抜き出して紹介します。
(前略)弥陀如来の悲願に帰し、一心にうたがいなくたのむこころの一念おこるとき、すみやかに弥陀如来光明をはなちて、そのひとを摂取したもうなり。
これすなわち仏のかたよりたすけましますこころなり。またこれ心を如来よりあたえたまうというもこのこころなり。さればこのうえには、たとい名号をとなうるとも、仏たすけたまえとはおもうべからず。ただ弥陀をたのむこころの一念の心によりて、やすく御たすけあることの、かたじけなさのあまり、如来の御たすけありたる御恩を報じたてまつる念仏なりとこころうべきなり
(中略) 寛正二年三月
(「御文章集成(帖外御文章)」「浄土真宗聖典全書(五)相伝・下』二二九頁)
このお手紙を発布された「寛正二年」とはいったいどのような年だったのでしょうか。
この年の二年前、一四五九(長様三)年は全国的な干ばつや京都への台風の直撃などで、西日本を中心に大飢催が発生した年です。翌年にも大雨による水害と干ばつが交互に訪れた上に、虫害と疫病も加わって、飢が全国に拡大していました。
京都への台風直撃では、加茂川が氾濫して多数の家屋が流出し、数え切れないほどの死者が出たほか、二年後(寛正二年)には飢催がより深刻化し、この年の最初の二カ月で、京都市中で八万二千人もの餓死者が出たと資料には記されています。
道ばたには、桁ち果てた数多くの遺体が折り重なり、それが洪水によって加茂川に押し流されてゆく。あの大きな川が遺体によって塞き止められ、川の流れが止まったとさえ、当時の資料は伝えています。街中には死臭が漂い、病人はその苦痛にのたうち回り、死を待つ人々のか弱きうめき声が街中を覆っていたのです。それは病苦とともに死に向かう恐怖と不安の「助けてください」の祈りの声だったに違いありません。このような惨状の只中に出されたのが、先の蓮如上人のお手紙なのでした。
たとい名号(念仏)をとなうるとも、仏たすけたまえとはおもうべからず。ただ弥陀をたのむこころの一念の心によりて、やすく御たすけあることの、かたじけなさのあまり、如来の御たすけありたる御恩を報じたてまつる念仏なりとこころうべきなり
なんと厳しいお言葉なのでしょうか。しかし、ここにたすけられた世界に生きる如上人の、揺るぎない心の表白が聞こえてくるのです。上人が「たのむ」という語をお使いになる場合は「まかせる」という意味ですから、「弥陀をたのむこころ」とは「阿弥陀仏にまかせるこころ」のことです。それは「必ず救う、われにまかせよ」と私の口に届いてくださる大悲の奥び声「南無阿弥陀仏(名号)」を、そのままに受け入れたこころです。ですから、私が申す念仏は「ありがとうございます」と「御殿をじたてまつる念仏」に他なりません。人知を越えた苦悩を救い送げることができるのは、人知を超えた仏智不思議の名号、南無阿弥陀仏しかないのです。
悲しみを縁として
高先生はこの「ただ弥陀をたのむ(阿弥陀仏にまかせる)こころの一念の心」によってのみ、人は救われるのだと語られています。逆にいえば、自分をたのむ
(人間中心の)心によってこの世を地獄と化し、人々は鬼となって、この世を果てしなき暗闇の世界へと墜落させていくのだともおっしゃるのです。
一人息子の真史さんを、十二才という若さで自死で喪ったとき、深い悲しみの中で先生は自らに問われました。それは真史さんが中学生になったときに、父親とし
て、「今日から、君は中学生だ、これからは自分のことは自分で責任を取りなさい・・・他人に迷惑をかけないようにしなさい」
と励ましの言葉を贈られたそうです。しかし、その人間中心の一言が彼を地獄に追い込んだのではないかと。あのとき何故、
「人はひとりでは生きていけない、迷惑をかけねば生きていけない存在なのだ」と言えなかったのか…・。ここに自らの無明の根本があるのだと気づかれたそうです。
その後「数異抄』に導かれて親鸞聖人に出遇い、阿弥陀仏のお救いにあずかられた先生は、これからを生きる子どもや青年たちに、他力に生きることの大切さを伝え続けられるようになります。
地獄に響く名号
真史さんが遺した多くの詩を「ぼくは十二歳』(筑摩書房)という詩集にして出版されたのも、そのような心からではなかったでしょうか。ここに朝日新聞への先生の寄稿があります。
ー自分支える足の声、聞いてー
ほくだけはぜったいにしなない
なぜならば
ぼくは
じぶんじしんだから
三十一年前、ひとり息子の真史は、人知れず詩を書きためた手帳の最後にこう春いて、自死しました。十二歳でした。「なぜ!」という自問をくりかえしながら、息子が残した詩を妻とともに「ぼくは十二歳」という詩集にまとめました。読者から多くの手紙が届き、訪ねてくる中高生も後を絶ちませんでした。
ある日、玄関先に現れた女子中学生は、見るからに落ち込んだ様子でした。
「死にたいって、君のどこが言ってるんだい。ここかい?」と頭を指さすと、こくりとうなずきます。私はとっさに言葉をついでいました。
でも、君が死ねば頭だけじゃなく、その手も足もぜんぶ死ぬ。まず手をひらいて相談しなきゃ。君はふだんは見えない足の裏で支えられて立っている。足の裏をよく洗って相談してみなさい。
数カ月後、彼女からの手紙には大きく足の裏の線が描かれ、「足の裏の声が
聞こえてくるまで、歩くことにしました」と書かれてありました。
思えば、真史が最後までこだわった「じぶんじしん」とは、足の裏で支えられた自分ではなかった。そのことに気づかせてあげていれば・・・・・・。(中略)
命は一つだから大切なのではなく、君が家族や友人たちと、その足がふみしめる大地でつながっている存在だから貴重なのです。切羽つまった時こそ、足の裏の声に耳を傾けてみてください。
(『朝日新聞二〇〇六年十一月二十二日掲載」)
また、先生は東京大学へ特別講義に招かれた時の心情を、書籍の中でこのように紹介されています。
(エリートの道を歩んできて)挫折を知らないものが挫折した時が、一番危ない。
すぐ死にたくなる。どうかこれからの問題として、そういうときは「たすけてください」と叫びなさい、と私は(学生たちに)言いました。叫んで、叫んでいくと「仏たすけたまえとは思うべからず」このようにおっしゃっている蓮如聖人のお言葉に出遇うことができる。その時、人生が本物になってくるのであります。
(「悲の海は深く』)
この若者たちがこれから先の人生で、いくたびも出遭うであろう地獄への悲嘆。
先生は「生きる」という世界に捕らわれ苦悩する若者たちに、「生かされているいのち」への気づきを強く促されています。それは「たすけてください」と叫ぶより先に「かならずたすける」という阿弥陀仏のいのちの叫び(名号)が、もう既に私たちの地獄に響いているという真実への誘いでもあったのです。
(田中 信勝)